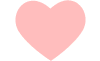★小さな子どものおもちゃは、見える収納がいい。
きょうは、食育に関係のない、おもちゃの収納の話・・・
笑
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
こんにちは。食育コーチの井上ききです。
なめこを甘辛く煮て、大根おろしを添えていただくと、おいしいです。大根も、日に日においしくなりますね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、今日は大掃除の中でも、やっかいな項目だった、おもちゃの整理を完了しました。小さな子どものおもちゃは、見える収納がいい。
こう思って、思い切った整理収納をしました。
BEFORE。
我が家では、このおもちゃ収納にだけ、シールを貼っていい事にしていました。私の母がそうしてくれていたように。
しかし、この収納、中身が見えない。子どもたちは、何が入っているのかイメージできず、遊ぶものがないな~・・・と感じているときが多いかもしれない?
大人にとっては、自分の持ち物って、頭にイメージがすぐにわく、これが当たり前な感じがします。
でも、子どもも同じ??
自分はどんなおもちゃを持っているのか、何をして遊ぶのが、楽しいのか、忘れちゃうのでは?こんなことに、井上はようやく気づいたんです。
そこで、AFTER.
10段の透明な収納ケースを2本買いました。ひとつ¥4,980.-。(カインズホーム)
長男も来年は一年生。少しずつ、お勉強の道具なども増えてきています。これなら、自分で片付けやすいかも。
なにより、便利なのは、こうして引き出しごと持ち出して、机や床へ移動できるところ。
いい感じでしょ?←自画自賛
「片付ける」って、生きていく上で、けっこう大切なこと。
ひとつひとつの おもちゃや道具に向き合って、それを分類したり、次に使うときのことを考えたりして、元の場所に戻すこと。
これは、人生において、さまざまな「やるべきこと」や「面倒なこと」に、ひとつひとつ向き合って、完了させてゆく力になる。
子どもたちが、ぼちぼちでいいので、お片づけを身に着けて行くサポートになれば、何よりです。
同時に、夕方の忙しい時間に、おもちゃを次々に出して、夢中になって遊んでいてくれると、食事の準備もはかどります。(これ本音。)
さらに、子どもたちお腹がすいて、一石二鳥・・・の予定です。
肝心の子どもたちは、まだ保育園に行っているので、おもちゃの新しい収納は見ていませ~ん。笑
たんなる、自己満足なのか!?
★「たくさん食べようね。」でいいですか?
きょうは、「たくさん食べようね。」という言葉がけについて、考えてみようと思います。
食育コーチの井上ききです。
先日、祖父江の銀杏がおいしくてたまらん・・・と書きました。毎日、毎日いただいています。他の産地のものも買ってみましたが、やはり祖父江の銀杏は、すご~い!
苦味が少なく、味のばらつきもない。全部、安定して美味しい。他の産地の銀杏は、苦いものや美味しいもの、いろいろな感じ。
とうとう、こんなの作ってみました。
次男のおもちゃになっています。
「たくさん食べようね。」とか、「いっぱい食べられたね、すごいね!」とか、子どもへの言葉がけの定番です。私たちが子どもの頃にも、こう言われて育った記憶があります。
でもね、私たちは大人になると、「食べ過ぎに注意しましょう。」と言われたり、あるいは、たくさん食べないように気をつけている時のほうが多いのです。
なので、我が家では「たくさん食べる」ことに、あまり価値を置かないようにしています。
たくさん食べる必要があったのは、昔のこと。
現代は、栄養価の高い食品も多いです。また、便利な生活によって、消費カロリーも減っているのです。
つまり、日本人の生活習慣から考えると、あまりたくさん食べないほうがいいのですね。
子どもたちには、「たくさん食べようね。」よりも「色んなものを食べようね。」と伝えましょう!いろんな食材を偏りなく食べることによって、様々なメリットがあります。
同時に、「きちんと選んで食べること」も少し大きくなったら伝えてゆきたいですね。世の中には、体にやさしい食べ物と、そうでない物がある。
「色んなものを食べようね。」
「きちんと選んで食べようね。」
こうやって育った子どもたちは、大きくなったときが違います。
「コンビニのお弁当を買って来ちゃったけど、でも、野菜ジュースを飲もう。」と思ったり、「昨日は、コンビニ弁当食べちゃったから、今日は、玄米を炊こう・・・」と考えたり、居酒屋さんで、揚げ物の分だけ、サラダを注文したり・・・
毎日、毎日食べるごはん。子どもたちの心も体も、元気にしてくれますように・・・


[副菜] さつまいものきんぴら
[副副菜] 大根菜のふりかけ
[汁物] 玉子ともやしとわかめのとろとろスープ
さつまいものきんぴらは、塩だけの味付けです。
大きな鉢にいっぱいのさつまいもが、あっという間に消えてゆきます。
★無理やり口に押し込んではいけない理由は?
ごはんを楽しく食べていますか?今回は、「ごはんの時間にやってはいけないこと」、について。
こんにちは、食育コーチの井上ききです。
最近、アメブロにお引越ししてきたんですが、アメブロ面白いですね。いろいろな方とコミュニケーションがとれて・・・
まだまだ無礼をすることもあるかもしれませんが、ちょっとずつ、アメブロのコミュニケーションにも慣れて行きますからね!
どうぞ、よろしくおねがいします。
さて、先回は子どもの好き嫌いについて記事にしました。そのときに、無理やり口に押し込むのは、ぜったいにやめてくださいね。と書きました。
当たり前・・・なんですが、
一生懸命、栄養バランスを考えて作ったお料理、ついついやっちゃう、というお母さまもいらっしゃるのが現実です。
では、ぜったいにやってはいけない理由です。
子どもたちは、食べることを通じて、様々な食材の味のデータを蓄積させています。味が記憶されてゆく。
もしも、ほうれん草を無理やり口へ押し込んだなら・・・
「嫌な感覚」や「悲しい感覚」、「強い憤り」などの感覚と、ほうれん草の味をセットで記憶してしまいます。
つまり、いつかほうれん草を“美味しい味だ”、と感じるどころか、このマイナスの記憶がある限り、いつまでたっても、好きになれない、という結果になりやすいのです。
こんな理由で、子どもたちとの食事では、どうしても食べてほしい場合でも、無理やり口へ押し込むことは、ぜったいにしてはならないのです。
同じような理由で、ごはんの時間に、お説教することや、全部食べるまで、怖い顔をして目の前に座っていることなども、してはならないこと、だと思います。
つまり、楽しく食べることこそが、何より大切なことなのです。
子どもたちが、食べることが大好きなり、食べることによって、癒されたり、気持ちが楽になったりするためには、
「ごはん」と「楽しい」をセットで記憶させてやればOK。
大人になって、少々困難な出来事や、悲しい出来事があっても、食事をすることで、元気になれたら、心配ないですもんね。
大切な子どもたちの未来のために、楽しくて、あたたかい食卓づくり、一緒にがんばりましょうね。
いろいろな根菜と豚肉をコトコトにました。
ウインナーと一緒に煮ると、美味しいですよ。
我が家は、ウインナーを切らしていたので、
豚こまを使いました。
ごぼうや、かぶ、さつまいもが入っています。
★子どもの好き嫌いの原因は・・・
きょうは、子どもの好き嫌いの原因について書こうと思います。好き嫌いって、時々、たんなるワガママに観えるときがある。でも、実はきちんとした理由があるんです。
こんにちは。食育コーチの井上ききです。
先日、コーチング研修の講師として、稲沢市の祖父江にて、お仕事をさせていただきました。そのときに、スタッフの方が、「銀杏」をお土産にくださいました。祖父江は「銀杏」の名産地。
まったく存じ上げず、失礼しました。朝も晩もいただいております。こんなに美味しい秋の味覚、あったんですね。祖父江の銀杏は、ただの銀杏じゃない。
とまらなくなっちゃう。でも、銀杏って、たくさん食べちゃダメなんですよね?
さて、好き嫌いの話に戻りますが、子どものころ、わたしにも好き嫌いがありました。たぶん、銀杏も食べられなかったはず。
好き嫌いは、子どもに多くて、大人になるにつれて、食べられないものも減ってきますよね?ここが好き嫌いの原因に関係する点です。
人は、初めて食べる味を、「おいしい」と感じることができないんです。
でも、何度ほうれん草をお料理しても、子どもたちは、いつまでたっても「おいしい」とは言いませんよね?うちも、そうですよ。
その原因は、何かと言うと、
ほうれん草は、毎回微妙に、違う味をしているからです。
自然の中の食べ物は、産地や、細かい種類、収穫される季節などによって、微妙な味の違いがあります。しかも、お母さんのお料理の方法によっても、味や触感が変わってきます。
ですので、ほうれん草を「おいしい」と感じるまでには、膨大なほうれん草の味のデータが必要なのです。だから、大人になると、だんだん食べられるものが増えてくる。
季節の野菜を美味しいと感じることができるのは、少しずつでも、野菜を食べてきたからなのです。
一方、インスタント食品や、加工食品は、いつもどこで食べても同じ味。だから、子どもたちは、大好きなんですね。子どもたちに限らず、みんな大好きです。
子どもたちが、インスタントの物を好んで食べるからといって、与え続けると、好き嫌いは改善しないまま、大人になってしまう可能性が高いと言うことです。
だからと言って、きらいな食べ物を無理やり口へ押し込むのは、絶対にやめてくださいね。「無理やり食べさせる」事が更に、好き嫌いを多くしちゃいます。
この続きは、次回書きますね。
お楽しみに~!
〔主菜〕 さといもと豚肉の煮物
〔副菜〕 納豆
〔副副菜〕 蒸し白菜を、ごまと塩昆布としょうゆをかけて
〔汁物〕 たまねぎ、豆腐、わかめのお味噌汁
★子どもの「味覚」を大切に育てる。
今日は、子どもの「味覚」について書こうと思います。
小さな子どもに、スナック菓子を食べさせる。という事が、どのような未来を作っているのかな・・・?
こんな事を考えてみようと思います。
スナック菓子に限らず、市販されている加工食品には、化学的な調味料が加えられています。この化学的な調味料には、強烈な「うまみ」がありますよね?
これは、自然の中にある食べ物には、決してありえない「うまみ」なのです。
化学的な「うまみ」に慣れてしまうと、自然の中にある、やさしい「うまみ」では、美味しい。と感じることができなくなってしまいます。
つまり、スナック菓子や市販のハンバーガーばかり食べさせる、ということは、大人になっても野菜嫌いが直らない。という可能性を広げています。
井上はいつでも、こう思っています。季節の野菜の「うまみ」を『幸せな味だな・・・』と感じることのできる舌を、育ててやりたい。
今は好き嫌いいっぱいだけど、いつか、『季節の野菜を食べると、元気になるな~』と子どもたちが感じていてくれること。
こんな事を目指して、なるべく手作りする食卓を目指しています。
おやつを手作りする、とまでは、なかなか難しいですが、市販のお菓子の中にも、化学調味料の使われていないものを見つけることができますよ。
きょう我が家にあった、おやつ達を紹介しま~す。
有機バナナ
うちでは、めったにバナナを買わないので、子どもたち大興奮のごちそうです。

げんこつあめ
きらず揚げ
愛知県高浜市の豆腐メーカーが製造しているお菓子です。しっかりした歯ごたえの、おせんべいでもなく、クッキーでもなく、あられでもない、きらず揚げ。

干し芋
これが、もっとも体にやさしいおやつだと思います。砂糖も塩も何も加えてない、正真正銘の「無添加」。

近所のパン屋さんで売っている、昔ながらのクッキーです。甘すぎるのが、難点ですが、たまにはこんなのも・・・

赤ちゃん用のおせんべい
我が家では、もうすぐ6才の長男も喜んで食べています。これ、赤ちゃんのころから、知っている味。つまり、子どもたちにとっては、安心とやさしさの味なんですね。