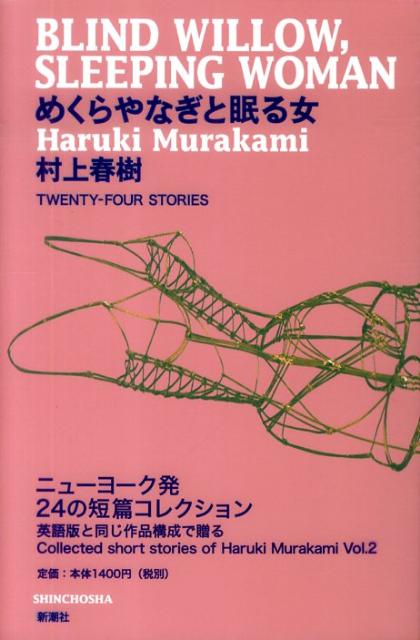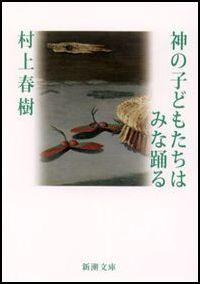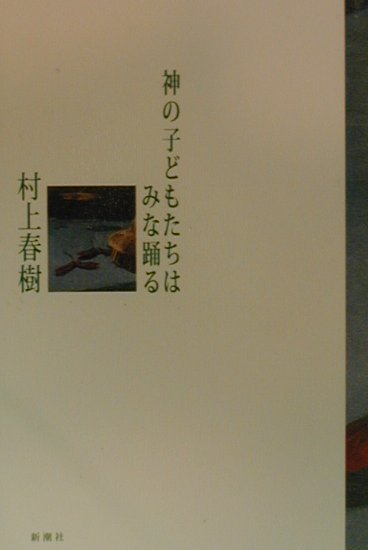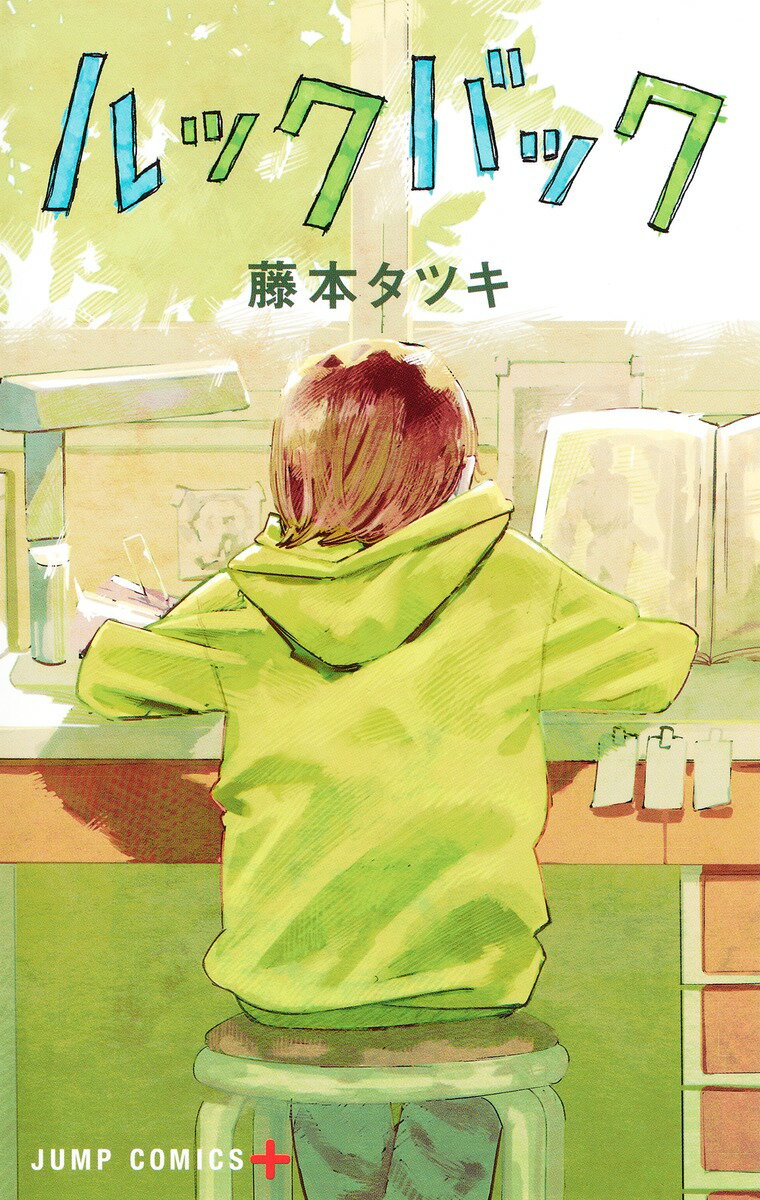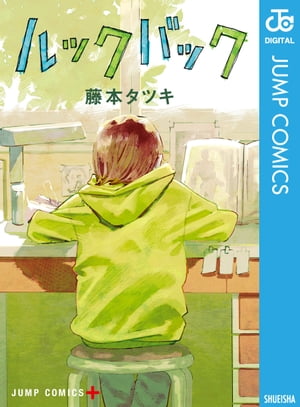あらすじ
(1998年オリジナル)
幼女誘拐殺人…。娘を殺された宮下は、謎の男、新島の協力を得ることによって、復讐を実現しようとしていた。
ある組織の幹部、大槻、檜山、有賀を次々に拉致し、拷問まがいのやり方で、事の真相を問いただしていく。3人は自分の身の保身のために、罪を擦り付けあい、醜い争いを繰り広げる。
娘を殺したのは誰なのか?そして、新島の本当の狙いは?
(2024年セルフリメイク)
8歳の愛娘を何者かに惨殺された父親アルベール・バシュレは、偶然知り合った精神科医・新島小夜子の助けを借りながら、犯人を突き止めて復讐を果たすべく殺意を燃やしていた。やがて2人はとある財団の関係者たちを拉致し、次第に真相が明らかになっていくが……。
感想
「岸辺の旅」「スパイの妻」の黒沢清監督による1998年に手がけた同名映画をフランスに舞台を移してセルフリメイクした作品。
オリジナル版も配信で観直したので、両作品の感想を残しておきます。
娘を惨殺された男と、その復讐を手伝う新山という男(セルフリメイクでは女性)との依存的な関係と奇妙な道程を辿るお話。
(1998年オリジナル)
当時隆盛だったVシネマのフォーマットな作品でありながら、復讐劇のドロドロさよりも、運命の逆転や物語の輪転を利用して、復讐そのものの空虚さを語るような、フィルムノワール的な味わいがあり、シナリオの美しさが光る作品という印象でした。
物語の短さが快活に感じる部分と、淡泊に感じる部分があり、Vシネマのスピード撮影の影響もあると思いますが、若干雑に見えてしまう感覚も残りますが、荒唐無稽ないわゆるヤクザがらみのガンアクションに留まらない映画としての個性は強いです。
哀川翔X香川照之さんの名演に、柳ユーレイさんなどの配役の妙もあり、個々の配役が色濃く個性が発揮されていて、印象に残りやすいのもありました。
終盤の部分に触れますが、当時の都市伝説的なリアルな殺害を撮影したスナッフビデオの裏流通にまつわる展開になることと、数式や輪転の効果もあって、時世的な過激さと曖昧さが混ざり合って、独特な後味として残すことに成功していると感じました。

(2024年セルフリメイク)
フランスを舞台にしていることと新山が塾講師から精神科医に変更され、精神科医と患者というバディで復讐を完遂しようとする流れは、新山の真意は終盤まで明かされないものの、関係性としては依存になりやすく、台詞や辻褄合わせの展開からも、より現実よりの分かり易い映画に変容しているところが散見されていて、オリジナル版を知っているとその味わい深さは若干薄まったと感じてしまいました。
新山を演じる柴咲コウさんは切れ味はあるし、フランス語のナチュラルさも不自然は全くないのですが、フランス語翻訳のせいか脚本そのものも問題かは不明ですが、台詞そのものが、行動の過激さに反比例して、ソフトに感じられるところと、フランス人俳優陣の演技までも、少し没個性に感じてしまう部分もあり、物足りなさが残りました。
例えば、幽閉した容疑者に対して、亡くなった娘のビデオを見せるシーンでも、オリジナル版では重いブラウン管テレビを運び、ビデオテープをセットするプロセスに意味があるのですが、リメイク版ではその行為や動画そのものが演出の過程でしかなくなっていて、終盤にある娘の殺害の目的そのものが変わってしまうことに、このビデオを見せるシーンの意味合いが軽くなってしまうことなどもあり、オリジナル版の感想で触れた「フィルムノワール的な味わい」をより現実的な犯罪の復讐に置き換えることで、シーンを似せてつくっていても、違う味わいの内容になってしまうことが、少しマイナスに働いているように感じました。
印象に残るシーンは全てオリジナルにあるものなので、オリジナルを知らなければ、映画自体良さはより感じられるものの、オリジナルの補完以上に現代のリアルよりのシナリオが仇となっているのは否めません。

 『夏を終わらせる儀式』
『夏を終わらせる儀式』