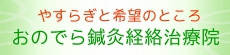今回は、現在人類が得ている有名な発見や知識の中には、実はアマチュア科学者と呼ばれる人々によってもたらされたものが結構多くあるというお話。
なぜそのような事態がたびたび起こるのか。
そこにはアマチュアならではの立ち位置というものも大きく関係しているようである。
科学の世界においてアマチュアとは、教育機関できちんとその専門分野を修めていない人々のことをいう。
大学の学位、それも一般的には博士号を持っていないと、権威ある科学者からはアマチュアとしか見られない。
例え、一つの分野でノーベル賞を受賞するほどの成果を挙げたとしても、別の分野ではアマチュア扱いされるのである。
例えばルイス・アルバレスがまさにいい例だという。
彼は素粒子理論で1968年にノーベル物理学賞を受賞した人物である。
その10年後、地質学者である息子ウォルターと共同研究を行い、恐竜が絶滅したのは巨大隕石が地球に衝突したことが原因だったとする説を唱えた。
科学者たちははじめこの説を一笑に付した。
ルイス・アルバレスがその分野の専門教育を受けていないことが分かると、一層疑いの目を向けた。
しかし、衝突があったと思われる6500万年前の地層に高濃度のイリジウムが含まれているという科学的根拠と、その後ユカタン半島沖の海底に巨大クレーターが発見されたことからその説は認められるようになったという。
(イリジウムはマントル中には高濃度存在すると考えられているが、地球の表層・地殻にはほとんどないレアメタルである。しかし、隕石中には多く含まれることから、この物質が存在するところは隕石が落ちたか、地球深部由来のものと判断される)
恐竜絶滅説を最初に唱えた人というのも十分すごいが、彼は本書の主人公の1人ではない。
本書では10人のアマチュア科学者の業績が紹介されている。
その10人とは、
〇遺伝学の基礎「メンデルの法則」を発見したグレゴール・ヨハン・メンデル
〇レビー彗星を発見したデイビッド・H・レビー
〇地球―恒星間の距離を測る方法を見出したヘンリエッタ・スワン・リービット
〇酸素を発見したジョセフ・ブリーストリ
〇「ファラデーの法則」を発見したマイケル・ファラデー
〇電波望遠鏡を作り電波天文学のパイオニアとなったグロート・リーバー
〇今や世界に無くてはならない通信衛星の発案者アーサー・C・フランク
〇近代考古学の先駆者であり、第三代アメリカ大統領・「アメリカ独立宣言」の起草者でもあるトーマス・ジェファーソン
〇ティラノサウルスの全身骨格を発見したスーザン・ヘンドリクソン
〇細菌感染症の治療法として注目されるバクテリオファージの発見者フェリックス・デレル
である。
どれも一度は聞いたことのある業績の数々であり、中には学生時代に習った法則まである。
それらがアマチュア科学者によってもたらされたという事実はなかなかに衝撃的である。
もちろんどの人も全くのド素人ではなく、それなりの専門知識を有したうえでの数々の発見なのだが、プロが研究で結果を出すことが求められ、壮大な分野に目を向けがちになることに対し、アマチュアはそうした縛りがない分、自由な発想でニッチな分野に取り組みやすいというメリットがあるという。
ノーベル賞に絡んで、基礎研究についてよく言われることであるが、やはり科学者には自由に研究に没頭できる環境を与えることが大きな発見を見出す近道なのかもしれない。
今回はその10人の中からティラノサウルスの全身骨格を発見したスーザン・ヘンドリクソンを紹介してみたい。
それは1990年8月12日のことだった。
スーザンはサウスダコタ州の岩地を5キロ歩いてきたところだった。
2週間前に遠くに荒れた砂岩の崖を見つけ、妙に気になっていたのである。
本当は民間の化石採集会社、ブラックヒルズ地質学研究所はトリケラトプスを発掘しに出かけるところだったが、おんぼろトラックのタイヤがパンクしたために行けなくなったために、この機にと思い立ちやってきたのだった。
スーザンはまず崖下を調べた。
零れ落ちた化石がないかどうかを探すためだ。
化石があればその上方のどこかにも埋まっている可能性はぐんと高くなるからだ。
彼女は目ざとく小さなかけらを見つけた。
そして崖を調べてみると、地面から3mほどのところに大きな椎骨3個と大腿骨1個が見えた。
彼女はその形状からTレックスだと思ったが、同時にそんなはずはないと否定する思いも感じたという。
それまでTレックスは11体しか見つかっていなかった。
しかも、完全体は全くなかったのである。
初めてTレックスが発掘されたのは1902年で、その後1905年、1907年と発見され、いずれも恐竜化石ハンターとして名の知られたバーナム・ブラウンによるものだった。
それから1966年までは発見されていないという希少なものだった。
そもそも「恐竜」が関心を持たれだしたのは1840年代のことだという。
それ以前にも化石は見つかっていたが、恐竜のものだとは分かっていなかったとのこと。
「恐ろしく大きなトカゲ」を意味する「dinosaur(恐竜)」という言葉を初めて用いたのは1841年、イギリスの解剖学者リチャ-ド・オーエンだった。
古くは1677年に、おそらくはメガロサウルスの大腿骨の膝関節部分と思われるスケッチが残されており、それ以降も数々の骨が発掘されてはいるが、この時までは単に「大きな生き物の骨」という認識でしかない。
人類における「恐竜史」の始まりである。
数々の化石が見つかると、次第に進化論をめぐる論争も活発になっていき、やがて一般の中にも恐竜ブームが巻き起こってきたのだった。
しかし、完全体で見つかる化石はなかったために、初期の頃の恐竜の想像図は、後に研究が進み導き出されたものからはかなりかけ離れたものだったようだ。
それでも、太古にとてつもない大きさの恐竜がこの地球上に存在していたという事実は、人々をワクワクさせたに違いない。
化石を見つけるにはどうやら特殊な才能が必要なようだ。
ある程度このような場所で見つかりやすいというのは経験値が教えてくれるだろうが、それだけではなかなか見つからない。
いわゆる「鼻が利く」能力が必要なようだ。
Tレックスを最初に見つけたパーナム・ブラウンはまさにそのような人物で、彼は「恐竜の死骸の臭いを嗅ぎつけている」と言われていたらしい。
そして、スーザン・ヘンドリクソンもその1人であった。
彼女の発見がいかに希少で貴重なものだったか。
そもそも化石がほぼ完全体で見つかるということ自体が極々まれだという。
まず、死体が捕食動物に見つかれば途端にその身体はバラバラにされる。
川の流れにつかれば骨は削られ原形をとどめない。
堆積物には押しつぶされ、地殻変動によって地表まで押し上げられたとしても、その過程で地層のズレによってバラバラになる。
運よく地表に現れたとしても古生物学者の誰かに見つけられなければ風雨に侵食され、これまた原形をとどめることはないだろう。
しかもその完全体が食物連鎖の頂点に立つTレックスであればなおさらである。
彼らは餌となる草食恐竜に比べれば圧倒的に個体数が少ないのだ。
彼女の発見に際し、トラックのタイヤのパンクという偶然が重なったことは事実だが、そのTレックスが埋まっていた崖に彼女以外には目をつけていなかったことを考えると、彼女の業績がいかに大きいものであったかが分かる。
彼女が所属するブラック・ヒルズ地質学研究所の所長のピーター・ラーソンもこの埋まっている化石はTレックスのものと判断した。
彼はその化石に「ティラノサウルス・スー(スーザンのス―)」と名付けた。
本当であれば彼女の偉大な業績は華々しく称えられただろう。
しかし、この「スー」はその後裁判闘争の火種となる。
土地の所有者とはあらかじめ何かが見つかれば謝礼を渡すことで契約は成立していた。
しかし、原住民族の保留地だったことで、原住民「スー族」がブラックヒルズに対して「スー」の返還訴訟を起こしたのである。
その後の経過は結構複雑だったようだが紙幅の関係上割愛する。
結論から言うと、「ティラノサウルス スー」は土地の所有者に返還され、彼はオークションにかけて売却した。
「スー」は836万ドルという高額で売られ、シカゴのフィールド自然史博物館が手に入れ、2000年5月から展示されることとなったのである。
当のスーザン・ヘンドリクソンはTレックスを見つけて間もなくブラックヒルズを去っていた。
彼女はあの「インディージョーンズ」に例えられるような人物で、本当に冒険好きで世界をめぐっているという。
フロリダでは海に潜って水族館の標本を採る仕事で数々の新種を発見し、沈没船を引き上げるサルベージダイバーとしても働いた。
ドミニカ共和国では海洋考古学調査にも参加したし、鉱物の発掘では世界に6体しかないとされる琥珀に閉じこめられた完全体の蝶を3体も見つけた。
そんな彼女はしばらくブラックヒルズで落ち着いていたのだったが、再び冒険の虫が騒ぎ出し、自分が見つけた「ティラノサウルス スー」に頓着することなく世界に向けた出発したのであった。
ちなみに、彼女も一度は大学に入り、学位をとることを目指したこともあったが、それをとることの意味を見出せずやめている。
しかし、崖に埋もれている骨を見て即座にTレックスの骨であると判断できるほどの豊富な知識は身につけていたのである。
彼女は考古学調査には「学位」はむしろ邪魔であるとさえ感じているようだという。
詳細は是非とも本書をお読みいただきたいが、どうだろう。
実にかっこいいではないか。
彼女はティラノサウルスに「スー」の呼び名がつくことすらも本意ではなかったという。
名誉欲は全くなく、純粋に自らの興味があることに没頭し、行く先々で多くの実績を残して、そしてまた次の場所へと旅立つ。
そういう彼女だからこそ「ティラノサウルス スー」は見つかったのだと思う。
2026年の締め始まりに偉大なアマチュア科学者たちに出会ってみてはいかがだろうか。
前回取り上げた「処方カスケード」は、処方された薬の副作用を医師が「新たな病状」と誤認して新しい薬が処方されるというもので、「ポリファーマシー(害のある多剤併用)」は複数の医療機関を受診することで生じやすくなる薬害であることを紹介した。
それらは医療者側も患者側も全く意図しない中で起きる状況だが、今回は患者がその弊害を半ば知りながら薬の過剰摂取(オーバードーズ)についついはまり込んでいく状況を取り上げてみたい。
日本では精神科の患者に対する多剤大量処方が問題となり、2014年度からは一定数を超えた処方箋の診療報酬が減額されることとなった。
それによって、むやみやたらと大量に処方されることがある程度予防されることになったことは喜ばしいことだろう。
しかし、2010年に原因不明の死亡を司法解剖した約3000人から医薬品(28%)やアルコール(22%)の検出が多く見られたという(医薬品の内訳は睡眠薬10%、精神神経用薬10%等)。
そうした実態が現在ではどれほど改善されているのか資料を持たないが、あるサイトではその後も大量処方を繰り返す医者が中にはいると報告されていたし、オーバードーズという言葉が一般にも認識されるほど社会的問題化してきているのが実態である。
アメリカでは11年連続で過剰摂取による死亡が上昇しており、驚くことに原因薬物は一般医薬品や違法薬物ではなく、処方箋医薬品が半数以上を占めているという。
2010年には38329人が薬物過剰摂取で亡くなり、その原因薬物1位はオピオイド系の鎮痛剤で16651人、2位はベンゾジアゼピン系の鎮静催眠剤で6497人、3位は抗うつ剤で3889人となっているとのこと。
なぜそのような事態となるのか。
それは大手製薬会社による副作用の隠蔽や、処方した医師に対して奨励金を支払う、適応のない病気に対してもマーケティングを行うなど違法な販売方法をとることで販売実績を大幅に上げたことによって生じている。
彼らはそれらの違法行為に対し罰金を支払っているが、それ以上に儲けの方が大きいということだろう。
正規に処方された薬による死亡が、違法薬物による死亡よりもはるかに多い。
そんなめちゃくちゃなことがあるだろうか。
同様の傾向はイギリスでも起きており、英米では交通事故の死亡者数よりも上回るという。
個人的にはそうした大量販売を進めたい製薬会社、処方すればするほど儲かる医者、制度的な制限をあまり進めようとしない国の姿勢などが、若者たちにオーバードーズが広がりやすい素地となっているように思われてならない。
現在SNS上では「つらくてまた飲んでしまう」「明日から学校。死にたい気持ちをごまかした」などという投稿とともに大量の薬の画像を挙げる若者が増えているのだとか。
社会問題化となっている「オーバードーズ」とは多幸感を得て精神的な苦痛から逃れようと、医師から処方された薬やドラッグストアで買える咳止め薬などを大量に摂取することを言う。
そして、過剰摂取による薬害は時に命をも奪ってしまうのだ。
以下はその主な症状である。
〇意識の変化: 意識消失、または混乱状態になることがある。
〇呼吸困難: 薬物の種類によっては、呼吸が抑制されることがある。
〇激しい嘔吐: 薬物の過剰摂取により、吐き気や嘔吐が引き起こされる。
〇心拍数の異常: 心臓のリズムが乱れる(不整脈)。
〇幻覚や錯乱: 特にコデインやデキストロメトルファンを含む薬物の過剰摂取では、幻覚や興奮状態が現れることがある。
〇肝臓や腎臓への負担: 大量の薬物が体内に入ることで、肝臓や腎臓に深刻なダメージを与える可能性がある。
NHKのWebリポート(https://www.nhk.or.jp/shutoken/wr/20210701.html)が伝えるところでは、リアルの世界での生きづらさに悩む若者が、SNS上でオーバードーズのことを知って自らその世界に入っていくとのこと。
そこではリアルの世界で生きづらさやオーバードーズした際の感覚などが共有され、自分の「居場所」であることが実感されるようである。
また、多くの「いいね」が付くことで承認欲求が満たされ、より大量のオーバードーズをする人が崇め奉られるという。
下記の表は2014年以降の薬物依存で治療を受けた10代の若者がどのような薬物を使用したのかを表したものだが、ここ数年で最も多くを占めていた危険ドラッグから市販薬に変化しているのが分かる。
これはこれまで以上に危険な状態ではないだろうか。
使用している本人たちには違法でないだけに危険の認識も低いだろうし、市販薬であるために気軽に手に入りやすい。
反社勢力やその予備軍と思しき者たちとの接点を持たずに手に入れられるというのは非常にハードルの低い入り口になると思われる。

市販薬とはいえ、咳止めや風邪薬には麻薬に似た成分が含まれていることもあり、中にはほかの薬物と比べても依存性が強いものもあるという。
単に依存性が高くなるだけでなく、市販薬に含まれるカフェインの大量摂取により致死性不整脈やアセトアミノフェンによる肝不全が原因で亡くなるケースも少なくないとのこと。
では、このような実態をどのように変えていくべきなのか。
リポートではオーバードーズをしている本人や家族の話なども出ているので是非お読みいただきたいが、基本的には今の若者が抱える生きづらさを理解するところからが始まりなようである。

国立成育医療研究センターが715人の児童・生徒を対象に行った調査では、一週間のうち「死にたい」「自分を傷つけたい」と思ったことがあると答えたのはおよそ4人に1人だという。
思春期に「死」を意識するのはありがちだが、年単位ではなく、週単位でそのような思いを抱えているのが4人に1人とはあまりにも多いだろう。
いま日本では7人に1人の子供が貧困に陥っていると言われている。
そうした経済状況も原因の一つであろうし、「自己責任」や「勝ち組・負け組」、「いじめられる側にも原因がある」など殺伐とした価値観が蔓延していて、大人でさえ息苦しくなっているのではないだろうか。
リポートではオーバードーズに陥っている子に対し、それを否定してはいけないと言っている。
もちろん、オーバードーズ自体早く辞めさせた方がいいが、それを否定するだけでは子供はネットからの情報の方が「正しい」と思っているので、「結局親は理解してくれない」と思われるだけだと。
オーバードーズをどうやめさせるかではなく、孤立している人たちが抱える苦しみにどう気づき、支えていくか。
周囲の人がどう寄り添っていくのかを考えなければならないと結んでいる。
リポートに登場する人には30代の既婚男性もいた。
決して10代の若者だけではないのだ。
あなたは生きづらさを抱えてはいないだろうか。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
「刺さない鍼」で快適な治療を、
「小野寺式リリース」で癒しを提供します
盛岡・西青山町の おのでら鍼灸治療院
URL: http://www.onodera-shinkyu.com/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
「処方カスケード」という言葉をご存じだろうか。
カスケードとは「小さな連なる滝」を意味している。
処方されたある薬による副作用が新たな病症として誤認され、その治療として別の薬が処方される。
そしてその薬によってまた新たな副作用が別の病症として誤認され…という連鎖があたかも小さな滝の連なりのようであることから生まれた言葉のようである。
一方、「ポリファーマシー」とは、複数の医療機関にかかって、足し算的な処方がなされると、必要以上の薬や不必要な薬が処方されやすくなる。
複数を意味するポリと、調剤のファーマシーからなる語で、「害のある多剤服用」を意味するという。
この「害のある多剤服用」は単純に薬の数が多いということではないそうだが、有害事象を引き起こす事例はやはり数の多さに比例するとされており、薬の数が6種類を超えると発生頻度が大きく増加するという。
もちろん、適正な薬の処方が6種類以上になることもあるし、6種類以下の処方でも有害事象が発生することもあるというので、「処方内容が適正かどうか」が肝心とのこと。
薬の副作用を別の病状と誤認し新たな処方がなされる「処方カスケード」。
複数の医療機関にかかることで足し算的に時に不必要な処方がされることで「害のある多剤服用」をしてしまう「ポリファーマシー」。
どうしてこのようなことが起きるのか。
一つにはすでに症状が安定した、あるいは治癒していて必要となくなった薬が漫然と処方され続け、無意味に服薬し続けることで有害事象が生じることがあるという。
また、処方された薬を患者側がきちんと服用していないにも関わらず、医師がそのような状況を把握できずに処方薬の効果が低いとして増量や処方薬の追加などによるものもあるという。
さらには、複数の医療機関にかかっているケースで、かかりつけ薬局やお薬手帳がうまく活用されていない場合に起こりやすいとのこと。
高齢化に伴い複数の医療機関に通っている人の割合は増え、シニア世代では半数以上が2か所以上の医療機関に通っている。
また、認知機能の問題などで服用の仕方に問題も生じやすい。
あるいは加齢に伴う生理的な変化によって一般成人よりも薬物への反応や効果の度合いが異なることも有害事象を引き起こす原因となりやすい。
症状としては軽いめまい、ふらつきから、肝機能障害や低血糖を引き起こすもの、果ては死亡に至るものまであるという。
治療のために薬を飲んで死亡するなど本末転倒も甚だしい。
薬の副作用が別の病状と誤認され、新たな薬が処方される事例にはどのようなものがあるだろうか。
あるサイトでは以下のようなケースが挙げられていた。
〇降圧薬による咳に抗菌薬が処方される
〇抗精神病薬による薬剤性パーキンソニズムにパーキンソン病治療薬が処方される
〇認知症治療薬(コリンエステラーゼ阻害薬)による尿失禁に抗コリン薬が処方される
〇鎮痛薬による高血圧に降圧薬が処方される
〇利尿薬による痛風に痛風治療薬が処方される
〇降圧薬や抗菌薬などによる吐き気にメトクロプラミド(吐き気止め)が処方される
〇抗菌薬による不整脈に抗不整脈薬が処方される
〇躁病などの治療薬による薬剤性パーキンソニズムにパーキンソン病治療薬が処方される
〇吐き気止め)による薬剤性パーキンソニズムにパーキンソン病治療薬が処方される
もちろん、薬の素人が注意を促すまでもなく多くの医者や薬剤師の方々はそうしたことも念頭に置いて処方されているだろうが、現実に「長年飲み続けた多くの薬をやめたらシャキッとして元気になった」人がいるのも事実である。
素人ではあるが、何らかの服薬をしている人に何かの症状が出た場合、医者や薬剤師に「これは薬の副作用でしょうか?」と一言尋ねるだけでも防止策になるのではないだろうか。
薬が体にとって基本的に異物であることは間違いない。
正しい使い方で上手に健康を維持していきたいものである。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
「刺さない鍼」で快適な治療を、
「小野寺式リリース」で癒しを提供します
盛岡・西青山町の おのでら鍼灸治療院
URL: http://www.onodera-shinkyu.com/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆