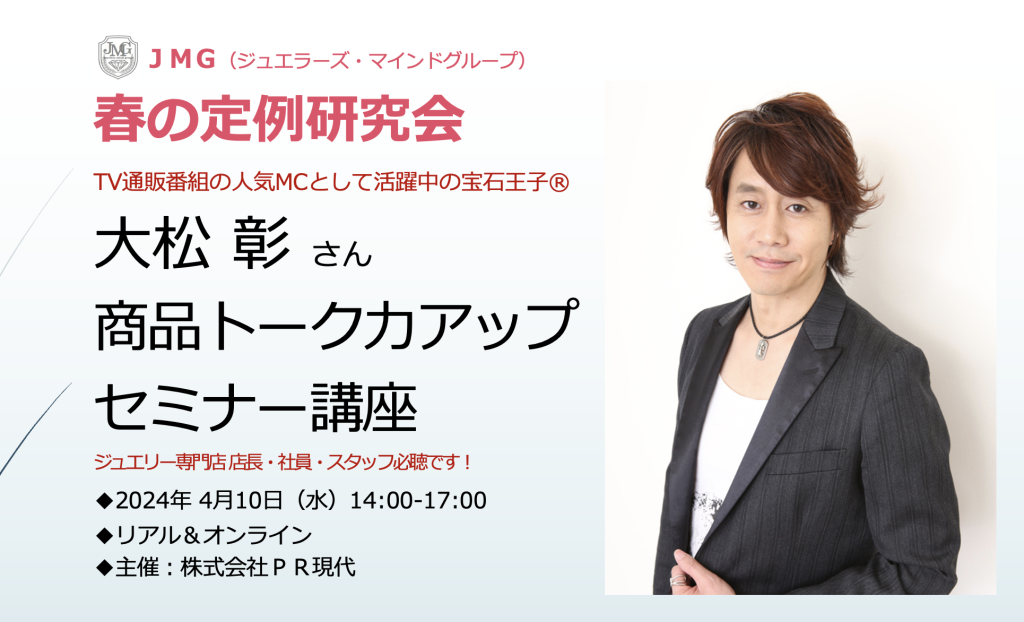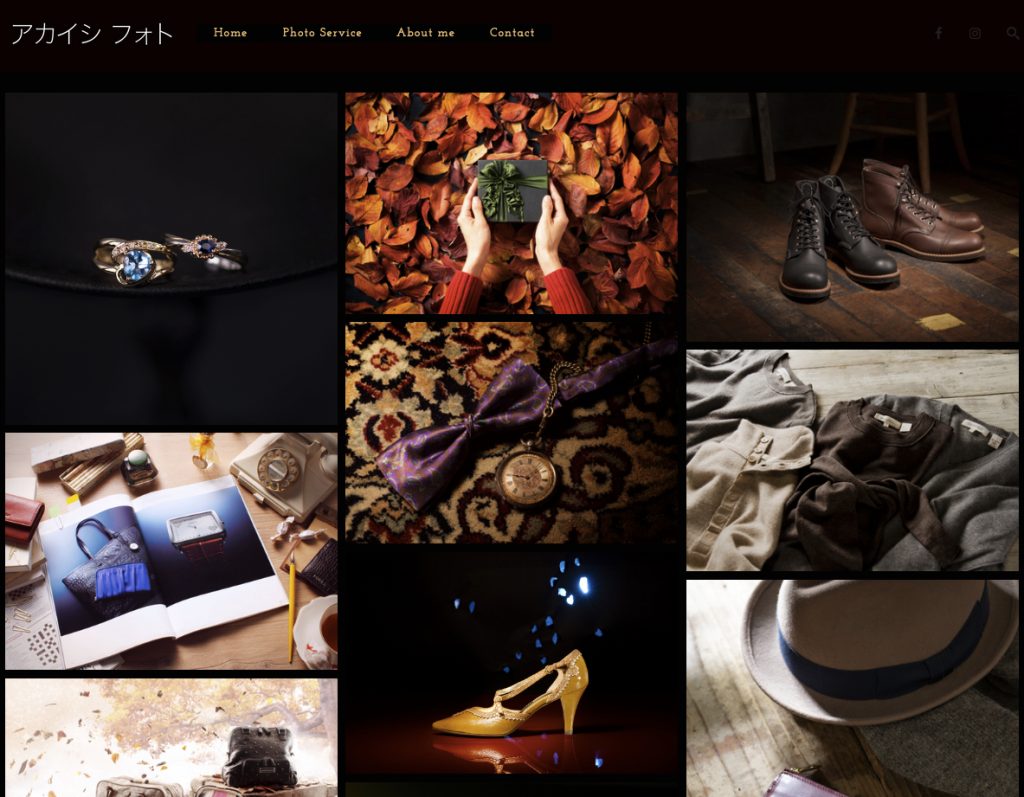こんにちは、しもじんことPR現代の下島です。
今回は6月12日(水)に開催いたします、
JMG夏の定例研究会「橋本佳代 講師による講演会
『ポンデュプレジール』ファン客創造マーケティング 」の情報です。
オンラインとリアルを融合したマーケティング成功店
今回のJMG定例会で講師を務めていただく、JC1級の資格をもつジュエラー橋本佳代さん。
以前、ジュエリーコーディネーターの勉強会「JCヌーボー」でご一緒させていただき、2028年ジャパンジュエリーフェア(JJF)ではパネラーもお願いさせていただきました。
昨年には(株)ジュリルを設立され、オーダー、リフォームジュエリー、そしてオリジル商品の販売などをオンラインとリアルを組み合わせて展開する同社のマーケティング戦略を紹介していただくことになりました!
地元の四日市という商圏にとらわれず、全国に多くのファンをもつ同店はオンラインとリアルを融合させたグッドスモールショップの成功店と言えると思います。
◎「あなたの物語にジュエリーを」という明確なメッセージ性。
◎特徴のある商品づくり、ハイセンスなオーダー、リフォーム提案。
◎オンライン受注会により、ファンとの関係性をより強化。
ジュエリーを通じて、お客様の人生に物語を届けたいというメッセージを、オンラインを中心にさまざな取り組みで発信しています。
どのお店様もホームページやLINE公式アカウントを持つようになりましたが、有効に運用されている方は意外と少ない状況です。同社の取り組みから多くのヒントが得られると思い、今回の講演会を企画いたしました。
『ポンデュプレジール』におけるファン客創造マーケティング
そこでPR現代 が主宰する宝飾小売業のマーケティング実践研究会JMG(ジュエラーズ・マインドグループ)は、6月12日(水)、「JMG夏の定例研究会」にて、「橋本佳代 講師による 『ポンデュプレジール』ファン客創造マーケティング 」をオンライン&リアルで開催することにしました。
当日は、(株)ジュリル代表である、JC1級ジュエラー・橋本佳代さんを講師に迎え、
オーダー・リフォームジュエリーの実際をはじめ、各種SNSでの情報発信(HP、YouTube、LINE運用のポイント)、YouTubeライブ、オリジナル商品の販売・今後の展望、夢 などをご紹介いただきます。
◎オーダージュエリー、ジュエリーリフォームをさらに強化したい方
◎ホームページや、ブログ、LINEなどを活用し自店のファン客を増やしたい方
◎ユーチューブを活用したオンライン受注会のやり方を学びたい方
ぜひ、この機会に一緒に学びましょう。
講師の橋本さんには当日会場でご講演いただけることになりました!
開催形式はリアル&オンラインのハイブリット型です。
これからの宝飾店における、ウェブとリアルを融合したファン客づくりを学ぶことができる実践的な内容です。
多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
◆特別講演会(オブザーバー参加大歓迎)◆
『ポンデュプレジール』におけるファン客創造マーケティング
・日時:2024年6月12日(水)14:00-17:00
・開催形式【リアル(会場:PR現代)】または【オンライン(ZOOM ウェビナー)】
・主催:株式会社PR現代・JMG
プログラム
第1部14:00-14:50 スタートアップ
◆JMG会長 花島路和 宝飾専門店が今大切にすべきこと
◆JMG顧問からの最新情報トピックス(業界動向:深澤裕/DX:佐藤善久)
第2部15:00-17:00 講演会
◆『ポンデュプレジール』におけるファン客創造マーケティング
講師:橋本佳代氏
参加料
○JMGメンバー:無料(1社5名様まで参加可能)
○ 一般(オブザーバー):1社 11,000円(税込・累計3回3名様まで参加可能)
・全国の宝飾小売店(商圏により参加できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください)
お問合せ
株式会社PR現代 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-1-21 ヤマジョウビル4F
TEL 03-3639-1253
お申し込みは、こちらからお願いいたします。
多くの皆さまのご参加をお待ちいたしております。
JMGは宝飾小売業のマーケティング実践研究会です
(株)PR現代が主催する「JMG(ジュエラーズ・マインドグループ)」は花島路和氏(ジュエリーハナジマ代表)を会長に、46社が加盟する宝飾小売業のマーケティング実践研究会です。一商圏1社(市区村ごと)が加盟でき、隔月での定例勉強会や情報交流、個別相談、WEBや販促物などの会員割引制作などをを行なっています。詳しくは、こちらの専用ホームページ をどうぞご覧のうえ、お気兼ねなくお問い合わせください。