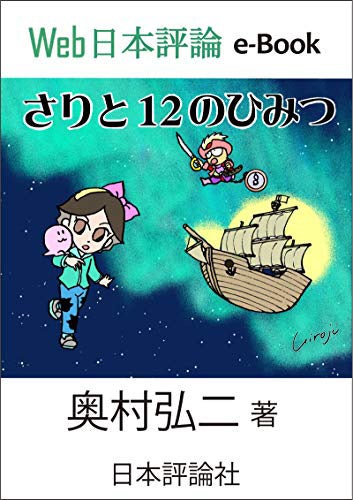解説編に登場するマクスウェルは19世紀の物理学を代表するスコットランド生まれの物理学者で、電磁方程式であまりにも有名な人です。
24歳のとき、ファラデーの電場や電気力線を数式化する論文を発表し、26歳のときには、ファラデーとの間で初めての書簡をやりとりしています。
ファラデーは自分がマクスウェルの書いた数式を理解できないことをわびつつも、磁気作用が伝わるのに時間がかかるかもしれないということを実験しようと思っていると手紙に書き、マクスウェルをびっくりさせています。
このファラデーの指摘が、後になって、マクスウェルの電磁方程式が電磁波の存在を予言することになる萌芽だったといわれています。
マクスウェルの方程式はそれまでばらばらに知られていた電気・磁気の現象を4つの方程式にまとめたものです。それらを組み合わせて解くことで、電気・磁気の作用が波となって時間をかけて伝わることが示されたのです。
その波(電磁波)がヘルツによって実験的に発見されたことで、マクスウェルの成功は揺るぎないものになりました。
19世紀の物理学者たちは、マクスウェルの成功によって、物理学者の仕事が変わると考えました。
マクスウェルの方程式は物理現象の最後の謎を解き明かした最終方程式であり、その後物理学者には応用面の仕事が残されているだけだと、誰もが思ったのです。
実際には、19世紀末、光についてなお2つの謎が残されていました。
光速についての謎と、電磁波の放射にかかわる謎です。
しかし、当時の物理学者たちは、それは些細な謎にすぎず、実験技術の向上や理論のわずかな修正で、謎は謎でなくなると信じていました。
それほどに、マクスウェルの方程式の成功は衝撃的だったのです。
その2つの些細な謎が、いずれ19世紀までの物理学をひっくり返し、新しい物理学を生むことになるとは、誰も夢想していませんでした。
でも、これはまた別の機会に触れることにしましょう。
さて、前置きが長くなりましたが、「空の青、海の青」解説編をお届けします。
こちらは高校生以上向けの内容になっています。もっとも、興味と意欲のある方でしたら、小学生でも読んでいただいて結構です。むつかしい数式が登場しますが、わからないところは今はそのままでかまいません。
解説編にあるように、光の散乱は原子の双極子振動によって生じます。
電磁波は電場磁場の振動が伝わる波です。電磁波が原子のところにやってくると、その電場によって原子の電子が力を受けて位置がずれ、マンガの図にあるように、原子が電場方向に正負に帯電(分極といいます)します。
電磁波が通り過ぎるとき、それに伴って正負が入れかわるなど、原子の分極状態も変わり、双極子振動と呼ばれる振動が起きます。
双極子は入射光に対して垂直な平面内で振動しますが、入射光(太陽光)が偏光していないため、双極子の振動方向も様々になり、その平面内で楕円を描いてくるくると回転するような運動になります。
それに伴い、双極子の正負の電荷がつくる電場も変動し、新しい電磁波が生じて、双極子を中心に四方へ広がっていきます。
これが双極子放射です。
双極子放射は一般に楕円偏光になりますが、入射光に対して垂直な方向からそれを見ている人には、平面偏光(直線偏光)として観測されます。
平面を真横から見たら線になります。その平面内で回転する様子は、真横から見たら一本の線上を往復する単振動に見えますね。
双極子放射が散乱光の正体なので、当然散乱光は偏光しています。空からの散乱光を、太陽光に対して垂直な方向から眺めると、偏光が一番はっきりするのは、この仕組みのためです。
さて、今は原子一個からの放射光について述べましたが、空には無数の原子分子があります。原子集団からの放射光がどうなるか、調べる必要がありますね。
原子が結晶のように規則的に並んでいる場合、ある方向へ向かう放射光の道のりは、少しずつ差ができます。
光が観測者に届くときには、振動がその分だけずれた光がやってきます。それらの光が重なり合って干渉を起こすのですが、少しずつずれた光が無数に届いて干渉するときには、光は打ち消し合って消えてしまいます。つまり、放射光すなわち散乱光が消えてしまうわけです。
この場合、光は散乱せずにまっすぐ透過していきます。
でも実際には、大気の分子は密度が薄い上に、熱運動をしているので、大気の密度は場所場所により、また時間により異なることになります。これを揺らぎといいます。
この場合、原子が規則正しく並んでいるとはいえませんから、先ほど述べた干渉で打ち消し合うということも起きず、散乱光が生じます。
大気中の細かいチリも光を散乱していますが、今述べた事情により、例えチリがなくても、大気は光をしっかり散乱します。
水や氷のように、原子の結びつきが強く、熱運動による密度揺らぎが小さいものになってくると、放射光が干渉により消えるケースに近づきます。
ただし、これは程度の問題です。
どんなに規則正しい原子配列の結晶があったとしても、必ず熱運動による密度揺らぎがありますから、散乱光が完全に無くなることはありません。つまり、完全に透明な物体は存在しない、ということです。
というわけで、空の青色は正確にいうと、大気中のチリと、大気の分子の密度揺らぎによる散乱光の色です。
高校の教科書ではそれを(細かいことには目をつぶって)「大気の分子とチリによる散乱」といっているんですね。
ところで、双極子放射の強度を示す式は、放射方向の角度も考慮に入れて「レーリー散乱」として知られています。が、このマンガでは、もっと単純に、放射される散乱光の全強度の式で考えています。
本質的な内容は変わりませんから、単純な方で進めましょう。
双極子は固有振動数を持ちますから、それと異なる振動数の入射光が来た場合は、双極子は強制的に振動させられることになり、エネルギー効率が悪くなります。
それが散乱強度や物質の屈折率の波長依存性につながるのですが、理論の詳細はここでは触れないで起きます。(数式を扱いますので、テキスト形式ではちょっと説明しづらいのです)
興味を持たれた方は、参考文献にあげたような電磁気の本を読んでいただければと思います。
例えば「ファインマン物理学」では、基本的な原理から、光の散乱強度Iが(ωの4乗)/{(ω0の2乗ーωの2乗)の2乗)}に比例することが証明されています。
ωは角振動数と呼ばれる量で、振動数fに角度2πをかけたものです。振動数の親戚だと思ってくださって結構です。ω0は双極子の固有角振動数、ωは入射光の角振動数です。
入射光が可視光の場合、気体分子の双極子振動の固有角振動数ω0は、可視光の角振動数ωに比べてかなり大きいので、p7にメモしたように、散乱強度は近似的にωの4乗に比例することになります。
つまり、振動数の大きい紫や青の光の散乱強度は、他の光に比べてかなり大きいのです。
p6p7の数式は、これらの関係式をなじみのある振動数fの式に書き直してありますが、式の本質は同じです。
振動数が大きい方が散乱しやすいということがわかると、次のような疑問を持たれる方もあると思います。青より紫の方が散乱されやすいのだから、空の色は紫色じゃないのか?
これは分光器などで太陽光のスペクトルを見てみるとすぐにわかります。スペクトルの中で、紫色に見える部分は、青に見える部分に比べて非常に少ない。だから、散乱光はもともと含まれる量の多い青が目立つことになります。
さて今度は海の青ですが、だいたいの説明は本編の解説文に書いたとおりです。
海の色は散乱光の色ではなく、水の色です。せっかくですから、もう少し詳しく見てみましょう。
さきほど書いたように、水や氷の分子も散乱を起こすことは起こします。揺らぎのまったくない水や氷は存在しないからです。さらに微粒子も含まれますから、本質的には大気の状況と変わりありません。要は程度の問題です。
もし、海の色が空と同じく散乱の色だったとしたら、深い海に潜って上から降り注ぐ光を見たら、夕焼け空と同じように真っ赤に見えなくてはいけませんね。やってくる途中で散乱により青い光が抜けてしまうからです。
実際には深く潜っても海は青い。
もちろん、水にコロイド粒子などの微粒子を入れた実験では、本編p1のように、まさしく夕焼け空と同じ赤色を見ることができます。
水は可視光に対しほとんど透明ですが、可視光のさまざまな波長の光に対する吸収率は異なり、赤い光は青い光に比べてかなり吸収されます。
専門書のデータを見る限りでは、水中を長い距離進む光は、選択吸収によりまず赤や橙、黄の光が吸収され、さらに緑や紫の光が吸収され、最後に青色の光が残ります。ですから、この青色は深い水、つまり海の色なのです。
リンゴの赤色、ミカンの黄色と同じ、物体の色ですね。
最後に、雲の色について。雲は小さな水滴や氷粒の集まりですが、こちらは白いし、明るい色ですね。
水滴からの散乱光は、水滴内にある分子集団からの双極子放射の重ね合わせになります。
液体は気体と違って、分子間の距離が短いので、可視光の場合は、入射光の波長のごく一部の長さの中にいくつもの分子が並びます。これらの分子は波の似たような場所に並び、似たようなタイミングで双極子振動しますから、そこから放射される光は重ね合わさった結果、大きな振幅の電磁波となります。
分子が2つで振幅が2倍の場合、振動のエネルギーは4倍になりますから、いくつもの分子がこのように振動するときに放射される光の強度はすごく大きくなります。
もっとも散乱されやすい青の光は、こうして放射強度がどんどん大きくなるのですが、水滴が大きくなってくると、その振動を打ち消す動き方をする分子が現れてきます。青い光の放射強度は無制限に増えるわけではなく、水滴が大きくなるにつれ限界に達することになります。
しかし、青の光より波長の長い光(緑や橙や赤)にとっては、青の光に対して限界に達した大きさの水滴でも、まだ余裕がありますから、放射光が重なり合って同様に強度が増していきます。
分子1個の場合は放射強度に差がある青と緑・橙・赤など他の光ですが、上に述べた仕組みで、水滴が大きくなるにつれ青い光と同程度の放射強度になることができます。
こうして、水滴から散乱される光の強度は、入射光の振動数(波長)による差がほとんどなくなり、散乱光は明るい白になります。
これが雲の明るい白色の原因だと考えられています。
大気中のチリによる散乱も、チリの大きさが大きくなってくると、雲と同様な効果が現れます。霧やスモッグなど、あるていど大きい微粒子では、青空・夕焼け効果が消え、雲のように明るい白色が支配的になります。
ところで、マクスウェルの電磁気理論は古典物理学と呼ばれ、ミクロな世界の粒子や光の振る舞いを説明できません。
原子や分子がどのような光を吸収するのか、その理論は量子力学によって説明されます。Quest2に登場したプランクや、未登場のボーアなど、たくさんの物理学者によって生み出された新しい物理学です。
マクスウェルが亡くなったのは1879年で、量子力学のさきがけとなったプランクの黒体放射理論が発表されたのが1900年。もうひとつ、光速の謎を解いたアインシュタインの特殊相対性理論が発表されたのが1905年。
マクスウェルは現代物理学と邂逅することなく去っていきました。
でも、マクスウェルの業績は死んではいません。
新しい物理学が生まれた今日でも、マクスウェルの方程式は依然として有効であり、物理現象のかなりの部分を説明できるのです。
「空の青、海の青」本編 はこちら。
※主な参考文献
本編の参考文献に同じ。そちらをご参照ください。