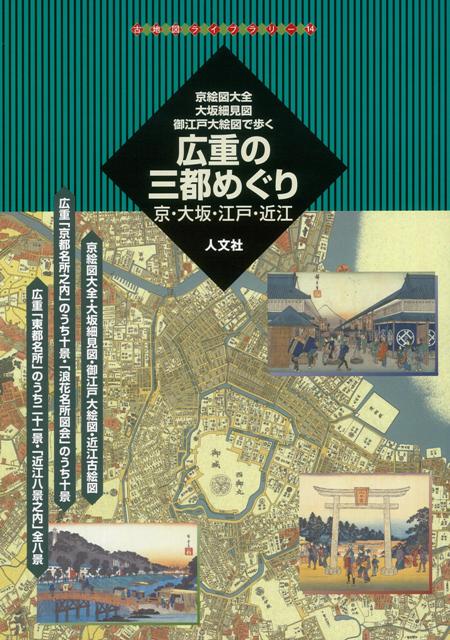ホルヘ・ボレット
リスト作品集
曲目/
1.愛の夢 第3番 S541/3 4:54
2.2つの演奏会用練習曲 第2曲 小人の踊り S145/2 3:15
3.3つの演奏会用練習曲 第3番 “ため息” S144/3 5:39
4.葬送曲 S173/7 11:32
5.ラ・カンパネラ S141/3 4:51
6.2つの演奏会用練習曲 第1曲 森のささやき S145/1 4:03
7.半音階的大ギャロップ S219 4:18
8.スペイン狂詩曲 S254 13:51
9.ワーグナー~リスト タンホイザー序曲 S442 * 16:27
ピアノ/ホルヘ・ボレット
録音/1972/08/21-24
1973/07/16* RCAスタジオA、ニューヨーク
P:ジョン・ファイファー
E:ベルナルド・ケヴィル、エドウィン・ベグレイ*
仏SONY CLASSICAL 88883717462(RCA原盤)
手元にあるのはフランスでリリースされた「PERFECT PIANO COLLECTION LA DISCO THEQUE IDEALE PIANO」と題されたボックスセットに収録されている一枚です。LP時代は発売されたことがなく、2001年に初めてCD化されました。そのため本来のタイトルは「Jorge Bolet – Rediscovered - Liszt Recital」というタイトルで発売されています。下がその時のジャケットです。
このリストの作品集を収録した1973年には「ラフマニノフによるトランスクリプション集」というアルバムも録音されているのですが、そちらはレコードで発売されました。RCAはどうしてアルバム一枚分の録音を収録していたのに発売しなかったんでしょうかねぇ。不思議です。やがて1975年からボレットはデッカと録音契約を結びせっせとリストのアルバムを録音して次々と発売していきました。まあ、RCAは発売のタイミングを逸したともいえます。まあ、この時代はRCA自体が迷走していましたからさもありなんといったところでしょう。
こういう響きはボレットの演奏するリストには適しているのでしょうか。シャープな立ち上がりと、強靭なアタックがリストに向いているからです。ボレットといえばデッカの専属のイメージがあったのですがRCAにも録音していたんですなぁ。知りませんでした。でもって、これが中々易しいタッチで最初の愛の夢からほれぼれする演奏になっています。そして驚きは、「ラ・カンパネラ」です。まあ、フジコ・ヘミングの演奏が話題になりましたが、あれはかなり個性的な演奏です。ボレットは正統派と言えるタッチの「ラ・カンパネラ」で、聴き惚れてしまいました。うーん、この一枚は掘り出し物です。