
ルイ・レテリエ監督、ジェシー・アイゼンバーグ、ウディ・ハレルソン、アイラ・フィッシャー、デイヴ・フランコ、マーク・ラファロ、メラニー・ロラン、マイケル・ケイン、モーガン・フリーマン出演の『グランド・イリュージョン』。
スゴ腕の4人のマジシャン、ダニエル(ジェシー・アイゼンバーグ)、メリット(ウディ・ハレルソン)、ヘンリー(アイラ・フィッシャー)、ジャック(デイヴ・フランコ)は、古代エジプトの「ホルスの目」が描かれたタロットカードによって呼びだされてチームを組むことになる。1年後、“フォー・ホースメン”と名乗る彼らはラスヴェガスのステージ上でパリの銀行から大金を強奪する。FBI特別捜査官のディラン(マーク・ラファロ)はインターポールから派遣されたアルマ(メラニー・ロラン)とともにフォー・ホースメンを追うが、彼らはつねに追っ手の一歩も七歩も先をいっていた。
“ミスディレクション”とは──
わざと間違った方向に誘導すること。
奇術やミステリー小説などでよく耳にする言葉。
以前、クリストファー・ノーラン監督の『プレステージ』、またエドワード・ノートン主演の『幻影師アイゼンハイム』というステージマジックを描いた作品を観て、それぞれけっこうファンもいる映画なんだけど、どちらも僕は「…う~ん」だったんです。
2本とも1度観たきりなんで内容はだいぶ忘れちゃってますが、なんというか、観終わってまず感じたのが「それ奇術じゃねーじゃん」ということでした。
ネタバレになるんであまりつっこんで書きませんが、これらはCGを使ってマジックを映像化していて、その時点でライヴやTVのヴァラエティ番組で観るような生身の人間が実際に客の前で見せるマジックとは違っていた。
これならなんでもオッケーじゃないか、と。
ライムスター宇多丸さんもラジオ番組で言ってたけど、たしかに映画とマジックって意外と食い合わせが悪いんじゃないだろうか。
ジョルジュ・メリエスの時代ならばともかく、あるいはそこまで大昔じゃなくてもまだCGが氾濫する以前だったら映画のなかで信じられないような映像に心底驚けたかもしれないが、現在の観客はなにが映っても「どーせCGでしょ」っていう目で観てるから(ヘタすりゃ、ほんとにやっててもそう言われる)、VFX(視覚効果)を使って“マジック”を見せたってなんの感動もないのだ。
なので、この『グランド・イリュージョン』に対しても、若干の不安がありました。
それでもすでに観ていた人たちの「実写版ルパン三世(※『念力珍作戦』ではありません)」という例えに、なるほど、トリックがどうとかいうんじゃなくて、そういうノリなら楽しめるかも、と思ったんで観に行ってきました。
結果的には、たしかにそのとーり!
テンポよくさくさくストーリーが進んでくんで退屈しなかったし、楽しかったです。
デヴィッド・カッパーフィールドが協力してたり、日本語版でメンタリストのDaiGoが監修をつとめてたりしてw
ただし、劇中で披露されるマジックのタネや映画のオチについて細かくツッコみだすときりがなくて、マジックのトリックの見事さで「ををっ」と唸らされる類いの作品ではないです。
どうやったのかタネ明かしされないマジックもいくつも出てくるし、CGもバンバン使ってる。
誰も「ルパン三世」の盗みのトリックに期待したりいちいち文句言ったりしないのと同様、この映画も現実に可能かどうかを云々するのは野暮というもの。

ところで、先日、伊集院光がラジオで(ラジオばっか聴いてんな俺)例の「ほこ×たてヤラセ問題」に言及していて、「“ヤラセの名人”と“ヤラセを見破る視聴者”の対決が観たい」とおっしゃってて笑いました。
んで、この『グランド・イリュージョン』では4人のマジシャンたちに対抗してモーガン・フリーマン演じるトリックの見破り名人が登場する。
そういえば「ほこ×たて」でもそういう対決やってたよね。すっごく面白かったけど、番組終了決定しちゃったようで残念です。
少なくともあのマジシャンと見破り名人の対決では、(途中まで)タネを解明して実際にやってみせていたので僕はかなり楽しめたんだけど。
ミステリー小説とマジックは切っても切れない関係があるけれど、映画には映画独自の文法、お約束を利用したトリックというものがあって、つまり映像のモンタージュによって場所や時間を錯覚させることもできるし、映画が誕生して百年以上ものあいだに作り上げられて観客も「そういうもんだ」と慣れ親しんでいるルールや常識をあえて破ることで、いままで信じてきた世界が一気に反転するような快感を得ることも可能。
たとえばM・ナイト・シャマラン監督の『シックス・センス』もいくつも伏線を張っておいて最後のどんでん返しでそれらが活きてくるように作られていたし、あれも観客がオチに気づかないようにいろいろとミスディレクションされてました。
僕があの映画が好きなのは、オチの見事さもさることながら、それ以外の親子のドラマの部分が秀逸だったからなんですが。
ほかにもアレハンドロ・アメナーバル監督の『アザーズ』、ジェームズ・マンゴールド監督の『“アイデンティティー”』、先ほどちょっとケナしちゃったノーランの『メメント』など、やろうとすれば小説でも成立するけど、それでも映画だからこそその効果が最大限に発揮できるトリックを使った素晴らしい作品群がある。
今回の『グランド・イリュージョン』もまた全篇に“ミスディレクション”がほどこされていて、事実、劇中で何度もこの単語が使われる。
そもそもこれはどういうお話だったのか。
では、これ以降さっそくネタバレがありますのでご注意ください。
あと、これまでのさまざまな「どんでん返し映画」のネタバレにもつながるので、そういうの知りたくない!ってかたはお読みにならない方がよろしいかと。
では、いきますよ。1、2…
“アイ”と呼ばれる秘密結社的な組織によって4人のマジシャンが集められる。
彼ら“フォー・ホースメン”は大々的なマジック・ショーの演目として次々とありえない方法で、あるときは大手銀行の金庫から、あるときは損害保険会社の社長の口座から大金を手に入れていく。
そして、せしめた金は観客たちにバラ撒かれる。
彼らの目的はなんなのか。
金?名声?それとも単なる愉快犯?
そもそもこの映画の主人公は誰なのか、という問題。
一見するとジェシー・アイゼンバーグ演じるダニエル・アトラスが主人公のようだが、映画を観終わったあとは誰もそうは思わないだろう。
そう、ダニエルも、そして仲間のマジシャンたちも、すべてはマジックの小道具。彼らの存在自体がミスディレクション(意図的な誤導)だったのだ。


それがわかったとき、この映画そのものが僕たち“観客”に贈られた“イリュージョン(幻影)”だったことが判明する。
最大の謎は、4人のマジシャンを集めて彼らに脅威のマジックを披露させた「5番目のホースメン」の正体。
観客は最初、それはフォー・ホースメンのスポンサーだったトレスラー(マイケル・ケイン)ではないか?と疑うが、やがて彼はカモだったことがわかり、次にマジックの見破り名人サディアス(モーガン・フリーマン)だろう、と目星をつけ、今度はインターポールからやってきたアルマではないか?と疑心暗鬼になる。


そのどれもがどうやら間違いだった。
そうなると残るはただ一人しかいない。つまりこれは「探偵=犯人型トリック」だった、ということ。「叙述トリック」の一種でもある。
「新ルパン三世」の最終回「さらば愛しきルパンよ」のオチとおなじです。
よーするに、アガサ・クリスティのある小説と同様に観客(読者)がこれまで信じてきたことをおもいっきり裏切る反則技だった。
映画ならアラン・パーカー監督のある作品を思い浮かべもする。
あの映画では後半でニューオーリンズが舞台となるが、『グランド・イリュージョン』でも中盤にニューオーリンズでマジック・ショーが行なわれる。
ニューオーリンズはフランスとかかわりが深く、またブードゥー教が盛んな地域でもある。
魔術的な土地なのだ。
偶然か意図的か、この映画の監督ルイ・レテリエとヒロインの一人メラニー・ロランはフランス人。
また、劇中しつこいぐらいに催眠術のシーンが繰り返される。
「催眠術」というのは科学的にはまったく立証されていない、人間観察と暗示によるエンターテインメントだ、と言及される。
ただし、実在のメンタリストの技にはタネがあるが、ウディ・ハレルソン演じる催眠術師メリットが何度もやってみせる技にはトリックなどない。


「催眠術というのは、この映画のなかでは普通に存在するものですよ」と僕たち映画の観客に刷り込んでいるのだ。“暗示”をかけているんである。
観客の一人がラスヴェガスからパリに瞬間移動するのも、やはりショーの観客たちがアメフト選手になったつもりで「ハルクの中の人」にタックルするのもすべてこの催眠術によるもの。
ミスディレクションと催眠術。
この二つのキーワードで勘のいい人ならオチが読めるだろう。
ディランとアルマの出会いやその後の唐突にもおもえる接近は、はたして偶然だったのか?と。
マジシャンはさまざまな手順を踏んで客の前でマジックのタネをこっそり回収するが、ミステリー小説や映画では最後にタネ明かしをするから、オチのためにわざと伏線を散りばめておく。
近づきすぎるほど見えなくなる。
これまた何度も念を押される文句だが、このもったいつけた言い回しこそがミスディレクションなのだ。
僕がこの映画に好感を持ったのは、「マジックは人を楽しませるためのもの」という大前提があったこと。
フォー・ホースメンの目的は不明だが、「犯罪」を行なう過程で彼らは観客たちをおおいに楽しませる。
映画を観ているうちに、彼らの目的は純粋に「観客を楽しませること」、それだけではないのかとおもえてくる。
そこに僕は、エンターテイナーであるマジシャンたちの矜持を見たのだ。
やがて、ストーリーはさらなる飛躍を見せる。
いにしえから存在する“アイ”という魔術師たちの組織。
フォー・ホースメンはその末裔ではないか、という超展開になっていく。
彼らは言う。「魔術を現代によみがえらせる」と。
一応申し訳程度にされていたマジックのタネ明かしがどれもおざなりだったのも、結局彼らが人々に見せていたのは「ほんとうの魔術」だったのだ、ということならばもはやツッコミも入れられない。
クライマックスで彼らが人々に告げる「信じてくれてありがとう!」という言葉に、おもわずウルッときてしまった。

そんなわけで、僕はこの映画、わりと好きなんですが、きっと「納得いかん」というかたもいらっしゃると思います。
じつのところ僕だってイチャモンはいくらでもつけられる。
フォー・ホースメンが繰り広げるマジックやFBIからの逃走劇。
100歩譲ってこれらは可能だとしよう。
あのオチについてもひとまず不問とする。
でも、「物語」としては疑問が残る。
ニューオーリンズでのショーでフォー・ホースメンは、保険料を支払っていたにもかかわらず災害で被害を受けてもトレスラーの保険会社から補償を断られた人々に、彼の口座から金を“移動”する。

僕はそれを観たときに、これは社会の不正にマジックで立ち向かう者たちの話なのかと胸がすく思いがしたのだが、それ以降このような“ねずみ小僧”的展開は鳴りを潜める。
では、彼らはただひたすら観客たちを楽しませるためだけにこのような大掛かりなマジック・ショーを行なったのか。
しかし、最後に真相が明かされる。
かつてライオネル・シュライクという有名マジシャンがいたが、サディアスによってマジックのトリックを次々とバラされたために追いつめられて、ついに水中に沈められた金庫からの脱出に失敗して消息を絶った。
じつはディラン捜査官はシュライクの息子であり、そして「5番目のホースメン」こそ彼なのだった。
ディランは父を事故死させた不良品の金庫の製造会社とサディアス、そして補償に応じなかったトレスラーにマジックを使って復讐する。
それこそが彼の真の目的であった。
…う~ん、と、どうだろうか。
けっこうスルスルッと進んでっちゃうんでなんとなく観てしまうけど、みなさんこれで納得できたんでしょうか。
僕は、最後にフォー・ホースメンが「これから世界中の戦争や飢餓、差別を消してみせます!」ぐらいのぶっ飛んだ宣言をしたってよかったんではないかと思ったんですが。
だって、この映画のなかで描かれてる彼らのマジックだって、「荒唐無稽」ということではどっこいどっこいなんだから。
それに、映画のなかでフォー・ホースメンは「魔術を悪用する者たち」について語っていたではないか。
トレスラーはまさに現実社会での「詐欺師」だ。
世のなかにはこのように「魔術」を悪用する者たちがいる。
フォー・ホースメンの真の敵はそういう奴らではないのか。
マジックは私利私欲のために使うものではなく、純粋に人々を楽しませるためにあるんでしょ?
アルマが飛行機のなかでディランに見せたささやかなカードマジック、おもわず笑みを浮かべるディランにアルマは「楽しかったでしょ?」と言う。

あれこそがマジックの真髄だったんではないか。
だけど、この映画では結局は復讐のために使われてしまう。
いきなりこじんまりした話におさまってしまうのだ。
しかも、悪徳保険屋のトレスラーはともかく、金庫の一件はマジックの実演中の事故なわけだし、サディアスにいたっては、自称・超能力者や霊能者相手ならいざ知らず、シュライクはマジシャンなんだから、そのタネをバラすというのは単なる営業妨害だろう。抗議するなり訴えるなりすりゃいいじゃん。
なぜかこの映画のなかでは、マジシャンとそのタネを明かす者はガチで敵同士なのだ。
でもそれはあくまでもショーの一環ではないか。「ほこ×たて」とおなじように。
“アイ”のメンバーに選ばれなかったことを恨んでマジックのトリックを見破ることを生業にするようになったマジシャン崩れのサディアスなど、ほんとうの敵ではないはずだ。
モーガン・フリーマンを牢屋にぶちこむのはお門違いでしょ。
だいたいトリックの見破り名人のはずなのに、この人つねにあとから解説するだけでまったく役に立ってないし。なんのためにおねえちゃん連れてヴィデオキャメラ廻してたんだよ。

そうじゃなくて、イルミナティまで担ぎ出してきたんだから、これはもっと壮大な話になるはずだったのではないか。
マジシャン=魔術師の末裔たちのほんとうの敵は、魔術を悪用する者たちだ。
それはこの映画では描かれなかったが、どこぞの国でなにやらどーでもいいニュースの影でいつのまにか国会で重要な物事が決められてしまっていることとか、振り込め詐欺とか、まさしく“ミスディレクション”によって人々の目をあざむいて悪事を働く輩のことだ。
世界から魔術を悪用する者たちを駆逐すること。
これこそが“アイ”の目的ではないのか。
ホースメンが手を取り合って中空に札束となって舞ったとき、僕はかなりグッときたんですよ。
音楽も盛り上がってよかったし。
この映画には、ただ単に「どんでん返し」でアッと言わせてやろう、というだけじゃない、マジックを観てるときは誰だって幸せだよね、っていう作り手の熱いメッセージのようなものを感じたんだよね。
エンターテインメント礼賛、というか。
作り手たちは、この映画で僕ら観客に魔法をかけようとしたんでしょう。催眠術師のメリットのように。
こういう楽しいひとときをすべての人々が味わえるように、って。
映画が現実を変える。それこそ史上最大のマジックだ。
この映画の途中まで、僕はちょっと期待していたんです。
この映画の登場人物たちが、僕たち観客に現実を変えるほどの魔法をかけてくれるのを。
作り物の投影でしかない「映画」と観客が、スクリーンを越えて交感する素晴らしいエンディングを。
ピーター・パンがティンカー・ベルの命を救うために、読者の子どもたちに「拍手」を求めたように。
惜しいなぁ。
まぁ、そんな感じでぶつくさ文句も言ってきましたが、いろいろと想像を羽ばたかせてくれるなかなか楽しい映画でしたよ。
ちなみに、ジャックを演じるデイヴ・フランコは、ジェームズ・フランコの弟。たしかに似てるね。

ジェシー・アイゼンバーグはいつものように早口で女の子からは「冷たい」と言われてるし、ウディ・ハレルソンはハゲてるし(おなじ監督による『トランスポーター』のジェイソン・ステイサムからのハゲつながりか?)、メラニー・ロランはかわいかったし、あいかわらずモーガン・フリーマンはどこにでも出てくるし。
「実写版ルパン三世」といいながらもシリーズ化は難しい作品だけど(どうやらオリジナル版にはエンドクレジットのあとにつづきがあるようなんだけど、日本版にはなかった)、気になってるかたはごらんになってみてはいかがでしょうか。
それでは、Au revouir!(ごきげんよう!)
関連記事
『グランド・イリュージョン 見破られたトリック』
『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』
『スポットライト 世紀のスクープ』
『ガルヴェストン』
グランド・イリュージョン スタンダード・エディション [DVD]/ジェシー・アイゼンバーグ,マーク・ラファロ,マイケル・ケイン

¥3,360
Amazon.co.jp
トランスポーター [DVD]/ジェイソン・ステイサム,スー・チー,フランソワ・ベルレアン
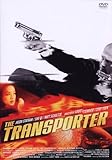
¥1,890
Amazon.co.jp
タイタンの戦い [DVD]/サム・ワーシントン,ジェマ・アータートン,マッツ・ミケルセン
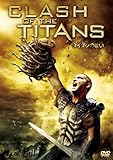
¥1,500
Amazon.co.jp
シックス・センス [DVD]/ハーレイ・ジョエル・オスメント,ブルース・ウィリス,トニ・コレット

¥4,179
Amazon.co.jp