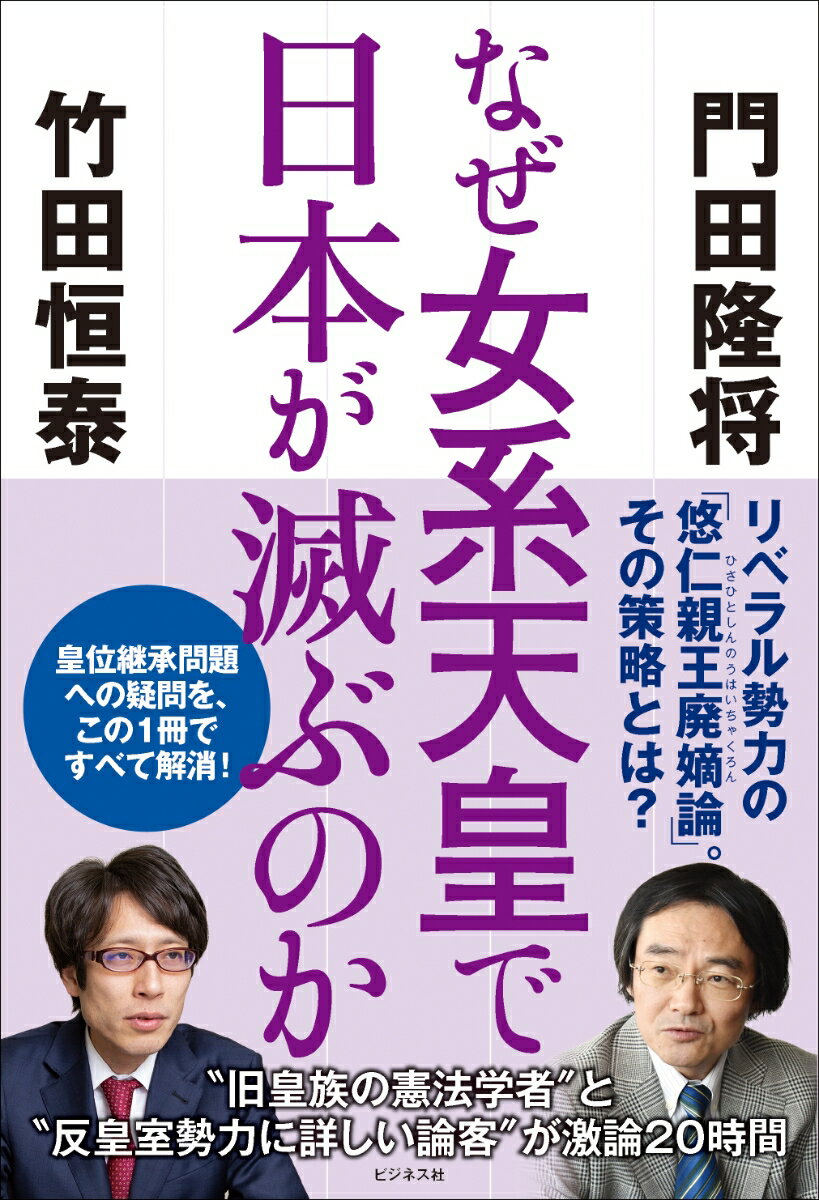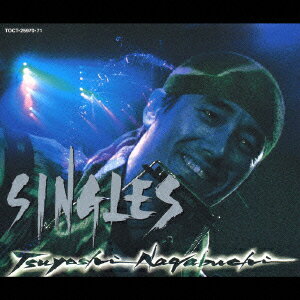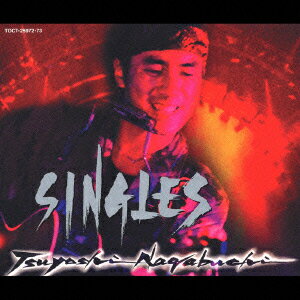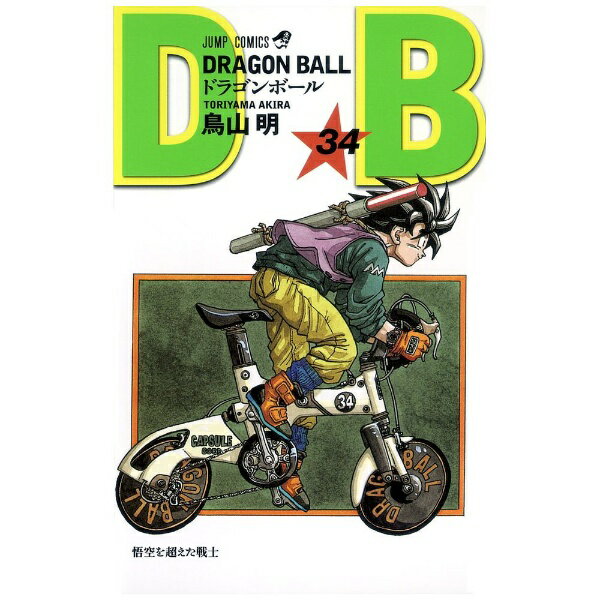昨日2月23日,天皇陛下が66歳の誕生日を迎えられました。
おめでとうございます。
日本を象徴する天皇陛下をはじめとする皇族の方々に,これまでの日本は支えられてきました。
しかし,皇族の人数は年々減っており,今後の皇室を案じる声が多く聞かれるのも事実です。
今回は,将来的に皇室を安定させるためにはどうしたらよいかを綴ります。
※かなり個人的思想の強い記事です。
不快な方は読まれないことをおすすめします。
また,特定の思想の方々を排除・非難する意図は持ち合わせておりません。
皇室の現状と皇位継承
現在,皇室には16名の構成員の方々がおられます。
そのうち,男性は5名です。
平成元年の時点では8名の男性構成員がいらっしゃいましたので,大きく減少していることがわかります。
しかも,60歳未満の若い世代に絞ると,現在では秋篠宮皇嗣家の悠仁親王ただ一人となっています。(平成元年時点では8名中7名が60歳未満でした。)
女性構成員は11名いらっしゃり,そのうち60歳未満は6名です。
そのうち,秋篠宮文仁親王妃の紀子さまは今年の9月に60歳になられますので,60歳未満は近いうちに5名に減ります。
皇室に関わる法律「皇室典範」において,皇位継承ができる(=天皇になれる)のは男性皇族のみとされています。
皇室典範第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
ちなみに,天皇及び上皇は皇室構成員ではありますが,皇族には含まれません。
よって,今上天皇はもちろんのこと,上皇にも皇位継承権はないわけです。
つまり,現時点で皇位継承権をもつ皇族は3名のみとなります。
皇位継承順位1位 文仁親王 60歳 天皇の弟
皇位継承順位2位 悠仁親王 19歳 天皇の甥/文仁親王の長男
皇位継承順位3位 正仁親王 90歳 天皇の叔父/上皇の弟
皇位継承者の不足
上記のとおり,皇位継承権をもった皇族は3名しかおらず,そのうち次世代に該当するのは悠仁親王のみです。
皇室典範では,天皇の長男が皇太子となることが決められていますが,今上天皇には男子がいらっしゃらないので,その次に血統が近い弟の文仁親王が皇嗣という形で皇太子と同じような役割を務められています。
つまり,次期天皇は今のところ文仁親王ということが決まっています。
しかし,現実問題を考えたときに,今上天皇が崩御または退位されたとき,果たして文仁親王に天皇の役割を果たせるのかどうかは,慎重に考える必要があります。
今上天皇と文仁親王は6歳しか離れていません。平成の天皇が85歳で生前譲位されたことから考えると,これくらいの年齢で天皇の役割を務めるのはかなり厳しくなってくることがわかります。その先代の昭和天皇も,86歳のときに体調を崩され,87歳で崩御されています。
仮に今上天皇が30年間天皇を務められるとすると,その頃には89歳。文仁親王は83歳になっています。その段階で文仁親王が即位することが可能なのか,という懸念があります。即位できたとしても,次の元号はかなり早くに終わってしまうことになります。現に,文仁親王が皇嗣になられたばかりの頃,ご自身がそれと同じ趣旨の発言をされていたという報道もありました。
そうなると,事実上の次期天皇は悠仁親王と考えることができます。
悠仁親王が生まれた2006年まで,皇室では40年以上もの間,男性皇族が誕生しませんでした。
文仁親王が生まれた1965年以降,皇室では9人連続で女性が誕生したのです。
もちろん,このことに科学的根拠は一切なく,たまたま巡り合わせがそうだったというだけの話ですが,確率的にはあり得るということです。
仮に将来,悠仁親王が子宝に恵まれご子息が誕生したとしても,男性が生まれる保証はどこにもないわけです。
悠仁さまに何かがあったら皇族が絶滅してしまう……。そんな綱渡りの状態が続くのは大変危険です。
じゃあどうするのか,という議論が,俗にいう「皇位継承問題」ですね。
愛子天皇待望論
世論では,今上天皇のご子息である愛子さまに次期天皇になってほしいという意見がとても多いようです。
愛子さまは天皇家の直系であり,人柄や所作も大変美しく見えるので,天皇にふさわしいという意見はわからなくもありません。
ただ,皇室典範で女性天皇は認められていないのです。
皇室典範がなかった時代には,女性が天皇を務めたことが10例だけあります。
しかし,それはすべて中継ぎ的践祚であり,次期天皇候補とされた男性皇族が成人するまでの間などに,スポット的に天皇を務められたのです。
愛子さまと悠仁さまは6歳しか離れておらず,しかも悠仁さまも既に成人していますので,愛子さまが中継ぎ的践祚をする必要がないのです。
さらに言えば,皇室典範を何とか改正して女性天皇が認められることになったとしても,それを現皇族に適用させるとは考えにくいです。おそらく,次世代の女性皇族から適用される形になるでしょう。
どのみち,愛子さまが天皇になるという道はとても狭いと言わざるを得ません。
女性天皇と女系天皇
愛子天皇待望論が持ち出されるとき,それとセットで必ず議論されるのは,「女性天皇」と「女系天皇」の違いについてです。
ここで整理しておきましょう。
女性天皇 … 天皇に即位した女性のこと。両親が皇族であるか否かは関係ない。
女系天皇 … 父親が皇族以外である天皇のこと。本人が男性か女性かは関係ない。
初代・神武天皇以来,126代すべてにおいて,女系天皇が即位した例は1つもありません。厳密には,母親が皇族の天皇がいましたが,その天皇は父親も皇族でした。つまり,女系でもあり男系でもある天皇という例はありますが,女系のみという例は一度もありません。
愛子天皇が誕生したとします。愛子さまは父親が天皇なので,男系天皇ということになります。このパターンは,前述のとおり10例あるので,やむを得ない場合はOKです。
ただ問題なのは,その愛子さまの次の天皇をどうするのかということです。
愛子さまは女性皇族なので,一般人の男性と結婚する可能性が高いです。そうなると,愛子さまのご子息はその時点で男系ではなくなるのです。
女性皇族は国際結婚も認められていますので,極端な例として,愛子さまがスミスさんという一般男性と結婚したとします。そしてそのご子息に天皇を継がせた時点で,日本は神武天皇王朝ではなく,スミス王朝に変わるわけです。
世界最長とされている2,600年間続いた王朝が,この瞬間に途絶えるのです。
女系天皇がいかにあり得ないことかがわかりますね。
現在継続的に議論されている「女性宮家の設立」についても,それをしたところで女系天皇を誘発するだけなので,まったく得策とは言えません。
天皇は総理大臣とは異なり,人柄・能力・人気によって選ばれるものではありません。伝統と法律によって揺るがなく位置づけられているものなのです。
「愛子さまが素敵だから」とか「秋篠宮家はいまいちだから」とかそういう理由で片付けられる話ではありません。
養子案
男性皇族の数が少ない,女系天皇もダメ,となると,皇族確保のために取れる策は1つしかありません。
それは,旧皇族の復帰です。
旧皇族とは,1947年まで皇族だったのに,GHQの指示によって皇族の身分を失い一般人に臣籍降下した方々のことです。
このとき,昭和天皇の兄弟よりも血統が遠い宮家は,すべて皇籍離脱させられました。実に11宮家51名が離脱したのです。
その中には,男系子息ができずに断絶または断絶見込みとなっている宮家もありますが,4つの宮家には現在でも男系の子息が残っています。この中には,愛子さまと同世代の男子も複数います。
これらの男子を皇室に復帰させるというのが,今考えられる中では最適解と言えます。
復帰というと語弊がありますが,正確には養子に取るという方法が最善です。
現在皇室にいる女性皇族と結婚してもらっても良いですし,跡取りがいなくて断絶見込みとなっている宮家に養子に来てもらっても良いです。
皇室典範では,皇室への養子は認められていませんが,その部分を改正すれば良いのです。どうせ改正しなければならないのなら,女系天皇を認めるよりもはるかに現実的な方法です。
これらの旧皇族は,現皇族との共通の先祖まで600年遡ります。室町時代の皇族ですね。
さすがに遠すぎる,という意見もありますが,血統に近いも遠いもなく,男系で血が繋がっているという事実だけで重要なのです。
さらに,男系男子がいる旧宮家の中には,女系で明治天皇の血を引く方もいらっしゃるので,血統の遠さという懸念を補強することも可能です。
皇室典範は国会が提起しなければ改正できません。有識者会議とやらで話を進めているような体裁だけは繕っていますが,実際には何も話が進んでいません。
理由は簡単で,話が大きすぎるためにどの政権も手を出したがらない案件なのです。
安倍元総理は,男系死守の考えが強い方でした。そのイズムを継承する高市総理に,何とか頑張ってもらいたいですね。
【関連記事】
一般参賀
建国記念の日【「建国記念日」ではない理由】