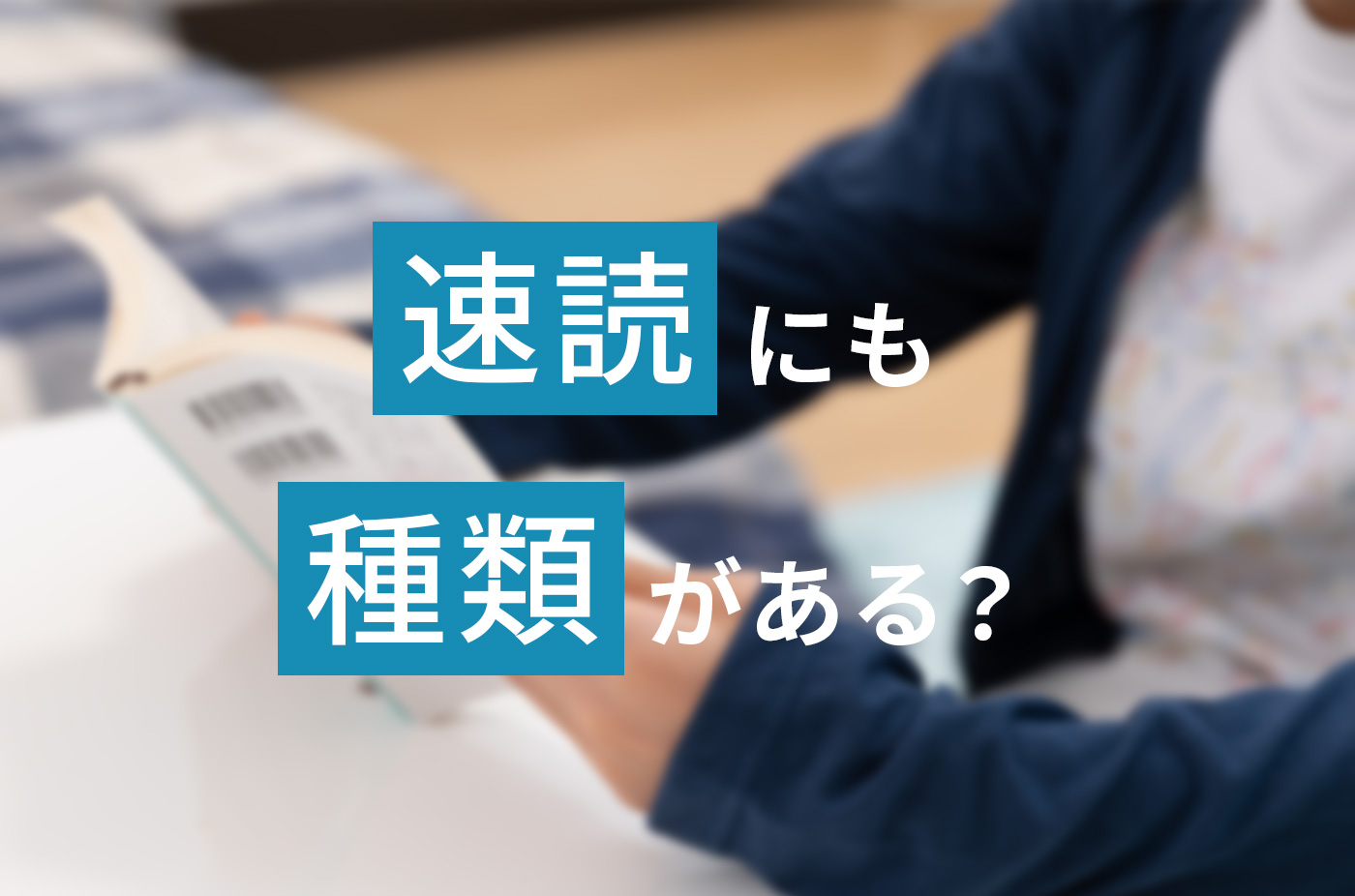通勤時あるいは街を歩いているとき、はたまた数々のニューズを観ている際、「乱舞」がまばゆく感じることがある。
といっても、おれの認知が乱れているわけではなく、現実に、視界のなかで、「乱舞」が繰り広げられているのである。
古今東西、
「賢者」の言説は「同じ」
だという。
そのときそのときの趨勢に左右されず、ぶれることなく、見解が常に一貫している。
ただし、それは「一人の賢者」が一生を通じて、いつでもどこでもつねに「筋の通っていること」を言っているというだけに留まらず、いつの時代の、どの地域の賢者も、つねに「同じこと」を説いているという意味らしい。
「Aについてどう考えますか?」という問いにたいしては、古今東西どの賢者の解答も「共通」しているというわけだ。
一方、「愚者」の言説は?
「愚者」という言葉で十把一括りにしたい感情とは裏腹に、愚者の言説は千差万別だという。
そのときそのときの状況に流され、影響され、それこそ「なにを口走るか予想がつかない」ブラック・ボックス。
愚者の言説は、まさに百花繚乱なのだ。
ドナルド・トランプもウラジーミル・プーチンも、その政治的思想や大義は共通していて、「同じ世界」を目指していると思われるが、それを否定し去ろうという連中のほうは、「そこまでしちゃうんだ!」という愚かさの多様性に満ちている。
偽旗作戦、テロによる挑発、不正選挙、不当逮捕、経済制裁、文化破壊、プロパガンダ報道、総デジタル化、等々・・・。
今回のコロナ惑沈の接種にしても、たぶん「賢者」の見解には共通項がある。
「治験が済んでおらず、安全性が確認されてもいない、薬だか毒だか判らないものを接種すべきではない」
この認識に至る背景(感性や予備知識等)はさまざまだが、どこかに一貫した、ぶれないコアが存在したように思う。
だが、惑沈を積極的に肯定したり、推奨したり、非接種者を人道にもとるとばかりに非難したりしていた「反・反惑沈」の言説は、おそろしくヴァリエーションに富んでいた。
おれからすると、「そういう理屈まで動員して惑沈接種を肯定するんだ!」という驚きの連続だった(それは過去形ではなく現在進行形だ)。
なかでもおれが驚いた「言説」は、
「接種による集団免疫の確立」という理屈と、
その屁理屈と対になった、
「非接種者が感染しないのは、接種者による集団免疫のおかげ。非接種はただ乗りをしてるんだ!」
という批判だった。
Deep・Sのドレイタレントのパト○ック・ハー○ンに至っては、「非接種=ただ乗り」という論を展開したあと、「日本はただ乗りの国じゃないないよね」という表現で、さらに接種を推奨していた。
だが、おれはここで「非接種者=賢者」「接種者=愚者」という図式的な思考を展開しているわけではない。
「賢者」「愚者」の境界線は、現実に接種したか否かとは微妙に異なる。
自分ではとくになにも考えていなかったのだが幸運にも非接種という人もいるだろうし、接種は避けたいと思いながらも、強制的に接種せざるを得なかった立場の人もいるだろう。
そうではなく、「接種を肯定・推奨・半強制する見解」こそがまさに「愚者の見解」そのものであり、それゆえにヴァリエーションに満ちていたということを、あらためてレ・ビューしているだけである。
(パ○リック・ハ○ランが愚かであることもふくめ)
さて。
通勤時、あるいは私用で街中を歩いているときに遭遇する「愚かな行為」も千差万別で、ある程度の頻度で「新種の愚行」を発見する。
そのたびに「このパターンがあったか!」と三嘆久しゅうするほどだ。
そのなかのひとつが、今年3月のブログでも触れた例である。
駅構内を歩いているおれの前方から、数人から成る「スマホ歩き連隊」が迫ってきていたので、おれがその間を苦心してすり抜けようとしたところ、その際に瞬間的に距離が近くなってしまった連隊長格の男から、舌打ちとともに睨まれた、という話だ。
このときも、「新しいパターンだ!」「新種発見!」と、まるで新しい植物を発見したときの牧野富太郎のように眼を輝かせたのだが、最近、またしても新種に出遭う機会に恵まれた(これも「スマホ歩き属」だ)。
駅のホームには極端に狭い場所がある。
階段があったり、エレベータがあったりして、互いに身体を斜めにすれば、かろうじてすれ違えるという幅しかないところもある。
まさにそこがそうだった。
その「狭い場所」に差し掛かったところで、前方から大きなバッグを提げた女性がこちらにむかってきていた。その女性はすでに「狭い場所」の途中まで進んでいたので、おれとしては当然、その手前に立ち止まって、その女性をやりすごそうと待っていた。
その女性が、もうすぐで「狭い場所」を通りすぎようという段階で、おれのあとから来た別の女性が、前方から来ているその女性とぶつかり合ってもかまわないという勢いで、平然とスマホを見詰めながら、その「狭い場所」に進んでいった。
どういう状況か、おわかりだろうか?
例えば、2台の自動車がすれ違えないような狭い道に差し掛かったときは、一方の自動車はその手前の「待避所」でいったん停まり、対向車が過ぎるのを待つだろう。そのときに、待っている自動車のあとから来た別の自動車が、対向車とガリガリ接触してもかまわないとばかりに、狭い道に突っこんでいくようなものである。
大きなバッグを提げている女性からすると、せっかく「優しそうなジェントルマン」が道を譲ってくれてありがたや、とほっこりしてるところへ、急にスマホ歩きのジャンキー女が前方から突進してきたと思うだろうし、おれからすると、待っているおれを差し置いて先に行くのか、と釈然としない気持ちになる。おれが「待ったこと」の成果も台無しだ。
平和なのは、そのスマホ・ジャンキー女だけである。
そういった、現実を「虚化」している輩がもっとも厄介なタイプに属すると思うのだが、そのほかにも愚かさの方向性は多岐に亘る。(多岐に亘りながらも、それぞれの特質が微妙に重なり合っている)
他者への無意味な対抗心。
場違いな自己主張。
自分が嫌な思いをしてでも他者を快適にはさせないというスパイト行動。
赤の他人のためには1ミリたりとも譲らず、1カロリーたりともエネルギーを費やすまいとする狭隘な料簡。
それから、最短距離主義者も珍しくない。
頭のなかに「無人の地図」しかないのだろうか。
他人がそこにいる・いないにかかわらず、とにかく、物理的に最短となるラインを盲進し、通路の動線の矢印を超然と無視して、ひたすら物理的なインコースを突いてくる。
他人のためにカロリーを費やすのは名折れであるという対抗意識が肥大しているわけではなく、とにかく1カロリーたりとも余分なエネルギーは使わないというゴリゴリの倹約家なのだろう。
そこで節約したエネルギーを、さぞ、他の局面で有効活用しているのだろう、と皮肉のひとつも言いたくなる。
「余計なエネルギー」は一切使わないことが正義である、といったひとに遭遇するたび、おれは
「息をするのも面倒でいやだ」とボヤく『北斗の拳』の愛すべきザコキャラのひとりであるゲイラを連想する。
これこそが究極の吝嗇であり、その考えを突き詰めると、「生きていること」自体がムダとなる。
ともかく。
おれからすると、よくわからない「謎の内在的論理」が錯綜し、賑々しくもあでやかな「乱舞」が、季節とは無関係に、年中クルい咲いている。
「石川や浜の真砂子は尽くるとも世に盗人の種は尽くまじ」(by石川五右衛門)
この「盗人」を、「愚者」や「愚かさ」に替えても同じことが言える。
ヴァリエーションも豊富だが、数も多い。
「賢者」は基本的に少数派だが、「愚者」は次から次へと、まさに尽きることなく湧いてくる。
これからも、まばゆさと謎に満ちた新たな「内在的論理」に、きっと出遭えることだろう。

おれ自身は賢者ではない。賢者を目指してはいるけれど。