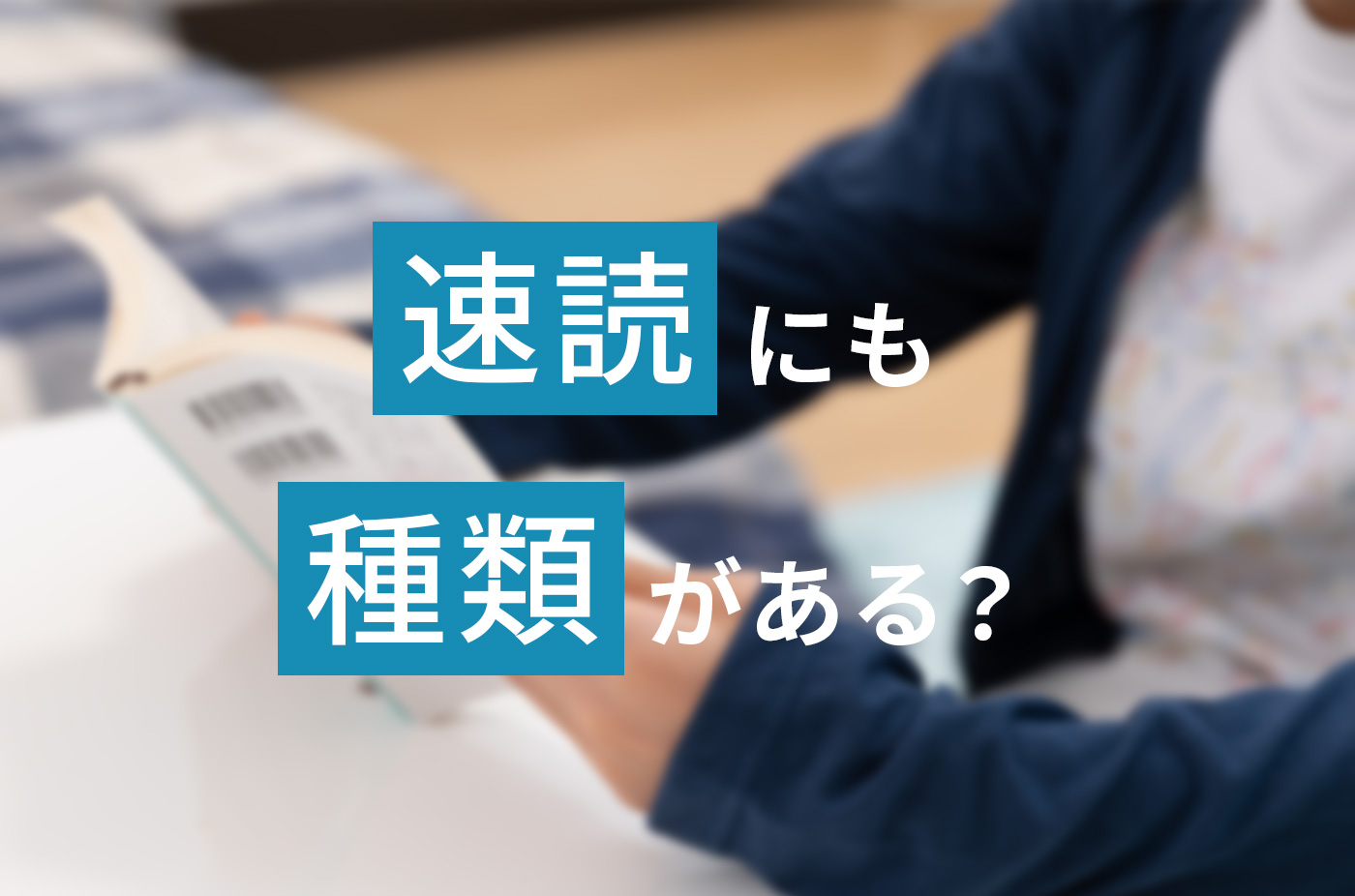先週、筒井康隆に触れたので、始めに、氏の有名な文章の一部をここに載せる。
みなさんも読んだことのある文章かもしれない。
青春時代の読書によって一生の読書傾向が決まるといっていいだろう。たまたま自分の波長に合わぬ本ばかり読んだ人は一生ハウ・ツーもの以外何も読まなくなる。速く読む癖を身につけた人は一生速読する。熟読・再読の癖はなかなか抜けず、とばして早く読んでしまうと気持ちが悪くてしかたがないし、気に入った本を常に身のまわりに置いておくことになる。
(後略)
筒井康隆著『言語姦覚』(中公文庫/1986年発行)所収「青春時代の読書」より
初出は、あの「新潮文庫の100冊」として有名な「新潮文庫パンフレット」(1978年3月)。『言語姦覚』が未読でも、パンフレットのほうで読んだことがある方も多いのではないかと思う。
「再読」はともかくとして、おれはまさに「とばして早く読んでしまうと気持ちが悪くてしかたがな」くなる質(たち)で、これは「青春時代の読書」の影響というより、もともとそのような性格なのだろう。
三島由紀夫が『文章読本』で説いている(奨励している)「精読者(リズール)」の概念に感銘を受けてからは、ますます熟読の度合いが深まり、なかでも文学作品の場合、「読み飛ばす」ことはほとんどない。
それでも、「速読」にたいする憧れはある。
「もっと早く本が読めたらな~」と思ったことは、これまで一度や二度ではない。
(精読者でありながら古典をすべて読破しているとされている三島由紀夫は、どれほど読むのが速かったのだろうと想像してしまうことがある)
「速読」というのは、読書を趣味(あるいは職業)とする者にとって、一度は夢に見る「能力」かもしれない。
一般に流布している速読の「コツ」は、「斜め読み」と「飛ばし読み」、あるいは「拾い読み」だ。
これらは、いわゆるキーワードを適宜とらえて、内容を把握していくとういう技法である。
こちらに詳しく書いてある。
一般社団法人 日本速読解力協会の「速読にも種類がある!自分に合った速読の方法とは?」のページ
だが、この速読技法が、自然に行われている場合もある。
概して、「読み慣れている文章」は速く読める。
たとえば、部下から提出された、どれも似たような内容の報告書。これをいちいち精読する必要はない。
それが営業報告なら、極端な話、「予算達成」なのか「未達」なのか、そのキーワードを拾い読みをすればいいだけだ。未達の場合の「言い訳」や「弁明」に使われている単語も、たいてい似たり寄ったりなので、これも速く読むことを可能にしている。
だが、それは読書ではないし、速く読めるとしたらそれは職業的な習熟によるもので、必要なワードをあらかじめ把握しているからこそである。契約書や論文などの「定型文」を読む場合もこれに該当する。
また、知識は積み重ねであるから、それまで培ってきた素養が次に読む書物への理解を助け、結果として速く読めるということは、もちろんある。
それは、文学書でも、法律書でも、歴史書でも、医学書でも、数学書でも、経済書でも変わることはない。
だが、ここで言おうとしているのは、そういった「慣れ」や「熟達」、あるいは「素養」や「把握力の高さ」などによって速く読めるというレベルを超え、よく言われるように「1ページ1秒」といった速度で本を読み、しかも普通に読んだときより内容を深く理解でき、記憶にも永く残るという「魔法」のような速読術についてである。
多くの「速読術」の解説書で説かれているのは、同じく日本速読解力協会のサイトでも解説している
「フォトリーディング」
「1ページ読み」
といった手法である。
毎秒 1 ページを超えるスピードでページをめくり、写真を撮るように本の情報を脳に送り込む速読法です。
事前に読書の目的を明確にし、読む価値があるかどうかまで検討します。
一度にページ全体を眺めて本の全体像をつかみ、要点や必要な情報を自分自身に問いながら読み進めることで、必要な情報を効率的に取り出します。
つまり、文字を「言語」としてではなく「画像」ととらえるというわけだ。
もちろんトレーニングによる習熟は必要だが、言語ではなく画像のほうが理解度も高まり、記憶にも残る、と(日本速読解力協会だけではなく)多くの「速読本」でも説いている。
おれからすると一番の疑問は、ページを写真(画像)として脳に送りこんで、果たして内容の理解が速まったり、深まったりすることがあるのだろうか、ということである。
このような疑問は、たぶん誰でも抱くのではあるまいか。
同サイトでは、以下のように解説している(以下、多くの「速読本」も同様の主張だ)。
速読ができたら、魔法のように知らなかった言葉の意味が急に分かる!といったことはありません。
外国語の文章を読むためには語彙や文法を学ぶのと同じく、日本語であっても難しい本、たとえば専門書などであれば文章内に出てくる用語の意味を知らなければ理解は困難となります。
基本的に読むために必要な知識となる単語・文法、教科知識や専門用語などはトレーニングと別で学習が必要となります。
知らない単語をじっと見てしまったり、文法を知らないことで意味が理解できずに文章を何度も読み返したりしていては、せっかく鍛えたスピードも十分に発揮できない…ということになります。
速読の効用を説いていながら、やや腰が引けているようにも思うのだが、結局、いくら画像を脳に「プリント」しても、そのことによって「それまで知らなかったこと」を即座に理解することは無理なのだ。
考えてみればあたりまえのことである。
おれは以前、「数学」に関する本を集中的に読んでいたことがあり、そのレビューで、
紹介される個々の概念にしても、
できるだけ、そのイメージ(あるいは数学史的な意義)を
理解しようとしながら読み進めたので、
1時間で1~2ページしか進まなかったこともあり、
400ページほどの本文を読み切るまでに
半月以上かかってしまった。
と書いたことがある。
(2011/9/25投稿 ジョージ・G・スピーロ著『ポアンカレ予想』のブログ)
こういった読書体験を通じて、おれは、速読の「メイン・メソッド」である「ページを画像として脳にプリントすること」の有効性に、あるときから、はっきりと「否」を突きつけていた。
「速読」は憧れだけど、原理的に無理だな、と。
なんど読み返してもなかなか理解できない文章を、仮に「絵」として把握(記憶?)できたとしても、そこにはなんの意義もないな、と。
逆に言えば(これこそがおれのメインの主張なのだが)、
ページを「画像」として脳にプリントして即理解できる程度の文章なら、わざわざ読むに値しない
ということなのだ。
それは(少なくとも)おれの求める読書体験とはかけ離れたものである。
「いやいや、たしかに専門的な記述のある書物なら熟読は必要かもしれないが、たとえば、平易な物語のストーリーを把握するだけなら、『フォトリーディング』も有効でしょう」という反論に対して、おれはこう再反論する。
「平易な物語というが、そのなかに、はたと立ち止まって、熟読吟味するような記述はないのか?」と。
もし、そんな記述がないというなら、はやりその物語を読む意味もないのではなかろうか。
平易な物語である『ピノッキオの冒険』のなかにも、はたと立ち止まらずにいられない場面は多々あった。
そういうものを感じるための読書ではないのか。
最後に、「速読術」にたいする反論を2点だけ挙げて終わりとする。
まず、「画像というのは文章より印象的だから記憶に残りやすい」という前提。
これは個人差があり、たとえば、絵や写真を職業としているような人のなかには、「一度眼にした画像を忘れることなく、いつでも脳内で再現できる能力」を持っている場合もある。
(TVドラマの『ドラゴン桜 2シーズン』のなかにも、「カメラアイ」の瞬間記憶能力を持つ、たぶんASDの生徒が登場した)
速読トレーニングによって、そういった視覚情報処理能力をある程度は養成できるのかもしれないが、多くの人は、毎日見慣れているはずの家族の似顔絵を描こうとしたとき、「あれ? どんな顔してたっけ?」という程度の再現能力しか持ち合わせていないのだ。
画像=印象的なのはまちがいないが、誰の脳内でも、それが崩れることなく、いつまでも残存しているかどうかは疑問である。パソコンだって、テキストデータより、画像データのほうが容量を要する。
2つ目。
速読の能力を持つ、いわば「速読の達人」は、たいてい本を出版している。
だが、そのテーマの多くは「速読術」に限られる。
速読の能力を活かして常人の何十倍、何百倍もの書物を読破しているなら、そこで得た豊富な知識を基に速読術以外の「専門書」も著せるのではないかと思うのだが、どういうわけか、
書くものは「速読術」の解説ばかりである。
いったい、速読術の達人たちは、ふだん何の本を読んでいるのだろう。
「青春時代の読書」の後半はこうである。
最初、あまりにも面白い本にぶつかってしまった場合はちょっと困ったことになる。最初の本の面白さに及ばぬ本ばかりを読むことになるし、「あの面白さ」を求めるあまり、別の種類の面白さを持つ本を読んでもその面白さに気がつかない。ついにはあきらめて本を読まなくなってしまうのだ。
なんとなく、恋愛に似ているではないか。
恋愛に似ている面もあるが、イコールではない(と思う)。
呉智英は、読者には段位がある、と説いている。およそ500冊読むごとに段位(読者としてのレベル)が上がるという。
でなければ、ある程度の量を読んだら、もう読みたい本がなくなってしまうではないか、と。
だが、現実には読めば読むほど、読みたい本(これまでよりさらにレベルの高い本)に出逢うものだ、と。
だいじょうぶ。
最初に読んだ本がどれだけ面白くても、読みつづけていれば、それを凌駕する書物はかならず現れるはずだ。