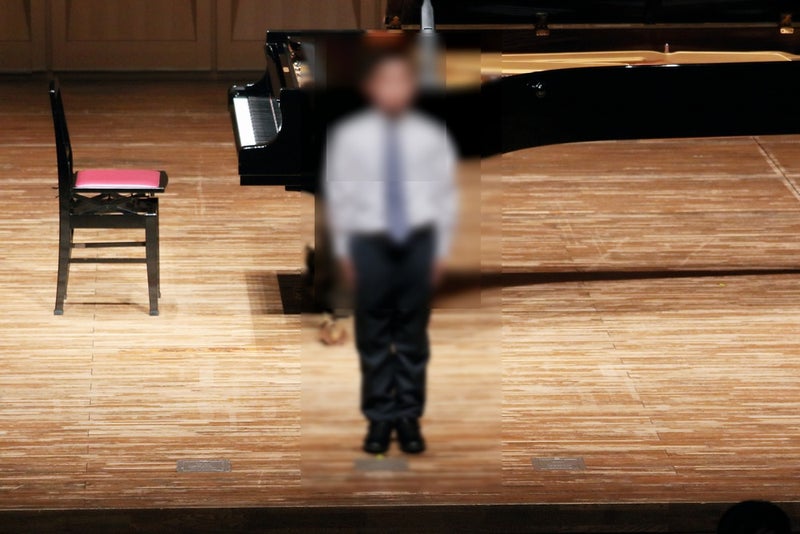この前、ピアノ発表会の撮影をした時に、その場にいた「生徒さんのお父さん」(かなり高級なカメラを持っていたので、写真マニアだと思います)から、「プロとアマの撮影方法の違いって、なんですか?」と質問されました。
この時、すごく忙しかったので、「ご返事はブログに書きますので、あとで読んで下さい」と答えてしまいました。なので、この場に記載させていただきます。
いろいろあるんですが、大きな点をひとつだけ書かせていただきます。
これは、私が若い頃に、「音楽発表会専門の写真事務所」で修行していた頃に、そこの経営者に厳しく言われたことです。
この業種のカメラマンって、経験を積むほどに、「この曲を演奏する際は、1分経過した時に、すごくかっこいい指使いになるから、その時にシャッターを押そう」なんてことがわかってきます。だから、「曲の最初は撮影せずに待機している」なんてことがあるんですが、これ、絶対にだめなんです。
本当のプロは、演奏者のかっこうが悪くても、顔がこっちを向いてなくても、とにかく、演奏が始まったら、なんでもかんでも撮るんです。
これ、どうしてか? というと、素人の発表会の場合、緊張で演奏ができなくなってしまうケースが時々あるからなんです。
椅子に座って、鍵盤に手を触れて、音を一個出しただけで、「あ、だめだ、やっぱり、無理だ」とあきらめて、演奏をやめて舞台袖に引き上げてしまう生徒さんがいます。このあと、先生や親御さんが必死に「がんばろうよ!」と説得しても、結局、ピアノに戻らずに、その生徒さんの発表は、「最初の一音だけ」で終わることがあるんです。
この時に、「演奏開始後、かっこいい姿勢になるまで、撮影するのは待機する」なんていう撮影方法だったら、「演奏写真は1枚も残っていない」ということになってしまいます。これは悲しいことです。
プロの場合、「生徒さん全員をなるべく公平に撮る」という使命がありますから、上記のようなケースでは、「最初のワンタッチだけ」でも、記録に残しておかないといけません。ですから、かっこうなど気にせず、とにかく「演奏が始まったら、パパパと撮る」ようにしています。
極端な話、その生徒さんが舞台袖でぐずっている様子がわかる場合は、ピアノの前の座る前の、舞台上に姿が現れた時点でバシャバシャ撮り始めて、最悪、「ピアノに一切触れずに戻ってしまった」という場合でも、その生徒さんが「舞台に上った」という証拠写真を残します。
このように「子供さんがぐずる」というケースだけでなく、「高齢者の生徒さんが舞台に上がった途端に、緊張感で、心臓に負担がかかり、急性心筋梗塞で救急車」なんて場合もありますから、とにかく、どんな生徒さんの場合でも、「姿が見えたら、すぐに何枚か撮る」というのは、プロ写真屋としては必須なのです。
生徒さん側の事情だけでなく、カメラマン側の機材の故障が突然起きて撮影不能になる場合もあります。それも考えて、「考えるな! とにかく撮れ!」ということを肝に銘じています。(「燃えよドラゴン」のブルース・リーみたいなもんです)
これは、修行時代にきつく教わったことです。当初、「そんなことないでしょ?」とか思っていたんですが、経験を重ねてくると、実際に、そういうのを何回か経験するわけでして、その時になって、「こういう時のためだったのか~」と感心した次第です。
こういうことは、場数の少ない、素人さんは考えつかないことだと思います。このように、プロは「一見、無駄に思えるような撮影」も実際にはやっています。
ネットの「暮らしのマーケ*ト」とかで、非常に安い撮影料で撮ってくれる、?のつくプロカメラマンは、こういうことは考えていないと思います。