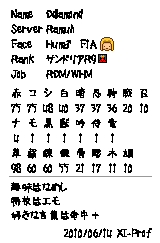毛虫は不快な存在だ。彼が何ら悪意のない善良な毛虫であっても、なんの他意もない無邪気な散歩であっても、込み上げる嫌悪感を抑えることが出来ない。何故だろう。多分理由はない。不快だから不快なのだろう。みみずもそうだ。蜘蛛だって気持ちが悪い。天上を這っている虫の、非生物的な足の動きをじっと見ていると、まるでそれが自分の肌の上を這いずり回っているように感じてしまう。そして勝手にこそばゆくなり、鳥肌が立つ。哀れな虫は棒切れで小突き回されて潰されてしまう。
ではそれが巨大な生き物だったらどうなるだろう。まがりなりにも知性を持っていて、言葉を喋るとしたら。それが横柄で、傲慢で、面の皮が厚く、礼儀知らずで野蛮で粗野で無教養であったら。青いクロークを羽織り、細身の剣を腰にして、我が物顔に闊歩していたら。ムーンは村の中を徘徊する不快な生き物に神経をすり減らしていた。
夢使いの村は狭い。行水が出来る井戸は一つしかないし、用を足す場所も村に数ヶ所しかない。特定の者を避けて暮すことはとても困難なのだ。
「王様、王様よ。」そんな呼び声があちこちから掛けられる。不快な村の寄生虫、キャリオットを呼ぶ村人の声だ。
「おう。」キャリオットは、声が聞こえる限り呼びかけに応じる。機嫌は良くも悪くもない。潜在的に持っている機敏さからすれば気を抜いている程度の動作で現れる。その態度は何処か侮蔑的で薄ら笑いを浮かべていることもある。用事は概ね大体力仕事だったりする。薪割り、水運び、荷役、天上の掃除からどぶさらいまで、キャリオットに振られたクエストは多岐に渡った。以前は村で一番若いムーンが呼びつけられていた仕事、または村人が何人がかりで何日掛けていた仕事を、若さと体力と強引さであっというまに片付けてしまう。
といっても、キャリオットが好意の慈善家でないのは言うまでもない。キャリオットは仕事をしながらありとあらゆる罵詈雑言を尽くした。老いぼれ、もうろく、能なし、こんなことも出来ないで無駄に歳を喰ったもんだ、情けない、涙が出る、いい加減くたばっちまえ、長生きしたってろくなことはない、ぼけたか、呆けやがって、無能、ごくつぶし、恥知らず等々、これでもかこれでもかと老人達を馬鹿にする。キャリオットは戦士にしてはやや小柄だが、体躯は鋭く鍛えられており、俊敏さ、器用さも目を見張るものがある。どんな仕事をさせたって盛りを過ぎた老人達とは比べるべくもない。彼はそれを知っていてなお老人達を侮蔑する。そういう無神経さはムーンの最も不快な性質だった。
こんな暴君を相手に、村の老人達もお人好しが過ぎる。無能な貴様らのためにやってやったんだぜと恩着せがましい態度が見え見えのキャリオットに、わざわざ丁寧に礼をして、やれ茶だの菓子だのと世話を焼く。しかも、キャリオットはそういうものを女子供の食い物だと馬鹿にして、にべなく断ってしまう。そのくせ、朝晩に必ず誰かの家を奇襲しては、飼葉桶一杯の雑炊を食らい、一年分の寝酒を飲み干していくのだ。要するに育ちが卑しいのだろう、野蛮で無知な田舎者なのだ。
村人達はとにかくキャリオットに対しては腰が低い。豚鬼を追っ払って貰った恩は確かにあるが、それだって最後の一匹を切り倒しただけで、ほとんどは村人の力で追い返したのだ。それ以前にキャリオットは瀕死の所を助けられた義理がある。あの男はそんなことすっかり忘れてしまったのだろうが。
相手は夢の力などかけらもないただの戦士だ。ムーニエ老、ユピト老達に限らず村の夢使いなら戦って勝てない相手ではない筈だ。なにもここまでのさばらせなくたって、あの傲慢な鼻っ柱をぴしっと叩いて、分をわきまえさせることくらい出来ない相談ではない筈なのに、誰もそれをしようとはしないのが、ムーンには不思議で、腹立たしかった。
確かにキャリオットは便利な存在だ。おだてれば薪割だって荷運びだって村人の3倍は楽にこなす。だからといって人を便利に使おうというやり方には賛成できない。キャリオットが居なくたって、今までなんとかやってきたのだ。こんなに屈辱を与えられてまでキャリオットに媚びる必要などないではないか。
しかし結局、ムーンを苛立たせるのはキャリオットの間抜けさ加減である。王様王様と口先で言われたくらいで汚れ仕事までほいほいやってしまう調子の良さ、自分が便利に使われている事に気がつかないのだろうか。あれで自分が尊敬されていると本気で思っているならば希代の大馬鹿者でるが、どうやら本気で思っているらしい。
こんな大馬鹿者の看病を必死でやっていたのかと思うと、自己嫌悪に陥ってしまう。しかも、その男に淡い恋心を抱いていたとなると。
悔しさと情けなさで翌日は布団から起き上がる気力もなかった。毎日休まず続けていた広場の掃除もさぼり、日が昇ってから沈むまでカーテンを締め切った部屋でアットと二人で転がっていた。窓の外から時折聞こえる馬鹿笑い。あれはいも虫のキャリオットだ。あんな下品な笑い声は、以前の村にはなかった。
ムーンを心配して、村の人が見舞いに来てくれた。ムーンはその度に頭が痛いとかおなかが痛いとかその場を取り繕って言い訳をしなければならなかった。嘘をつくのは苦手なので、見舞いの人とは目を合わせられなかった。いつも布団をかぶり、背中を向けていた。
見舞いの話題はいつもキャリオットだった。事件の少ない村だから仕方がないのだが、ムーンには辛い試練だった。キャリオットの名前が出るだけで、ムーンは激しい嫌悪感と戦わなければならなかった。だからといって、ムーンは胸の内を吐き出すようなことは出来なかった。なんにせよ、他人をあしざまにけなすのはムーンのキャラクタではない。結局内気な性分なのだ。
「体調が悪いなんてついてないわね。ムーン。」ムーニエ老の奥様は小さな城主の娘だったそうで、気品の感じられる老婦人である。部屋にこもったムーンの為に豆のスープを作ってくれたのだ。彼女は村人が病気になるとスープを作って届けるのを使命だと思っている。
「このスープね、出掛けにキャリオットさんに味見をして頂いたのよ。精がつきそうでいいって、こういうものはあんまり召し上がらない方なのにね、嬉しくなっちゃったわ。」彼女は屈託なくころころと笑う。ムーンの4倍も生きている老婦人が、あどけなく見える。ムーンは彼女のそういうところに都育ちの優雅さ感じて憧れる。
「キャリオットさんがいらしてから、村が明るくなったわ。貴方も早く良くなってちゃんと御挨拶しないとね。」
「でも」ムーンは後ろめたさに苛まれながら、ぼそりと呟く。「あの人、私は、どうも。」言いたいことがうまく言葉にならない。
「そうね、あの人は口が汚いから。ムーンみたいな若い子にはきついのかも知れないわね。でも、いい人よ。」
”でも”の中身を、言えるものなら言ってもらいたいものだ。ムーンは心で毒づく。しかし、悲しいことに顔には引きつった笑いが浮かんでいる。我ながら情けない習慣だと思う。
「ムーンが一生懸命看病してくれたことは、村の皆さんがちゃんと言ってますから、貴方はちゃんと体を治すんですよ。顔色が優れないんじゃ美人もかたなしですからね。」
「私のこと、言ってるんですか。」ムーンは慌てた。
「大丈夫、みんな良く言ってますからね。」婦人は時々的外れなことを言う。あの夜以来、ムーンがキャリオットを虫けらと同格で嫌っていることなど誰も知らないのだから仕方がない。
ここで村人がキャリオットに何を吹き込んでいるのかムーンが知ったら卒倒したかも知れない。曰く、看病の仕方は尋常じゃなかったですよ、真心がこもっていました、運命の糸を感じます、あの子は照れ屋で引っ込み思案だからああいうことになりましたけれども、そりゃ心の中では貴方を慕っているのには相違ありません、いい子ですから幸せにしてやって下さい・・・
ムーンは自分のことにあんまり触れないで下さいと遠慮がちにお願いしたが、多分後の祭りなのだろう。ムーンはさらに気が重くなった。
ムーンが部屋にひきこもって丸二日。始めは上機嫌でムーンにすり寄って、ムーンの脇で惰眠をむさぼっていたアットもさすがに飽きてきた。飛び猫というのは何をするにも長続きしないのだ。二日目の夜中、アットは目を覚ました。もみくちゃになったふとんの上で伸びをして、羽根をたたみ直し、肩のあたりをぺろぺろと舐めた。ムーンは眠っている。アットはムーンの鼻面の当りをうろうろした。寝つかれたアットは、今度は遊んで欲しかったのだが、ムーンはぐっすり眠って起きる気配がない。
アットは諦めて、今度は床に降りてうろうろした。机の下にごはんの入った皿と水の入った皿が並んでいる。ごはんのお皿には魚の頭の食べさしが入っていた。夕方に食べた残りだった。匂いを嗅ぐと、少し酸っぱかったので、前足で砂をかく動作をして、また臭いを嗅いだ。2、3回やっても臭いがちっとも消えないのでアットは飽きてしまった。水は生ぬるかった。アットは汲みたてのきんと冷えたのがお好みだったので、ちょっと寂しかった。
アットはつまらなくて、みゃうと鳴いた。そのとき、アットは部屋の扉が半開きなのに気がついた。アットは扉にすり寄って匂いを嗅ぎ、鼻先をすき間に押し込んだ。木製の重たい扉は軋みながら僅かに動き、アットの頭が通るくらいまで開いた。アットは柔らかいおなかを変形させてすき間をくぐり、夜空へ飛び出した。
アットは外が好きだ。家の中に居ると、外に出たくて出たくて、どうしてもうずうずが止められない事がある。ちょっとした隙を見つけては、制止も聞かずに飛び出してしまう。外で何をしているのかというと、別段変わったことをする訳ではない。ぼーっと座って空を眺めたり、ヒゲでそよ風を感じたり、昼寝をしたりしている。ひとしきり遊び疲れると寂しくなる。だけどもアットは家に帰ろうとはしない。なぜ帰らないのかはわからない。たぶん、帰りかたを忘れているのだろう。それとも家そのものを忘れているのかも知れない。アットは切なくてあたり構わず鳴きまくる。
結局、ムーンが見つけ出すのは路地の隅とか庭先に干してある桶の中とか生け垣の奥とか、狭っ苦しい所と決まっている。寂しさと寒さと空腹に責められてぶるぶる怯えているのである。ムーンが手を差し伸べるとすがりついて胸元に駆け上がり、爪を出してがっしりしがみつく。頬を押し付けてぶるぶると喉を鳴らす。そんなに怖いなら外になんか行かなければいいのにと、ムーンはいつも思っている。だからムーンは普段アットを一人で外に出さないようにしている。
夜空は涼しくて気持よかった。アットはふんわりふんわりそよ風に乗って滑空した。飛び猫にしては太めにアットが軽やかに宙を滑る姿は不自然な感じがしないこともない。しかし物理法則がどうであれ飛んでいる事実は変えられない。
アットには行きたい所も、行くべき所もない。ひとしきり空の散歩を楽しんで、民家の軒先に降りた。後ろ足で耳の裏をかっかと引っかくと、住んだ夜空に黒毛が舞う。そよ風に乗った毛は月の光を反射して一瞬つややかに輝き、宵闇に消えていった。
アットの左右の耳が前方に向く。ぷーんという妖しげな音。月の光にきらきら光る羽根、アットのお気に入りの遊び友達、蚊とんぼである。適度にのろく、適度に素早く、弱っちくて絶対反撃されない。アットは体勢を低く構え、羽根をしずかに上下させて飛び立てるように調整する。尻尾は斜め上方四十五度に緊張してピンと立つ。猫族の習性で、お尻を2、3度振って、目標に向かって飛込んだ。蚊とんぼの方は迷惑極まりない。慌てて向きを代え、アットの単調な攻撃を交わし交わし逃げに転じた。
蚊とんぼが命からがら逃げ延びた後もエキサイトしたアットは獲物を追っているつもりでやみくもに飛び回った。何処に居るのかわからなくなっているうちに、村の垣根を越えていた。疲労が興奮を打ち負かした。アットは息が上がり、舌を出してふらふらと地面に降りた。
月明かりを背にした人影が、アットを見ていた。そのシルエットは満月を背にしてなお黒い。彼はゆっくりアットに近づいた。アットは気がつかなかった訳ではない。急に走ってきたり、手を振り上げたり、変な臭いがしたり、その人影には悪い気配を感じなかったので、アットは逃げずにじっと見ていた。
「みゃう。」
アットは真ん丸な目で、近づいてくる人影に挨拶した。人影がゆっくり掌を差し出した。アットは中指の臭いを嗅ぎ、ぺろりと舐めた。掌は頭にのせられ、アットの頭を優しく撫でた。左手がアットの柔らかなおなかに掛かる。両手を添えて、アットは抱き上げられた。その男、大人の部下、ネガティブの青年、タワーの胸の中で、アットは上機嫌でぶるぶると喉をならした。
セピア色の髪、セピア色の肌、緑がかったセピア色の瞳。アウトラインはほとんど人間族と同じでありながら、全く別の印象を与える色合い。ネガティブ人間という表現がふさわしいだろうか。しかもタワーは均整の取れた体躯、知的で切れ長な瞳、鼻筋の通った美青年である。その姿が美しければ美しいほど奇怪さを増すと言うことがある。ネガティブはもともと奇怪な外見の人種であるが、月明かりに照らされたその姿はより一層不気味で、それゆえ神秘的であり、荘厳でさえあった。
タワーは何万を数える軍勢を率いる領主ルイの家臣団でも名実供にナンバー2の要職にある人物だが、常人には理解しかねる突飛な思考と行動の持ち主で、護衛を付けずに出歩くことも珍しくない。彼は、他の家臣のように直属の親衛隊も、参謀も持たない。それでも今の地位を不動のものとしていられるのは、彼が数少ない夢使いの術を心得ているからであった。
夢使いは摂理に合わぬ不条理な事をいとも簡単に紡ぎ出す事が出来る。その力は利用の仕方次第では何万の兵力を凌ぐ。無論、タワーは夢を最大限に活用する知略にもたけている。故に彼は、謀略の達人と言われ、油断も隙もない領主ルイの元で道具として利用されるに留まらない活躍が出来るのである。
タワーはアットを驚かさないように注意しながら地面に腰を落とした。心配するまでもなく誰にでも愛想のいいアットは腕から逃げ出そうとはしなかった。むしろ、胸にがっちり掛けられた爪で痛い思いをしたタワーの方が被害者かもしれない。
そのままタワーは地面に寝転んだ。アットはタワーの脇でくつろいでいる。
「君の村の事について、少し教えてもらうよ。」
タワーは夢の世界へ入っていった。
************************************************************
さて、やっと話が本筋に入ってきました
ここらへんまでついてきてくれる人がどのくらいいるか