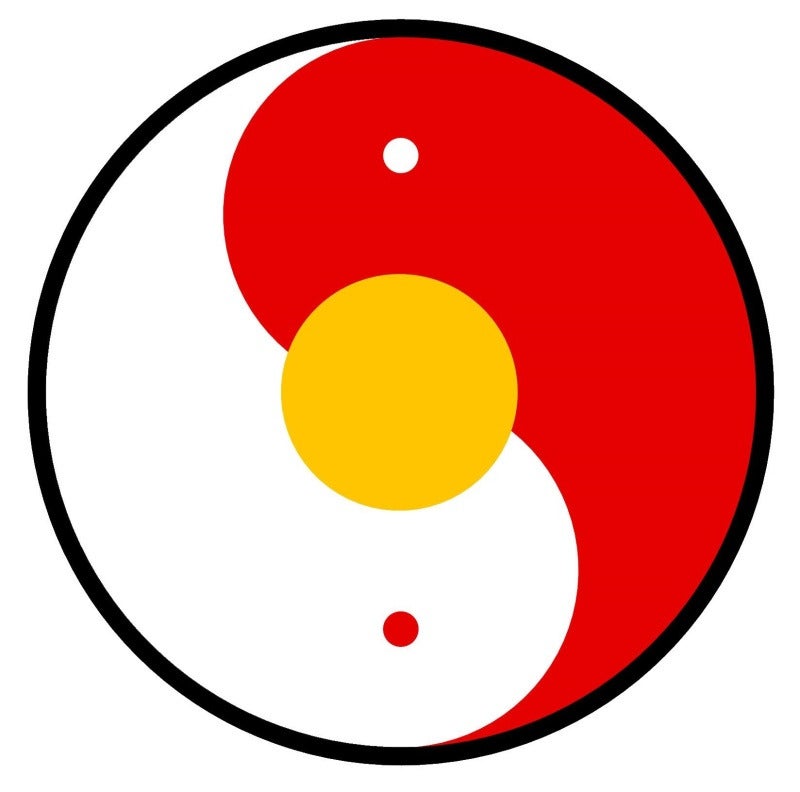“カレッジが始まって数週間経ったある日、クラスメートの一人とお昼を一緒にとりながら、リチャードのことを打ち明けた。すると同情に満ちたクラスメートの瞳が、ある思いで輝いた。
「亡くなった人に本を読んであげることが供養になるって、ルドルフ・シュタイナーが言ったこと知ってる?」
「えっ、本当?詳しく教えてくれる?」
私は興奮して大きな声を出していた。
「*キリスト者共同体の、ルイス司祭に電話するといいわ。詳しく話してくださると思う」
*キリスト者共同体とは、1922年に中部ヨーロッパで開始されたキリスト教運動のこと。その設立の際、シュタイナーの提案や援助を得た。
彼女は、司祭の電話番号を教えてくれた。彼女にお礼を言うと、食堂の公衆電話へと急いだ。サクラメントに引っ越してきてすぐ、私は一度だけキリスト者共同体の礼拝に出席したことがあった。電話番号をダイヤルしながら、私の心ははやった。読書がリチャードのためになるという気が、確かにしていた。
電話口に出たのは、ルイス氏本人だった。私が用件を告げると司祭は、本を読むことは確実に、亡くなった人の供養になるのだと語り、シュタイナーの本から何カ所か、死者のための読書を勧めている部分を教えてくれた。
「亡くなった人のために本を読むことは、たいへんな供養になります。**死後、最初に体験することを乗り切る時、死者の魂は精神的な糧に飢えています。彼らのために本を読むということは、とても良い栄養を与えることになるのです」
**生前を逆時系列で振り返る期間をカマロカという。生前の生存期間の約三分の一をそこで過ごす。
「何を読めばいいでしょうか?」
「精神的な成長を促すものであれば、何でも構いません。たとえば、聖書、特にヨハネによる福音書(13章から17章まで)、詩、瞑想のための詩、スピリチュアルな歌など。もちろん、ルドルフ・シュタイナーの本はどれも最適です。息子さんはどんなことに興味を持たれていましたか?」
リチャードが音楽に関心を持っていたことを告げると、司祭は続けた。
「シュタイナーは音楽に関する連続講義をしています。カレッジの図書室に、講義集の冊子があるはずです。それから始めるのがいいかもしれませんね。授業のために読んでいる本も素晴らしいですよ。基本書の五冊は、シュタイナーの業績の基礎ですからね」
具体的にどのように読書したらいいのかと尋ねると、司祭は、詳しい読み方を説明し、死者の魂のためにシュタイナーが書いた詩を、後でいくつか送ると言ってくれた(次頁および、一八四頁【付録Ⅰ】参照。)読書をする前にこの詩を読むことで、リチャードを呼び出すことができるのだという。私は胸が高鳴るのを感じた。”(P98~P100)
“リチャードや既に故人である他の家族たち、そして友人たちが、自分の前に立っている姿を想像し、一人ひとりの名前を呼んだ。準備した文章に没頭するように努め、それぞれに愛情を込めて読むように心がけた。
「神よ、亡くなった魂に読書をする間、どうぞ私をお守りください」
と私は唱えた。ルイス司祭が、読書の前にこのような祈りをするようにと教えてくれたのだ。なぜなら、死者の魂は私達とは異なった波動を持っているため、私達の代謝作用を狂わせることがあるからだそうだ。ろうそくに火を灯し、私は詩を読み始めた。
神の聖霊よ、守護天使よ
あなたの翼が、私の愛の願いを運んでくださいますように
この時空で、あなたのご加護に身を委ねるこの者のために
そして、あなたの力と相まって
私の愛が、愛を求める魂に、救いの光を照らしますように
精神の世界にいるあなたに、私は注意を向けています
そう、そちらにいるあなたに
私の愛が、あなたの心をやわらげますように
私の愛が、あなたを暖めますように
この愛が、あなたに届き
あなたを精神の暗闇から光へと
導く助けになりますように
何という美しい詩だろうか。特に二連目の部分を読んでいるうちに、あふれる思いで胸がいっぱいになった。
リチャードに、生きている間に力になってやれず、すまなかったと詫びた。そして、ようやく助けになるであろうものを見つけたと伝えた。それから『音楽の本質と人間の音体験』についての、一日目の講義録を読み始めた。(P101~P102)
“やがて六三歳になり、体調を崩していた私は、もしかしたら自分の死期が近づいているのではないかと感じていた。ソファーに腰かけ、感じるままを日記に記し、衝動的にリチャードに質問を書きつけた。
「もし私が死んだら、私に会ってくれる?」
すると、私の周りで、イライラした波長を感じ始めた。リチャードはそこに来て、まだ私がこの世を去る時は来ていないことを知らせてくれたのだ。彼にはまだ、私の助けが必要だったのだ。「お母さんがすべてをあきらめてしまうなんて考えたことはない、この世で僕を救えるのはお母さんだけなんだよ」と彼は私をたしなめた。”(P131~P132)
“リチャードの死後、私達二人は共に問題に向き合うことで、大きく前進したと感じざるを得なかった。もちろん、まだ私にとっては、彼が精神の世界で他の人と一緒に働いているらしいということは驚きであったのだが。
私に霊能力があり、思いのままにリチャードと交信することができたらどんなにいいだろうか、と思ったものだった。なぜならリチャードは、何度も私と交信しようと試みていたかもしれず、ただ私には、聞こえなかっただけなのかもしれないのだから。
リチャードが死後どれだけ成長したのかは、やがて一九八八年七月四日に明らかになった。それは彼が逝って、六年が過ぎようとしている頃だった。リチャードはまた夢に現れた。今回の夢は、過去二つの夢とはまったく違っていた。リチャードは、今までとは違う場所に移っており、そこは光に満ちた部屋だった。リチャードは生前、整理整頓ができなかったというのに、その部屋はきれいに整理されていた。部屋の棚には、幸福で前向きな生活を象徴するような美しい物や、記念の品々があふれていた。部屋に入ると、リチャードは私を見上げてうれしそうに言った。
「ここから何でも見えるんだ」
私の心は、深い感謝の気持ちでいっぱいになった。リチャードはようやく安らぎを見つけたのだ。そして私の心も、安らいでいくのがわかった。
この夢を見たこともあって、リチャードの今回の人生と自殺に関して、ある種の完了感を得ていたのだが、私はそれからも読書を続けた。これからわたしたちがどこへ向かうのかは、見当もつかなかった。
それから数ヵ月後の一九八八年十月、私は「悪」に関する研究会に出席していた。講演で、当時アメリカの人智学協会の書記長をしていたワーナー・グレン氏が、「自殺者に本を読み、交信することで関わっていかねばならない」と語った。自殺者の霊は、深い絶望の中で孤立しているだけでなく、彼らに残された生命力は、「悪魔的な存在」によって、人間の進化を破壊的な方向へ向けるのに利用される可能性があるということだった。だが、もし私達が自殺者に助けの手を差し伸べるのであれば、彼らの残りの生命力は、大きな善行に活かせるのだという。リチャードと私の行った作業が有意義であったと聞いて、私はうれしかった。”(P146~P148)
(ドレ・デヴェレル「闇に光を見出して わが子の自殺と癒しのプロセス」イザラ書房)
*この本「闇に光を見出して」は以前にも紹介させていただきましたが、シュタイナーは、亡くなられた方の供養として霊的な読書を行うことが、死者の魂にとって、何よりの救いとなると言っています。この本の中には、その具体的なやり方や、実行してみて著者がどのような体験をされたかなどが、詳しく述べられています。霊的読書のための本として、「霊界物語」やスウェーデンボルグの著作などもふさわしいと思いますが、仏教で葬式をされた方であれば、たとえば日本語訳のお経(阿弥陀経や法華経など)を、自分自身も内容を理解しながら、そして描写されている浄土の光景などを思い浮かべながら、故人の魂に語りかけるように読まれるのが良いと思います。もちろん、神仏にその方の霊魂を導いて下さるよう祈るべきなのは言うまでもありません。
“人間が死の門を通っていくときには、それまで秘せられていたすべての魂の力や憧れも表に現われて、死者となったその人の魂に影響を及ぼします。その人が生前、心中ひそかに抑えていた願いのすべてが浄化期(カマロカ)を生きる魂の中に現れます。この世で霊学の敵であった人たちも死の門を通った後では、霊学をこの上なく熱心に求めようとします。霊学嫌いな人が死後になると、霊学を求めるようになるのです。
そうすると、次のようなことが生じます。・・・もしその人に生前、霊学書を手渡そうとしたら、叱りつけられたことでしょう。けれども、死者となったその人に対しては、霊的に深い内容を持った書籍、聖書やお経を読んであげること以上によい供養はないのです。生前の死者の姿を生きいきと心に思い浮かべながら、心の中で、または低い声で、死者たちに読んで聞かせるのです。そうすれば、それが死者に対してもっとも好ましい働きかけになります。そのような例を私たちは人智学運動の内部で数多く経験してきました。家族の誰かが世を去り、後に残された者が、その死者に対して朗読して励ました例をです。そうすると死者たちは提供されたものを深い感謝とともに受け取ります。そしてすばらしい共同生活を生じさせることができるのです。
まさにこのことにおいてこそ、霊学が実際生活の中でどんな意味を持ち得るのかがわかります。霊学は単なる理論なのではなく、人生に働きかけて、生者と死者の間の壁を取り除くのです。断絶に橋が架けられるのです。死者たちには読んで聞かせてあげること以上によい助言はありません。
そこで次のような問いが生じます。・・・一体死者は、霊界で教え諭してくれるような霊的存在を見出すことができないのでしょうか?ええ、見出すことはできないのです。死者は、生前結びつきのあった霊的存在たちとしか関係が持てません。死者がこの世で知ることのなかった神霊や死者たちに出会っても、死者はその存在を素通りしてしまうのです。どんなに役に立ってくれそうな存在に出会っても、生前関係がなかったのでしたら何の役にも立ってくれないのです。(1913年1月21日、ウィーンでの講演)”
(「シュタイナーの死者の書」(ちくま学芸文庫)より)
*シュタイナーによれば、生前何の信仰も持っていなかった人は、死後に霊界で自分を救ってくれる霊的存在を自分の力で見出すことができません。しかし、親族や親しかった友人たちの声、想念は彼らのもとに届きます。そのように、死者の魂は生きている人、特に親族の方々の援助、祈りを必要としており、自死された方の霊魂であればなおさらです。また、江戸時代の霊界通信「幽顕問答」にも、『無念の事は人界より解き貰はざれば止む事なかりけり』とあります。死者の魂の救済には、必ず「人界」つまり現世の側からの働きかけが必要とされます。
・死者のための「霊界物語」の拝読
“「霊界物語」の拝読は、私たちのみたまの糧として大事なことはよく判っていますが、また亡くなられた霊にとっても、大事な糧であるという一例を申し上げてみたいと思います。
綾部へ聖師さまのお供をさしていただいた時の話ですが、聖師さまはいつもお寝みになる時は物語の拝読を聞きながら、お寝みになられるのですが、いつものように山水荘で物語を拝読しておりますと、誰もいるはずの無い二階からトントントントンと下りてくる人の足音がして、衣擦れの音と共に、私の横にチョコンと座る気配が致します。私は“アッ、気持ちが悪い”と思いましたが、“ナーニ聖師さまがおいでになるのだもの、こわいことはない”と思って、物語を読み続けていました。
終わって見廻しましたが、もちろん誰もいません。聖師さまに「さきほどここに人の座る気配が致しましたが、あれは何だったでしょうか」とお聞きしましたら、「あれは中有界に迷っている霊が物語を聞きにきたのや。物語を聞いて、あれで天国に救われるのや、だからそこらに人がいなくても声を出して読めというのはそのことや」とお教え下さいました。”
(「おほもと」昭和47年10月号 三浦玖仁子『神は見通し聞きとおし』より)
*亡くなられた方の供養として「霊界物語」を読まれるのであれば、特に47巻と48巻の「天国篇・霊国篇」が良いようです。