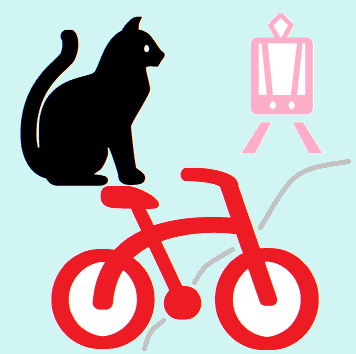週3日だけ公開!千葉にある貴重な「昭和初期」の町役場建物…当時の議場が復元されてます♪
今回ゆるポタしてきた場所は、千葉県千葉市中央区浜野町1290-3にある「旧生浜(おいはま)町役場庁舎」です。
以前の記事でも外観写真を公開していますが、内部公開が週3日(火木土)に限定されるうえに祝日も市役所の意向で休館するなど、建物内に入る機会が今までありませんでした。
旧生浜町役場庁舎は、かつての生浜町(昭和30年に千葉市へ編入)の役場庁舎として、今からちょうど90年前の昭和7年8月に竣工しました。
(資料出所:□外部リンク参照)
千葉市内では数少ない昭和初期における洋風建築物のひとつで、建築技術や意匠には東京などの中心都市の建物に比べて地方色が強く見られる内部に、初潜入するチャンスに恵まれましたので、今回の記事にてご紹介したいと思います。
すぐ左に町長室
正面玄関入って現在は管理人(NPO法人「ちば・生浜歴史調査会」)の事務所になっている場所が、かつての町長室だったようです(今は、ただの「受付事務所」化された内観)。
昭和30年に千葉市と合併した後、暫くは生浜支所となり、その後は生浜地区市民センターとして平成3年までは現役で使用されていたようです。
生浜地区市民センターが新築移転した翌(平成4)年、千葉市教育委員会が保存・整備に着手。
近代建築史の変遷を考える上で貴重であると判断され、平成6年に千葉市指定有形文化財(建造物)に指定されました。
戸籍の窓口
正面玄関入ってすぐ右手は、現在でも我々が普段利用している住民票の写しや戸籍謄本などの交付申請、および転居の際における窓口だったようです。
「戸籍(昔の書き方だと、逆方向に横書きするので“籍戸”)」の文字がほとんど消えかかっていましたが、当時のままの状態でプレート表示が残っていました。
事務所側に入れて頂くと、昔懐かしのゴム印を収納する木製BOXがありましたよ!
狭い事務所スペースを有効活用する為でしょうか?・・・
※敷地面積は495.86㎡(25×20m)、建物面積は1階:156.40㎡(15×10m)+2階:107.57㎡=合計延床面積263.97㎡
受付窓口の正面を向くのではなく、横向きで市民(町民)と対応し、その場で即時に事務処理を行い必要な書類を交付していたのが、この生浜町役場における特徴です。
現地案内人(管理人=先述NPO所属のボランティア)の話によると、窓口部分(内部事務所側)における机の配置については、役場当時の状態を再現しているとの事。
生浜の産業史を展示
生浜町の役場が置かれた、海辺に近い浜野地区における以前の主産業は漁業(貝類養殖、海苔養殖、はぜ漁、簀建=“すだて”と呼ばれる迷路状の定置漁具で干潮時に魚を獲る漁法)。
以前に過去記事でもご紹介した、同じ千葉県内における東京湾岸の浦安市や行徳(市川市)の事例とほぼ同じような状況だったようですね。
漁業権放棄は、京葉工業地域として一足早く埋立が進行した浜野の方が、浦安よりも10年早く昭和36年だったとの事。
旧生浜町役場の1階では、かつてこの地で行われていた海苔養殖に関する漁具の展示とビデオ上映や、この地区に隣接する蘇我(千葉市中央区)や八幡宿(市原市)の埋め立てが徐々に始まりつつある頃の古地図など、当時の生浜を偲ぶ資料がありました。
議会
2階には、当時の形に復元された議場になっていて、「議長」や「書記」といった席が再現されて町議会の議場に居る議員さんの気分を味わうことができるかも?
千葉市に合併(編入)する以前の、歴代町長の写真も掲示されていました。
2階の議場の扉から出入り可能な玄関ポーチの上にあるバルコニーは、明治初期から大正期に建てられた郡役所建築によく見られ、この建物を特徴づけるものですが・・・
旧山形県庁(山形県山形市)のように、天皇陛下が来て手を振ったりすることはありませんでしたが、女性職員がお昼にバルコニーに出てお弁当食べたりしていたとの事。
また、山形(旧)県庁のように結婚式は無いけど、当時の男女が出会う社交ダンス会場になったりしたらしいと、案内して頂いたNPOの人による説明があり・・・
当時を偲んで暫くの間、2階の窓から塩浜橋の交差点を眺めていました。
2階の階段横には和室6畳の「議員控室」も設けられていたようです。
懐かしの道具
再び1階に戻り、役場機能の中枢を担って職員たちが執務をしていたメインの事務室内に展示されている「電話室」を見学。
この「電話室」は、元々は役場にあったものではなく、近隣にある小湊バス(小湊鉄道のバス部門)の塩田営業所に置かれていたものを移設保存しているとの事。
千葉市中央区浜野町は、房州往還(現在の国道16号・127号に相当)と、茂原街道(県道14号)が結節する交通の要所であり、そこへ路線バスの車庫と公衆電話が置かれたようですね。
※元々は道路元標がある浜野交差点にバス車庫を置いたが手狭になり、現在地(本記事内後述)の場所へ「飛び地拡張」したのが、現在の小湊バス塩田営業所?
昔の電話には「数字ダイヤル」は無く、左手に受話器を取り、右手で電話機右横にあるハンドルを回して、出てきた交換手に自分が掛けたい相手の番号を伝える方法で使っていたとの事。
さらに、1階左手奥にある用務員室(小使室)には昔の生活道具が展示されていて、昔懐かしの形をした行火(あんか)に、自分が幼少の頃(40年前)に見た婆ちゃん家を想い出しました。
上棟札
1階左手(小使室)の手前にある職員の宿直室として使われてていた部屋には、昭和7年3月着工、同年5月に上棟した旨を示す上棟札が展示されています。
さらに、この木造2階建ての洋風建築の屋根に使われているフランス瓦がありました。
保存整備の方針が打ち出された平成初期における大改修では、基礎の部分から「丸裸」にされて腐食して傷んだ部材を交換・再生しているようですね。
もはや「リフォームの匠(テレビ朝日ビフォーアフター)」とか、「新築そっくりさん(住友不動産)」の世界観ですな・・・
塩田天満宮
「旧町役場」見学の後は、近隣(170mほど北側)にある天満宮様へご挨拶。
※千葉市中央区塩田町207、『文政元年寅?霜月吉祥日』(1818年)の鳥居あり
天満宮(塩田町)の創建年代は不詳ながら、北生実第二区(塩田町)の鎮守だったといいます。
※本殿は間口2間×奥行2間、境内528坪の規模
ちなみに、「塩田町」の地名由来は、川の曲流部にあたる「しおた(撓田)」で、浜野船着場(浜野河岸)に繋がる浜野川下流域の「たわんだ地形」に因んでいるとの事。
残念ながら、普段は手水舎に水が無いようですが、境内は綺麗に整備されていました。
本殿の左側に、菅原道真公を祀る神社には、ほぼ必ず置いてある撫で牛が一体。
境内の裏側に、前述した小湊バス塩田営業所(車庫)がありました。
元々は、明治6年に開学した塩田小学校が存在した場所のようです。
現在における千葉市立生浜小学校、およびそこから分化した生浜西小学校のルーツになった1校と思われます(□外部リンク参照)。
いかがでしたでしょうか?
今回は、今からちょうど90年前に竣工した「旧生浜(おいはま)町役場庁舎」の、建物内部を見学した時の様子をご紹介いたしました。
JR内房線の最寄駅「浜野」から徒歩15分なので、歩けない距離ではないのですが、千葉駅から蘇我駅を経由し浜野・八幡宿方面行きの路線バスに乗れば、バス停はすぐ近く!
「塩浜橋」というバス停で降りて、ローソンの看板目指して歩いて、信号機のある交差点を渡ったすぐ左手(踏切の45m手前)にありますよ♪
もし数少ない公開日に偶然通りかかったら、せっかくのチャンスを活かして皆さんも是非とも、貴重な有形文化財である昭和初期の役所洋館の内部を覗いてみてはいかがでしょうか?