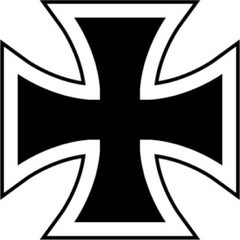今回は大楠公・楠木正成の「凄み」が十二分に発揮された回でした。
思えば、楠木正成と言えば戦前の皇国史観で散々にその本質を歪められた一面がありました。「忠臣」という側面ばかりが強調され、その戦術家としての見事な軍略の天才ぶりが伝わらない。今回はフィクションも交えながら、その軍神の凄まじさ、そして新たな一面に着目した彼の凄みが十二分に発揮されています。やはりこれは
南北朝のラスボス足利尊氏を倒せるのは大楠公のみ
という当時の人の考えを体現しているのでしょう。実際、本作を見たら、「彼なら倒せる!」と思っちゃうほどの大活躍ぶり。なお最後に(目逸らし)それでは本編感想参ります。
〇錦の御旗をもう一つ用意すれば怖くない
遂に始まった湊川の戦い。大船団を組んで海陸双方から迫る足利の大軍。『太平記』では例によって例のごとくこの時の足利軍の兵数を50万騎以上と盛るに盛ったりの極みの数字を持ち出していますが、いずれにせよ足利軍対帝派の新田・楠木軍の兵数についてはやはり足利の方が兵力が上だったのは事実とみてよいでしょう。大楠公はその大軍ぶりに息を呑みますが、何も分かっていない様子の新田義貞は
新田義貞「先の戦同様…朝敵だと思い知らせば足利の士気はガタ落ちだ!」
そもそも先の戦いで足利軍が士気ガタ落ちだったのは何よりも後醍醐帝を深く敬愛する総大将のメンタルがガタ落ちになった所為であって、しかもその総大将が出陣するとあっという間にひっくり返されたのを忘れた様子です。そして彼が逆転の秘策として用意したのが
マジか…コイツ、話にならん!(画像略)
嘲笑をもって迎えられる錦の御旗。もちろん既に足利サイドは「錦の御旗対策」を用意していました。その対策を提言したのが、この画像のコマにいる赤松円心。逃げ若では彼が「対策グッズ」を用意するキャラでその役割を描写しています。ここで歴史解説。この時代はある事情により、天皇家は2つの皇統に分かれ、それぞれが交代で帝位を即位している「両統迭立」という歪な状態となっていました。始まりは鎌倉時代中期、後嵯峨帝という天皇(院)が2人の息子のどちらの系統が嫡流にするのか明確に遺言せずに崩御してしまったこと。その結果として朝廷はそれぞれの系統とそれと結びついた貴族たちによってドロドロの権力闘争に発展。鎌倉幕府は両者に配慮する形の仲裁案として、「両統迭立」という形にしたのでした。しかし、当然ながら2つの系統「持明院統」と「大覚寺統」にしてみれば不満の残る内容。何しろ代を重ねていけば、どんどん疎遠となって赤の他人に近い親戚に位を譲り、その次にいつ自分の系統がなれるか分からないのですから。結局、鎌倉幕府が用意したこの折衷案は当座のゴタゴタを治めることはできても、将来的に大きな禍根を残すことになります。更にこれもまた代を経る毎にそれぞれの系統内部でも継承に関していくつかの派閥に分かれていきます。ことに大覚寺統に至っては3派にわかれての内紛。一応持明院統の方はまだマシな方でした。やがてそれが巡り巡って大覚寺統内での「自分の血統で帝位を独占したい」と考える後醍醐帝というエゴの塊のような帝王に逆恨みされて、倒幕戦争を仕掛けられる羽目になるのですから皮肉なモノ。そして今まさにそれが最悪な形で発露されることになります。足利側は密かに持明院統の光厳上皇と接触して、お墨付きを得ることで賊軍を回避することになったのです。もっともこれはある意味では禁断の一手。相争う二派がそれぞれ別の系統の帝を持ち出せば、双方官軍になるというのだからより混迷は増すというもの。その意味でも「両統迭立」は色々な意味で禍根を残すものであり、結局この南北朝時代以降は行われなくなりました。ある意味当然ですね…最も幕末戊辰戦争時に奥羽越列藩同盟は自らの正統性をアピールするために皇族を擁立して東武皇帝として即位させる構想(結局どこまで真剣に考えられたのかは疑問ですが)があったので、そうなるとまたどうなるか分かったものではありませんが。いずれにせよ
解説「この選択が超絶面倒な時代の到来を招くことを当の尊氏は…」
流石は南北朝のラスボス、目先のこと優先で深謀遠慮とか言う言葉はこの男の辞書には存在しない!
〇湊川決戦!開幕
かくして激突する足利軍VS新田・楠木軍。ここら辺からの展開はオーソドックスに『太平記』準拠で、東の方へ船団を向かわせ、それにまんまと引っかかった新田義貞が東の方へ軍勢を向けて、結果楠木軍と新田軍が分断されて、孤立してしまうという展開に。もっとも大楠公はその辺は織り込み済みな模様。うーん、やはり大楠公、新田義貞を全然戦力としてまったく当てにしていない様子で、この辺は『太平記』『梅松論』での冷淡な態度と一致しているな。ただこの状況を見るとどう足掻いても圧倒的兵力差がある以上、新田義貞ばかりが責められるのは酷というもの。
大楠公「我が七百騎で…百倍の敵を倒せば済む話」
と不敵に笑う大楠公なのでした。まずは狙うのは陸路で進撃していた腹黒い弟の直義。ブラコンの鑑というべき南北朝のラスボスが愛する腹黒い弟の危機に何もしない筈はありません。
鬼神の如く奮戦し、凄まじい武勇を発揮する大楠公。16回もの突撃は『太平記』に記されている通りで、思わず腹黒い弟が一時窮地に陥る程。当然ながら南北朝のラスボスを弟を救わんと高兄弟を向かわせます…ここまで『太平記』通り。しかしここからは逃げ若独自のオリジナル展開で進みます。ある意味、本作らしさ全開。
〇軍神大楠公の本領発揮
足利軍最強の戦闘ユニットである高兄弟が襲い掛かり、「三つ鍬形の兜」を被った大楠公を容赦なく斬り捨て…それは影武者でした。普段は烏帽子しか被らない大楠公がこれ見よがしに突撃前に兜を被ったのは実は伏線。そして真の狙いは…
大楠公「全ては尊氏殿、そなた一人を討つためだ」
忽然と手薄になった南北朝のラスボスの近くにただ一人で対峙する大楠公。そう、彼はまったく諦めてはいなかったのですね。全ては南北朝のラスボスのブラコン愛をも計略に組み込めての一大計略。慌てて護衛の武士たちが駆け込もうとするも周囲は撒き菱を敷設、あの突撃は全てこの地ならしのためであったのです。結果、尊氏と正成という2人のこの時代を代表する英雄の周りには結界となす、
大楠公「京を使った防衛線なら楠木は足利に勝るゆえ、撒き菱と16の突撃で京32の路を区画したこの一騎打ちに邪魔を入れぬための結界
名付けて『偽京の計』!」
『太平記』では既に死地に赴く覚悟であった楠木正成でしたが、『逃げ若』世界での大楠公にそんな「死にたがり」はそもそも本作の世界観には全くマッチしません。全ては尊氏一人を孤立させ、倒すことで勝利を目指すという
『銀英伝』でのバーミリオン会戦でのラインハルト一人の打倒を目指すヤン
を彷彿させる「決して勝算なき戦いはしない」という如何にも本作の大楠公らしさ全開です。史料に残る限られた情報を取り入れながら、そこは逃げ若独自の解釈で全く違う世界ながら、引き込まれてしまう見事さ。何より南北朝時代の日本最高の智将らしさをこういう形で描いたか!と膝を打つ思いです。なおも大楠公に付き従う郎党たちが更に撒き菱を散布し、足利軍の武士たちを足止め。自らの郎党たちの練度と絆も信頼し、対決の時間に十分な時間を手に入れた大楠公。もちろんそんなことに焦る南北朝のラスボスではありません。
南北朝のラスボス(軍略の天才楠木正成…個の武の強さは聞いたことは無いが果たして…)
つ、強い!何だこの凄まじい強さは!
ひとかどの戦士であった護良親王の攻撃すら
こんな余裕綽綽であった南北朝のラスボスが冷や汗をかくほど!「軍略の天才は個人的戦闘力が無い」なんて固定観念を木っ端みじんにしてしまうぐらいのインパクトがありました。でも実は考えてみれば、大楠公はかつて時行くんの鬼心仏刀を封じる時に素早くその技の本質を見抜くなど高い戦闘力を示す伏線はあったのですね。そこに『太平記』でも記述された「湊川の戦で正成は16回もの突撃を敢行した」に着目して、そんなことができる男が弱いわけはないと着目したとはすばらしい。軍略にも秀で、武勇にも隔絶した戦闘力を有するまさにこの時代最強の名将・楠木正成、その面目躍如!となった回でした。
大楠公なら…楠木正成なら…南北朝のラスボス足利尊氏を倒すことができる!…
そう思った時がありました。
〇南北朝のラスボスはまだ本気を出してなかっただけ
大楠公「未だ誰も足利尊氏という男の底を見た者はいない」
勝つためにはいかなる手段をも利用する大楠公らしさ全開で、潜ませていた含み針による奇襲、さらに腕に一撃を加え、更に蹴りで膝を折るというまさに卑怯もへったくれもない容赦ない攻撃で南北朝のラスボスを追い詰めていきます。かくして、今まで想像もしなかった南北朝のラスボスが地面に叩きつけられると言う展開に思わず息を呑んでしまった。目つぶし、腕を貫き、脚と首を折った上に、持っていた太刀を失ってしまった南北朝のラスボス。遂に決着がついたかに見えたその時
南北朝のラスボス「光栄に思うがいい!この本気を見せるのは貴方が初めてです!
貴方だけです楠木殿。我が本気を引き出してくれるのは」
うーん、読者までをも圧倒的絶望感に叩き込む展開。まさに「勝てる!」と思わせてのUGてOTす展開。
解説「命に危機が迫った時程尊氏は穏やかな笑顔を浮かべたという」
南北朝のラスボス「ご安心を。一刀で逝けます」
だ、ダメだどう足掻いても絶望しか感じない。本当にフリーザ様に匹敵するよな、南北朝のラスボス。
ちなみに劇中で登場した骨喰は室町幕府で代々伝わる足利家の大薙刀。その後は爆弾正、大友宗麟、信長、秀吉、家康と持ち主が変わり、更にこの過程で脇差へと打ち直されているので、薙刀としての骨喰の姿は分からないので、自由にデザインし放題。うーん、まさにラスボスに相応しい禍々しい薙刀になっているな…