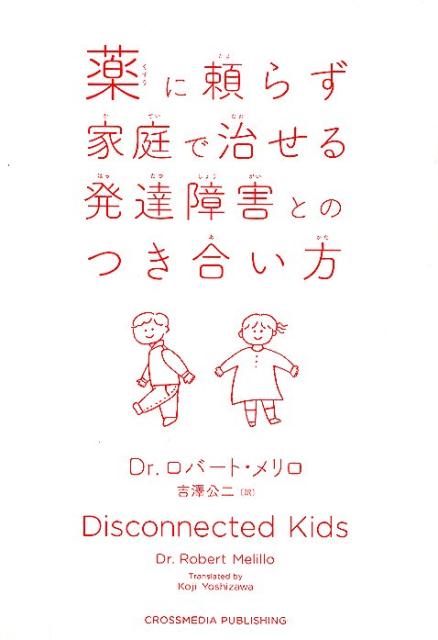BBIT認定療法士の後藤保彦です。
左右脳の機能的なバランスを調整して統合させることを目的に、BBIT(脳ベース統合セラピー)を提供しています。
今回の記事は、④になります。
最初から見たい方は、先にこちらからどうぞ。
①
②
③
さて、ご存知ロバート・メリロ博士がTEDトークに招待されて収録したものが公開されています。
続きの翻訳を載せていきます。
(ここから)
8:28
生後3年が経つと、今度は左脳が活発に働き始めます。
左脳の発達が遅れると、ディスレクシア(読字障害)、学習障害、情報処理障害、うつ病、双極性障害、拒絶過敏性不全(RSD)などの問題が現れることがあります。
左脳の役割は「細部を分析すること」です。世界を小さな要素に分解し、それらを順番に並べ、直線的・連続的にパターンを見つけて、次に何が起こるかを予測しようとします。そして、それを繰り返し行います。
左脳は「小さな部分」に焦点を当てます。例えば、記号や文字、数字といった静的なものを識別するのが得意です。
また、左脳は「親しみのあるもの」を好み、同じことを何度も繰り返す性質を持っています。この傾向が極端に強くなると、強迫性障害(OCD)の症状として現れることがあります。
さらに、左脳は運動活動の開始をコントロールする役割を担っています。この機能が過剰になると、チック症、常同行動(stimming)、多動、トゥレット症候群(Tourette's syndrome)、音声チック(vocal tics)といった症状が現れることがあります。
左脳は「運動計画(モータープランニング)」も司ります。これは、小さな筋肉を素早く順序よく動かす能力であり、例えば「手書き」や「タイピング」などが含まれます。この機能に問題がある場合、「発達性協調運動障害(ディスプラクシア)」や「書字障害(ディスグラフィア)」と診断されることがあります。
また、左脳が最も複雑に制御する運動機能は「言語」です。言語の表出(話すこと)や受容(聞いて理解すること)など、すべての「言語的な機能」は主に左脳によって管理されています。そのため、吃音(どもり)、発音の問題、言語の発達の遅れなどは、左脳の発達に関連する問題と考えられます。
さらに、左脳の「弓状束(Arc of Fulcus)」と呼ばれる部位に過剰な接続(ハイパーコネクティビティ)がある場合、「反響言語(エコラリア)」や「スクリプト化(決まったフレーズを繰り返すこと)」が見られることがあります。
左脳は「アプローチ行動(接近行動)」を司る脳でもあります。これは、「何かを求める、探しに行く」という行動のことで、例えば、多動の子どもが常に動き回ってじっとしていられないのも、何かを探している状態だと考えられます。
左脳はまた、「目標を設定し、それを追求し続ける能力」を担っています。目標を立て、それに向かって努力し、継続することに関与するのが左脳です。そのため、目標を設定できない、追求できない、習慣を作るのが苦手、あるいは「やる気が全く出ない」という場合、これは左脳の発達の遅れが原因かもしれません。
一方で、「やる気がありすぎる」と、それは「躁状態(マニア)」と呼ばれます。逆に、「やる気がなさすぎる」と、「うつ病(ディプレッション)」として現れることがあります。
左脳も「感情」を司りますが、それは「ポジティブな感情」に関係しています。例えば、「喜び」や「幸福感」、「誇り」などが挙げられます。しかし、喜びや幸福感が過剰になると、「躁状態(マニア)」につながることがあります。また、誇りが強すぎると、それは「自己愛(ナルシシズム)」として現れることがあります。
一方で、右脳は「怒り」を制御します。実は「怒り」はポジティブな感情でもあり、困難に直面したときに「諦めずに続ける」ためのエネルギーを与えてくれます。しかし、左脳の活動が過剰になると、小さなことでもすぐにイライラしてしまい、それが「癇癪(かんしゃく)」や「パニック」、または将来的な「怒りのコントロール障害」につながる可能性があります。
また、左脳は「明示的記憶(エクスプリシットメモリー)」を担当します。これは、「意識的に学習し、記憶する能力」のことで、私たちが何かを意識して学ぶとき、左脳を使っています。もしこの機能がうまく働かない場合、「記憶障害」や「学習障害」につながる可能性があります。
さらに、左脳は「学問的・知的な分野」に強く関与しており、特に「数学」「科学」「工学」などの論理的思考を必要とする分野で重要な役割を果たします。もし左脳に遅れがあると、学業に苦しんだり、ディスカリキュリア(算数障害)や学習障害などが見られることがあります。
左脳は「交感神経系(ファイト・オア・フライト)」を制御します。これは、体を危険から守るために戦ったり逃げたりする反応を引き起こします。前述のように、これが腸機能を低下させ、夜眠れなくさせ、常に危険にさらされているような感覚を与えることがあります。これが不安を引き起こす原因にもなります。
左脳は免疫系の活性化も行い、感染症に対抗するために免疫系を働かせますが、過剰に活性化すると、右脳に遅れがある場合に見られるように、過敏状態になり、腸に漏れが生じると、グルテンや乳製品などに対する過敏症が発生することがあります。これがアトピーやアレルギー、喘息などを引き起こすことがあります。これらはほんの小さな例であり、さらに多くの例を挙げることができますが、要するに、これらすべての状態や症状は、脳の片方のネットワークが過剰に活性化し、もう片方のネットワークが不十分であることによって説明できるという考え方です。
(ここまで)
今回は、左脳の役割についてまでです。
箇条書きにすると、以下の通りです。
左脳の役割(箇条書き)
・細部を分析し、小さな要素に分解して順序立てる
・静的な情報(記号・文字・数字)を識別する
・親しみのあるものを好み、繰り返しを好む
・運動活動の開始をコントロールする(過剰だとチック、多動など)
・運動計画(モータープランニング)を司る(例:手書き・タイピング)
・言語機能(話す・聞く・理解する)を制御する
・弓状束の過剰接続により反響言語やスクリプト化が見られることがある
・アプローチ行動(目標に向かう行動)を促進する
・目標設定と達成に関与する(やる気・モチベーション)
・ポジティブな感情(喜び、幸福感、誇り)を生み出す
・過剰な左脳活動で癇癪・怒りのコントロール障害に繋がることがある
・明示的記憶(意識的な学習・記憶)を担当する
・学問的・知的分野(数学・科学・工学)に強く関与する
・交感神経系(ファイト・オア・フライト反応)を制御する
・免疫系を活性化し感染症に対抗する(過剰だとアレルギー体質に)
次回、「どうすれば改善できるのか」について、話が続いていきます。お楽しみに!
この話の続きを日本語で読みたい方は、
「いいね」
「フォロー」
「コメント」
をよろしくお願いします。
もっと詳しく知りたい方は、本の最新版(英語)をどうぞ。
Disconnected Kids, Third Edition: The Groundbreaking Brain Balance Program for Children with Autism, ADHD, Dyslexia, and Other Neurological Disorders
Dr. Robert Melillo (著)
日本語で読みたい方は、原著のひとつ前の版になります。
『薬に頼らず家庭で治せる発達障害とのつき合い方』
Dr.ロバート・メリロ (著), 吉澤 公二 (翻訳)
脳バランスを整えたい方は、
510バランスカイロプラクティック自由が丘へどうぞ。
ケースレポートは、こちら。