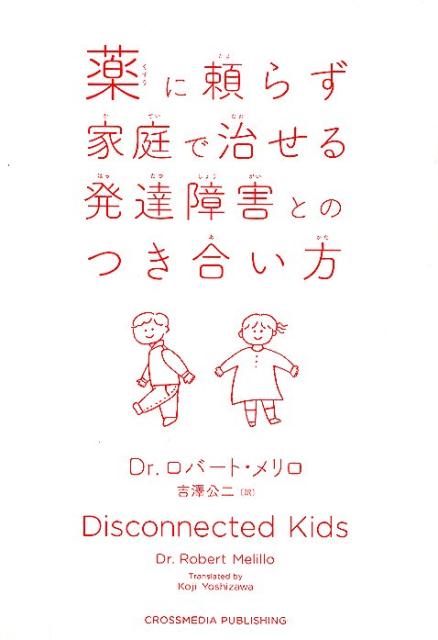BBIT認定療法士の後藤保彦です。
左右脳の機能的なバランスを調整して統合させることを目的に、BBIT(脳ベース統合セラピー)を提供しています。
今回の記事は、②になります。
最初から見たい方は、先にこちらからどうぞ。
①
さて、ご存知ロバート・メリロ博士がTEDトークに招待されて収録したものが公開されています。
早速、本編の翻訳を載せていきます。
(ここから)
すべては、ある1つの疑問から始まりました。「ADHDの子どもの脳内で何が起きているのか?」 私がこれを知りたかったのは、自分の子ども、長男がADHDと診断されたからです。私は神経科学のバックグラウンドを持っており、それが単なる行動の問題ではなく、脳の問題であると信じていました。そして、実際に彼を助けようとする前に、まずそれが具体的に何なのかを知りたいと思ったのです。
最初に出会った概念は「スキルの不均衡」というもので、これは基本的に、ADHDの子どもたちがすべてに苦しむわけではないということを意味しています。実際、彼らは脳の特定の分野では進んでいたり、才能がある場合もありますが、他の分野では苦しむことがあります。これは自閉症、強迫性障害(OCD)、失読症(ディスレクシア)など、すべての神経行動障害に当てはまります。これらの障害を持つ人々は、しばしば天才的な能力を発揮することがよくあります。
10年後、私は自分の研究に関する本を出版しました。その中で、私は主要な質問に答えましたが、その過程で、息子を助けるだけでなく、多くの人々を助けるための独自のアプローチも開発しました。90年代初頭、すべての脳の研究は、ネットワーク間の機能的結合性に関する問題を調べていましたが、私は主な問題が「機能的切断症候群」というものであることを発見しました。簡単に言えば、これは脳の両半球の間の不均衡です。脳には病理、遺伝子変異、または他の傷害はなく、これは遺伝的特性と呼ばれるもの、そして認知スキルの上に重ねられた発達的成熟の不均衡です。
この不均衡に最も影響を受けやすいのは、しばしば最も才能のある人々であるということです。
人間の脳は非対称的、つまり側性化されています。すべての脳がそうであり、これによって私たちは大きな利点を得ています。これは、まるで「二つの脳を一つに持っている」かのような働きをします。例えば、動物は左脳を使って食べ物に集中しながら、同時に捕食者の存在を察知することができます。
人間の脳は、最も側性化が進んでおり、左右の半球は本来、完全に同期し、バランスよく機能するように設計されています。しかし、このバランスが崩れると、多くの症状が現れる可能性があります。特に、行動面やメンタルヘルスに関する問題が引き起こされやすくなります。
実際、多くの症状を見てみると、一見すると理解しがたいものがあります。ある分野では非常に優れた才能を持ちながら、別の分野では大きく苦しんでいる人々がいるのです。この現象を理解する唯一の方法は、脳の非対称性の観点から見ることです。では、それについて詳しく見ていきましょう。
まず、右脳についてです。
右脳は胎児期から最初に発達し、生後3年間は特に重要な役割を果たします。右脳の発達に問題がある場合、ADHD、OCD(強迫性障害)、トゥレット症候群、チック、自閉症スペクトラム、統合失調症、拒食症、愛着障害などの症状が現れることがあります。
右脳は感覚に関わる領域であり、特に痛み、空腹、喉の渇き、疲労といった初期の感覚に注意を払います。また、異なる感覚を統合する役割も担っており、ここに問題が生じると「感覚統合障害」と呼ばれる状態になります。
さらに、右脳は注意を払う役割を担っているため、注意欠陥(ADHDなど)は通常、右脳の発達遅延と関連しています。
右脳は物事を全体的に捉え、文脈を理解し、すべてを統合して見る能力を持っています。
また、大きな筋肉の発達や姿勢の維持、いわゆる「固有感覚」(proprioception)も制御します。
この領域に遅れがあると、運動発達の問題が見られることがあり、子どもが不器用だったり、ぎこちない動きをしたり、バランスが悪かったり、筋肉の緊張が低かったりすることがあります。これを「協調運動障害(ディスコーディネーション・ディスオーダー)」と呼びます。
右脳は非言語的な側面を担う脳の部分であり、非言語的コミュニケーションを通じて情報をやり取りします。つまり、人の表情や体の姿勢、声のトーンを読み取り、言葉を使わずに相手の考えや感情を理解する能力を持っています。これは「ソーシャルブレイン(社会的脳)」とも呼ばれ、他者とのつながりや社交スキルに関連しています。
したがって、社交性に問題がある場合、それは非言語的コミュニケーションと右脳の発達の問題と深く関わっています。
また、右脳は身体と強く結びついており、「自己認識(self-awareness)」や「身体の所有感(body ownership)」を形成します。これは直感や「腹の虫(gut feeling)」とも関係があり、自分の感情や身体に意識的に接することができる能力を意味します。この自己認識があることで、他者の感情を理解し、共感することが可能になります。
もし自分自身の感情を感じ取ることができなければ、他者がその感情を抱くこと自体を想像することも難しくなり、ましてやその感情を理解することはできません。
また、右脳の発達が遅れると、目を合わせること(アイコンタクト)が苦手になります。アイコンタクトの欠如は、非言語的コミュニケーションがうまく機能していないことを示しており、その結果、他者の表情や感情を正しく読み取ることができなくなるのです。
(ここまで)
長くなってきたので、右脳についての前半部分(約5分間)で今回は切りたいと思います。
この話の続きを日本語で読みたい方は、
「いいね」
「フォロー」
「コメント」
をよろしくお願いします。
もっと詳しく知りたい方は、最新版(英語)をどうぞ。
Disconnected Kids, Third Edition: The Groundbreaking Brain Balance Program for Children with Autism, ADHD, Dyslexia, and Other Neurological Disorders
Dr. Robert Melillo (著)
日本語で読みたい方は、原著のひとつ前の版になります。
『薬に頼らず家庭で治せる発達障害とのつき合い方』
Dr.ロバート・メリロ (著), 吉澤 公二 (翻訳)
脳バランスを整えたい方は、
510バランスカイロプラクティック自由が丘へどうぞ。
ケースレポートは、こちら。