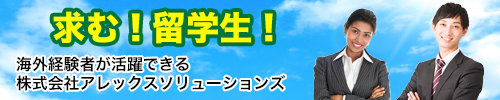先日の社員総会で、社員からうれしいニュースを続いて聞きました。
結婚します、パパになりました、ママになります、家買いました、移住しました、などなど。新婚旅行行きます、ビザ取れました、なんていうのもありました。社員総会はそんなリアルタイムの報告が聞けるうれしい場です。先日はOBからも家族が増えるニュースをいただきました。
うれしい話の中には、社内結婚もいますし、当社に在籍中に3人目の出産の方もいます。
ここで好きな人を見つけて、カップルになり、結婚して、子を作って新しい家庭を作る。。。
この人生で一番重要なライフステージを、自分が創った会社を舞台にして行われるなんて、我ながら「自分は少しは人を幸せにしてるのかな」とうれしく思います。
オフィスに見せに来てくれた、小さな赤ちゃんの顔を見ながら「自分が会社を作らなかったらこの子は生まれていないのかも…」と考えると、なんとも不思議な縁です。
なるべく多くの人を雇用してその人たちを幸せにすることが社長の使命だと思うと、少しはその使命を果たせているかなと思うこともあります。でもまだまだ足りません。これからもたくさんの人に感謝される人間でいたいと思います。
みなさんグッドニュース、ありがとうございました。
雑誌『経済界』に「人材育成企業」として掲載されました。