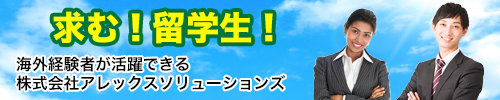先日、週末に携わっている少年ラグビーチームの夏合宿に行ってきました。場所は長野県菅平高原。「ラグビー合宿の聖地」として有名なところです。
そこでは、少年ラグビーだけでなく、中学生高校生のチームも練習をしています。そんな他チームの指導者やコーチを見ていて、「会社経営もチーム作りと一緒だな」とつくづく感じました。
毎年毎年試行錯誤して、いろんな工夫をしてよりよい練習を考える。時にはチームの方向性を直接伝えたり、時にはリーダー陣に任せてこちらは口を挟まない。攻め方や守り方も、チームトークで選手自身で考えさせる。
ラグビーではよく「同じ絵を見る」という表現を使いますが、一緒に試合をしている味方全員が同じ状況と戦略を共有していることを言います。2019年の日本代表はこの同じ絵を見ることができていて、快進撃を続けました。
会社経営にもこの言葉がそのまま当てはまります。いろいろな角度からのコミュニケーションで、社員に同じ絵を見るように仕向ける。そのための仕掛けや仕組みを考えて、それをコツコツと実行する。
高校ラグビーの名監督が、毎年毎年試行錯誤しながらチームを作るように、会社も毎年毎年改善改良しながらコツコツと作っていかないとと、菅平の青空と緑の下、練習する子供たちを見ながら思いました。
雑誌『経済界』に「人材育成企業」として掲載されました。
2020年4月「週刊新潮」取材動画
動画はこちら↓