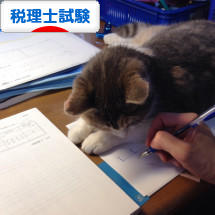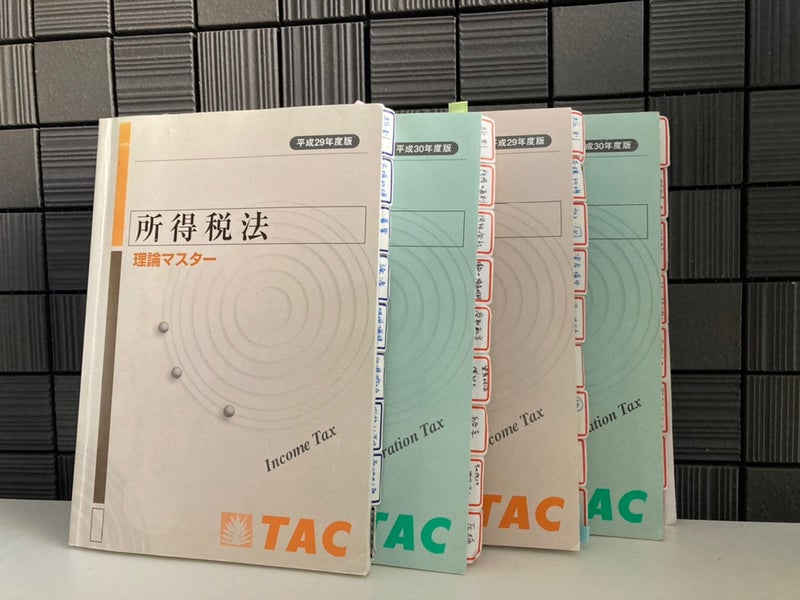どうもーーー!
生きてます♪
最近、何が忙しいかわらからないんですけど、バタバタとしておりましたが、
久々にリフレッシュしたので、現在絶好調です!
だいたい、いつも絶好調ですが。
っということで、ゆっくりと読書する時間が取れたので、
右の本を読みましたー☆
大好きな高山先生のこのシリーズ
個人事業主 v.s. 法人
これは、いろんな人にほんとによく聞かれます。
でも、これって、すごく答えるのってむずかしくないですか。
所得税と法人税の違いだけじゃないですし、
金額のこと考えたら社会保険の有無の影響の方が大きいですし。
未だとインボイス導入も見据えて消費税のことも。
それ以前に、事業そのものへの影響、
登記費用のこと、
会社法の機関設計、株主比率・・・
ほかにも、、、、
税目をまたいだ有利不利のシミュレーションに加え、
様々な要素を複合的・多面的に考えなければいけない。
気軽に聞かれますけど、答えるには難易度高い。
相談者さんに
「税理士(税理士事務所)なんで、他のことは・・・」
とはいえませんからね。
っということで、こちらの本に、ばっちり書いてあります。
知識はもちろん、私がそれと同じ、いやそれ以上に勉強になったことが2つ。
1つ目は、金額の相場観。
特に融資制度のとかって、公庫(日本政策公庫)などのHPみると
設備資金 最長〇〇年、最大〇年
って書いてあるじゃないですか。
でも、それってMAXなので実際は満額になることってほとんどないじゃないですか。
そういう相場観みたいなのって、制度一覧、みたいな本ではわからないんですよね。
逆に、MAXで伝えちゃうと、そんなふうにならなかったじゃないか、的なことを言われかねない。
こういうのって、OJTじゃないと学べないと思っていたわけですが、書いてくれているわけですよ。
でも、自分の経験的な相場観を本に書くのって、わりと勇気いりそうじゃないですか。
公表されているものをまとめるだけなら、リスクないですけど、つまらない。
自分の経験や意見を言うのって、前置きをしつつも、怖いじゃないですか。
書いちゃっていいのかな、自分の経験だけで。。。とか。
あ、いや、想像です、想像。
でも、こういうことこそ知りたいことなので、とっても勉強になりました。
二つ目は、伝え方と相談者のリアクション。
会話形式で展開していくのですが、
相談対応している税理士さんの答え方。
どういう言葉で、どんな温度で伝えるのか。
あと、勘違いしそうなところを補足していく説明の仕方。
税理士事務所で働いていると、当たり前のように使っている言葉を、
わかりやすく、誤解なく伝えるのって、難しいじゃないですか。
どういう言葉を使うと伝わりやすいかな、、、というのは
私はまだ業界4年目のペーペーですが、悩みながら自分なりに工夫してきたつもりではあったんです。
でも、本書に出てくる税理士の先生の言葉を見て、
なるほど、こういう説明がわかりやすいのか。こういう補足をしておくと誤解なく伝わるのか、
っとかめちゃくちゃ勉強になるわけです。
そして、それ以上に、相談者さんのリアクションが勉強になる。
こういうところに驚くのか、とか
こういうところを誤解している可能性があるのか、とか。
会話形式のやりとりを読みながら、
ベテランの税理士先生の相談対応に同席しているような疑似体験ができた気がします。
でも、ベテランの先生の相談対応に同席なんて、実際できないじゃないですか。
一部を横で聞くくらいは、チャンスがあるかもしれませんが、
最初から最後までどっぷり、、、なんて無理なわけですよ。
それが、この本で疑似体験できる。
ほんと、こういう本を出版してくださって良い時代だーーっと思いました♪
著者は、、、なんとアメブロの住人、高山弥生先生☆
3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ (ameblo.jp)
1冊目の出版のだいぶ前からブログをずっと読んでいたので、
勝手に親近感を持っています。
ほんと素晴らしい本をありがとうございましたー
自作を楽しみにするとともに、
一度読んだ本ももう一回読み返してみます。
ぁ、途中までで積んであるのもある・・・
ではーーーー!
ランキングに参加しています。クリックしていただけると嬉しいです♪

にほんブログ村