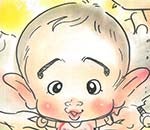「浜学園・公開学力テスト(小2・9月)の難易度:2枚目」からの続きです。⇒
夏休み明けの前回、大きく崩れてしまって偏差値30に急降下してしまいました。正直なところ、パパとしては心が折れてしまいました。
しかし、くじけている訳にはいけません。今回はそこからの脱出を目指します。主な対策は次のようなものです。
- 塾授業の受講をすっぱり止めました。浜学園は板書主義。授業時間内に書き写す(板書)ことを繰り返すことで、「聞く」「書く」「考える」を同時に訓練し、答案作成の記述スピードと正確さを養います。
療育において避けるべき「二重課題」(デュアルタスク)そのものです。おそらく、ゆうくんには合っていません。なのでしばらく受講はお休みです。 - パパ塾を塾授業に食らい付いていくための予習から、半年前の週テスト振り返りにシフト。やってみて分かったのは、きれいさっぱり忘れているということでした。塾授業を止めた代わりに、パパ塾100%で「聞く」「書く」「考える」を別々に進めています。
早く自走させて、パパ塾抜きでも塾授業を受講できるようにしないといけないことは十分に理解しつつも、焦るのは止めました。よそはよそ、うちはうちです。時間無制限を止めて、時間厳守で週テストを解けるようになるまで、何度も何度も繰り返す営みに変えています。
さて、どのような結果になったのでしょうか。
※ 例示の問題は、意図的にアレンジしています。実際の問題とは異なります。
<1枚目>
(1)計算問題
絶対に検算するように前回も約束したのですが、今回はキツくキツく約束し直しました。問題用紙に検算の痕跡が残っていれば、答えの正解・不正解を問わず、「ねり消し」を買ってあげる約束です。
偏差値20近くアップしましたーーーー!!!!
ボリュームゾーンに復帰です。真ん中よりちょい上でないと応用クラスに返り咲くことはできないので、そこには届きませんでしたが、百傑(下から数えてね!)からは脱することはできました。いや、まあ、マジで、全国の塾生の中で、最下位から数えて〇人目って、かなりの衝撃ですよ?
何しろ前回は、3問しか合っていませんでしたらね? 今回はおそらく10問全問正解です。しっかり検算したおかげであることは間違いないです。計算問題に時間を使い過ぎて文章題はほぼ壊滅ですが、それでOKです。偏差値30台に転がり落ちる崖は、計算問題にあると断言できます。
(2)一行問題
数字カードを並べて数式を成立させる覆面算です。先月のラスボス問題に続いて、連続での登場です。でも、今月は<1枚目>ですからね。3桁引く2桁で、繰り下がりあり、答えの成立するパターンが複数ありといった、先月の凶悪な難易度からは一転して易しくなっています。
2桁引く2桁で、繰り下がりなし、答えも1パターンだけ。1、2、3、4、7、9のカードを並べて、アイ-ウエ=オカ の数式を作りなさい的な感じですね。十の位(ア-ウ=オ)と、一の位(イ-エ=カ)に分解して、当てはまる組み合わせを探すだけです。ここまでレベルを落としてもらえると、ゆうくんでも解くことができます。
ゆうくんが解けたのは、ここまで。以降の文章題は壊滅です。それでもボリュームゾーンまでは戻ってきましたからね。1枚目さえ完璧に仕上げることができれば、2枚目が白紙でも、応用クラスには戻れると思われます。まあ、そのレベルだと「ギリギリで」応用クラスなので、授業には付いていけませんけどね。経験者は語る、です。
(3)偽コイン問題
重さの分かっていないコインを、天秤を使って、重い順に並べる的な問題です。実際に中学入試で出題されることもありますが、算数クイズとして見覚えある方の方が多いのではないでしょうか?
5枚のコインがありますが、1枚だけは偽コインで、本物より軽いことが分かっています。天秤を使って偽コインを特定しましょう。ただし、天秤は2回までしか使えません的な問題です。まず4枚を選んで2枚ずつ比べる。釣り合えば、選ばなかった残り1枚が偽コイン。傾いた場合、軽かった方の2枚のうち、どちらかが偽コインです。
探偵ゲーム「レイトン教授」に出てきたやつだーーーー!!
ただ、そのまんま出る訳ではなく、実際の出題ではアレンジされています。同じ解き方の問題だってことに、ゆうくんは気付けなかったようです。
<2枚目>
(4)面積迷路
エルカミノ式でお馴染みの「面積めいろ」です。ただ、小2では長方形の面積(長辺×短辺)を習っていませんからね。長方形の周りの長さ(長辺×2+短辺×2)で代替しています。そこまでやるなら、面積の計算方法も教えちゃえばいいのに。解き方自体は同じですね。
ゆうくんが間違えたポイントは2箇所。まず1つは、周りの長さを(長辺+短辺)で計算してしまったこと。はい、アウトー。
さらにもう1つは、問題用紙に描かれた図の辺の長さから、目測で数字を推定したこと。「図を見ると、長辺が短辺より2倍の長さっぽいぞ!」「周りの長さが6cmなら、長辺は4cm、短辺は2cmだ!」はーい、計算しないで答えが出るとか、おかしいと気付いてくださーい。目測だけで答えが出るとか、そんな問題、出ねーよ!!
ちなみに低学年向け中学受験塾には、「中学受験向けカリキュラムのスパイラルを、早めに回し始める」タイプ(浜学園など)と、「パズル的なカリキュラムで、できる子が育つ(できる子を選別する)」タイプ(エルカミノなど)に分かれます。エルカミノのコンセプトはズバリ、「できる子を育てる」ではなく「できる子が自ら育つ」!
一応、以前に買ってみたんですけどね。面積迷路も載っていますけどね。いや、まじで難しい。大人でも難しい。ぶっちゃけパパも、中レベルより上の問題は解けませんでした。テクニックとか解法とかではなく、本当に「地頭」を問われるカンジです。
(5)道順の場合の数
方眼マップが用意されていて、スタートからゴールまで何通りの道順があるのか数える問題です。
習ってないんですけど!!!???
場合の数自体は、掛け算を使わないため小1から出てくる単元となります。高学年だとコンビネーション(C:組合せ)とか使うんでしょうけど、小1・小2の段階では公式で教えることはしないため、全てのパターンを書き出していく解き方となります。
これまでに習った解き方を、初見で「道順の場合の数」に応用できる子って、本当にすごいと思います。それとも応用できるようなお子様は、最初から上位コース(最レとか灘合)で習っているのでしょうか? これが教育格差ってやつですね。
ちなみに、上位コースの皆さんが全員満点になって退屈しちゃうと困るため、出題自体はさらにひと捻りされていました。2箇所の地点から別々にスタートした2人が、互いにぶつからないでゴールできる進み方は、全部で何通りあるでしょうか?的な感じです。あ、もちろん制限時間は5分ぐらいね?
解けてたまるか!!!!
いや、まあ、全国上位のお子様は解けちゃうんですけどねー。うん、やっぱり<2枚目>は気にしちゃダメです。灘中経由で東大を目指すようなグループと、同じ問題を解こうとしても徒労に終わるだけですね。
当面は塾授業を完全休止して、パパ塾のみで続けてみようと思います。ただ、この間にも、塾授業はどんどん進んで、未着手の単元が積みあがっていくんですよねー。ひえー。ど、どどど、どうしたらいいんだろう。とりあえず思考停止して、目の前のことだけを頑張ります!
⇒「全統小、偏差値40台からの脱出ゲーム! 脱出成功率は?」に続きます。