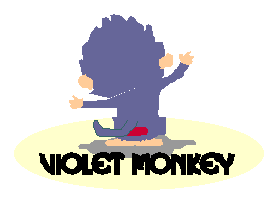「おい、あんまりおどかすなよ、ヤハウェの謎のかぎが、僕の手の中だって? 僕の手の中はいま、田所くんが水ついでくれたときこぽれたのを、拭きとって、まるめた紙が入ってるぞ・・・」
どうも、ほんとうに失礼いたしました。それにしても、老人二人のこんにゃく間答、本気なのか、はぐらかし合っているのか…
「なるほど、まるめる、ね、そのまるめるから、なにか思い出してもらおうか」
「なんだ、こんどは連想ゲームか?」
「エジプトの宗教とつきあうのには、連想ゲーム的センスが必要なんだ」
「そういうの、田所くんのほうがうまいだろ? なにが思いつく?」
「第一ヒントが中村先生で、第ニヒントがまるめるなら、…昆虫記?」
90パーセントは、あてずっぽうで言った。
「そう! その昆虫記のスカラベが、このなぞの鍵・・・」
桃棲じいさんが、ゆっくりと三つ四つ拍手した。私がむかし読んだファーブルの昆虫記は〈中村浩訳〉だった。スカラベの訳語が、この本では〈玉ころがし〉となっていて、それがじつは、この虫に〈糞ころがし〉の和名がついているのを、つくづく哀れに思った中村博士が、このときばかりは、『生物の名を正しくおぼえよう』と唱導する日ごろの姿勢にもかかわらず、あえて例外をおかして、みずからこの虫に贈った名だ・・・と知ったとき、私は感銘をうけたものだった。それ以来ファーブル、玉ころがし、中村先生・・・は、ひと組のイメージとなって、私の心の中に納まっている。
「なんだ、スカラペか、そういえばあの虫は古代エジブトで神聖な存在だったんだよね、宝石に彫っておまもりにしたり。今でも指輪なんかにしてるの、よくあるよ」
ツタンカーメンのブローチ
「動物の糞をまるめて、巣穴へころがしていって、その中に卵を生み付けるんですね? あの虫が、どうして神聖なんですか?」
「そこが、エジプト人の、連想ゲーム的感覚なんだよ。さっきも言ったとおり、太陽神レエの別名だが・・・完全なものを意昧するアトンとか、存在を意昧するケプリ・・・このケプリの語源は、'Khpr の存在するという動詞から来てる、というわけだが、一方、それとは、まったく関係なしに、このスカラベの名前が、古代エジプトではケペレルとかケぺリ
だった。これを子音だけで綴ると、これがまた Khpr 。そこで、エジブトの象形丈字では、〈太陽神〉と書くときには、このスカラベの絵を描くことになった。まさに、これはあて宇なんだが、おかげでこんどは逆に、スカラベそのものが神聖なる太陽神のお使いということになった・・・」
「すっかり僕のお株とられたね」
博士の、教え子の答えが上首尾だったときの教師のような笑顔が、パイプに持っていくマッチの炎に映える。
「それで? スヵラベとヤハウェとはどこで、どう結びっくんだ?・・・」
「YHWHを、今日われわれはヤハウェとよんでるね、だがこれは便宜上の発音で、本当のよびかたは誰も知らないんだ。ユダヤ教徒は自分たちの唯一神をあらわす〈聖なる四字(テトラグラム)〉を、そのまま声に出して呼んだりしなかった。大昔は、年に一回、〈購罪の日〉に、大祭司だけが、神殿の奥で声を出して称えることが、ゆるされていた。
ところが、紀元70年に、エルサレムがローマ軍に破壊されてから、正式な読みかたが、わからなくなってしまった。
しかし創世記(四-26)に『この時、人びとは主(YHWH)の名をよびはじめた』とあるところからみると、カインの末裔たちやケニひとの間では、『神の名を口に出して称えてはならない』というタブーはなかったといわなければならない。
それからまた出エジブト記(三-14)では神がモーセに向かって『わたしは有って有る者{エヘイエ・アシエル・エヘイエ〉』あるいは『わたしは有る』と名乗っている。
これから考えて、YHWH〈ヤハウェ〉は、〈ある〉という意味をあらわす動詞HYHからきた名だというのが、多くのユダヤ教神学者のいう、ところなんだね・・・。
そこで、かのケプリ=太陽神の別名の、語源の間題だが、これもまた、存在する、生まれる、成立する、創造する・・・という意昧の動詞KHPRなのだ。・・・となると、エジプト語でケブリとよばれる神と、ヘブライ語のHYHがなまってYHWHとなった神とは、同じ神なのではないだろうか?
すくなくとも、その当時ヨセフの一家はエジプト語とヘブライ語を、まぜこぜに使っていたにちがいないと思う・・・
その彼らにとって、この二つの神のよび名は、発音はちがってもまったく同じ意昧として併用されていたんじゃないか?
まあたとえばクリスチャンが、〈キリスト〉といったり〈メシア〉といったりするときの意識には、ほとんどちがいがないようにね・・・
さあそうなると、ユダヤ教のYHWHは、すなわちエジブトのケプリという名の神であり、同時にそれは、太陽神レエでもあり、そしてさらに、〈完全なるもの〉を意味する唯一の神アトンとも一体でなければならない・・・」
「うーん、そうか・・・そうなると、『アドナイ(主)は准一の神である』という祈りの本来の言葉は『アトン(太陽神レエ)は唯一の神である』だった、というフロイド説は、かならずしもナンセンスだとは言えなくなるな」
「そこでもう一ぺん、イクナトンが死んだ直後に話を戻すけれども、ヨセフと彼の一族郎党は、テーべの神官たちの迫害をおそれてシナイ半島の荒野にのがれた。おそらくは点々と放浪しながら、宗教的協同体の生活を続けていたんだろうと思う・・・。ところが100年ほどたって、エジプトでは強制労働がはじまった。例の建築好きのラメスニ世のとき。それで大量の逃亡者が、砂漢の彼らを頼って避難してきた。・・・おそらく、そのころのイブリ(放浪者)たちはかならずしも固執する信仰をもっていなかったろうから、ヨセフの子孫たちが崇めている神を、〈唯一の神〉として素直にうけいれたにちがいない。しかし砂漢の暮らしとは言っても、エジブト本土から、そう離れたわけではないのだから、その〈唯一の神〉の名が、テーべの神官の目の敵であるアトンだとは、うっかり洩らせない。しかもヘブライ語でHYHといえば、それがエジプト語のケプリであることが知れてしまう・・・」
「それで、神の名を口に出して呼ばないことになったか・・・」
「だが、そうこうするうち、続々とやってくる逃亡者がふえる一方で、不毛の砂漢での生活圏は飽和状態になった。そこでやむをえず、ヨルダンの川を渡ってパレスティナ地方へ侵入ぜざるをえなかったんじゃないかと思う」
「それにしても、ちょっと気になるね、イクナトンは戦争は好まなかったんだろ? もしヨセフの子孫たちが、そのイクナトンの遺志をつぐつもりなら、なぜ、他人の土地へ侵賂して行ったんだろう? 旧約聖書に、ものすごい残虐な攻めこみかたをしたって書いてあったな」
「その疑間は明快に解けるんだ。
イスラェル十二部族がヨルダンを渡ってカナンの地にはいったという旧約の中の記事が事実だとすれば、それは、さっきも言ったラメスニ世の息子のメルネプタの時代からあとのことだろうというのが、歴史家の推測として多いわげだ。なぜかというと、現在残っている、メルネプタが建てた記念碑・・・紀元前1220年代といわれるその中に、彼のひきいる軍隊がバレスティナ地方を徹底的に攻略した結果、『イスラエルは荒廃して、子孫も絶えた』と書いてある。だから、もし十二部族が、それ以前にカナンの地に入っていたら、彼らは絶滅までとはいかないにしても、大打撃はうけたはずだから、ヨシュア記以降のイスラエルの歴史に、それらしい記録が出てこなければならないはずだろう。ところが旧約聖書には、その当時、いわゆるペリシテびとをはじめとする周囲の小民族と戦った話は、くり返し出てくるが、エジブト軍が攻めてきたことは、一言半句書いてない。そこで、もし十二部族がカナンの地に入ったのが、いわゆる『イスラエルは荒廃し子孫も絶えた』という事件の、直後だったと仮定すれば、彼らがほとんどなんの抵抗もうけずに、文字どおり無人の境を占領するという具合だったんじゃないかと思うんだ」
「エリコの町をみな殺しにしたというのはほんとのことじゃないんですか?」
旧約の中の、いくつもの残虐物語が、一つ一つ理由のあるウソだということになるなら、聖書というものに、どれほどか親しみがもてるだろう・・・
「だが、その代わり、ここにもまた、別の疑間が起こってくるんだ。・・・というのは、いま言ったメルネブタの記念碑に〈イスラエル〉という名前が出てくること。聖書ではイスラエルというのはヨセフの父の、ヤコブの別名だね、そのヤコブに12人の息子があって、その子孫が、いわゆる〈イスラエルの十二部族〉になったというんだが、もしそれが事実なら、その十二部族が、カナンの地に入る前に、メルネブタが、〈イスラェル〉という地方を攻略した・・・とすれぱ、これはどういうことになるか?・・・だ」
「イスラエルという地名は昔からあった・・・ヤコブの別名も、これにちなんでつけられた・・・と解釈できないこともないが、どうやら相撲とって勝ったから、イスラエルと名乗れといわれて改名した、という話自体がうさんくさいね・・・」
「そうなると、ヤコブに12人の息子があったということも、一応、疑ってみなければならなくなる」
「また話が錯綜しそうだな」
博士があきらめたように苦笑する。

「じゃあ、結論から先にいうよ。要するにイスラエルの十二部族が、12人の兄弟の子孫だというのは後世のこしらえごとにすぎないんだ。
実際の話は、ヨセフを先祖とする部族だけが、つまりヨセフの息子であるエフライム、マナセの二部族だけが、いわゆるイスラエルとよぱれた地方に移り住むようになってから、その後しだいしだいに周囲の都族たちにヤハウェ信仰が、つまり太陽神アトンの信仰がひろまった結果、同じ信仰を持つ者同士が、宗教的連盟をむすんだ。・・・それが、いわゆるイスラエル十二部族だった。
ただしそれも、最初から十二部族だったわけじゃない。
したがって、十二部族が団結して、同時にカナンの地に入ってきた、というのも、事実ではないらしい。
・・・その証拠にはね、十二部族がカナンの地に入って、領土をわけあったいきさつをくわしくのべているヨシュア記の主役は、ヨセフの子のエフライムを元祖とするエフライム族出身の、ヨシュアだけで、この物語の舞台になっているところはほとんどが、後のエフライム族の領土か、ヨセフの弟のベニヤミンを元祖とするベニヤミン族に関係する土地ばかりといっていいくらいだ。そのうえ、あの契約の櫃・・・イスラエル十二部族にとって最も神聖視されていた契約の櫃だが、あれは後になってユダ族出身のダビデが、自分の領土内のエルサレムに移すまではほんのわずかの例外をのぞいては、終始一貫、エフライム族の領土内に安置されてあったのだ。
・・・つまりね、あの有名な出エジプト記からヨシュァ記にかけての、いわゆるイスラエル民族の建国物語はおもにヨセフの子孫たちの伝承だった・・・ということになるわけだ」
「・・・しかしそれなら、あの偉大なるモーセという預言者の存在は、どうなるんだ? 彼はエフライムやヨセフの子孫ではなかったんじゃないのか?」
「モーセと彼の兄貴のアロンという人物はレビ族の出身で、ヤコブの妻のうち姉のレアの子が元祖だということになっているが、ヘブライ語で〈レビ〉は加わるという意味だというから、これはレビ族が、出エジプトの時に、『神に仕える者として別格にされた』のではなくて、逆に、あとから十二部族に加わったのだということを、暗示しているのかもしれない。現に民数記の記述は、レビ族が脱けたためにヨセフ族がエフライムとマナセの二部族にわかれて十二部族の数をそろえたといういきさつの説明が、いかにも取ってつけたような感じがする」(1-47以下参照)
「しかしレビ族が、もともと十二部族の仲間でなかったとしても、モーセやアロンが、レビ族から出ている以上、エフライム族といっしょにエジブトからやってきた、ということは動かせないんじゃないのか?」
「聖書研究家はたいていそう言っている。それ以外に、つじつまのあわせようがないんだ。だがね、それは、モーセとアロンの兄弟が、歴史上に実在した人物だった場合の話だ」
「まさかきみは、ほんとうはモーセなんていなかった、などというっもりじゃないんだろうな」
「モーセは実在したのか、架空の人物か?を議論するまえに、彼の兄貴のアロンが実在したのかどうかを調べてみよう。
・・・結論をまずいうと、大部分の聖書研究家が、いわゆる〈モーセの五書〉(創世記、出エジブト記、レビ記、民数記、申命記)に出てくる、アロンに関する記述の90パーセントはユダ族の捕囚後に創作されたものだといっている。その証拠というのは無数にあるから、いまいちいちとりあげるまでもないげれども・・・まあアロンという人物が実在しなかったとするのは、無理でもなんでもないのだ。
そこで、いよいよモーセの間題だがね。彼がシナイ山で神から十戒をさずげられるあたり(出エジプト記20章)から以降の大部分の記事は、これまたソロモンの死後に、少しずっ成文化されていったものだ、ということは、多くの聖書研究家によって明らかになっている。
・・・それなら、モーセの生いたちは? といえば、例の、パピルスで編んだ籠に入れられて、ナイル河の岸の、葦の中におかれたのを、ファラオの王女が通りかかって拾いあげた話はメソポタミア地方の歴史で最も有名なサルゴン(B.C2350~2300)という王様の生いたちを焼き直したものであることは、疑う余地がない」
「じゃあモーセという人物の存在も、すぺてを事実無根だとするのか?」
「ところが、モーセというのは古代エジブト語で〈子供〉という意昧だ。たとえば〈トトという神の子〉というときは〈トトメス〉となる。そこで、例のイクナトンはファラオで、ファラオは〈太陽の子〉なのだから、レエ(またはラー)のモーセ、つまりラムセスとよばれてもいいわけだ」
「それなら、そのラ・モーセを略して、ただモーセと呼ぶこともありそうだな」
「よび名といえば、イクナトンは、彼自身を〈最大の先見者〉とよんでいたらしいんだ。これは元来、例の太陽神の総本山オンの神殿の大祭司につける称号であって、オンの神殿の一般の祭司が〈先見者〉、高級祭司は〈先見者の長〉、そして最高の大祭司が〈最大の先見者〉とよばれることになっていた。
・・・ところで、サムエル記創世記からはじまって、旧約の9番目だ・・・ここを読んでみると(上9-9)『昔、イスラェルでは・・・今の預言者は、先見者と言われていたのである』・・・ここでは、預言者サムエルのことを説明しているのだが、一方、モーセのことは、申命記の最後のところ(34-10)に、『イスラエルにはこののち、モーセのような預言者は起こらなかった』と書いてある。しかしサムエル記の記述からもわかるように、モーセのことを預言者とよび出したのは後世(サムェル時代以後)のことで、本来は、〈最大の先見者〉だったに相違ない。」
「イクナトンが〈モーセ〉でもあり〈最大の先見者〉でもあるとすると、二人は同一人物の可能性あり・・・か」
「そこで、もう一つ臆測を重ねると〈モーセの五書〉に、砂漠生活の間、エフライム族出身のヨシュアだけが、つねにモーセと行動を共にしていた、唯一人の人物だった・・・と記述されていることは、ヨシュアこそが〈先見者の長〉であり、イクナトン(=モーセ)の正統な後継者だったことを、物語っているのではないだろうか」
注:紫門
ヨシュア=イエス=世尊は
モーセの後継者であり、
イクナートンの後継者だった。
これを隠して伝承するために
石工組合が存在したのです。
イエスは全てを赦し
ワンネスへの教えを説いた。
それがイクナートンの教えだった。
アトン=at one=一つに
〝贖罪(atonement)〟
〝一体化(atonement)〟
「それがもし正解だとすると、モーセの五書のヒーローは、大予言者モーセではなくてエフライムから出たヨシュアだった、ということに、なってきそうじゃないか」
「だからこそ、その後も長い間エフライム族の人びとは、自分たちこそイスラエル十二部族のリーダーだと自認していたわげだ。
それにもかかわらず、出エジブト記では『祭司の職は永久の定めによって、彼ら(アロンとその子孫たち)に帰するであろう』(29-9)というようなことをくり返している。
しかしこれは、バビロニア捕囚後に、アロンの子孫と称するザドク一家の祭司たちが創作したフィクションにすぎない。その証拠にはモーセ以後の最大の預言者といわれるサムエルはレビ族出身でもアロンの子孫でもなくて、エフライム族の出身なのだ(サムエル上1-1)。
したがって、その預言者サムエルが、ベニヤミン族のサウルを十二部族全体の統率者として選んだときにはベニヤミン族とエフライム族は非常に親しい間柄だったから、まあまあ我慢したのだが、間もなくサウルの一家が亡びて、ユダ族出身のダビデがイスラェルの王となることを宣言した。しかもダビデは、レビ族出身の祭司たちと結託して、『祭司の職はアロンの末にかぎる』という永久の定めがあるとか、『その祭司が油をそそいだ者(メシァ=キリスト)は、絶対に神聖にしておかすべからざる者である』ということを、ひろく一般に根づよく植え込んだ。
エフライム族たちは、胸中はなはだ面白くなかったが、ダビデと、その息子のソロモンの政治的手腕にはまったく歯が立たなかったから、やむをえず家臣として従わざるをえなかった。
しかしソロモンが死ぬとすぐ、エフライム族を筆頭とする十部族が、ベニヤミン族だけを残して、ユダ族と決裂することになってしまった・・・と旧約に書いてある」
「メシアを油塗られた者として絶対視していたのは、結局ユダ王国関係者だけだったんだな?」
「でも、そのとき、なぜ、ベニヤミン族はユダ族のほうに残ったのですか?エフライム族と親しかったはずなのに」
「ベニヤミン族をひきいていたサウル一家と、彼らをたすけていた実力者の大部分が、ダビデの策謀によって絶滅されたことと、ベニヤミン族の領地だけが、ユダ族の領地に隣接していたから、とうてい反旗をひるがえすことができなかったんだよ」
「それにしても、もしエフライム族をリーダーとするイスラエル王国が、自分たちを正統だと主張するのなら、なぜ唯一神ヤハウェを捨てて偶像崇拝をはじめたんでしょう」
「イスラエル王国の信仰が、果たして本当に異教的な偶像崇拝だったかどうか、ユダ族の側で書いた独断的な歴史書だけから見て断定することはできない・・・」
「そういう判断は、どこからできるんですか?」
「・・・列王紀(下)の第22章と、歴代志(下)の第34章を読めば、それがわかる。ユダ王国のヨシヤの時代(B.C621)に、エルサレムの神殿の中から、今まで誰も知らなかった〈律法の書〉(あるいは〈契約の書〉とも書いてある)なるものが出てきて大さわぎになった話が、くわしく書いてある。
ヨシャ王はそのとき、非常に驚いて、ユダのすべての人びとを神殿に集めて、あらためて問題の律法の書を読みきかせた。
そして神に向かって『主に従って歩み、心をつくし精神をつくし主の戒めと、あかしと、定めとを守り、この書物にしるされている契約の言葉を行います』と誓った。・・・それで『民は皆、その契約に加わった』とある」
「よほど、まじめな王様だったらしいな・・・」
「それにしても、これから先の所に、ヨシャが国内にあるすぺての異教的なものを、ことごとく取り払った話が、くわしく書かれてあるが、今、ここで間題にしなけれぼならないのは、当時のユダ王国の人たちが、今日のモーセの五書に出てくるような厳しい淀を、そのときまで、まったく知らなかったらしい、ということなんだよ」
「ヨシャのとき見つかった〈律法の書〉というのが、モーセの五書の中の申命記ですね」
「『多分そうだろう』と、ほとんどの聖書研究家が言っている」
「見つかったのがヨシヤ王のときだとしたら一体、いつ誰が書いたんだ?」
「さあ、そこが大間題なんだが・・・18世紀の中ごろまで、モーセの五書はモーセが書いたもの、と思われていたのが、だんだん聖書批判学なんかが現われてきて、五書は最終的には、ユダ族の捕囚以後(紀元前六世紀以後)にまとめあげられたということが、はっきりしてきた。しかしその中でも、申命記だけは少し性格が変わっていて、いつ誰が書いたか、についての意見が、かなり、まちまちなんだな」
「ヨシヤと側近の人たちが、こっそりつくりあげておいて、神殿の奥から偶然発見したように、芝居をしたという説もあるでしょう?」
「それは一応考えられる。しかしもしヨシャのときに、神殿の奥で発見された〈律法の書〉が、今日の申命記だったとすれば、あれだけの量とあれほどに詳細な内容を、短期間にまとめあげるにはなんらかのよりどころがあった、と考えなげれぱならない・・・とすれぱ、その底本はなんだったか? となってくると、ふたたび、かのフロイドが提起した間題が思い出されるわげだ、・・・『イスラエルよ聞け、われわれの神、主は唯一の主である』(申命記6-4)・・・もしも、フロイドが主張したように、このアドナイ(主)=YHWHが、じつはアトン(太陽神レェ)だったとなると、申命記という書は19世紀以降の聖書批判学者たちの推定とは逆に、紀元前14世紀のイクナトンの時代にまで、その〈原典〉のありかをさかのぽらなけれぱならなくなる。もちろんこんなことはすべての聖書研究家が否定するにちがいない。それにしても、申命記が、『ほかの神々に仕えてはいけない。それらの像も名前も全部こわして削りとらなげればならない』と、くり返しくり返し命じていることは、いまだに研究者たちを困惑させている間題なのだ。もともと唯一神を崇めている民に向かって、なぜこんな戒めを、しつこくしなげればならないのか、とね。
しかしフロイドの仮説にしたがうなら、この疑間は氷解する。
〈唯一の神ならざる神々〉=アモンの神殿の神官たちと、全力をあげて闘ったイクナトンならば、この対立意識は当然だった。ことに、『また刻んだ神々の像を切り倒して、その名をその所から消し去らなげればならない』(12-3)などというのはイクナトンの時の状況にそっくりじゃないか。・・・それからまた申命記には奴隷をいたわらなけれぱならないことがくり返されているが、『あなたがかつてエジブトの国で奴隷であったが、あなたの神、主が、あなたをあがない出されたことを記憶しなげれぱならない』・・・こういう言葉が、もしイクナトンが若き目のヨセフに語ったものだったとしたら、どうだろう・・・そう思って気をつけはじめると、申命記の全文を、いちいち間題にしなげればならないという気になってくる。
・・・いずれにしても、ヨシヤの時に発見されたものが、〈いわゆる申命記〉であって、その申命記にはそれ以前に書かれた、なんらかの底本があったとすれば、それはイクナトンからヨセフヘ、そしてヨシュアからエフライム族の子孫たちに伝わったものだったかもしれない・・・という仮説を、一応たてて見ずにはいられないんだ。・・・となると、ヨシャ時代より前のユダ王国側が、唯一の神ヤハウェに忠実であるのは自分たちだけであって、イスラエル王国は終始、異教的な偶像を拝んでいた、と一方的に非難するのは、当たらないといわなげればならない。それなら、そのヨシヤ以後はどうかとなると、この〈律法の書〉を原動力として、国の総力をあげてかかった戦争が失敗に終わって、ヨシヤ自身が戦死するしこの書が発見された年から三五年ばかりでユダ王国は完全に滅亡してしまった。
そして、その後のユダヤ人にとって重大な意昧を持つ、かのバピロニア捕囚の時代がはじまる・・・
つまりね、『ユダ族・・・というよりはむしろエルサレムの神殿に仕える祭司こそ、ヤハウェ信仰の唯一の正統派であって、彼らにそむくものはすべて異教である』と、強烈に言いはじめるのは、そのときからなのだ」
「しかしなぜ、そう急に変わったんだろうね」
「理由はいろいろあるだろうが、なんといっても申命記の影響は大きかったと思うな。なにしろ申命記という書物にはすべての人間に対して、というより、鳥獣や樹木にさえも思いやりのある博愛主義が説かれている反面、ヤハウェに従わない者には、残虐のかぎりの報復を宣告しているんだ。
・・・『見よ、わたしは、きょう、あなたがたの前に、祝福と、のろいとを置く、もしきょう、わたしがあなたがたに命じるあなたがたの神、主の命令に聞き従うならぱ、祝福をうけるであろう。もしあなたがたの神、主の命令に聞き従わず、わたしが、きょう、あなたがたに命じる道を離れ、あなたがたの知らなかった神々に従うならば、のろいを受げるであろう(申命記11-26~28)』といったような、神の祝福と呪いが、重ねあわせて説かれている」
「その両面ともイクナトンの思想だというわけか・・・それとも元来は博愛主義だったのをヨシヤ王以後のユダ王国系の人間が、従わなげればただではすまさないぞ、というのを、書き入れたんだろうかね」
「そこが非常に断定しにくいところだが、とにかくユダヤ人が〈神にそむいた罪〉を意識するようになったのはユダ王国が滅亡して捕囚時代に入ってからのことだろうな」
「モーセの五書が、いわゆる、厳正なる律法の書としてのスタイルを調えたのも、その時代ということになるのか…・:」
「たしかに、捕囚時代から、その作業ははじまっただろう・・・そして、本当に完成するのは捕囚が終わって100年ほど後のことらしい。だが、その裏面には深刻ないきさつが、かくれているんだ。
・・・バピロニアがペルシア帝国に征服されて、紀元前538年に、それまで60年間バピロニァに捕囚されていたユダ族の人びとが、ペルシァのキュロス王から、故国に帰るゆるしをもらうね、そして、エルサレムの神殿の復旧も許可される。ところが帰国してみると、エルサレムとその周辺には捕囚期間中もずっと本国に残留していた庶民たち・・・旧ユダヤ王国やイスラェル王国の下層庶民たちと、アッシリァ帝国時代に強制的に移住させられてきていた異民族たち(列王紀(下)17-24参照)が、いたるところに住みっいていて、もと所有していた放牧地や家屋敷を返してくれない。
バビロニアからひきあげてきた人びとは途方にくれた。とうてい神殿の再建どころの状況じゃない。
ところが100年ばかりたって、紀元前444年(一説では397年ごろ)〈モーセの律法に精通した学者〉である祭司エズラが、神の律法を携えてバビロニアからやってきたことによって、事態が急転することになった。というのは、そのときのペルシア国王がエルサレムヘ帰るエズラに対して、『神の律法に照らしてすぺてのユダヤ教の信者を裁き、その教えを守らない者を投獄し財産を没収し追放しあるいは死刑にする権利』を与えたからだ(エズラ記7章参照)」
「そのエズラが持ってきた神の律法というのが、モーセの五書だったわけか」
「完全にではないが、ほとんど同じものだったろう」
「その、神の律法が、残留組と引揚げ組との利権衝突の事態を急転させたんだな?」
「それは見事に効を奏した。最大のきめ手はレビ記(25-8以下)にある〈ヨベルの年〉の制度だったろう。つまり『50年に一回まわってくるヨベルの年にはすでに売り渡した土地でも、ユダヤの旧地主は、無条件でそれをとり返すことができる』という神の淀だ」(二五128,31)
注:紫門
これがネサラの債務免除です
苦し紛れのユダヤ人救済法を
大昔からの神の掟にしてしまった。
聖書を改竄したと言うことです
「・・・捕囚時代が約六〇年で、しかもそのあと100年たっていたのなら、エズラが帰ってきたときは、その間すくなくとも2回はきている計算になるな」
「当然、すべての土地も建物も、捕囚以前の持主の手にかえさなげればならないわげだ。しかも、それは大昔からの神の淀なのだから、もしそれに従わないものがあったら、財産を没収し追放し死刑にしてもいいというのでは、誰ひとり異議をとなえようがない」
「残留組の完全な敗けだな」
注:紫門
この残留組がサマリア人であり、パレスチナ人です
「モーセの五書をよく読めば、ヤハウヱを信仰する者に都合がよくて、異教徒は徹底的に排撃しろ、ということになっている」
「そうなると、きみ、さっき言ったことは?・・・そもそも旧イスラエル王国の十部族は、はたして異教を信じていたのかどうか、って」
「そこなんだよ。ユダ族の側では、『主は大いにイスラエルを怒り、彼らをみ前から除かれたので、ユダの部族のほか残った者はなかった』(列王紀下17-18)と断言しているのに対して、旧イスラエル王国内に住んでいた人びとは・・・この人たちが、のちのサマリアびとになるわけだが・・・『エズラが持ってきたモーセの五書は、にせものだ』と反駁して、その論争は、延々、今日にまでおよんでいるんだ・・・」
桃棲じいさんは、ふっと小さく息を吐くと、かすかに首をかたむげて、博士を見やった。