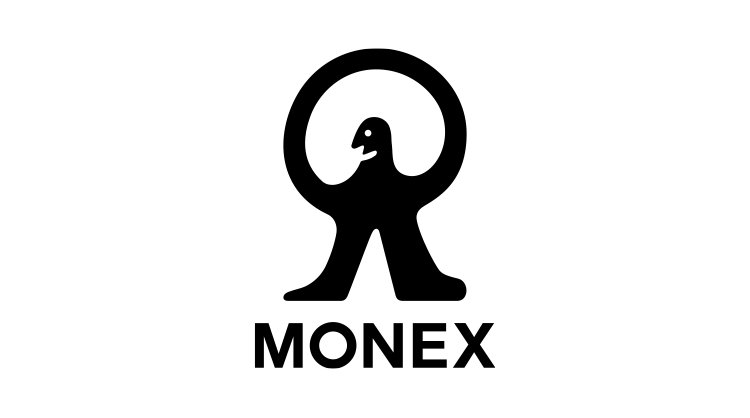
いよいよ二月の勝者が決まる東京受験がスタートするぞって所で
受験教材思い出メモ書き残しです。
投資と関係ないので読み飛ばしてください。
3年間手探りで頑張りました。
・国語
ものすごく悩ましい科目。
早熟なら5年生くらいまではあまり勉強しなくても点数が取れてしまったりする。ただし、受験問題のレベルが小学生にしてはかなり高いゆえに文章のレベルがぐっと上がる時期にキャパを超えると一気にできなくなることも。遅咲きだとまったく点が取れない酷語男子多発の印象。
ただし実は親がじっくり研究すれば一番介入しやすい科目。なぜなら塾の授業はあまり役に立たない教え方をしてると感じる割合No1の科目だから。集団授業の限界。課題量も多すぎる。
我が子に欲しいのはそこじゃない感が多発する。
なのでやっぱり親か個別で教えた方が効果出るんじゃないか?
漢字と語彙をできるだけ低学年で先取りしておきたい。
大人が使うような語彙を日常に織り交ぜられたら最高だが工夫が必要。
ある程度早熟で点数取れてた我が家では、忙し過ぎるときの調整弁であり今週は国語の読解カットというのが多発した5年生。予シリは基本問題しかやってない。ただ文章レベルが上がると安定しなくなったので、6年夏休みからは1日1題の読解でテコ入れ。直前期は国語に時間かけるなと言われたのを無視して、逆にきちんと時間をかけてレベルに合った国語の過去問を解き続けた。結果かなり読解力伸びたと思うし本番でもしっかり点数取ってくれてると思う。
★お世話になりました★
るりるり先生は素晴らしいのだが時間が長いのが難点
・「塾技」国語(難しいので6年夏休みがちょうどよかった)
・下剋上受験の桜井さんの書籍色々(国語に対する認識変わる)
・算数
最重要科目なのは間違いない。
問題集の解説が不親切だったりするので、動画解説があったらすごくいい。
(下剋上受験塾やコベツバなど)
5年生がいちばん辛かった。
1週間で身につけようとする初見の論点が多すぎるから。
復習回、季節講習、6年前半と何回もスパイラル学習することになるので
例題と基本をきっちり、練習をなんとか、応用は触れるくらいでも。
このリズムを構築できるかどうかが最重要。
難関を目指すなら練習問題以上、最難関を目指すなら応用までしっかり取り組みたい感じ。
算数だけは塾カリキュラムとひかるん先生に不満なし。
★お世話になりました★
・補足教材として、「速ワザ算数」が分野別に強化出来てよかった。
・すぐる学習会の解説は素晴らしく役に立った
・原田式のプリントもよかった。特に立体切断を予習に使えた。
・社会
範囲がものすごく広い。
その割に基礎問題集が足りないのが要注意。
外から引っ張ってきた資料が一番多かったかもしれない。
地理
桃鉄がめちゃくちゃ役に立った科目。
あと都道府県パズルを早期にやってたのがよかったか。
白地図というやつは1度もやってない。
問題に出てきたらその都度覚えて行く感じで主要な山川平野などはなんとかなった。
歴史
歴史授業に入る前に歴史まんがを読むかアニメ動画なんかで流れをつかんでおきたい。
歴史の流れだったり、人物に親しみ度がないと辛すぎる。
年号語呂合わせも早いうちに準備しておきたい。
公民
池上彰の〇〇に興味を持ってくれたのがよかったか
できるできる先生は好感度高く地理が得意に。
歴史変身先生は細かいことやりすぎであまり合わなかった感。
★お世話になりました★
・ゆずぱさんの各種資料
・新演習の教材(基礎固めに追加投入)
・理科
ほっしー先生は割と良かったけど、カリキュラムには結構不満。
特に計算の基礎問題が足りなすぎる。
物理分野の計算はみんな苦手だけど算数に比べたら楽なはず。差を付けられる。
そこでこちらも新演習の教材を基礎固めに追加投入
生物
不条理な暗記項目はかなり捨てた。
抽象項目はある程度覚えても具体的な花の名前だの、おしべめしべが何本だの無理。
化学
物理
地学
何よりも計算問題を理屈で解けるよう最重視。
★お世話になりました★
・ゆずぱさんの各種資料
・「新しい教養のための理科」を資料集代わりに
・原田式素晴らしかった
できる子図鑑、つまづき検索・・・他にもたくさんお世話になりました。
最期を意識した時
最近は某ホテルREITをタイミングよく買えてました。
久々にREITをNISAに投入です。
確定申告も作ってますが長時間作業は体に毒なのでなかなか進まず。
先ほど森永さんが亡くなられたとの報道。。。
最後の方はムチャクチャ言ってましたけど何となく寂しいものがあります。がっちりマンデーでよく見ていました。
ライザップでダイエットしてたのはバブル状態になってた頃じゃなかったっけ。もうちょい前かな。
自分のあの頃を思い出すと、持ち株が絶好調で本も2冊目を出すところまで行って、表向きは順風満帆だったのに、体に異変が生じていて精神状態が陰と陽に大きく振れてた頃。
メタメタなのに初めてのセミナーに挑戦だとかよくやれてたもんだと思い返すが、逆にそういう時だからよかったのかなぁと。2冊目の本なんか、これ遺作になるんじゃねーのって一人思うこともあったような。
(それは大げさでも体が不自由になることで社会的に抹殺される感はたしかにあった)
森永さんも最後まで本を書き続けていたようでした。
想いは似てるのかもしれない。
幸いにしてあれから7~8年。
あの頃の想像より退化のスピードは遅い。
(これは絶対に仕事をやめたおかげもあるだろう)
がしかし、健康体ってわけではないし普通の老化も加わるのでね。
最近はますますお金より時間の貴重さを意識する機会が増えたかも。
ただ普段できることは美味しいものを食べることくらいか。最期を意識した時、もう自分にはそんなに時間がないんじゃないかという感覚からくる行動は、なかなか理解されないかもしれないとも。
で、なぜか久々にこの記事見た。
気合いの入りようがすごい別人みたい(苦笑)
これ書面で長文提出したのをインタビュー風にしてるんですが、書いていたのって時期的に色々あって精神的にボロボロな頃のはず。が、まったく感じさせないので笑えた。やらされる仕事はもう無理だけど、自分が主人公になれる仕事はむしろ最期まで大歓迎なんだろうなぁと思い返した夜です。
2冊目の本を出版するにあたり別館にて詳細を書いていきます。
http://blog.livedoor.jp/vcom2/
違和感から解決策を探る
埼玉受験を経て明日からは千葉が始まります。
・九九のすべての答えを足すと2025になる
・2025=45×45=3×3×3×3×5×5
みたいなことを覚えておくと2025年受験組は役立つかもよと
1年前にどこかで見た気がしてメモして時々話題にしてました。
模試でも1回か2回さらっと触れられてたと思いますが
実際に埼玉入試の各地で出題されてるとか笑えた。
引き続き受験生活を通じて思うことをメモしておきましょう。
何年か前に早稲アカのスケジュールを見た時感じたのは、これって生活のすべてを受験に注げってこと?
それはやだなぁという第一印象。
小5/小6生のスケジュール(週3)
17:00~18:40
18:50~20:30
・夕飯食べる時間はいったいどこに?
・100分の授業なんて集中できるの?
・これに加えて復習や宿題で隔週くらいで週末にテストがって何?
やったことといえば、実際にこうしたスケジュールをこなしてる人たちのブログとか見て回ったかなぁ。すると授業中の内容を全然覚えてなくて家で1から復習みたいな体験談。
(そんなものは合格体験記とかには出てない)
何も考えず塾に放り込んだら、うちもそうなってしまうかもという危機感。
それをどうにか解決できないかと考え続け通信にたどり着いた。初期に早稲アカ通ってた頃は上位30%くらいで安定もしてなかったのが、通信に切り替えて慣れてからは上位10%くらいで安定してきたので、あぁこのスタイルが合ってるんだな(おそらく優位性もある)と最後まで突き進むわけですが、一番大変だった小5の話はまた別の機会に。
2冊目の本を出版するにあたり別館にて詳細を書いていきます。
http://blog.livedoor.jp/vcom2/