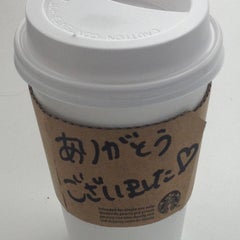中学受験の勉強をしているとき、あまり入試には出題されないわりに、覚えるのが面倒と言われているのが「面積の単位」です。
1a=100㎡
こんな風に覚えていると、確かに大変ですよね。
1ha=10000㎡
数が大きすぎるんです。それは混乱もします。
1a=0.0001㎢
こんなのはもはや使い勝手としても最悪です。わかりづらい。
そうではなく、まずaやhaがなぜ必要になったかを考えてみましょう。
長さにおいて、1mの次の単位は1kmです。それをそのまま平方して面積にすると、
1㎡=1m×1m
1㎢=1km×1km=1000m×1000m=1000000㎡
その差は実に「100万倍!!」です。
そこで新しい単位が希求されたのです。たぶん。たぶん、と書いたのは証拠がないからですが、おそらく正しいと思います。使い勝手の問題です。
そういう観点で、もう1度、a(アール)とha(ヘクタール)を見直してみましょう。
1㎡=1m×1m
1a=10m×10m
1ha=100m×100m
1㎢=1000m×1000m
おわかり頂けたでしょうか。先に書いた100万倍の差が大きすぎたので、なんのことはない、1辺の長さを10倍ずつ大きくして、新しい単位を2つ作っただけです。。
そして覚えるときも、このかけ算の形で覚えるべきです。
せっかくmとkmは長さで既に習っているのですから、それを使って空隙を埋める!
さらには、すべてをm表記で統一して覚える。必要なときだけ、覚えたかけ算を計算すればいいのです。
わかりましたか?
余談ですが、L(㍑)もそうです。
1L=10cm×10cm×10cm
こうやって覚えます。繰り返しますが、計算するのは必要なときだけですね。
以上です。