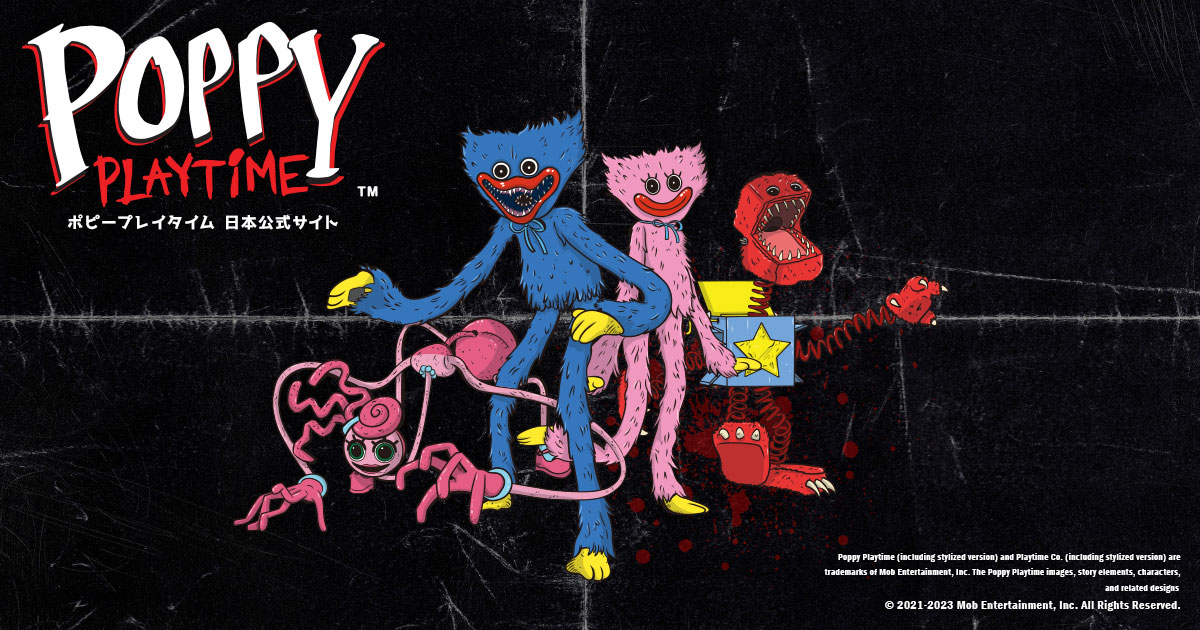第58話/天真爛漫
神心会本部で行われている独歩による模範組手である。
末堂に続き、大会上位入賞3名が挑戦したが、みんなはなしにならないまま終わってしまった。とここで、末堂のナイス煽りもあり、克巳が挑むことになったのである。
武であれ芸であれ術であれ、“道”と語られるものはなんでも、やがては合理化に向かうのが道理だと独歩はいう。道理も理の一種ではあるから、ある意味で“道”は歩み始められたときから合理に支配されていると、暗く受け止めることもできそうだが、それを発見する旅だとも言い換えられるかもしれない。「コツ」とはそういうことだと。極めるとはそういうこと。
そうなってしまえば、相手が誰だろうと何人だろうと「百戦危うからず」だ。
前回はわからなくて適当に済ませてしまったが、調べたらこれは孫子だった。調べるほど、これは数学的帰納法と同じ構造である。要するに、ひとりめを倒したあと、ふたりめを倒すことができるなら、理論的にはさんにんめも倒せることになり、それはどこまでも続く。もちろん、戦況は刻一刻と変化する。しかし、コツとは、それをつかむことなのだ。スタミナが切れてきたら、それに合わせた変化を自身に施し、パターンを守る。必勝の思考法なのである。
克巳はなんか独歩の説教がめんどくさそうにみえるが、克巳ってもともと高慢なキャラクターとして登場して、デザインもそうなってるせいか、いつもそう見える。たぶん尊敬の気持ちは強くあるんだろうけどぜんぜんそう見えない。
開始、克巳がかまえ、かなりゆっくり距離をつめていく。移植した烈海王の右手が前だ。ほぼ眼前にせまるそれを、独歩が無造作になめる。なんかやななめかただな。擬音も「エロ…」となっている。女子部が観戦してたら小さい悲鳴が出そうなねっとりしたなめかただ。
たぶん独歩はあえてねっとりやってる。体育会系育ちがちょっと驚くくらいでなければこれは意味がないからだ。不意打ちすぎて克巳も声を上げて手を引っ込めている。その金的へ、独歩が背足をそっとあてがう。威力はないが一本である。
あまりのことにあっけに取られる道場性の前で、独歩が息吹を披露する。意味はわからないが、なんだろう、まだまだ、体力じゅうぶん、余裕だよみたいなことかな。
じっさい、余力はじゅうぶん、まだやりたいものはいるかと独歩はいう。みんな黒帯とはいえいち道場生に、末堂や克巳が完封されたあとでなにができるのか。もちろん誰も応えない。少し残念そうに独歩は退場、克巳が「お見それしました」の言葉をかけるのだった。
つづく
独歩はあれだな。達人になりすぎてしまって、勝負を成立させない方向に強さの意味が変わってきてしまっているな。内容は異なるけど、たたかいの場にたどりつけなあ渋川の境地に達している。
渋川は護身を極めてそうなったが、事実としてはふたりともだれより強くありたい武術家、強いんだ星人である。この組手内容では、勝利であり、また生還ではあったとしても、強さとして評価することは難しい。いずれ独歩もこれでは満足できないとなるかもしれない。
渋川剛気だけではない。コツについて語る独歩の姿は、理を極めれば速さ等無用みたいなことを言っていたときの郭海皇とかぶってみえた。理とはそもそもなんなのか。たとえば理合とは、一般に、理想的な動きに漸近し、やがて合致することを意味するだろう。そのために技術がある。ここに、まず理想が流派によってまちまちであることと、そこへのアプローチたる技術体系、すなわち解釈もまちまちであることで、スタイルというものが生じる。だが、独歩や、郭や渋川のような達人が語る理は、思想的な意味での理想、もしくは合理、システムのようなものを指しているわけではないように思われる。げんに今回独歩は、合理化が道理だと、そもそもの前提条件に理を忍ばせている。こうした超ベテランたちが、ある種の悟りとともに見出すものでしか感じることもできない摂理のようなものが武術にはあるのである。
そして、おそらく、彼らにとってすら、その理は全貌が明らかではない。それは顔の見えない神のようなものだ。しかしときどき、それの存在が感じられるときがある。彼らはその経験をよりたしかなものにしようと、技を磨く。そうして、彼らはやがて技の内側に理を見つけるようになる。なるほど、こうすればいいのかという発見の積み重ねの先に、少しずつ理は明らかになる。だがそれは存在証明にはならない。信仰者が日々の幸運に神を見出すようなものだ。「コツ」とは、理の全貌を把握することを意味しないのである。
これは考えてみれば別に特殊なことではない。自転車にのるときわたしたちは明らかにつかんだ「コツ」を行使しているが、それは別に、自転車のしくみや物理法則を熟知しているからではない。ただ、それがそこにあることは、少なくともわたしにはわかる。このとき、理が兆す。帰納法やアブダクションなど、思考と経験を結びつけることから物理学は始まったが、科学の初期地点では極めて重要かつ自然な推論方法だ。彼らベテラン武術家はたくさんのことを経験している。そしてそのさきに、なにか網羅的なものを感じ取る。彼らがなぜか「理」という硬度の高い、意味内容がしばられそうな語を使いがちなのかというと、そのアプローチが科学のものとよく似ているからなのだ。
ファイトの際には、とるべき行動はそのときどきで無数に存在する。今回の手をなめるという動作も、これでなければいけないというものではない。だから理とは、その響きとは裏腹に、台本のようなもの、アカシックレコードなのではない。だが独歩らは、あるかないかの「理」があらわれるパターンだけは熟知している。つまり、そのとき、それをするしかないと思われることをただする、それが「コツ」を掴んだという状態なのである。若い道場生にはまったく参考にならない模範組手にはなってしまったが、独歩はたしかに、「コツ」の向こうに範、つまり理を感じているのであり、これは模範のつかまえかたをみせた組手だったのである。
管理人ほしいものリスト。執筆に活かします↓