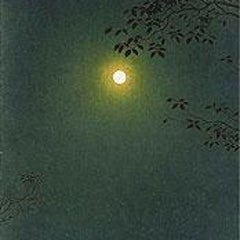昨日、個別指導で「確率」の中で出てくる「期待値」をやりました。それで思い出したことを。
「期待値」※とは、ざっくり言うと「平均してどれくらいの値が得られるか」を示すもの。
ご存知の人も多いとは思いますが「宝くじの期待値はいくらか」というと。
300円で買う宝くじの場合、その期待値はだいたい150円程だそうな。
つまり、平均すると、返ってくるのは購入額の約半分。
購入する人にとっては、残り半分が「ギャンブルで得られるワクワク感の値段」ということになるのでしょうかね。
ただし、「残り半分」のうち、一部は自治体に税金のように入る(あとは手数料、諸費用等として関連企業などへ)ので、「自治体に、より多く税金のようなものを払って地域貢献したい」という人にとって、宝くじの価値は「得られる金額の損得とワクワク感」だけでないのかもしれません。
因みに、確率を使って損得を判定する場合、金融工学などではこの「期待値」だけでなく「分散」も考えます。
「分散」とは「ばらつき」のこと。これが大きいということは「損する場合と得する場合の差が大きい」ということです。
期待値が同じなら、金融業界などにおいては一般的に分散が小さい方が好まれる事が多く(安定しているから)、ギャンブラーには分散の大きい方が好まれるようです(スリルがあるから)。
※「期待値」とは
得られる値と、その値を得られる確率を掛けて足していったもの。
例えば「100円を得られる確率が1/2、200円を得られる確率が1/2」なら、得られる金額の期待値は
(100×1/2)+(200×1/2)=150(円)
【宝くじは買うべき?東大生が教える「数学的」解答 】
【宝くじごとの期待値のまとめ】
【(宝くじの)収益金の使い道】