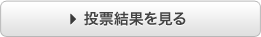- 蠅の王 (新潮文庫)/ウィリアム・ゴールディング

- ¥761
- Amazon.co.jp
あらすじ(裏表紙参照)
未来における大戦のさなか、イギリスから疎開する少年たちの乗っていた飛行機が攻撃をうけ、南太平洋の孤島に不時着した。 大人のいない世界で、彼らは隊長を選び、平和な秩序だった生活を送るが、しだいに、心に巣食う獣性にめざめ、激しい内部対立から殺伐で陰惨な闘争へと駆りたてられてゆく……。 少年漂流物語の形式をとりながら、人間のあり方を鋭く追究した問題作。 |
引用
「狩りをしていると、ときどき思いがけなく、まるで-」 彼は、突然赤面した。 「もちろん、なんでもないことなんだ。ただ、そういう感じがするだけなんだ。つまり、自分が狩りをしているのじゃなく、逆に-自分が狩りだされ追っかけられている、つまり、ジャングルの中で、しょっちゅう何かに追っかけられているという、そういう感じがするんだ」 (P.84) |
サイモンの面前には蠅の王が棒切れの上に曝され静まりかえってにやにや笑っていた。 ほど経てついにサイモンは絶望的になって、うしろを向いた。 白い歯と霞んだ眼と血は、依然として眼中から離れなかった。 そして、その彼の凝視は、あの古くから人間につきまとっている、のがれるすべのない認識の体験によって、釘づけにされたままだった。 (P.235) |
| 「正直なところ」と、士官は、なお自分の前に横たわる捜索の任務を思い浮かべながらいった、 「イギリスの少年たちだったら-きみたちみんなイギリスの少年だろう?-そんなんじゃなくて、もっと立派にやれそうなもんじゃなかったのかね-つまり-」 (P.347) |
感想
この物語は、『十五少年漂流記』や『珊瑚島』を戯画的に描いた話でもあり、無人島に不時着した少年たちの爾来を描いた、簡素な設定で成立している。 作中のキャラクター設定は、なかなか絶妙である。 その人間関係が織り成す様々な経緯は、緊迫感を持続させながら、読者を物語の最後まで誘う事だろう。 以下、主要なキャラクターを説明しながら、ストーリーも少し説明していこうと思う。 主役と言えるキャラクターは、ラーフという少年である。 ラーフは、時に勝気な面もあるが、物事を熟考する性格で、自分自身についてもよく知り、少年たちの為にベストな方法を提言し、リーダーシップを発揮する。 熟考する性格の裏を返せば、優柔不断でもあり、言いたい事を上手く伝えられない処もあるのだが、それでも少年たちは、リーダーに選出したラーフを信頼している。 最初に、ほら貝を見つけ、それを吹いて集会を開いた事による神妙なオーラも、魅力の一つとして手伝っているのだろう。 そして、ラーフが島で一番最初に出会う少年がピギーである。 ピギーは、太っちょで眼鏡を掛けている不器用な少年であるが、少年たちの中で最も物事を論理的に、そして実際的に考える事が出来る少年なのである。 しかし、ピギーは裨益しているに関わらず、デブで役立たずと皆に謗られ、碌に話を聞いてもらえない。 やがて、ラーフは彼を参謀役として認める事になるが、最終的にピギーは、ラーフと共に少数派に追い遣られてしまう。 ピギーのような理想的な思想の持ち主が迫害されてしまう過程は、不条理且つ切実なリアリティを持って、胸に迫ってくる。 因みに彼の眼鏡は、火を起こす為のレンズ代わりとなり、島では大変な貴重品となる。 ラーフと対称的なキャラクターであるのが、ジャックという少年である。 ジャックは、合唱隊のリーダーであり、島では最初から幾人の麾下を引率している。 ジャックは、決断力がある半面、血の気の多いワンマンタイプである。 その感情的な性格により、ジャックは島での生活の途中、粗忽により大きな失態を演じてしまう。 それは、ジャックが狩りに熱中する余り、烽火の見張りをしている合唱隊を狩りに引き入れてしまい、その間に、島の近くに居た船が通り過ぎてしまうという経緯である。 しかし、ここでジャックは素直にミスを謝罪して和解し、皆に認められるようになる。 ジャックは、自己中心的であるが人心掌握の術を心得ており、統率力は持っているようである。 漸次、ラーフとは対立を深めていくが、その溝こそが、人間が潜在的に畏怖の念を抱いている正体ではなかろうか、とも思わせる。 サイモンは、ジャックの合唱隊のメンバーだったが、やがて、ラーフたちと小屋を一緒に作るなどして、行動を共にしていく。 サイモンは、神秘的な物に魅せられる傾向があり、周りから変人扱いされるが、最後に、皆に最も賢明な進言をする事になる。 それは、少年たちが戦慄を覚える獣の正体を、皆で確認しに行こうという考えであった。 しかし、その考えは皆に受け入れられない。 その獣の正体というのは、実はパラシュートで落下した兵士の死体だったのだが、後にサイモンは、島の頂上に一人でそれを確認しに行く事になる。 この作品の中で、最も読者の脳裏に刻まれるシーンとなるのは、サイモンと、蠅の王こと死骸である豚の頭、との会話シーンであろう。 我々の一部でもある豚の頭とは、我々の内面を写し出す存在でもあるのだ。 それ以外に、双子のサイモン・エリックや残虐な性格のロジャー、その他の少年たちが登場するが、重要なキーパーソンとなるのは、上記の四人である。 以下、肝要となる物語の内容と感想について記していく。 物語の前半は、秩序の象徴であるほら貝を中心に、少年たちは規則について話し合い、安寧な生活を送る。 自由を謳歌する少年たちの暮らしは、前半に於いては一種のユートピアを想起させる程である。 しかし、時間が経過するに従い、島での人間関係に亀裂が生じ始める。 少年たちが決めた規則とは、救助される為に烽火を上げ続ける事、小屋を作りそこで寝泊まりする事、その他である。 しかし、ジャックは狩りに魅せられ、自らが周囲に豚肉を分け与える事によって、権威を示したいと考えている。 食物が、他には果物しかない島の生活に於いては、豚肉は貴重な蛋白源であるのは間違いない。 しかし、プライオリティーを考慮すると、烽火を上げる事や、小屋を作る方が重要だというのが、ラーフやその他の少年たちの一致した考えである。 狩りにばかり人手を割く事は出来ないのである。 しかし、小さい少年たちやジャックたちには、その論理が通じる事なく、やがて瓦解が生じる事になる。 その瓦解の決め手となるのは、集会の時に、ジャックが「ぼくの狩猟隊をどう思う?」とラーフに訊いたときに、それをラーフが邪険に扱った事によるものである。 ピギーがそれについてラーフに窘めたものの、ラーフは忖度する事も無く、聞く耳も持たない。 これによって、ジャックの承認欲求と矜持は打ち砕かれてしまう。 元々ラーフに対して含む処があったジャックは、我慢の限界に達し、暴言を吐いてラーフの元を去ってしまう。 そして、ジャックは「城岩(カッスルロック)」と呼ばれる場所に要塞を築き、そこで狩りをしながら仲間を次々と引き入れ、ラーフたちと対立して争う事になってしまう。 ジャックとジャックの仲間たちは、顔に隈取りを施し、匿名的な蛮人と化していく。 ここで、着目すべきは、ジャックの仲間たちは自分の意志で行動しているというより、常に風下に居て趨勢に流されてしまう、という習性を持っているという事である。 また、一見するとジャックが専制君主且つ悪因のように見えるが、決してそうではなく、島の少年たちが支配されていたのは蠅の王、つまり、内面的な問題と換言する事が出来るだろう。 そして、蠅の王とは、少年たち自身を滅ぼしてゆく存在なのである。 その後、ラーフは何とかジャックと和解しようと城岩を訪れるが、その過程で、サイモンとピギーが殺害されてしまうという悲劇が起きる。 ラーフはその後、ジャックたちの画策から逃れ、何とか生き延びてイギリスの海軍に救出される。 感慨深いのは、価値観を異にする人たちと共に暮らすという事が如何にシビアな事であるか、そして、そこでの軋轢は必然的に生じてくる、という事である。 無人島の少年たちは、その軋轢の解決を避け、匿名的な蛮人と化し、いつ誰が殺されるか分からないバトルロワイアル的な状況に追い込まれる事を、余儀なくされるのである。 物語中、あまり心理描写されていないが、いつ救助されるか分からないストレスフルな環境に置かれて、少年たちは無分別になり、刹那的に生きるようになってしまったのだろう。
無人島を社会の縮図として考えた場合、それは、社会を起源に立ち返って考える事に繋がっていく。 我々の周囲に於いて鑑みると、諍いや争いが絶え間ないストレス社会であり、何故、今のような社会になってしまったのか? と、人々が疑問を抱く事も少なくないだろう。 その上で、人類のルーツの生活から考えるシミュレーション的な機能を果たしているのが、この物語の面白い処でもある。 物語中、少年たちの多くは、秩序や論理よりも不埒千万な感情に流されていってしまうが、元来自然状態から始まった人類は、その後、どのように現代社会の秩序を築いていったのだろうか? 物語のラストでは、少年たちの原始的な争いの世界と、大人たちの複雑化したシステムに於ける戦争の世界が、見事に対比され描かれている。 現実の社会に於いて考慮してみると、この作品内に於けるプリミティブな人間性は、ときに隠微な形で現実社会に姿を現す事がある。 その為、この作品はとても絵空事とは思えないリアリティを醸し出している。 要するに、何が言いたいかとするなら、政治や法や社会システムについて考えるより先に、人間の内面について考える必要性を、この作品は問い掛けているように思うのである。 而して、ではどうすればいいのか?というのは、普遍的なテーマであり、様々なジレンマを抱えながらも、人々は思考し続ける運命にあるのではないか、と思う次第である。 |