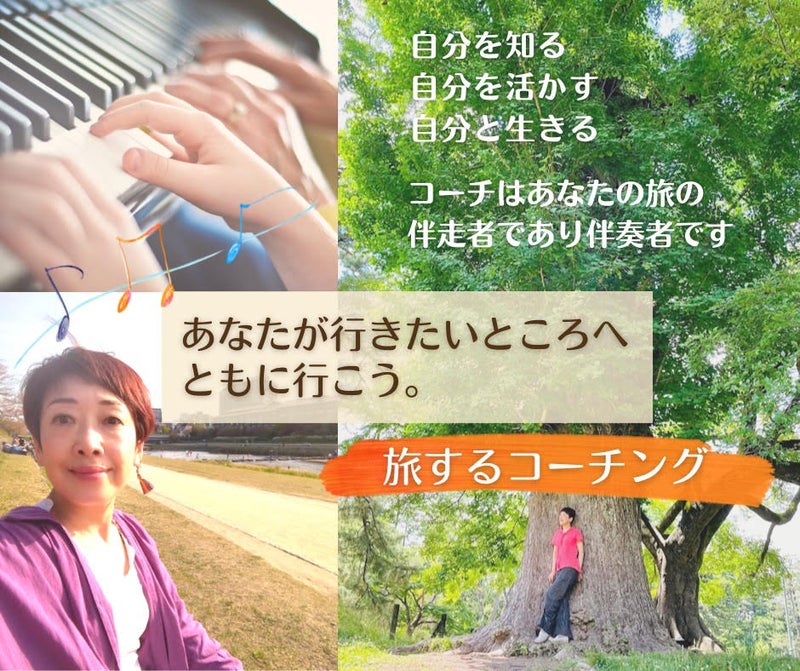父にも勧められ、
先日こちらのドキュメンタリー映画を
観てきました。
「小学校~それは小さな社会」
まずはこのキャッチコピーに惹かれました。
私たちは、いつどうやって日本人になったのか?
ありふれた公立小学校がくれる、新たな気づき
公式サイトにはこのようにも書いてありました。
イギリス人の父と日本人の母を持つ山崎エマ監督は、大阪の公立小学校を卒業後、中高はインターナショナル・スクールに通い、アメリカの大学へ進学した。ニューヨークに暮らしながら彼女は、自身の“強み”はすべて、公立小学校時代に学んだ“責任感”や“勤勉さ”などに由来していることに気づく。
「6歳児は世界のどこでも同じようだけれど、12歳になる頃には、日本の子どもは“日本人”になっている。すなわちそれは、小学校が鍵になっているのではないか」との思いを強めた彼女は、日本社会の未来を考える上でも、公立小学校を舞台に映画を撮りたいと思った。
6歳児は世界のどこでも同じようだけれど、
12歳になる頃には、
日本の子どもは“日本人”になっている。
どういうこと?って思いませんか?
でも映画を観たらわかります。
東京のとある公立小学校に
1年もの間、カメラを入れ
一年生と六年生を中心に
その日々を追っているのですが
子どもたちの様子や先生たちの関わりに
思わず涙する場面もたくさんありました。
驚きの場面もありました。
そして、監督のインタビュー記事なども
読ませてもらい、
さらに日頃クライアントさんをサポートしている
コーチとしてもいろいろ考えさせられました。
気づいたことをいくつか書いてみたいと思います。
ライフコーチの小国里恵@京都です
40代、50代の方が
《自分ともう一度生きていこう》と
思っていただけるようサポートしています
日本の教育は当たり前ではなかったこと
映画をみると
いかに日本の小学校では
教科以外の生活面にも
時間が割かれていることがわかります。
掃除や当番、委員会活動
いろいろな行事やそのための練習
皆でひとつのことに取り組むこと
なにかを成し遂げるために努力すること
礼の仕方
靴をそろえること
上級生が下級生の面倒を見ること
助け合うこと
役に立つこと
そして、それらは決して
海外では当たり前ではないということです。
まるで王道のように
地元の公立小、中、高校へと
進んでいった私にとっては
振り返って考えることもなかったことでした。
ハーフとして育ち、
「小学校のみ」日本の学校で学んだという
山崎監督はこのように語っておられます。
その6年間で培った常識がいまの自分に生かされていると思ったんです。
小学校で学んだ頑張ることの楽しさとか、何かを成し遂げる達成感や喜び、人の役に立つことで自分も嬉しくなれること。役割を担ったり責任を持ったりすることは面倒臭いことではなく、楽しくてワクワクすることとか……。小学生のとき私は掃除担当で、大臣並みに掃除を頑張っていたんですが(笑)、勉強は全然覚えていない代わりにその役割を果たすことが一番の生きがいでした。
あと、私の世代は「もっとできる、もっと頑張れる」という教育をされてきた世代だと思いますが、そのぶん「頑張る」ことに対する基準が高くなったと思います。大人になってからそれが自分の強さになっていると感じました。
生徒会長になることや運動会などの行事を楽しめたのも、それを頑張れば先がある、という思いがあったからだと思います。
これを読んでまた私は新たなことを思いました。
小学校で身に着ける価値観と私たち
山崎監督が語る「6年間で培った常識」
それは別の言い方をすれば「価値観」です。
私たちは、生まれた時は「まっさら」です。
文字どおり、何も身に着けてない。
でも、成長するにつれ
いろいろなものに触れて影響を受け、
ありとあらゆる「価値観」を身に着けていきます。
そして、知らず知らずのうちに
あれもこれもと
「着ぶくれ」状態になることもあるのです。
私は日頃、コーチとして
いろいろなクライアントさんと
対話をしながらサポートしています。
そこでは実に様々な悩みや課題が語られます。
その背景にあるのはその方の「価値観」です。
それはその方が大切にされている
考え方や信念。
そして、いつの間にか
「こうであるべき」
「こうあらねばならぬ」と
自分を縛るものになることもあります。
上記の監督インタビューで語られている
いろいろなキーワード ↓↓
✓頑張ることの楽しさとか、何かを成し遂げる達成感や喜び、人の役に立つことで自分も嬉しくなれる
✓私の世代は「もっとできる、もっと頑張れる」という教育をされてきた世代
✓そのぶん「頑張る」ことに対する基準が高くなった
✓それを頑張れば先がある、という思い
これらを読むにつけ、
同じ言葉なのに、
私が関わらせてもらった
クライアントさんからは
「逆」の側面で語られている
と思ったのです。
例えばこのような感じで
表現されていました。
●頑張らないと置いていかれる
●完ぺきにやり遂げないと認めてもらえない
●役に立たない自分はここにいてはいけない
●いつも何かを埋めるためにやってきた
●これまでハードルが高過ぎた
●やりたいことやっても、なぜか虚しい
これはどちらがいいとか、
正しい、間違いの話しではありません。
頑張ることがダメということではありません。
目標に向かって努力すること自体は
素晴らしいことです。
ただ、ものごとには
表と裏、両方の側面があるということです。
*監督は表裏があるとわかったうえで
今回は肯定的に「表」の側面を撮りたかったと
話しておられました。
6歳児は世界のどこでも同じようだけれど、
12歳になる頃には、
日本の子どもは“日本人”になっている。
監督の語られたこの言葉が
あらためて身に染みるような気がします。
そして、子どもたちが成長した先にある
大人が今の私たちだと思うと
これは大人が観て考えるための映画だとも
思えたのでした。
「ねえ、わたしたちって何なんだろうね?」という問いと答え
いろいろ書いていますが
映画は子どもたちの素朴な一面や
ほとばしるような優しさもたくさんあり
けっこう泣いてしまいました。
そのうえで、最後にでてきたエピソード
そしてそれにまつわる子どもたちの会話が
ある意味、私には衝撃だったのです。
この場面こそもしかすると
6歳児は世界のどこでも同じようだけれど、
12歳になる頃には、
日本の子どもは“日本人”になっている。
の、象徴なのかもしれません。
もちろん答えはありませんが、
なんというか、
子どもってすごいなあと思います。
ある意味、詩人なのでしょうか。
最後にそれについて書きたいと思いますが
一切ネタバレ嫌って言う方は
ここからスルーしてください。
***
映画の終盤の一場面。
一年生の子どもたちは
新たに入ってくる「新一年生」を迎えるために
「よろこびの歌」を器楽演奏することになります。
そのために「オーディション」をするんですね。
(これもちょっと驚き)
オーディション参加は自由。
先生の前で演奏して、合格したら
その器楽演奏に参加できるという仕組み。
もちろん、落ちる子もいます。
あやめちゃんは2回目の挑戦で合格。
ただ全体練習に参加したもののうまくいかず
準備不足で臨んだその態度を先生に叱られます。
先生も愛のある容赦のなさです。
大人でもガツンと来るような言葉です。
それだけに、あやめちゃんの心に
刺さっている様子に泣けました。
その後、他の子や担任の先生に支えられて
またチームに復帰していく様子に
また泣けるのですが、
話しはここで終わりません。
もっとも私が個人的に驚いたのが
その後本番を迎える直前の
あやめちゃんと仲間の子どもたちとの会話。
つまり、新一年生を迎えるその日。
もうみんな二年生になっているのです。
「一年生、来ちゃったぁ!可愛いね!」と
みんな廊下を覗き込んでます。
そして、その時
あれだけ泣き虫だったあやめちゃんが
やたら大人びた声で呟くのです。
・
・
・
「ねえ、わたしたちって何なんだろうね?心臓…の一部?」
すると別の女の子が
手でハートマークを作りながら答えます。
「わたしたちは心臓のカケラでみんなが揃ったらこんな形になる」
そしてハートマークをずらしながら続けます。
「で、ひとりこんな風にずれたら、もう心臓はできないよ」
あやめちゃんが少し笑いながら答えます。
「ほんと、わたしたちは過酷な…過酷な楽器だよ」
・
・
・
言葉のセンスにまず驚くのですが
なんというか、
なんとも言えない気持ちになります。
6、7歳でここまで考えるのか?という。
大人が勝手に意味づけるのも
無粋だと思いつつも。。。
ひとり一人が
心臓というとても大事な部分を
構成する大事な存在であるという一方
ひとりでもそこにいなければ
もう心臓が動かないというプレッシャー。
鼓動とリズム。
調和とハーモニー。
役割と責任。
もし、そのことを
「過酷な楽器」と言っているのだとしたら
なんというか
これからどこまでも続く運命を
静かに受け取っているというのか
小学校2年生の子どもから
すでに何か大切なことを見透かしたような
一種の「諦観」のようなものを
感じたのは私だけでしょうか。
映画の中ではある大学教授が
「協調性は諸刃の剣である」と
語られている場面が紹介されていたことも
同時に思い出しました。
そして、ただただこれからも
どんな音であろうと
あやめちゃんはじめ、
すべての子どもたちが
内なる美しい楽器を奏で
世界にそのまま、まっすぐに
響かせてほしいと思ったのでした。
私のコーチングセッションでは
ひとりひとりの持つ「価値観」を
オーケストラの「楽器」になぞらえて
話すこともあるので
なおさら、ズーンときました。
ちなみに価値観にはいいも悪いもありません。
***
まさかこの映画で
こんなにたくさんツラツラと
書くことになるとは
思いもしませんでしたが(笑)
当たり前に卒業した日本の小学校について
今回、映画をとおして
どのようなことを受け取ってきたのかを
考えることができました。
そして、それらが「今」に
少なからず影響を及ぼしていることを
実感できたことがとてもよかったと
感じています。
ここまで長々と
読んでくださりありがとうございました。
是非ともご覧になってみてください。
短編編はYouTubeで見ることができます
《思い込みをゆるませて楽になる5つの質問》
誰にでもある『思い込み』それは「あなたらしさ」でもあるけれど
一方で、気づかないうちに、あなたを
ギュッと窮屈にしていることもあります。
そんなときに味わってほしい5つの質問!
自分をちょっとゆるめて世界を拡げてみよう。

詳しくはコチラ↓もご覧ください。
思い込みをゆるませて楽になる5つの質問
公式ラインのご登録はこちらから!
ご希望の方は、5つの質問と
ラインへお送りください♡
●セッションを1回完結で体験できる
●継続セッションについて知りたい方のための
●公式ラインご登録者プレゼント
《思い込みをゆるませて楽になる5つの質問》
●公式ラインに登録せずに問合せ
\ お待ちしております! /
➡継続セッション「スパイラルコーチング」
➡継続セッションに関心ある方のための「無料個別相談会」
➡コーチング「単発」セッションのご案内
➡よくあるご質問
●小国里恵を知りたい方
➡プロフィール【公式】
➡プロフィール【非公式】![]()
■こんな気持ちになること、ないですか?
☑苦手な人がいてシンドイ
☑がんばっているのに自分を責めてしまう
☑人からどう見られるか気になって疲れる
☑ふとした時に、このままでいいのかって思う
☑人生折り返し、悔いなく生きたい
人生折り返し地点を迎えた40,50代の方が
《自分ともう一度生きていこう》と
思っていただけるようサポートしています!