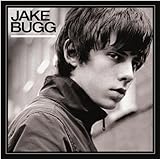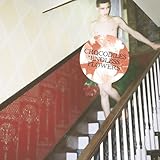昨日は酔った勢いで、とんでもないことを書いてしまいました。
反省したのでr、速攻削除しました。
いい歳していけない。
今日というか、昨日から遠い昔のことを考えていました。
小学生の頃、自分の家にはろくなオーディオ機器がありませんでした。
モノラルのラジカセ一台。
親が音楽に関心がなかったので、レコードもありませんでした。
だから、お兄ちゃん、または音楽好きな親のいる友達の家に行ってレコードを聴くのが楽しみでした。
またはレコード店、貸しレコード店のBGM目当てで、店をうろついたり。
友達とそんなことばかりしていました。
中学の時は、授業を抜け出して、近所の小川に行き、
そこにある土管に隠れて、ラジカセを聴いていたこともありました。
両親が留守のガールフレンドの家に行ったときも、目当てはもちろんレコード。
「ダブルファンタジー」とか「シンクロニティー」とか割とベタだったけど、
すごく興奮しました(もちろん音楽に。本当です!)
と、そんな勢いでロックを聴き続けてきました。
今はそこまでのエネルギーはないけど、芯は全く変わっていない自信があります。
ただ、当時同じ勢いを持っていた友人たちは、どうしているんだろう?
同じ価値観を持った「戦友」は、今も音楽を聴いているだろうか。
賑やかな場所でかかり続ける音楽に、ずっと耳を傾けているのかなと。
「親友」と「戦友」、僕は使い分けていて
「親友」は価値観が違っても通じ合える友。違うからこそ尊重し合える関係。
「戦友」は同じ価値観を持ち、同じ事を同じ温度で楽しめる関係。
そんな風に考えています。
だから、音楽仲間は自分にとっては「戦友」なんです。
そして、巡り会うのが本当に難しい。奇跡でも起きないとって言うくらい。
一生の「親友」には巡り会いました。
でも、一生の「戦友」だと思っていた人は・・・そうではなかったのかなと
昨日はそんな疑心が生まれまして。それで落ち込んでいたのです。
でも、何があっても自分は変わらない。もう、何があっても。
「天沼メガネ節」を読みながら
「日常」を聴きながら
そう思う。