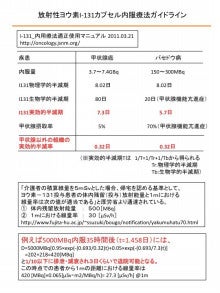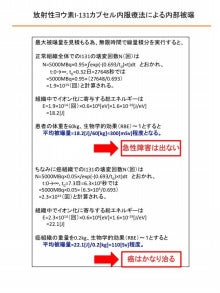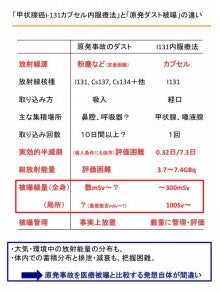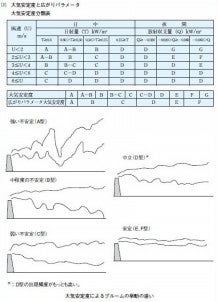今年は東日本大地震と原発事故があったので特別に
小学2年の息子に自由研究をさせる事にしました。
課題は「食べてる物の産地を調べてみよう」です。
1.目的:
・日頃どんなものを食べてるのか調べて感慨にふけってみる。
・産地が判らないものがどの位あるか調べてぞっとしてみる。
・日本地図に慣れる。
2.方法:
・茨城で2週間、九州の実家(帰省中)で2週間、食材を記録する。
・産地ごとの品目数とおよその重量を集計して図示する。
http://kotoba.littlestar.jp/sy-sirotizu.html
3.考察:
・関東と九州を比較して、食材の産地がどのくらい違うか?比べてみる。
・放射能が含まれてそうな食材がどのくらいあるか調べてみる。
(産地偽装や出荷地操作などは大人が推定する)
4.その他:
・一番面倒なのはお母さんでしょうが食生活を振り返るきっかけにはなるかも?
・兄弟、姉妹の宿題も実質的に1回の手間で済むメリットはあるかも?
・学校の先生に提出し、給食のずさんな管理を反省してもらう。
5.中高生には、、:
・内部被曝の計算やグーグルマップへのプロットなどすれば中学生でも良いかも?
・食品流通から排泄を経た拡散、肥料や建材、生態系内での放射性物質の循環を考慮し、
国内汚染の期間を推定したり、最終的な放射性物質の排出先(大半は海?)などまで
考察すれば学部生の卒業研究ぐらいにもなるかも?
小学2年の息子に自由研究をさせる事にしました。
課題は「食べてる物の産地を調べてみよう」です。
1.目的:
・日頃どんなものを食べてるのか調べて感慨にふけってみる。
・産地が判らないものがどの位あるか調べてぞっとしてみる。
・日本地図に慣れる。
2.方法:
・茨城で2週間、九州の実家(帰省中)で2週間、食材を記録する。
・産地ごとの品目数とおよその重量を集計して図示する。
http://kotoba.littlestar.jp/sy-sirotizu.html
3.考察:
・関東と九州を比較して、食材の産地がどのくらい違うか?比べてみる。
・放射能が含まれてそうな食材がどのくらいあるか調べてみる。
(産地偽装や出荷地操作などは大人が推定する)
4.その他:
・一番面倒なのはお母さんでしょうが食生活を振り返るきっかけにはなるかも?
・兄弟、姉妹の宿題も実質的に1回の手間で済むメリットはあるかも?
・学校の先生に提出し、給食のずさんな管理を反省してもらう。
5.中高生には、、:
・内部被曝の計算やグーグルマップへのプロットなどすれば中学生でも良いかも?
・食品流通から排泄を経た拡散、肥料や建材、生態系内での放射性物質の循環を考慮し、
国内汚染の期間を推定したり、最終的な放射性物質の排出先(大半は海?)などまで
考察すれば学部生の卒業研究ぐらいにもなるかも?