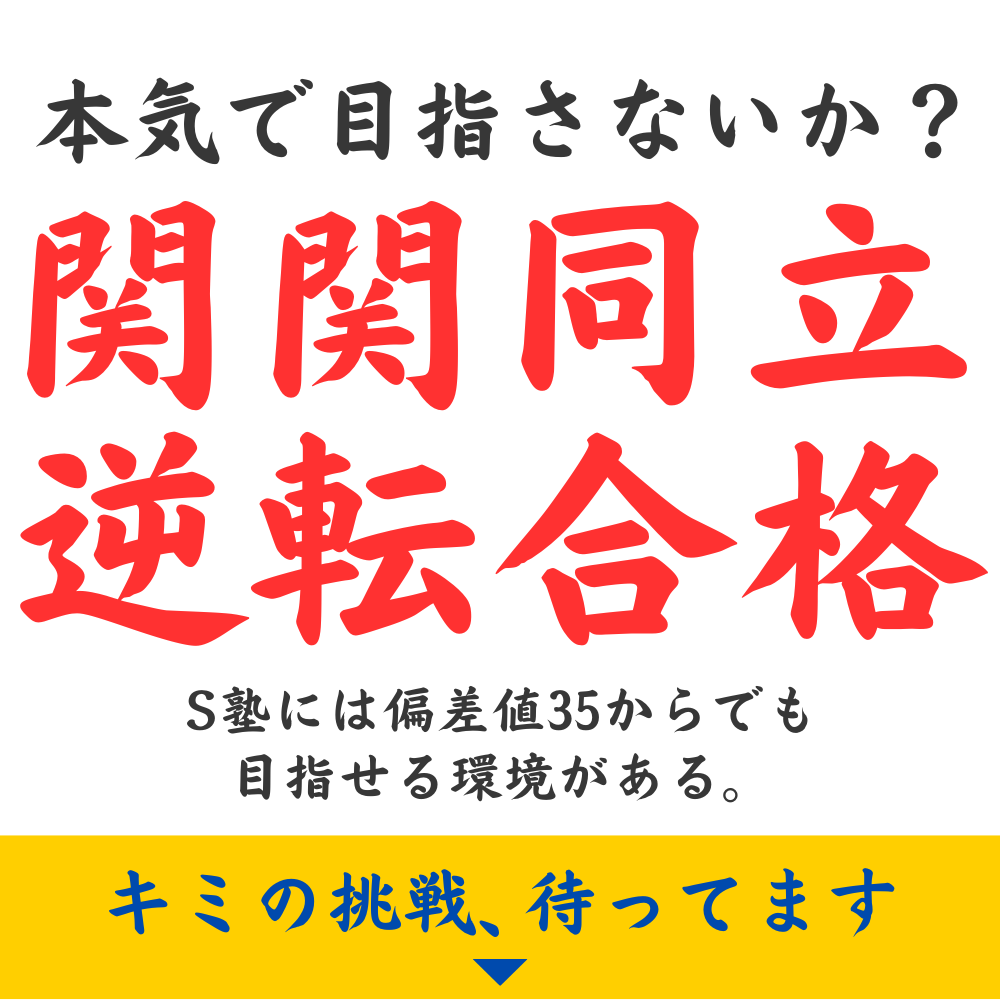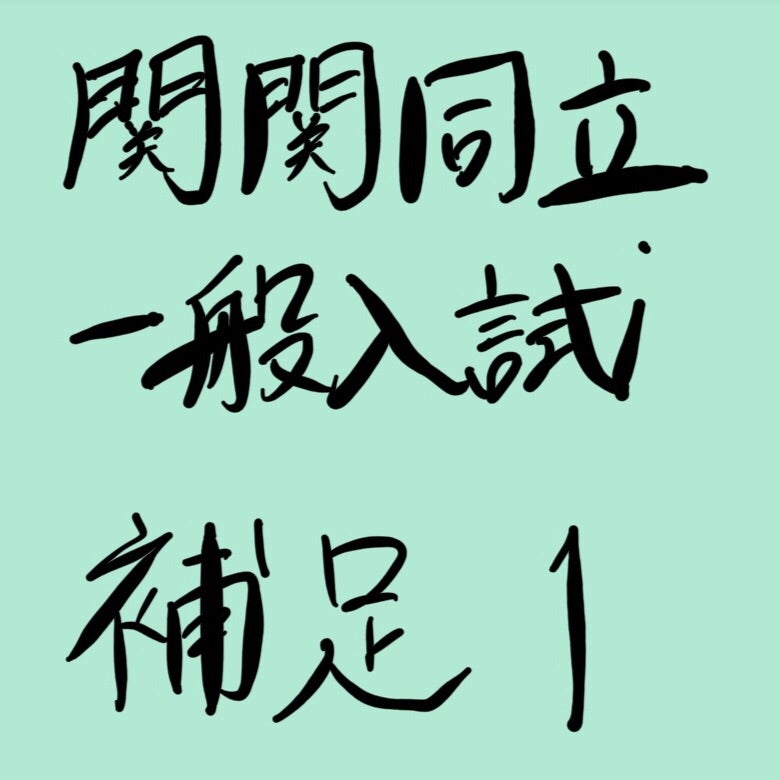前回↑↑↑、古文に関して
補助なしで自転車を乗り回す手前の段階までの勉強をしていただきました。
さて今回は、自転車を実際に乗ってみる段階として、
ストーリーを追いながら設問を捉えていくということを、
問題文に用意された様々なヒントを用いながら攻略する練習
をするために、
まずはセンター試験の過去問
その後、関西大学or同志社大学の過去問
に入ってみましょう!
(問題に散らばっている多くのヒントの活用練習にちょうど良いです)
または、
入試まで日がない状況なら
いきなり関西大学or同志社大学の過去問
に入ってみましょう!
(センター試験に比べるとヒントの数は少し少ないです)
(立命館大学・関西学院大学の過去問には、関西大学or同志社大学の過去問演習の後に入る方が勉強としてはスムーズにつながります)
第1段階:過去問に補助をつけて研究してみる⇒そのあと別問題で演習を重ねる
①過去問10題〜20題(拡大コピーしたものを用意)に対して、前回の①や③で得たヒントの捉え方を参考にして、
口語訳・解説・前書き・注・設問リード文・選択肢のヒント・本文中のヒント(主語・敬語・同じワード・プラスマイナス・順接逆接など)を確認しつつ、その設問に答えるためには最低何をどのように捉えるべきだったのか?について下線や書き込みなどでメモを残していく。
(その後、本文の通読をしておくことが大切です(口語訳は時々参考にしてみる))
②設問そのものが基礎的なことを運用する力を聞いてるだけで、そんなに深いことを聞いてるわけでもややこしい部分の解釈を尋ねてるわけでもないことが実感出来てきたら、 残りの過去問で自力テスト演習をしながらヒントの捉え方の検討を重ねるという作業を、テストごとに行っていく。
(テスト後の検討をを重ねないと、テストごとに成長していけないので、ここでの手抜きは厳禁です)
②の過程をきちんと行っていけば
センター試験(共通テスト)・関西大学・同志社大学の古文に関しては
攻め方や観点の捉え方がほとんど変わらないことに気づいてきますので、
得点力がアップしていくことが実感できると思います。
ただし、
その3つのテストにおいては
満点か1ミスまで仕上げておく必要がありますので
できる限りの演習を重ねて、スムーズに正確に解けるようになるまで
②の作業、及びこれまでの過程の復習を頑張ってくださいね!!
同志社大学は毎回、話のポイントを捉えているかを確認するために
関西大学はたまに、口語訳を
記述問題で出題してますので、
現代文の時と同様に、どのようなことを書いているのか(同志社大学)について
解答と本文をつきあわせながら考え直してみてください。
口語訳を書く場合、字数が少ない立命館大学なら部分点は少ないかもしれませんが
関西大学はそれなりの字数になりますので、基本単語と基本文法の部分はせめて頑張って書くようにして、
解答としてつじつまが合うように作成してみてください。
(気づいてる基本知識はしっかり盛り込むこと⇒そこに部分点の多くが入ります)
どうしても難しいところ以外はしっかり書いて
できるだけの点数を残そうとする意識は大切です。
大きな配点がかけられていますので
白紙だけは絶対に避けたいところですので。
第2段階:立命館大学・関西学院大学の過去問へ(必要な人のみ)
立命館大学・関西学院大学では
内容が入り組んだややこしい本文を用いながら知識問題を多めに混ぜつつ
文脈把握を様々な形式で尋ねてきます。
正直この2つの大学の合格ラインを考えると半分〜7割が取れれば十分ですので、
残り時間と他教科(進み具合・得点力)との兼ね合いで
どの程度力を注いで対策すべきかを考えておく必要があります。
知識問題と口語訳の問題のひとつと文脈把握問題を1つ〜2つ取れれば
たいてい合格ラインにはのりますので、この辺りを考慮して、
過去問をやり込む必要があるなら、
20題をひとつの区切りとして取り組むのが良いでしょう。
もちろん、テストが終わってからの検討が大切なのですが、
あー、これはちょっと(自分にとって)無理がある
と思えた設問は、切り飛ばしてもらって特に問題ないと割り切っておく必要がありますね。
(これに端を発して、細かいところまで知識などを確認しなきゃ、難しめの問題にもアタックしとかなきゃと焦らないことが大切です。それをしてる暇があったら英語や社会や現代文に力を注ぐべきです。)
この手のタイプの問題に苦手意識を感じるようなら
先に以下の問題集に取り組んでみてから再度過去問にアタックし直す
という流れでも無駄な遠回りにはならないので大丈夫です。
古文完全攻略 マドンナ入試解法(荻野文子著)
内容的には
立命館大学・関西学院大学にはちょうど良い難易度と形式となっています。
基本的な文法を使いつつ、
難解な本文の内容を類推したり飛ばしたりしながら解答していく流れが
順を追って説明してありますので、
解いてみて解説を順に追いながら、基礎の必要事項も確認していきましょう。
大切なのは
どうやって頭を働かせているか?を意識していかないと
自分のものにはならないので、考えながら読み進めるようにしてみてくださいね。
これを済ませてから、立命館大学・関西学院大学の過去問に戻って
必要な人は深追いしすぎずに演習を重ねていきましょう!!
どこまで時間をかけるべきか
どこまでの知識を作るべきか
が最も問われるのが両大学の古文ですので
くれぐれも、他の教科を圧迫してでも頑張ってやる!という気持ちで挑まないようにはしてくださいね。
何事もほどほどが大切ですから。
入試まで時間が無いときは、参考にしてみてください
関関同立の古文の対策としては以上になります!!
そして関関同立(特に関西大学・立命館大学・同志社大学)の
英国社の対策についても以上となります。
ここまで
ダラダラとした展開の中、辛抱強くお読み下さりありがとうございました。
最初から最後までという一連ものの流れを考えて書くのは初の試みだったのですが
途中で投げ出さず最後まで完遂できてほんまに良かったです。
(後記)
えらい多くの過去問をさせるプログラムやなぁ
と思われた方も多いことでしょう。
逆転して関関同立に合格しようとするなら、合格者並の学力をつける必要があるのですが
その学力を測るモノサシが実際の問題形式とは随分異なるマーク模試や記述模試では、
私大文系勢にとっては不安が残ると思いますし、
やたら偏差値や順位や判定を気にして、
自分が合格したい気持ちを抑圧的き自制しながら
いつの間にか特攻するがごとく関関同立に受験に行ったり、、、
志望校のレベルを下げて受験したり、、、
という結果になってしまう例を多く見聞きしてきました。。。
過去問に取り組むことで自身の現状が分かり
演習を重ねるごとに壁はありつつも点数が合格ラインに近づき
勉強に工夫を施すことで、点数は必ず合格ラインを突破してきます。
そこまで粘るか粘らないかで
逆転合格ができるかどうかは決まります。
その現実を目の前の生徒さんで数多く見てきました。
当初の学力より
そこまでどれだけ積み上げてトレーニングしてきたかで
合否は確実に決まります。
だからこそ、
余程の状況でない限り
関関同立一般入試での合格のチャンスはありますので
そこを指をくわえて見てるだけではもったいないですから
果敢にチャレンジして欲しいですね。
本当の意味での学力が多少(あまり)無くとも
過去問が安定してそれなりに解けてたら関関同立ならとりあえず合格出来るんやけどなぁ
という気持ちを指導方針に据えてプログラムを作成してみましたので、
上手く利用してみてください。
独学で頑張ってもらえるようにはしてみましたが
そこはそこで苦労も多いかと思いますが
合格を何としてもするんだ!
という強い気持ちを持って挑んでいただけたら幸いです。
あと、
共通テスト利用・共通テスト併用型の試験方式にも対応しやすいかと思い、
速単読み込み・速単リスニング・センター試験過去問(国)を
基礎習得のためにプログラムに組み込んでおきましたので
共通テストが近づいてきたらその対策をすることにも役立てていただけら嬉しいです。
これから本気で間に合わせるつもりで最後まで頑張ることで合格を果たし、
そこで得た自信を、次の段階へのステップに活かしてもらえたらと願っております。
推薦合格か一般合格か
というのは制度の利用の違いであり
どちらでも合格のチャンスはあるというだけです。
あなたが一般入試で合格したことは
あなたの中での自信を作ってるだけにすぎませんので
推薦入試合格者を揶揄するような態度に変えるのではなく
その先に対しての自身の挑戦の糧にしてもらえたら
頑張って逆転合格を果たした意味も見えてくるのではないかと思います。
他人と比べてどうこうと考えるのではなく
自分の中で、どうあるべきなのか、
それが他人にどう良い影響をもたらすことが出来るのか、
に気持ちを向けてほしいものですね。
関関同立に逆転合格するための受験サポートです
シリーズの補足内容です
このシリーズには一連の流れがありますので、出来れば順にお読みください