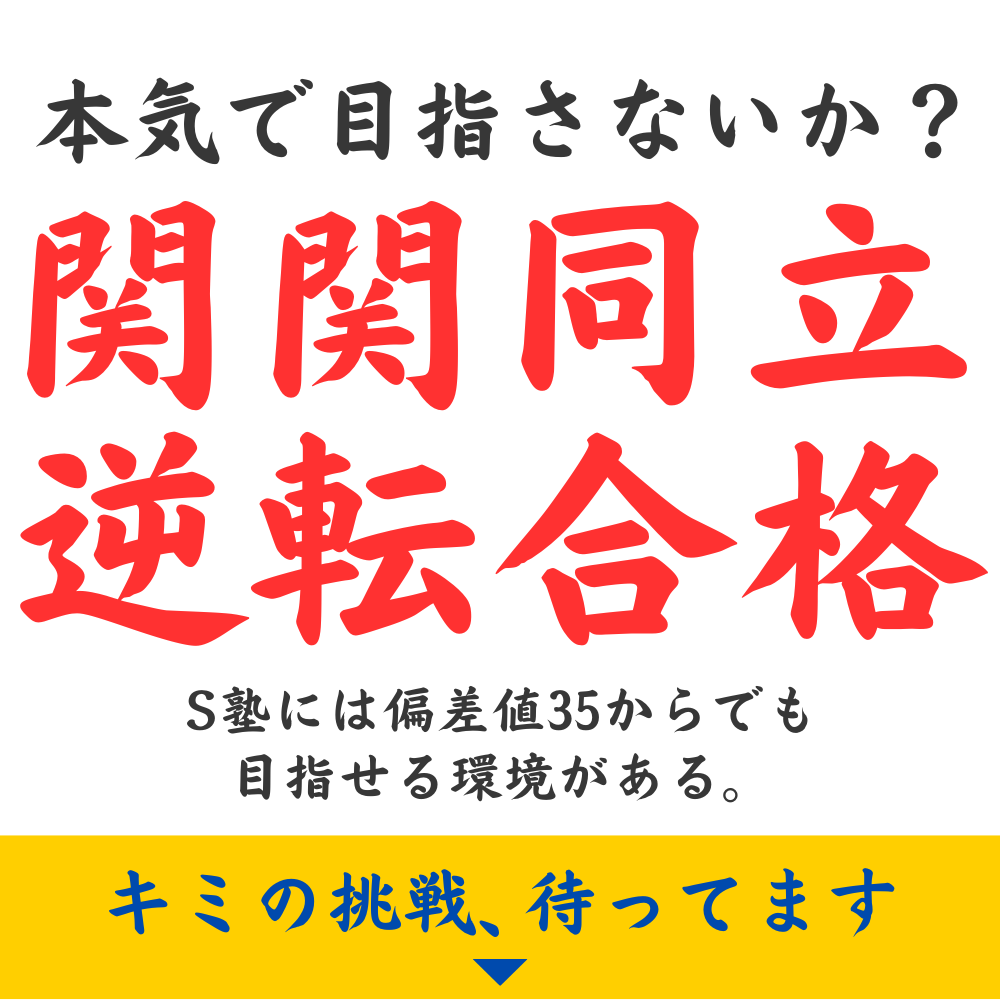前回↑↑↑は古文単語を覚えて、古文常識を仕入れておこう
という話をさせていただきました。
さて
古文単語は覚えましたか?
まだの人は今回の話について実行するのはストップして
気合い入れて憶えてください!!!
(完全じゃなくとももちろん構いませんが、90%は暗記したという状態にはしておいてくださいね)
覚えたら今回の話について実行していきましょう。
古文常識はあえて覚えようとせず、
読み流すだけでも結構ですから
スキマ時間にしっかり回しといてくださいね。
(まだ途中でも、今回の話を実行に移してもらっても大丈夫です)
今回の話に入る前に、
まずは関関同立の古文についての
難易度、出題パターンや配点などを確認しておきましょうか。
文脈寄せ問題(センター試験型問題)
関西大学(標準) 配点:75点/150点
·····文脈把握問題(選択肢長め)のみ (⇒過去、個別日程で口語訳記述があった)
同志社大学(標準) 配点:60点/150点 (記述配点20点)
·····単語問題+文脈把握問題(選択肢長め)+文法識別問題1問+話のポイント40字記述問題
文法知識寄せ問題(典型私大型問題)
立命館大学(やや難) 配点:40点/100点
·····文脈把握問題は少なめ+文法問題+主体問題+口語訳記述問題(字数制限)+文学史など多彩
関西学院大学(標準〜やや難) 配点:75点/150点
·····文脈把握問題は少なめ+単語問題+文法問題+古文常識+解釈選択問題+空所補充など多彩
(※)どの大学も本文は長めです(センター試験程度の長さ)
(※)センター試験を標準と見た上での難易度表示にしています
関関同立古文対策の大まかな方針としましては
関西大学・同志社大学
·····実戦的読解の基礎作りをまずは急ぐ
⇒センター試験過去問⇒志望校の過去問
立命館大学・関西学院大学
·····実戦的読解の基礎を作りつつも裏で文法にも力を入れておく
⇒センター試験過去問⇒志望校の過去問
ということになります。
どのみち、立命館大学・関西学院大学志望の人は、
同志社大学・関西大学も併願で受験することになると思いますから、
先ずは
実戦的読解の基礎作り
を頑張ってもらうことにしますね。
実戦的というワードをあえて書いてますが、
活用や接続や用法などの
単なる文法の基礎を真っ先に覚えるのではなく、
(ここで挫折したり力尽きる人が多い💦)
一刻も早く(読めるように)解けるようになるために
読み解きの実戦的基礎を先に作ろう
という意図からそう表現してみました。
もちろん、
古典文法を先に丸暗記するのも大事なのかもしれませんが、、、
(目的が明確にならないと、古典文法をマスターする気持ちにはなれないと思います)
それ、結果的に、小テスト・定期テスト以外で役に立ってますか?
初見の古文はある程度読めますか?
(細かいところは置いといても、
ストーリーのあらすじと
主人公の心情のうつろいを他人に語れますか?)
模試において、
単なる知識問題以外の
文脈把握問題で点数が安定して取れていますか?
むしろ
文法はおさえているのに、古文単語もマスターしてるのに、
古文が読めない・解けない
というチグハグな状況に陥ってる人って多くありませんか?
というか、
ほとんどの高校生・浪人生は
古文が読めないでしょうし、解けないでしょう。
(スラスラできる人が居たらゴメンなさいm(._.)m)
読む経験・長文問題を解く経験が足りないからに他ならない
のですが、ここに早くから着手する受験生はほんま少ないですよね。。。
(もう既にバリバリ経験を積んでる人が居たらゴメンなさいm(._.)m)
周りがやらないから
読解の基礎を作って、過去問をどんどんこなしていけば
周りと圧倒的に差がつけれるのが古文なのですが、
そこまで時間を割いてまで頑張っては居ないですよね。。。
(学校の予習は除く)
そこで
出遅れた人・暗記事項が読解には結びついてない人・予習や定期テスト準備などは頑張ってるのに古文が分からない人
に向けて
まずは読み解きから入る実戦的プログラムを用意してみました。
(ここからやると成果に表れるまでの時間が大幅に短縮できます)
(文法の暗記は今は優先的にやらなくても良いです。
覚える意味を見い出せてからで何も問題ないですので。)
(実戦的読解の基礎作りの最中にも重要なこと出現頻度の高いものにはどんどん遭遇し、勝手に吸収出来ます。後で文法を総チェックしてみると、たいていは顔見知りや親友になってたりしますから、覚える手間も自然と減っているはずです)
(塾では、単語を仕入れたあとはこの実戦的読解基礎からスタートしてましたが
特に問題になるようなことは無かったですね。
先に文法をやらせても
結局サボったり飽きて辞めてしまう人が多かったので
その当時は苦肉の策が功を奏した感じでしたが...笑)
それでは
実戦的読解の基礎作りのための参考書を3冊紹介しますね。
①三輪自転車の段階(倒れない・コケないレベル)
山村由美子 図解古文読解講義の実況中継
目次
第1章 主語発見法
第2章 人物整理法
第3章 状況把握法
第4章 具体化の方法
第5章 本文整理法
第6章 和歌読解法
第7章 入試問題ヒント発見法
巻末付録:これまでのワザ整理・活用表・助動詞助詞整理・敬語一覧・かな文法識別
文法項目別の読解でも
入試読解問題の羅列でもなく
戦略的な入試古文読解の実戦的側面で構成されてることに注目してください。
各章で
ワザ⇒練習問題⇒説明⇒練習問題図解解説⇒口語訳
という流れで
はじめのうちは短い一節からスタートして少し長めの本文ありの問題付き
となっています。
古文に挫折したりほほ初めて触れる人に向けて
多くの補助を出して、古文を現代文に近い感覚で読み進められるように
補助の出し方を工夫してある点が良きです。
まずはコレから始めてみて
古文への心理的ハードルを下げるだけ下げておきましょう!!
【使い方】
①ワザをよく読む(覚えるつもりで)
②練習問題が出てきたら先に口語訳をよく読む(2回〜3回)
③本文を、問題文図解を使いながら読む(2回〜3回)
④本文を、ワザを意識しながら図解や口語訳を見ないで読む
(⇒怪しいところは口語訳と図解を参考にして再トライ)
⑤入試問題に挑戦も、②〜④のステップで読んでみる
⇒古文を読むというプレッシャーを解放して
ワザと共に古文に慣れることに専念!!
文法用語や文法そのものを意識しすぎると
また元の古文アレルギーに逆戻りになる可能性が高いので
まずは古文の文章にルールを持って慣れていこう!!!
②後ろで支えてもらいながら自転車に乗る段階(⇒不安がありながも前に進んでみる)
古文上達 読解と演習45 基礎編(Z会)
本書は、古文の活用から始まる知識を45項目に分けて
ひとつの項目で学習した文法事項に関する簡単な問題を解いて
そのあと、まとまった内容の有名作品をひとつ読んで設問を解く
という構成となっています。
文法の習得を優先するより先に本文を読んでみる方に意識を向けたいので
使い方を以下の流れにしますね。
【使い方】
別冊の解説の方をしばらくはメインで使う。
①読解へのアプローチ・あらすじを先に読む
②本文の横に1行ずつ口語訳が並べて書いてあるので、それも参考にしつつ古文を読んでみる。(4〜5回)
⇒ワザを意識することを忘れないように。
③本文の左横に赤字で添え書きしてあるのが文法事項なので、それに対応する訳も意識しては見ておく。
⇒そのうちこういう平仮名はこういう助動詞でこういう訳になる、が勝手に身につきます。
④話を十分に理解し読み慣れたと感じたら、本体の問題冊子で読み直して問題を解いてみる。
⇒正答率を気にするより、設問解説は読んで理解をするように務めること!
⇒話が分かっているのに解けないところが固めておきたい知識であるので、そこを拾い上げておく気持ちで。
⑤45項目が終わったら、文法事項をひとつひとつ確認するために、本体冊子の1項目の最初の2ページを順にチェックしてみる。
⇒活用などを完璧にしなきゃ等 焦らずに、これまでに身についたものも相当あるので、落ち着いてひとつひとつ丁寧に見ていくと良いですね。
⇒大切なのは、文法用語そのものにプレッシャーを感じないように、整理しながら学ぶつもりで何度か反復しつつ読み進めてみることです。
⇒何度か周回させてみると、それだけで定着してるものもあれば怪しいものもあるので、怪しいものを取り出してそのタイミングで一気に覚えてしまいましょう!!
⇒細かいところまで完璧に文法を覚えるようとすることに執着しすぎないようにはしてくださいね!!
(これが挫折の元になりますので)
③支えなしで自転車を乗り回す前の準備段階
ここで
入試に即応した読み解きのコツを入手しておきましょう!
岡本莉奈の1冊読むだけで古文の読み方&解き方が面白いほど身につく本
①の段階で読み方の基礎を確認して
②の段階でとりあえず古文を読むことと文法にも少し慣れてもらったわけですが、
そのタイミングで読み進めてもらうと発見も多い内容となっています。
全てを熟読するというよりは
前半の読み方偏では
これは知ってるけどこれは知らないを振り分けながら
知らないことに注目してそこをしっかり読むと
後半の解き方編では
試験での手順・発想法・切り抜け方などを学ぶつもりで
用意された問題を解きながら、丁寧に進めていってください!
(⇒読み流すのではなく、自力で解いてから読むことが大切です。)
(⇒ここでの学びが過去問演習に入った時にほんまに必要になりますので、解いて確認する姿勢で少しでも実戦感覚を磨いておきましょう)
ここまでの段階を経てるなら
この参考書はコツコツゆっくり進めるよりは
一気に周回を重ねて仕上げるつもりで
コツの習得を急いでくださいね!!!!!
(⇒コツを試すために過去問演習に早く取り組みたいので)
巻末に受験用に文法事項がまとめてありますので、
これを使って、古文上達で学んだ文法に関して頭を整理するのに使うのが効果的です。
(⇒役に立つところだけピックアップするのも良いです。
また、
人によっては先にこちらで文法をおさえてから、
古文上達の1項目ずつをチェックし直すのが合ってる場合もあります。
⇒私はこっちタイプです。)
(※)
この本は①の段階やっても良いのでは?
と思われるかもしれませんが、
紙面に情報が多くて挫折するかも
文法寄せの説明になっているため挫折するかも
という懸念がありましたので、
先に古文に慣れてもらう意味で、この段階でのチェックとなりました。
また、
これをやらずに、②の段階が終わったら早速過去問へ
ということも検討しましたが、
後々、過去問を解き進める際の効率を考え、
一旦この③をやって、
言われないと気づかない解くコツを掴んでからから過去問へ
という方針にしておきました。
(解くコツを常に念頭に置いて過去問をこなす方が成果は出やすいですしね)
ここまでの学習が済んだら
さらに古文に慣れるために、
とりあえず過去問に入ってみましょう!!!
過去問も古文に関しては最初は補助が必要ですので
そのことについても、次回述べたいと思います。
関関同立に逆転合格するための受験サポートです
続きはこちらからどうぞ
このシリーズには一連の流れがありますので、出来れば順にお読みください