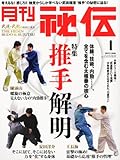師走のこの季節、いつの間にか、チキンを焼いてを食べるのが世間の定番になっているようで……
我々拳士にとって、「トリ」と言えば、開祖の愛した丸亀名物の「骨付鳥」!
発祥は、開祖がご贔屓にしていた、1952年創業の老舗
「骨付鳥 一鶴」http://www.ikkaku.co.jp/index.html
スパイシーで、バリッとジューシー
ビール片手に、ダイナミックに手で持ってかぶりつくと、もうやめられません
いまやこの骨付鳥は、拳士のソウルフード
ワタシも、本山に帰山するたびに、仲間と一鶴に繰り出して、骨付鳥で一杯やるのを楽しみにしているひとりです。
じつは、昨日は親子三代が集う身内のパーティーがあり、
メニューに鳥もも肉を焼く、というのがあったので、
それなら「一鶴風の骨付鳥に!」と提案したところ、調理担当者に任命され……
恐れ多くも63年の歴史を持つ、あの伝説の味の再現に挑戦することになってしまいました。
さて、どうなることやら……
まず、鶏肉をフォークでブスブスと刺して、
フードプロセッサーでたっぷりのニンニクと塩、胡椒などのスパイスをキュイーンとすりおろして混ぜておく
それをスリスリお肉に刷り込んで、およそ30分ほど放置して、味を染み込ませて、オーブンへ
途中で、一回ひっくり返して、天板にたまった鶏油(チーユ?)を肉にかけて、もうひと焼きで完成
こんな感じに出来上がり
(写真には写っていませんが、もちろん付け合せのキャベツも用意しました)
味はなかなか上々で、
集まった家族にも好評でしたが、
伝説の味の再現度は70%ぐらいかな?
足りなかった30%の内訳は、
第一に辛味
子供達も食べるので、ちょっとスパイスを控えめにしたのですが、
大人用は、あと1.5倍はスパイスを効かせてもよかったかなと。
次に焼き加減
もっとバリッとジューシーに焼き上げたかったので、オーブンの温度はもう少し高めがベターだったかも
(今回は250度に設定。一鶴のHPを見たら、本家は特注の窯で300度以上で焼くらしい)
あとはオヤ鳥が手に入らなかったので、次回は市場にでも買い出しに行って……
できれば、盛り付けもあのメタルのお皿にすれば、
再現度80%はいけるのでは!!
もっとも、拳法の技でもなんでも、肝心なのは、最後のツメ
技が決まるか決まらないかも、最後の決め手が左右するので、
なかなか本物の味には及ばないでしょう
(なにせ素人料理ですから)
もっと頻繁に一鶴に通って、味鶏稽古に精を出したいと思います(笑)
本日の「身体の知能指数」 (PQ=physical quotient) 『105』