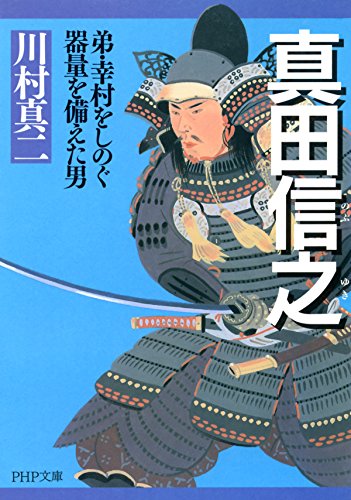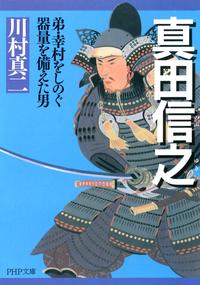人はどうしても、
華やかなもの、目立つものばかりに
目を向けてしまうものですよね。
だけど、
そういうものはなかなか
思うように手に入らないものであり、
それらばかりに目を向けていたら、
それを持っていない今の自分を嘆き、
それを持っている人をうらやむ
そんなふうに
生きてしまいがちになるかもしれませんね。
だから、
上を見て、目標を持って
今ここに無いものを手に入れることを
目指すことも大切だけど、
今ここにあるもの、
目立たなくて、
そこにあるのが当り前であり、
そこにあることにすら
気づけなくなっているもの、
そういうものの存在に
気づき、感謝し、大切に思うこと、
それができれば
何もしなくても
今この状況を「幸せだ」と
思えるようになるのかもしれませんし、
そういう当り前に
ここにあるものこそ、
私たちが
「何が何でも守り通していかなければならないもの」
そういうものかもしれませんね。
//////////
私たちの目の前にあるもの。
当り前のようにそこにありながら、
実は私たちを支え、守り
生かしてくれているもの。
その典型としてあげられるものが
地球の大気圏
と言えるかもしれません。
その存在は目に見えるものでもなく、
そこにあることを感じられるものでもなく、
光り輝く太陽、
青く果てしなく広がる海、
地球上の生き物たちを
力強く支える緑の大地、
と比べて地味なものですよね。
それでも、
当り前のことながら
大気=空気が無ければ
地球上の動植物とも
一切生きることはできません。
また大気圏の中の
「成層圏」
にあるオゾン層は
太陽から放射されている
紫外線の約90%を吸収することで
地表の生物たちを守ってくれています。
さらには大気圏は、
宇宙空間上を飛び交う無数の
塵や岩石などが
地上にそのまま落ちてくることを防ぐ
シールドにもなってくれています。
ちなみに、
地球の重力に引かれて
大気に突入した塵や岩石、
人工の宇宙船などが
大気圏突入によって燃える理由、
それは
「空気摩擦によるもの」
と考える人が多いと思いますが、実は
その主な要因は別のもの
だそうです。
それはさておき、
決して華やかで
目立つ存在ではなくても、
はるか太古の昔から
現代、今この瞬間に至るまで
私たち地球上の生物、
全ての大切な命を
守り通してきてくれている
地球の大気圏。
その存在は
「当り前」
ですましてはいけない、
感謝すべきものですよね。
そして、
人の世の中にも、
決して目立たないけれども、
実は大きなことを成し遂げている人。
大きなものを守り通した人。
そんな人もたくさんいますよね。
【国際宇宙ステーションから見た
日没時の地球の大気圏。
低層の部分は夕焼けで赤く輝き、
高層にいくほど青に近づき最終的に
黒になって見えています】
////////////////
祖父は
戦国最強とも言われる
あの武田信玄からも頼りにされた
智謀の名将。
父は
小国の領主ながら
北条氏や上杉氏とやりあい、
徳川には合戦で二度までも煮え湯を飲ませた
変幻自在、百戦錬磨の戦国武将。
そして弟は
大阪夏の陣で、徳川家康を
絶体絶命というところまで追い詰めて
華々しく散った、
江戸時代から現代に至るまで
日本人の記憶に鮮烈に残る
伝説の武将。
そんな親族たちに囲まれた彼は、
光り輝く太陽、
青く果てしなく広がる海、
生物たちを力強く支える緑の大地、
それらの前では全く目立たない
大気圏のような
存在と言えるかもしれません。
もしかしたら彼自身も
「自分も華々しく生きたい」
と思っていたのかもしれません。
そしてそれだけの
実力も持っていたはずなのに、
その知恵と勇気と力を
戦で闘うためだけでなく、
乱世を生き抜き、
乱世の終息後も、
幕府からの嫌がらせや、
自分がひとつ判断を間違えたら
お家お取り潰しとなる
絶望的な緊張感に耐えながら
藩を経営するために使うことで
真田の家名を守り、
大名として明治時代まで存続させる
礎を作った人物。
自分の使命を理解し、受け入れて
命ある限り、
その使命を果たした人物。
それが真田信之です。
//////////////
三大将軍、徳川家光が
特に信任していたといわれる酒井忠勝に
「信玄以来の兵法とは?」
と訊かれた際、
真田信之はこう答えたそうです。
「只兵法は譜代の臣を不憫がる」
(戦の仕方というものは、昔からの家臣を大切にすることである)
「それでは真田伝来の軍法は?」
と訊かれると信之は
「礼儀を乱さざることが軍法の要領」
(軍の規律とは礼儀を守ることである)
と端的な言葉で答えて
忠勝を震撼させたそうです。
兵法を会社・組織の運営方法、
家臣は社員・部下と置き換え、
軍法をマネジメントと置き換えると、
「組織の運営とは部下を大切にすること。
マネジメントとは礼儀を守ること」
となる、
現代の世界でも真理と言える
私たちもわきまえておくべきである
重要な価値観ですね。
また信之はこんなことも言っていたそうです。
「常に法度の多きは宜しからず」
(いつもルールでがんじがらめにするのはよいことではない)
誰が考えても、
組織を統率するには、
ルールは絶対必要であり、
上司の立場で考えれば、部下は
ルールでがちがちにしばった方が
楽なものですよね。
そんな価値観に逆行する
「ルールは最小限に」
という主張は
「そのくらい自由にやってくれてた方が
自由な発想や行動が生まれるものであり、
これによって組織は活性化し強くなる。
そんな組織を自分は使いこなしてみせる」
という
信之の上司としての
自信と器量の大きさを示すものであり、
現代を生きる私たちにも、
組織の運営方法の秘訣を
教えてくれる言葉ですね。
////////////////
信之は早くから父、真田昌幸の
片腕として活躍し、
第一次上田合戦をはじめとする
北条・上杉・徳川との戦いで勝利を重ね
真田家を守ります。
温厚で沈着冷静
と言われた信之ですが、
戦の際には総大将にも関わらず、
常に先陣を切って進むという
豪快さや行動力も持ち合わせており、
第一次上田合戦後、和睦し
真田家が臣従した徳川家康に
その才能を評価されます。
そして家康の重臣・本多忠勝の娘を、
家康の養女とした形で
妻として迎えることになります。
「これで真田家は安泰」
と言いたいところでしたが、
これが後に真田家が豊臣方と徳川方に
二分される悲劇の要因となっていきます。
///////////////
慶長5年(1600年)、
世にいう関ヶ原の戦いが起こります。
この天下分け目の合戦において、
父・昌幸(妻は石田三成の妻と姉妹)と
弟・信繁(妻が大谷吉継の娘)は
石田三成を総大将とする
西軍についたのに対し、
徳川家康の養女を妻とする信之は、
家康らの東軍に参加することを決めます。
一説には
「東軍と西軍、
どちらが勝っても真田家が生き残るため。
何が起きても真田の家名を残すため」
とも言われますが、
下手したら、東軍と西軍どっちが勝っても
「親族は敵対勢力についていた」
という口実で、
取り潰されるリスクが大きいことは、
少し考えれば誰にでもわかること。
だから、
真田家のこの時の決断は、
そのような薄っぺらい策略ではなく、
父・弟は父・弟の、
そして信之は信之の
「義理を貫き通す」
という信念に基づいた決断によるもの
だったのではないでしょうか。
そしてそれは、
それまで共に生き、
協力し信頼し合ってきた親族が
敵味方に分かれて戦うことを
選択するものでもあった、
つらく哀しい運命の決断でもありました。
この結果、
信之は徳川秀忠軍に属して、
上田城攻め(第二次上田合戦)において
父・弟の敵として参加することになります。
//////////////
幸いなことに、親族同士での
血で血を洗う戦闘は避けられたものの、
関ヶ原後、徳川から
西軍についた父・弟に対して
死罪が言い渡されます。
この時、信之は父・弟に対する
決死の助命嘆願を実施。
この助命嘆願が認められて死罪をまぬがれ、
紀州九度山に流罪となった父と弟に対し、
「生活に困らぬように」
と信之は自費で生活援助を
行い続けたと言われています。
一方、徳川幕府の二代将軍 秀忠は
第二次上田合戦で自分自身に
煮え湯を飲ませ、
その後の大坂の陣においても、
真田信繁が幕府軍を苦しめたことから、
真田家を敵視し続けました。
そんな
「ほんの少しでも
自分に落ち度があれば、
それを口実にして幕府は
即座に真田家を取り潰す」
という暗く重い
絶望的なプレッシャーが
絶えずかかる状況におかれても、
決して心折れることなく、
「真田家を守る」
という、
真田家に残された自分に
託された使命を果たすため、
信之は幕府からの
真田家の信頼回復につとめ、
献身的に幕府の公役を務めました。
さらに、
大坂の陣の約40年後、
真田家の跡取り騒動が起こった際、
既に93歳となっていた信之は
藩政に復帰し、
真田家お取り潰しを狙う幕府を相手に、
最後まで奮闘して騒動をおさめることで、
真田家を守り通した後、
その年のうちに生涯を終えました。
信之が死去した際には、
家臣のみならず領民たちまでもが
大いに嘆き、
周囲の制止を振り切って
出家する者が続出したといわれています。
真田家の家名を大名として
明治時代まで存続させる礎を作った
信之の心の中にあったのは、
老いてもなお、
「命ある限り、真田の家は
何が何でも守り通す」
という揺るぎない覚悟と信念であり
そして
そんな途方もない使命を
やり遂げさせたのは、彼の
自分を取り巻く
困難な現実に立ち向かうことのできる
知恵と勇気と強靱な精神力
だったのでしょう。
////////////////
「何事も
移ればかわる世の中を
夢なりけりと思いざりけり」
(何事も移り変わる世の中を夢であったなどとは思えない)
これが信之の辞世の句といわれています。
弱肉強食、
昨日の友は今日の敵、
といった移り変わりの
早い世の中であった戦国乱世を、
親兄弟と
たもとを分かちながらも
「真田家を守る」
という自らの使命を貫き通した
93年の生涯。
常に真剣に、誠実に、
逆境に対しても目をそらさずに
立ち向かい乗り越えて
生き抜いた人生は、
決して夢であったと思うことはない、
長く充実感にあふれた人生
信之にはそう思えたのでしょう。
そんな真田信之の人生が見せた
きらめくような輝きは、
偉大な祖父や父、そして
伝説となった弟の人生に
何ら見劣りするものではない。
確かにそう思えますよね。
【松代城】
元々は武田信玄が築城し、
川中島の戦いでの拠点とした海津城です。
真田信之は1622年に入城。
以後、
信之が生涯をかけて守り通した真田家が、
明治維新まで居城とした城です。
(今回のブログは2020/3/27に公開した内容を加筆・修正したものです)
////////////////
【こちらの記事も是非どうぞ】
【その他の名言記事へのアクセスは】
ここからアクセス!/過去の名言集記事 (# 251~# 260)
///////////////
大気に突入した塵や岩石、
人工衛星などが燃える理由。
それは
摩擦熱のせい
と思われている方も多いと思いますが、
実はその影響は
ほとんど無視できるレベル
であって、
物質が地球の大気圏に入って
燃えるのは、
「断熱圧縮」
という現象により発生する
高温が原因だそうです。
断熱圧縮とは
一気に圧縮された空気が、
熱を放出する現象で、
エアコンの暖房モードはこの現象を
利用しています。
大気圏に入ってきた物体は、
地球の重力によって猛烈に
落下スピードを加速します。
高度が200kmより下になると、
大気の密度があがり、物体の前方の空気が
エアコンとは比べものにならないほどの
エネルギーで圧縮されて膨大な熱量が発生。
この熱により塵や岩石、人工衛星は
燃える、というより溶けるそうです。
ちなみにその際、
塵や岩石と大気に含まれる
分子や原子がプラズマ状態となり
発光したものが
地表から見える
「流星(流れ星)」
であり、
最後まで溶けたり砕けたりせずに
地表まで到達したものが
「隕石」
と呼ばれます。