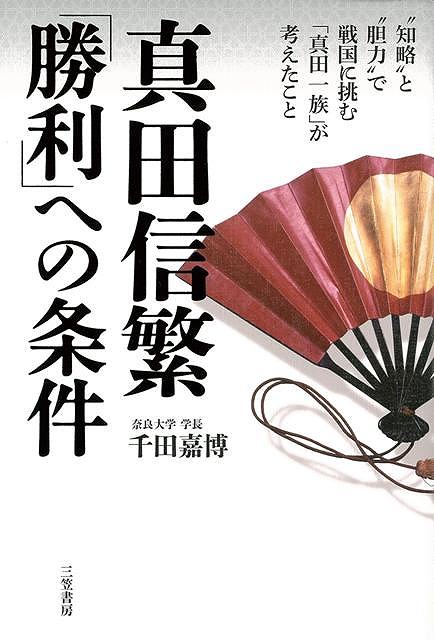暗く静かな水の底で、
息を潜めながら
じっと時を待ち続ける竜は、
その時が来たら、
雲を呼び、嵐を巻き起こし
逆巻く怒濤の中から、
一気に天へと舞い上がり、
大空を駆け巡るといいます。
関ヶ原の戦いの後、
紀州九度山での14年にわたる
幽閉生活は彼にとってまさに、
光ささない海底で泥に埋もれながら
ただひたすら時を待つような、
苦難と忍耐の時でした。
そして、
48歳となり、
わが身の衰えを嘆きながらも、
もう一度、陽の当たる場所に出て、
この力を思う存分、発揮したい。
そう願った彼の元に、
徳川家との関係が悪化し、
合戦が決定的になった豊臣家から
大坂城への入城要請が届きます。
時に慶長19年(1614年)、
真田信繁 (幸村)が再び歴史の
表舞台の上で、
疾風怒濤の活躍を遂げる、
大坂冬の陣
が始まろうとしていた時でした。
信繁にとっての九度山での14年間、
それは、
竜が水の中で時を待ち続ける
無限の時にも感じるような
年数に等しいものだったのでしょう。
ちなみに竜が大空を駆け巡るまでに
待ち続けるその年数は・・・。
(注記)
現在では、彼は「真田幸村」の名で
広く知られていますが、
このブログでは史実としての
「信繁」の名で呼ばせて頂きます。
///////////
一世一代・唯一無二のチャンス到来!
豊臣家からの大坂城への
入城要請を受けた信繁は
万難を排して九度山を脱出。
数千の軍隊を従えて大坂城に
駆けつけた信繁は、
大坂冬の陣における
では散々に幕府軍を蹴散らしましたが、
そんな信繁でさえ、
大きなきしむ音を立てながら
回り始めていた歴史の歯車を止め、
逆転させることはできず、
やがて彼自身も時代の怒濤の中に
飲み込まれていくのでした。
大坂冬の陣の翌年、
慶長20年(1615年) 5月6日
世に言う大坂夏の陣での、
道明寺の戦いでの負け戦からの
退却戦の殿(しんがり)軍
(軍勢の最後尾) を務めた、
信繁の隊は、追撃を仕掛ける
伊達政宗の騎馬鉄砲隊との
戦闘に入ります。
「関東勢百万も候へ、男は一人もいなく候」
(真田信繁)
(関東武者は百万人いたところで、
真の男は一人も居ないものだな)
政宗の軍勢を見事に打ち負かし、
豊臣全軍の撤収を成功させた
信繁はこう言いながら
悠然と撤収しました。
兄・真田信之によると
「柔和で辛抱強く、
物静かで怒る様なことは無い」
という、勇猛な武将のイメージとは
かけ離れた信繁でしたが、
そんな彼が、
敵を侮辱し、嘲笑うような
言葉を投げかけたのは、
豊臣家は圧倒的な不利な状況であり、
この戦いも、負け戦の末の退却戦という
絶望的な環境の中でも、
「絶対にあきらめない。
明日は必ず勝つ」
という姿勢を見せて、
味方を鼓舞し、
自分自身をも奮い立たせるため
・・・だったのかもしれません。
【上田駅前の真田信繁象】
////////////
道明寺の戦いの翌5月7日
信繁は、毛利勝永らと共に
最後の作戦を立案。
それは射撃戦と突撃を繰り返して、
家康の本陣を孤立させ、
急襲・横撃させるというもの
だったと言われていますが、
最後の頼みの綱だったこの作戦も、
毛利隊が合図を待たずに
射撃を開始してしまったため、
作戦を断念せざるを得なくなりました。
「今はこれで戦は終わり也。
あとは快く戦うべし。
狙うは徳川家康の首
ただひとつのみ」
信繁はそう述べた後、
真っ正面から真一文字に
家康本陣のみに狙いを定めて
突撃を敢行します。
松平忠直隊
15,000の大軍を突破し、
合わせて10部隊以上の
徳川勢と交戦しつつ、
後方の家康本陣に突入した真田隊は
家康の親衛隊・旗本・重臣勢を蹂躙。
家康はその攻撃のすさまじさに、
かつて、武田信玄に大敗を喫した、
三方ヶ原の戦い以来の、
自刃の覚悟をしたと伝えられています。
世の中、
用意した計画通りに物事を
運べる事の方が少ないもの。
それでも、どんな逆境においても、
あきらめず、他人を責めることをせず、
ニヤリと笑って、知恵を尽くし、
自分に残された最善の策を見出し、
そして断行する。
そんな覚悟と行動が、
竜が天に昇るかのような
疾風怒濤の勢いを呼び、
他の人間から見たら
「奇跡」
としか呼べない結果をもたらす。
そういうものかもしれませんね。
【三光神社境内の真田信繁象】
/////////////
「定めなき浮世にて候へば、
一日先は知らざる事に候。
我々事などは
浮世にあるものとは、
おぼしめし候まじく候」
(このような不安定な
世情ですから、
明日のこともどうなるかは
わかりません。
私たちはこの世にいないものと
お考えください)
激しい大坂夏の陣の戦闘の最中、
姉の夫、小山田茂誠宛に送った書状が
信繁が討ち死にする前の
最後の書状といわれ、
この文言が信繁の実質的な
辞世の言葉とされています。
あわやというところまで
家康を追い詰めた信繁でしたが、
数度に渡る突撃戦により部隊は消耗し、
兵力で勝る徳川勢にやがて
じりじりと追い詰められます。
信繁は四天王寺近くの安居神社の境内で、
傷つき疲れた身体を休ませていたところを
松平忠直隊鉄砲組頭に発見され、
「この首を手柄にされよ」
と最後の言葉を残して、
討ち取られました。
真田信繁、享年49歳。
しかし、真田信繁の名は
家康を追いつめた勇猛な名将として
日本中に轟き渡り、
島津忠恒は
「真田日本一の兵(つわもの)、
古よりの物語にもこれなき由」
(真田は日本一の武将だ。
昔からの物語にもこれほどの者はいない)
と信繁を称賛し、
黒田長政は、
大阪夏の陣屏風を描かせた際に、
ほぼ中央に真田信繁隊の
勇猛果敢な姿を配しました。
【黒田長政の陣屏風。中央の鳥居の下にいる赤備えの部隊が真田信繁隊】

滅びゆく豊臣方にあって、
「その人あり」といわれ、
徳川家康をあわや自刃
というところまで追いつめた
・・・とはいえ、
信繁は決して、
日本の歴史を変えたわけではありません。
勝者になったわけでも、
大名として家名を後世に
残したわけでもありません。
それでも、
暗い水の底に潜んでいた竜が
疾風怒濤を巻き起こし、
一気に天に昇るかのように、
その人生における、
唯一・最後のチャンスを生かし、
その名を歴史上に燦然と輝かせ
華々しく散っていった彼の姿は
私たち日本人の心に
感動と共感の思いをもたらし、
彼の名のもまた、
永遠に語り継がれていくのでしょうね。
(今回のブログは2020/3/20に公開したものを加筆修正したものです)
//////////
【こちらの記事も是非どうぞ】
【その他の名言記事へのアクセスは】
ここからアクセス!/過去の名言集記事 (# 251~# 260)
//////////
中国の古書『述異記』には、
水虺五百年化為蛟
蛟千年化為龍
龍五百年為角龍
千年為応龍
「泥水で育った蝮(まむし)は
五百年で蛟(みずち/雨竜)となり、
蛟は千年で竜(成竜)となり、
竜は五百年で角竜(かくりゅう)となり、
角竜は千年にして応竜になる」
そして
年老いた応竜は黄竜と呼ばれる
と書かれています。
蛇は500年で
蛟龍(こうりゅう)とも呼ばれる
鱗のある竜種の幼生である
(成長の過程の幼齢期・未成期)
蛟となり、
この蛟が1000年で成竜となり、
さらに500年で角がはえた角竜となり、
その後さらに1000年かかって
翼のはえた応竜となるそうです。
つまり、
嵐や雷雲を呼び、竜巻となって
空へ飛翔し大空を駆け巡る竜は、
その時を3000年の間、
待ち続けて進化した存在
ということですね。