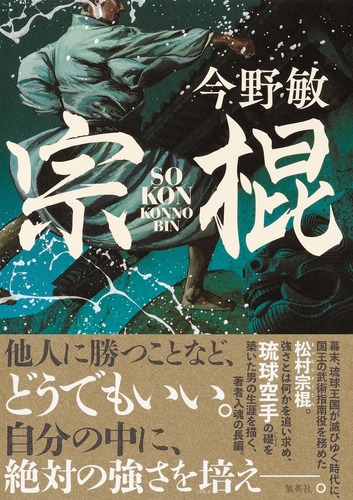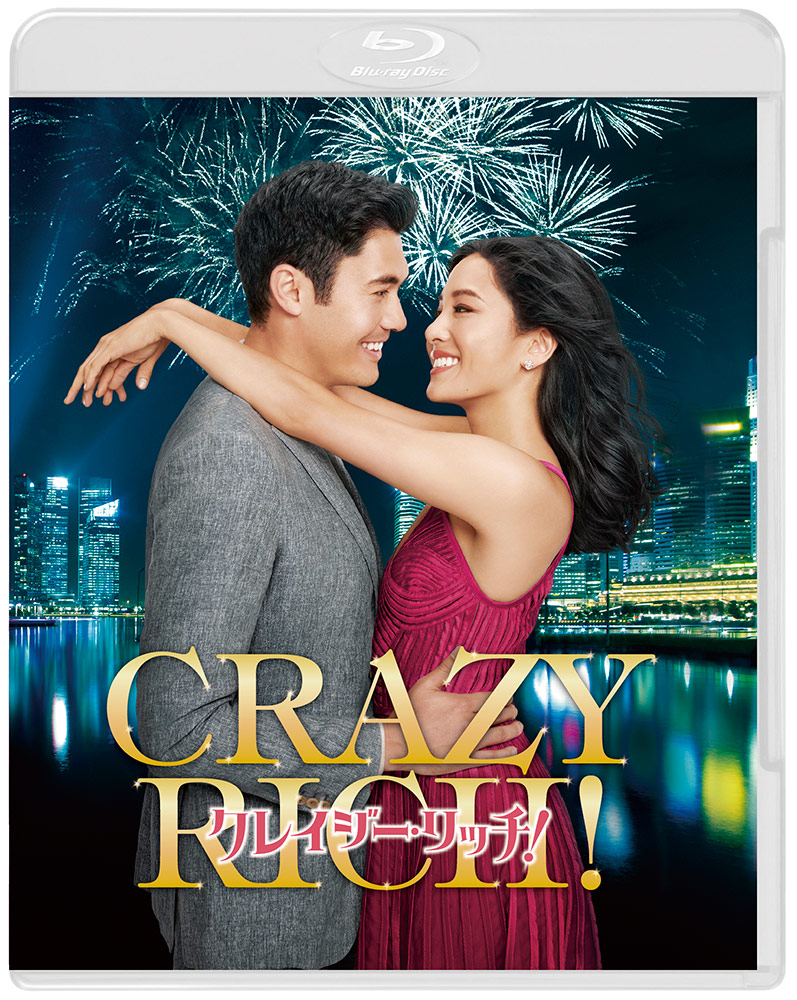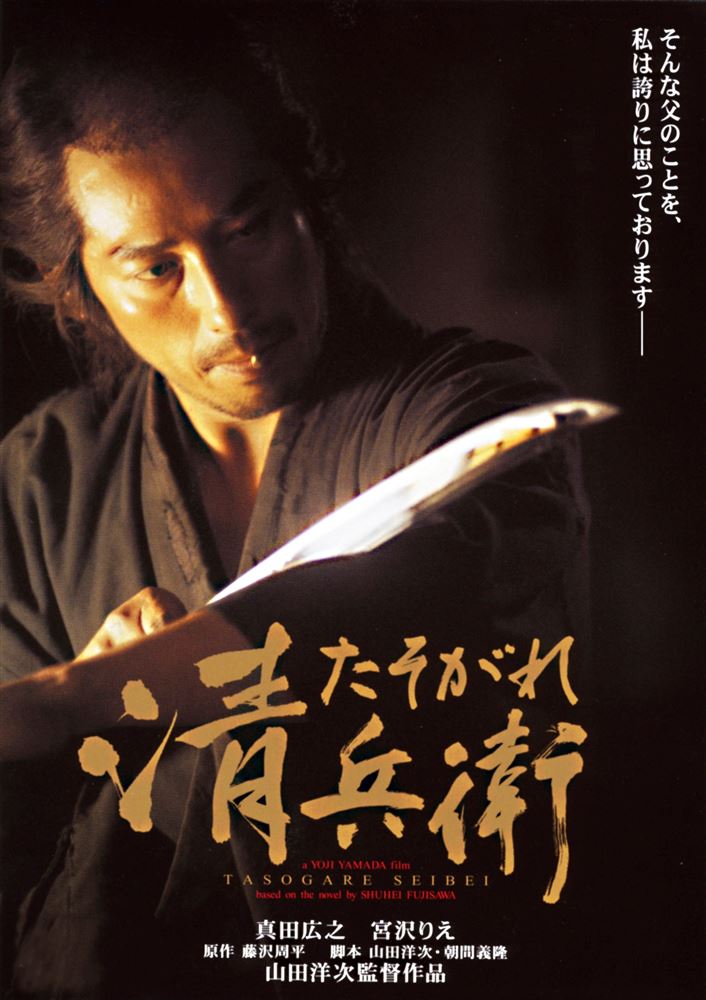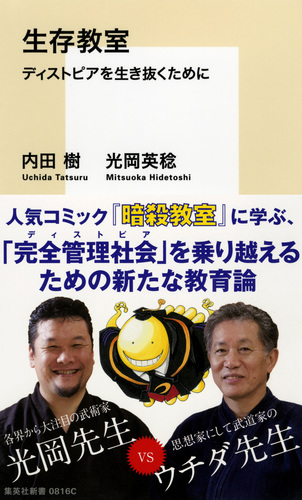Netflixオリジナル映画『スイートガール』はジェイソン・モモア主演のアクション・サスペンスだ。
Netflixの予告映像は、ユーザーの嗜好によって内容が変わるらしい。
最近、現実世界で電車内での犯罪が多く、自分が遭遇した場合にいかに自分の身を守るか、ということを頻繁に考えているせいか、本作の予告映像はジェイソン・モモアが電車内でナイフを持った男と戦うシーンだった。
強過ぎて参考にならないと思っていたら、実は重要なシーンであることが後に明らかになる。
その後のシーンでも、ジェイソン・モモアのような体格のいい男だからこそできる鈍重なアクションが度々繰り広げられるが、電車内のシーンの意味が明らかになった瞬間、それらのアクションの意味合いもオセロのように一気に塗り替えられていく。
そして、タイトルである「スイートガール」に込められた思いが明らかになる瞬間は感動する。
そのシーンの字幕はもう少し工夫した方がいいと思うが。
ジャンル映画だと思っていたら、なかなかどうしていい映画じゃないか。
一方、2022年1月21日公開の『ライダーズ・オブ・ジャスティス』は、劇場で観賞した際には少しがっかりした。
あらすじとしては、マッツ・ミケルセン演じる主人公のマークスは軍人で、妻が列車事故で亡くなったという連絡を受けて戦地から帰還する。
事故の際、マークスの妻と同じ電車に乗り合わせた数学者のオットーは、自身が目撃した出来事と統計学的な知識を組み合わせ、事故が「ライダーズ・オブ・ジャスティス」という犯罪組織によって仕組まれたものであるとマークスに告げる。
そこからマークス達の復讐劇が始まる。
「最強の軍人×理数系スペシャリスト-予測不可能な復讐劇が幕を開ける!?」という宣伝文句から、痛快なチーム・アクション、リベンジ・アクションを予想したが、実際は違う。
まず、さほど高度な学術的知識・技術は披露されない。
せいぜいハッキングで情報を得たり、顔認証で人を探したりする程度だ。
それ以上に、まったく痛快な作品ではない。
登場人物は皆、過去のトラウマや問題を抱えていて、それ故に苦しんでいるのだ。
マークスは強情な人物だ。
オットーやその仲間の意見に耳を傾けず、高圧的に命令するばかり。
実の娘やその彼氏にも「あなたは暴力でしか問題を解決できない」とまで言われる始末だ。
彼が解決しなければならない問題である。
一方、オットーは「偶然など存在しない」という強迫観念に駆られている。
過去に自動車事故で妻子を失くしており、自身の左手も麻痺してしまった。
そのため事故を「偶然」として片付けることができず、あらゆる事故を予測し、予防することを目的にアルゴリズムの開発を試みるが、目ぼしい成果を上げられずに研究は打ち切られてしまう。
オットーの言葉を信じてライダーズ・オブ・ジャスティスのメンバーを殺し始めるマークスだが、実は勘違いであるということに途中で気付いてしまう。
「統計上、偶然ではあり得ない」とオットーが主張した事故は、実際のところただの偶然だったのだ。
とはいえ、犯罪組織との戦いは途中で止められるものではない。
最終的にはマークス達が勝利し、戦いの中で深手を負って仲間達に助けられたマークスは「もっと人に頼るべきだった」と自らの強情さを反省し、克服する。
ただ、戦いに勝利したことは純粋に暴力によるものであって、マークスの人間的成長によるものではない。
オットーにしても、予測できない偶然もあるのだと知ったことで、過去のトラウマによる強迫観念を克服したことにはなる。
しかし、彼の強迫観念のせいで痛手を被った人物達がいる。
それは彼自身ではなく、勘違いに基づいてライダーズ・オブ・ジャスティスのメンバーを殺しまくったマークスであり、何より殺されたライダーズ・オブ・ジャスティスのメンバー達だ。
いくら犯罪組織とはいえ、法律で裁かれず、勘違いで皆殺しにされたのではたまったものではない。
また、オットーが「偶然など存在しない」という強迫観念を克服する過程で、マークスの娘であるマチルデの努力も軽んじられている。
マチルデは事故の際に母(=マークスの妻)と一緒に列車に乗っていたが奇跡的に生き残った。
それ以来、自らの母が死ぬ遠因となった出来事、例えば、「自転車が盗まれたから母に車で学校に送ってもらわなければならなくなった」とか「車の調子が悪く、母と電車に乗って遊びに行くことにした」といったことを付箋に書いて部屋の壁一面に貼って整理していた。
事故の真相究明に役立つのかと思っていたら、オットーに「無意味だ」と一蹴されて終わる。
母を失い、父のマークスには逆らえず、オットーの扱いもこれでは、あんまりだ。
このように、過去のトラウマや問題を解決する話でありながら、どうにも腑に落ちない展開なのでがっかりしたのだ。
しかし、本記事を書くに当たって他の人物のことも視野に入れて考えていたら少し思い直した。
オットーの友人で、マークスの仲間になる二人の人物だ。
そのうちの一人であるレナートは、言動から察するに父親や親戚に虐待された過去を持つ。
人に殴られそうになると、子供の頃の口調で「お願いだから叩かないで」と懇願し、尻を丸出しにして突き出す。
つまり、レイプされた方がましだと思えるほどの壮絶な暴力を子供時代に受けていたと思われる。
マークスらと行動を共にする中で、レナートはある男娼を救い出す。
過去の自分の姿を重ね合わせたのだろう。
この男娼が後にキーとなり、マークスらにとって重要な情報をもたらすこととなった。
虐待のトラウマこそ克服しないものの、レナートの他者への共感が物語を前に進めている。
もう一人のエメンタールは、こちらも推測だが人生のあらゆる場面で虐められてきた男だ。
そんなエメンタールはボーイスカウトでブラスバンドに所属していたが、年齢制限によって除隊すると演奏ができなくなってしまった。
制服を着て、隊列に入っていれば吹けたはずのホルンが吹けなくなったのだ。
本作『ライダーズ・オブ・ジャスティス』は、すべての片を付けた仲間達が集い、そこでエメンタールがホルンを吹くシーンで終わる。
一人ではできないことも、仲間といればできる。
そんなファンファーレが胸に響く。
物足りないところはあれど、本作もなかなかどうしていい映画ではないか。