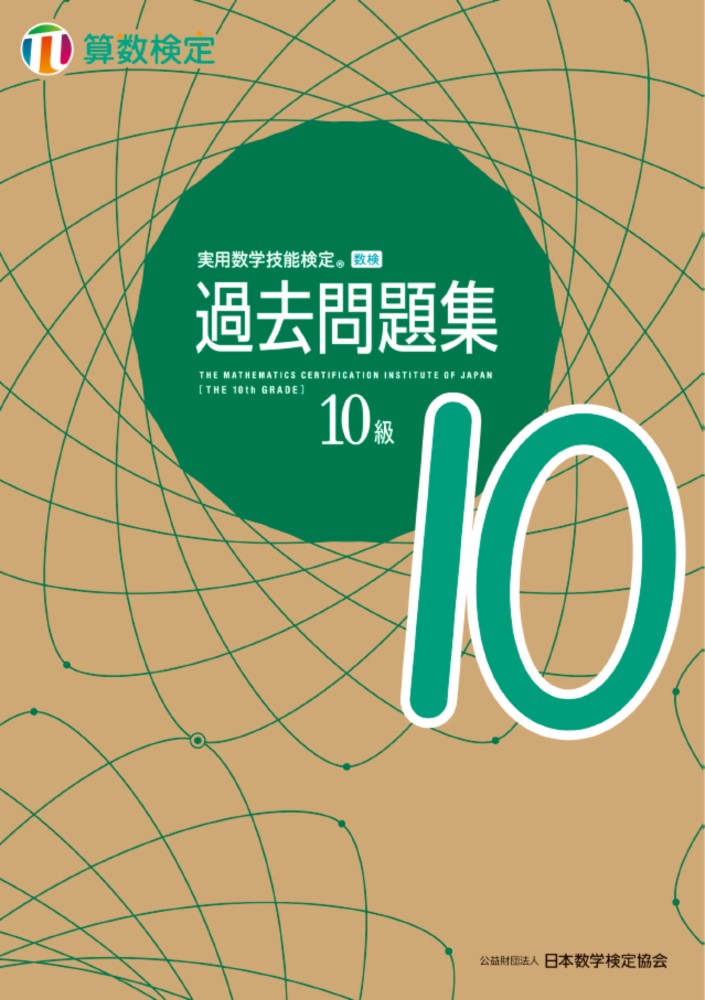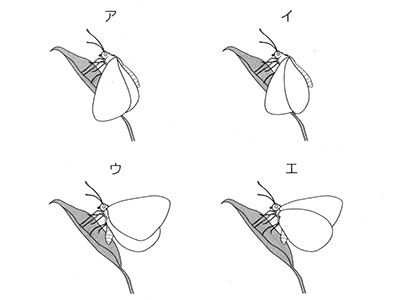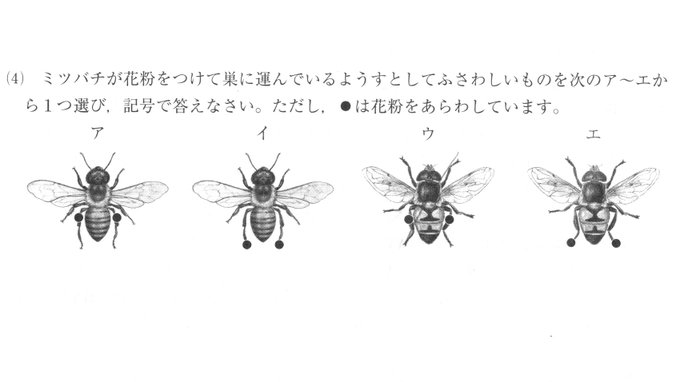最近は小3の範囲をやっています
小3ではわり算が登場
といっても、息子は公文でやったので
計算自体はスムーズ 文章題は100%とはいかないです
他に、4桁までのたし算ひき算
これも公文でやってたので思い出すだけ
あとは、単位換算
長さ、重さで、km,g,kgが初登場
ただ、体重測ったりでkgは目にするわけで、
そこまで難解ではないかなと
これからやるところで、主だったものは
・分数小数
前に概念は説明済 覚えているか、思い出せるか?
・かけ算の筆算、二桁のかけ算
これも計算自体は公文でやったところなので、
さらっとできてほしい、、、
こう見てみると、内容としては難しいことはやってないですね
(息子は億などの数は理解できず、そこは飛ばしましたが)
単位についても、正直これくらいは日常で知っていても
特段先取りし過ぎとも思えないですし
小学校受験で、季節や草花なんかを覚える代わりに
そういったものをやっているんであれば、まあいいかなって思います
振り返ると公文の恩恵が大きいですね、、、
楽しんでやれていたら、辞めることも回避できたかなあ、、なんて
小3の筆算も、計算の仕方をわかっていれば
あとはただの計算スピード勝負ですね
巷では、幼児、低学年のうちは
山本塾の計算ドリルや、100マスやっておけばいいんじゃないかって
目にしますが、結局そこに行きつくのはそういうことなんでしょう
複雑な計算の基礎は、1桁のたし算ひき算
ただ、ひたすら修行のようにそれだけやるのは
親も子もちょっと飽きてきたり苦行だったりするわけで
我が家は教科書レベルをちょろちょろ進めていくことにします
100%理解が理想ですが、そこは甘めで80-90%で
また忘れたころに復習していくサイクルを考えています
そういえば、全統小の結果について
電話連絡あり
私「しばらく取りにいけませんが、、」
受験した塾「じゃ、着払いで郵送しますね」
私「あ、すみません、、、」
なにからなにまですみません
また送られてきたら、やり直してみようかねえ
![]()