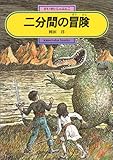兎の眼 (角川文庫)/角川書店
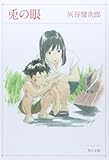
¥617
Amazon.co.jp
みなさんこんばんは。
今日から仕事始めという方も多かったのではないでしょうか。出勤すると待っているのは溜まった仕事……あれよあれよとこなすうちに正月気分はすっかり抜けていつもの日常に戻ってしまうなんとも寂しい日です。管理人は正月ぐうたらしすぎて体力的にしんどかったです……。私のようなぐうたらは仕事をしないと真人間ではいられないようです……。
さて、本日の本は灰谷健次郎さん『兎の目』です。
名作との誉れ高い本作は、教師のバイブルとも言われる作品だそうです。
大学を出たばかりの新任の小谷先生は、小学校一年生の担任。学校では一言も口を利かなくて、暴力的なところのある鉄三は問題行動ばかり。鉄三はごみ処理場に併設された長屋に、祖父のバクじいさんと住んでいました。ごみ処理場の暮らしは貧しくて、不潔で汚く、そこから学校に通ってくる子は馬鹿にされたりいじめられたりする風潮がありました。
誠実であろうと努力する小谷先生ですが、悔しさや悲しさで声を上げて泣いてしまうこともありました。やめてしまいたいと思うこともありました。しかし、彼女のひたむきな姿勢はほかの先生たちや、保護者を動かしてやがて大きな問題に立ち向かっていく力となっていきます。
以下ネタバレ
教師なら一度は読んでおけといわれるだけあって、教師とは?教育とは?といったテーマが描かれています。批判も多いこの作品ですが、それは「みな子」という知的障害を持った子供の扱いの部分ではないでしょうか。通常の小学校では対応ができないため、特別支援学級に入れられることとなったみな子ちゃん。小谷先生は彼女を自分のクラスで受け持ちたいと強く主張しました。
ほんの少しの間もじっと座っていることのできないみな子は、やはり小谷先生の行動を大きく制限し、まともに授業のできないことも多くありました。しかしそんなみな子と触れ合ううちに子供たちは自分たちで彼女の相手をしたいと主張するようになり、クラスに連帯感が生まれていく……そんなエピソードです。
この部分を読んで、ちょっと前に読んだ『教育の根底にあるもの』という本を思い出しました。その中で、子供は「発達の度合いに応じて等しく教育を受ける権利がある。(能力に合わせた異なった教育ではない)」という記述がありました。まさにこれは、その精神を示しているところだと思います。子供の中には「宝物」が眠っているのだから、大人が「この子はここまでやらせてやめておいたほうがいい」などと決めてしまってはならないという考えには確かに納得します。
しかし、みな子ちゃんのせいで授業が遅れてしまうのも事実。特に当番の子はその日一日授業どころではありません。この本の中では親御さんたちがそれを主張しますが、きっと今の子だったら子供でさえ「めんどくさい」だとか「なんで私たちが」のようなことを言うのではないでしょうか。それは仕方の無いことだと思います。子供たちは厳密にカリキュラムが決められ、どこからどこまで学ばなければいけないし、家に帰ったら塾、習い事、本当にいっぱいいっぱいですから。私も自分にもし子供がいたらきっと批判的になってしまうと思います。
それでも、きっと大人になったらこうして助け合った体験が、自分の人生の希望になっていくのでしょうね。
また、この作品には足立先生というものすごいキャラの濃いやくざみたいな先生が出てきます。彼が大事にしているのは「自分で考える」ということ。いつもは豪快で優しい先生なのに「これでいい?」と聞いてくる子にはぴしゃりと「自分で考えなさい」と対応する潔さに信念を感じます。指導の仕方も、誰かの真似なんかせずに自分で考えろという主張の持ち主。ちょっと過激なところがあるけれど、彼なりの哲学があるのだろうなぁ。
小谷先生はすばらしい教師ではあるけれど、家庭を軽んじている部分があり、わざわざ人間として未完成である部分が強調されているのはいったいなんでなんでしょう(旦那さんはもっとひどいけど!)。「私、教師として人として成長しすぎて旦那の低レベルな思考にはついていけませんの、おほほ」と思うことは果たしてすばらしいことなのかしら……。
もやもやする部分がちょっとずつあるんですが、賛否両論あるということはやはり名作なのだと思います。子供ができたときにまた読みたい作品です。
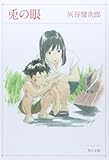
¥617
Amazon.co.jp
みなさんこんばんは。
今日から仕事始めという方も多かったのではないでしょうか。出勤すると待っているのは溜まった仕事……あれよあれよとこなすうちに正月気分はすっかり抜けていつもの日常に戻ってしまうなんとも寂しい日です。管理人は正月ぐうたらしすぎて体力的にしんどかったです……。私のようなぐうたらは仕事をしないと真人間ではいられないようです……。
さて、本日の本は灰谷健次郎さん『兎の目』です。
名作との誉れ高い本作は、教師のバイブルとも言われる作品だそうです。
大学を出たばかりの新任の小谷先生は、小学校一年生の担任。学校では一言も口を利かなくて、暴力的なところのある鉄三は問題行動ばかり。鉄三はごみ処理場に併設された長屋に、祖父のバクじいさんと住んでいました。ごみ処理場の暮らしは貧しくて、不潔で汚く、そこから学校に通ってくる子は馬鹿にされたりいじめられたりする風潮がありました。
誠実であろうと努力する小谷先生ですが、悔しさや悲しさで声を上げて泣いてしまうこともありました。やめてしまいたいと思うこともありました。しかし、彼女のひたむきな姿勢はほかの先生たちや、保護者を動かしてやがて大きな問題に立ち向かっていく力となっていきます。
以下ネタバレ
教師なら一度は読んでおけといわれるだけあって、教師とは?教育とは?といったテーマが描かれています。批判も多いこの作品ですが、それは「みな子」という知的障害を持った子供の扱いの部分ではないでしょうか。通常の小学校では対応ができないため、特別支援学級に入れられることとなったみな子ちゃん。小谷先生は彼女を自分のクラスで受け持ちたいと強く主張しました。
ほんの少しの間もじっと座っていることのできないみな子は、やはり小谷先生の行動を大きく制限し、まともに授業のできないことも多くありました。しかしそんなみな子と触れ合ううちに子供たちは自分たちで彼女の相手をしたいと主張するようになり、クラスに連帯感が生まれていく……そんなエピソードです。
この部分を読んで、ちょっと前に読んだ『教育の根底にあるもの』という本を思い出しました。その中で、子供は「発達の度合いに応じて等しく教育を受ける権利がある。(能力に合わせた異なった教育ではない)」という記述がありました。まさにこれは、その精神を示しているところだと思います。子供の中には「宝物」が眠っているのだから、大人が「この子はここまでやらせてやめておいたほうがいい」などと決めてしまってはならないという考えには確かに納得します。
しかし、みな子ちゃんのせいで授業が遅れてしまうのも事実。特に当番の子はその日一日授業どころではありません。この本の中では親御さんたちがそれを主張しますが、きっと今の子だったら子供でさえ「めんどくさい」だとか「なんで私たちが」のようなことを言うのではないでしょうか。それは仕方の無いことだと思います。子供たちは厳密にカリキュラムが決められ、どこからどこまで学ばなければいけないし、家に帰ったら塾、習い事、本当にいっぱいいっぱいですから。私も自分にもし子供がいたらきっと批判的になってしまうと思います。
それでも、きっと大人になったらこうして助け合った体験が、自分の人生の希望になっていくのでしょうね。
また、この作品には足立先生というものすごいキャラの濃いやくざみたいな先生が出てきます。彼が大事にしているのは「自分で考える」ということ。いつもは豪快で優しい先生なのに「これでいい?」と聞いてくる子にはぴしゃりと「自分で考えなさい」と対応する潔さに信念を感じます。指導の仕方も、誰かの真似なんかせずに自分で考えろという主張の持ち主。ちょっと過激なところがあるけれど、彼なりの哲学があるのだろうなぁ。
小谷先生はすばらしい教師ではあるけれど、家庭を軽んじている部分があり、わざわざ人間として未完成である部分が強調されているのはいったいなんでなんでしょう(旦那さんはもっとひどいけど!)。「私、教師として人として成長しすぎて旦那の低レベルな思考にはついていけませんの、おほほ」と思うことは果たしてすばらしいことなのかしら……。
もやもやする部分がちょっとずつあるんですが、賛否両論あるということはやはり名作なのだと思います。子供ができたときにまた読みたい作品です。