象牙の塔の殺人 (創元推理文庫)/東京創元社
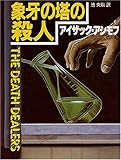
¥691
Amazon.co.jp
あけましておめでとうございます。
今年もどうぞ、暇で暇でしょうがなかったら拙ブログにお越しくださいませ。
このブログは基本的に個人の感想倉庫なんですが、もし同じ小説を読んだ人がいて「誰かと感想を分かち合いたいけど、友達が一人もいない!!!!」ってなったときにちょっと覗いていただければ嬉しいなと思って書いております。
新年一発目の本はアシモフ『象牙の塔の殺人』です。
大学の研究室のお話だということは知っていて読み始めたのですが、当初「大学の建物が象牙でできてるってすげぇなあ!!」と馬鹿みたいなことを思っていました。違いますね。
「象牙の塔」とは「芸術を至上のものとする人々が俗世間から離れ、芸術を楽しむ静寂・孤高の境地。学者などの現実離れした研究生活や態度、研究室などの閉鎖社会」を指す言葉。フランス語の訳語だそうですよ。「インテリ集団」というかっこいい意味の裏に、「世間知らずなやつら」というネガティブな意味もある言葉だそうです。
主人公は中年助教授ルイ・ブレイド。彼は自分の研究でなかなか芽が出ず、厄介な生徒を押し付けられる苦労人。家に帰れば「昇進は?」と聞いてくる無知な妻。哀愁が紙面からにじみ出ています。
そんな折、彼の指導している大学院生であるラルフ・ノイフェルトという学生が実験中に死亡しているのを発見してしまいます。当初は事故として片付けられそうになりましたが、ブレイドは彼の死が殺人であること、そしてその一番の容疑者は自分になってしまうことに思い至ります。自分の大学での職や、化学というものへの姿勢、恩師や同僚、生徒と生徒の恋愛、さまざまな問題に振り回されながらブレイドは象牙の塔の秘密を探っていきます。
以下ネタバレ
管理人はてっきりアシモフって物理関係の方だと思っていたんですが、ご専門は生化学だったんですね。私も少しばかり有機化学を齧りましたので今回の話は「あるあるあるw」の連続で面白かったです。化学系の学生だった方はより楽しめたのではないでしょうか。特に有機化学が軌道計算とかしてる量子化学におされていて、昔の場当たり的に合成を繰り返す教授は過去の人っていうのもあるあるすぎですわ。さすがアシモフ先生。
日本のポスドクの扱いが奴隷だという話はiPSの山中先生のインタビューなどで指摘されていましたが、ポストが無いのはアメリカも同じなんですね。聞いた話によるとアメリカでは優秀な研究員を二人雇って競わせ、どちらか片方だけ採用するといった風習があったのだとか。まさに競争社会という感じですね。
また、研究員の経歴で大事なのは「どの大学だったか?」というよりも「どの教授の門下生か?」だということなのもよく聞く話ですね。今回はそのつながりが強すぎたことが殺人の動機になってしまうというお話でした。それほど教授の影響力は強くて、学生や研究員はまさに生殺与奪の権を握られているという状況なんでしょうね。
今回の事件の発端にラルフの犯した「データの改竄」があるのですが、これは去年世間をにぎわせたSTAP細胞を思い起こさせます。老アンスンは「ラルフが死ぬようになったのはきみのせいだ。きみが殺したんだ。きみは責任を免れない。データの改竄が目の前で行われていることに気づかなかったきみの不明ゆえに、ラルフはあたら若い命を落とすことになったのだ(以上引用)」とブレイドを問い詰めますが、これはブレイド=笹井先生に置き換えて考えると……あぁ、ぞっとします。ブレイドも命を狙われますしね……。
これが50年以上前に書かれた作品だというのに、今なお一級の作品であるといわれる理由が分かった気がします。理系の人におススメのミステリです。
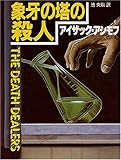
¥691
Amazon.co.jp
あけましておめでとうございます。
今年もどうぞ、暇で暇でしょうがなかったら拙ブログにお越しくださいませ。
このブログは基本的に個人の感想倉庫なんですが、もし同じ小説を読んだ人がいて「誰かと感想を分かち合いたいけど、友達が一人もいない!!!!」ってなったときにちょっと覗いていただければ嬉しいなと思って書いております。
新年一発目の本はアシモフ『象牙の塔の殺人』です。
大学の研究室のお話だということは知っていて読み始めたのですが、当初「大学の建物が象牙でできてるってすげぇなあ!!」と馬鹿みたいなことを思っていました。違いますね。
「象牙の塔」とは「芸術を至上のものとする人々が俗世間から離れ、芸術を楽しむ静寂・孤高の境地。学者などの現実離れした研究生活や態度、研究室などの閉鎖社会」を指す言葉。フランス語の訳語だそうですよ。「インテリ集団」というかっこいい意味の裏に、「世間知らずなやつら」というネガティブな意味もある言葉だそうです。
主人公は中年助教授ルイ・ブレイド。彼は自分の研究でなかなか芽が出ず、厄介な生徒を押し付けられる苦労人。家に帰れば「昇進は?」と聞いてくる無知な妻。哀愁が紙面からにじみ出ています。
そんな折、彼の指導している大学院生であるラルフ・ノイフェルトという学生が実験中に死亡しているのを発見してしまいます。当初は事故として片付けられそうになりましたが、ブレイドは彼の死が殺人であること、そしてその一番の容疑者は自分になってしまうことに思い至ります。自分の大学での職や、化学というものへの姿勢、恩師や同僚、生徒と生徒の恋愛、さまざまな問題に振り回されながらブレイドは象牙の塔の秘密を探っていきます。
以下ネタバレ
管理人はてっきりアシモフって物理関係の方だと思っていたんですが、ご専門は生化学だったんですね。私も少しばかり有機化学を齧りましたので今回の話は「あるあるあるw」の連続で面白かったです。化学系の学生だった方はより楽しめたのではないでしょうか。特に有機化学が軌道計算とかしてる量子化学におされていて、昔の場当たり的に合成を繰り返す教授は過去の人っていうのもあるあるすぎですわ。さすがアシモフ先生。
日本のポスドクの扱いが奴隷だという話はiPSの山中先生のインタビューなどで指摘されていましたが、ポストが無いのはアメリカも同じなんですね。聞いた話によるとアメリカでは優秀な研究員を二人雇って競わせ、どちらか片方だけ採用するといった風習があったのだとか。まさに競争社会という感じですね。
また、研究員の経歴で大事なのは「どの大学だったか?」というよりも「どの教授の門下生か?」だということなのもよく聞く話ですね。今回はそのつながりが強すぎたことが殺人の動機になってしまうというお話でした。それほど教授の影響力は強くて、学生や研究員はまさに生殺与奪の権を握られているという状況なんでしょうね。
今回の事件の発端にラルフの犯した「データの改竄」があるのですが、これは去年世間をにぎわせたSTAP細胞を思い起こさせます。老アンスンは「ラルフが死ぬようになったのはきみのせいだ。きみが殺したんだ。きみは責任を免れない。データの改竄が目の前で行われていることに気づかなかったきみの不明ゆえに、ラルフはあたら若い命を落とすことになったのだ(以上引用)」とブレイドを問い詰めますが、これはブレイド=笹井先生に置き換えて考えると……あぁ、ぞっとします。ブレイドも命を狙われますしね……。
これが50年以上前に書かれた作品だというのに、今なお一級の作品であるといわれる理由が分かった気がします。理系の人におススメのミステリです。

