冷たい方程式―SFマガジン・ベスト1 (ハヤカワ文庫 SF 380 SFマガジン・ベスト 1)/早川書房
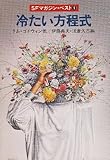
¥756
Amazon.co.jp
さて、本日の本二冊目はトム・ゴドウィン他『冷たい方程式』です。
短編の中ではSFのベストに選ぶ人も多い表題作。のちに「方程式もの」と呼ばれるジャンルを築いた記念碑的作品だそうな。
学生時代に使っていた汚なくて古い部室の本棚に、この本の日に焼けた表紙が並んでいたことをふと思い出しました。それくらい有名な本ってことなんでしょうね。このSF・マガジンベスト版は表題作のほかに、ほかの短編集には載ってないけれどいい作品だといわれる作品が6編入っています。
以下ネタバレ感想
①「接触汚染」キャサリン・マクレイン
地球人の移住のために新たな星を探索していたエクスプローラー号の乗組員たちは、マイノスという星にやってくる。マイノスで初めて出会った人物は、とても精悍な顔立ちのいわゆるイケメンのミードであった。ミードはかつてこの地にやってきた人類の生き残りらしく、「ほかの家族もまったく同じ顔」というように、どうやら彼の一族だけがこの地に定住できていたらしい。
免疫検査をして船内に入ったミードであるが、彼は独特な食菌細胞の持ち主だったらしく船の中のほかの乗組員に感染し男たちの健康な赤血球を次々と食い殺し始めた。(細胞って感染するの!?)最後の最後まで科学者たろうと必死に原因を突き止めるマックスであるが、とうとう力尽き、延命措置の施されるカプセルの中で最期の時を迎えることになる。
が、まさかの復活!!!!しかも男全員の顔がミードになってる!!どうやら感染力を持ったミードの食菌細胞は感染対象をミードそのものに変えて、この星に適応させる力があったらしい。愛するマックスがまったく別の顔になって戸惑うジューンであったが、徐々に受け入れられるようになっていく。イケメンだしね。だがそこにミードの妹がやってきて……。
自分のアイデンティティがどれだけ顔に依存しているかってことなんですね。他人とまったく同じ顔で、それでも自分は自分でいられるのかしらという。私は自分の顔大嫌いなので、こんな機会があるなら真っ先に船外に飛び出して感染しに行こうと思います。
②「大いなる祖先」F・L・ウォーレス
人類がさまざまな星で栄え、いろんな形に進化し、そこに世代間の格差・差別のようなものが生まれている時代。いろんな立場の学者四人は、非人間型のリボン人タフェッタをつれて、人類のルーツを探る研究を進めていた。このリボン人っていうのはリボンの意味が何かあるのでしょうか。もう最初のページ読んだとき笑いましたね。リボン!?え?リボン!?って。きっととても奇妙な形なんでしょう。
ルーツを追いかける彼らがたどり着いた事実は大変にショッキングなものでした。あー、害虫みたいなもんですかそうですかと。節操も無く数だけ増えて厄介な存在ですかと。まるでゴキブリみたいですねと!!!どれだけ差別し合っても結局お前らは同じ穴の狢なんだよというこのお話は、現代にも通じそうな気がします。
③「過去へ来た男」ポール・アンダースン
1930年代にアメリカ合衆国で軍人をしていた男が1000年代のアイスランドにタイムスリップ!!良かったですねぇ、日本じゃなくて……日本だったら天狗様にされてますよきっと。
タイムスリップしてきた男ジェラルドはやっぱり生活様式の違いに困ります。鍛冶もできない、羊も追えない、裁縫もできない、農作業もできない、できないづくしなんですね。当たり前ですよね。そんなの1930年代では全部道具がやってくれるんだもの。何もできないジェラルドが非難される様は「現代人は結局一人じゃ何にもできないんだよ。生きる力がないんだよ」と言われているよう。そんなことが重なったジェラルドは最後はキチガイ扱いされて不運な生涯を終えることになりました。
④「祈り」アルフレッド・ベスター
事の起こりはスチュワート・ビャキュナンという五年生の男の子が書いた作文『夏やすみ』でした。その作文にはなんと、彼の友人たちがずば抜けた能力の持ち主たちであることが記されていたのです。星が好きなトミーは破砕光線をつくり、野菜嫌いなアンメァリーは物質変換装置をつくり、飛行機好きのジョージは高性能な小型ロボットをつくり、怠け者のエセルはテレポートができるらしい。これらを軍や関連企業に売れば一儲けできるとたくらんだ主人公は、ビャキュナンという少年を血眼になって探します。いったいビャキュナンはどんな才能を持っているのだろうという期待をかけて。
オチ自体は「あ……うん……そっか」という感じ。その祈りの能力によって消されてしまった人たちの世界が怖い。
⑤「操作規則」アルフレッド・ベスター
超人的な能力を有した「プサイ」と呼ばれる人たち。彼らはその能力を、宇宙開発などに発揮していた。このお話ではウォーカーという物質を瞬間移動できる男が宇宙艇の打ち上げチームに加わる。しかしすばらしい能力はえてして普通の人間たちに理解されず煙たがられるもの。宇宙艇の乗組員のダントンとアリグリオは、この繊細で扱いに困る「プサイ」を良く思っていませんでした。艇長であるパウエルは彼らにプサイは機械のようなものだから、操作規則にのっとって、丁重に扱ってほしいとお願いします。
打ち上げの時間。あんなに自信に満ち溢れていたウォーカーは能力の制御に失敗し、艇を土星付近にまで移動させてしまいます。帰りの燃料はもちろんありません。乗組員はウォーカーに頼るしかないのです。良くこんな不確定な要素を打ち上げに組み込んだなおい……。
乗組員たちは操作規則にのっとって、ウォーカーをなだめすかし、傷つけないように、機嫌をそこねないように、落ち込ませないように、追い詰めないように扱います。でもウォーカーはどんどん自信を失って、自殺しようとまで考えます。
追い詰められたパウエルはウォーカーを機械として扱うことをやめました。とても清清しい素敵なラストだと思います。パウエルたちは人間としてプサイを扱うことで、結局は操作規則にあるような環境を作り出せたんですね。マニュアルはToDoリストを守る表層的なものではなくて、それが作られた理由を理解できれば自然とできることなんでしょうね。
⑥「冷たい方程式」トム・ゴドウィン
EDSは緊急時にパイロットと必要な積荷(医薬品等)と必要最小限の燃料だけを積んで目的地に向かう小型の宇宙船。もしそこに密航者が乗り込んできたら、有無を言わさず船外に放り出さなければならない。たとえそれが、兄に会いたい一心で何も知らずに乗り込んできた18歳の少女だったとしても……。
パイロットのバートンはこの事態を「どうしようもないこと」だといいます。確かに少女が降りなければバートンと6人の探検隊が命を落とすことになるでしょう。これは宇宙という厳しい世界が作り出した、変えることのできないルールなんです。
この冷たい方程式というのは天災のようなものを想定しているのでしょうか。大地震や大津波といった天災は、被害にあった人が「死ぬようなことはしていなくても」かまわずにその命を奪うものですよね。バートンはその天災の外にいて、サバイバーズギルトを感じているのかな。
少女の気持ちの変化と、毅然としてエアロックに向かう様は本当に胸を打たれて涙なしには読めないんです。が!このEDSのシステムの杜撰さに腹が立ったよわしゃ!!何で飛び立つ前に点検しない??というかなんで飛び立つ前に一般人がやすやすと入り込めちゃうの??そもそも人が入り込めちゃうスペース無駄じゃね???危険な場所に行くときは行き返りで燃料の1/3になるようにするのが常識だろ!!!
悲しさゆえに八つ当たりする管理人。
⑦「信念」アイザック・アシモフ
物理法則を完全に無視した空中浮遊の能力を得てたのが、物理学者だったとしたら……?という設定がとても面白い。大変でしょうね。既存の理論をぶち壊してこその研究者だと思うのですが、万有引力の法則を否定するのは天動説を否定するくらいきっと今では困難でしょう。ほかの物理学者の知り合いから気が違っただの奇術だのと非難される教授が可愛そう。そこで彼が取った手段とは……?
どうでも良いけどこの話に出てくる精神科医のサールが粋でかっこいい。
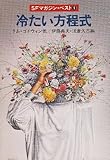
¥756
Amazon.co.jp
さて、本日の本二冊目はトム・ゴドウィン他『冷たい方程式』です。
短編の中ではSFのベストに選ぶ人も多い表題作。のちに「方程式もの」と呼ばれるジャンルを築いた記念碑的作品だそうな。
学生時代に使っていた汚なくて古い部室の本棚に、この本の日に焼けた表紙が並んでいたことをふと思い出しました。それくらい有名な本ってことなんでしょうね。このSF・マガジンベスト版は表題作のほかに、ほかの短編集には載ってないけれどいい作品だといわれる作品が6編入っています。
以下ネタバレ感想
①「接触汚染」キャサリン・マクレイン
地球人の移住のために新たな星を探索していたエクスプローラー号の乗組員たちは、マイノスという星にやってくる。マイノスで初めて出会った人物は、とても精悍な顔立ちのいわゆるイケメンのミードであった。ミードはかつてこの地にやってきた人類の生き残りらしく、「ほかの家族もまったく同じ顔」というように、どうやら彼の一族だけがこの地に定住できていたらしい。
免疫検査をして船内に入ったミードであるが、彼は独特な食菌細胞の持ち主だったらしく船の中のほかの乗組員に感染し男たちの健康な赤血球を次々と食い殺し始めた。(細胞って感染するの!?)最後の最後まで科学者たろうと必死に原因を突き止めるマックスであるが、とうとう力尽き、延命措置の施されるカプセルの中で最期の時を迎えることになる。
が、まさかの復活!!!!しかも男全員の顔がミードになってる!!どうやら感染力を持ったミードの食菌細胞は感染対象をミードそのものに変えて、この星に適応させる力があったらしい。愛するマックスがまったく別の顔になって戸惑うジューンであったが、徐々に受け入れられるようになっていく。イケメンだしね。だがそこにミードの妹がやってきて……。
自分のアイデンティティがどれだけ顔に依存しているかってことなんですね。他人とまったく同じ顔で、それでも自分は自分でいられるのかしらという。私は自分の顔大嫌いなので、こんな機会があるなら真っ先に船外に飛び出して感染しに行こうと思います。
②「大いなる祖先」F・L・ウォーレス
人類がさまざまな星で栄え、いろんな形に進化し、そこに世代間の格差・差別のようなものが生まれている時代。いろんな立場の学者四人は、非人間型のリボン人タフェッタをつれて、人類のルーツを探る研究を進めていた。このリボン人っていうのはリボンの意味が何かあるのでしょうか。もう最初のページ読んだとき笑いましたね。リボン!?え?リボン!?って。きっととても奇妙な形なんでしょう。
ルーツを追いかける彼らがたどり着いた事実は大変にショッキングなものでした。あー、害虫みたいなもんですかそうですかと。節操も無く数だけ増えて厄介な存在ですかと。まるでゴキブリみたいですねと!!!どれだけ差別し合っても結局お前らは同じ穴の狢なんだよというこのお話は、現代にも通じそうな気がします。
③「過去へ来た男」ポール・アンダースン
1930年代にアメリカ合衆国で軍人をしていた男が1000年代のアイスランドにタイムスリップ!!良かったですねぇ、日本じゃなくて……日本だったら天狗様にされてますよきっと。
タイムスリップしてきた男ジェラルドはやっぱり生活様式の違いに困ります。鍛冶もできない、羊も追えない、裁縫もできない、農作業もできない、できないづくしなんですね。当たり前ですよね。そんなの1930年代では全部道具がやってくれるんだもの。何もできないジェラルドが非難される様は「現代人は結局一人じゃ何にもできないんだよ。生きる力がないんだよ」と言われているよう。そんなことが重なったジェラルドは最後はキチガイ扱いされて不運な生涯を終えることになりました。
④「祈り」アルフレッド・ベスター
事の起こりはスチュワート・ビャキュナンという五年生の男の子が書いた作文『夏やすみ』でした。その作文にはなんと、彼の友人たちがずば抜けた能力の持ち主たちであることが記されていたのです。星が好きなトミーは破砕光線をつくり、野菜嫌いなアンメァリーは物質変換装置をつくり、飛行機好きのジョージは高性能な小型ロボットをつくり、怠け者のエセルはテレポートができるらしい。これらを軍や関連企業に売れば一儲けできるとたくらんだ主人公は、ビャキュナンという少年を血眼になって探します。いったいビャキュナンはどんな才能を持っているのだろうという期待をかけて。
オチ自体は「あ……うん……そっか」という感じ。その祈りの能力によって消されてしまった人たちの世界が怖い。
⑤「操作規則」アルフレッド・ベスター
超人的な能力を有した「プサイ」と呼ばれる人たち。彼らはその能力を、宇宙開発などに発揮していた。このお話ではウォーカーという物質を瞬間移動できる男が宇宙艇の打ち上げチームに加わる。しかしすばらしい能力はえてして普通の人間たちに理解されず煙たがられるもの。宇宙艇の乗組員のダントンとアリグリオは、この繊細で扱いに困る「プサイ」を良く思っていませんでした。艇長であるパウエルは彼らにプサイは機械のようなものだから、操作規則にのっとって、丁重に扱ってほしいとお願いします。
打ち上げの時間。あんなに自信に満ち溢れていたウォーカーは能力の制御に失敗し、艇を土星付近にまで移動させてしまいます。帰りの燃料はもちろんありません。乗組員はウォーカーに頼るしかないのです。良くこんな不確定な要素を打ち上げに組み込んだなおい……。
乗組員たちは操作規則にのっとって、ウォーカーをなだめすかし、傷つけないように、機嫌をそこねないように、落ち込ませないように、追い詰めないように扱います。でもウォーカーはどんどん自信を失って、自殺しようとまで考えます。
追い詰められたパウエルはウォーカーを機械として扱うことをやめました。とても清清しい素敵なラストだと思います。パウエルたちは人間としてプサイを扱うことで、結局は操作規則にあるような環境を作り出せたんですね。マニュアルはToDoリストを守る表層的なものではなくて、それが作られた理由を理解できれば自然とできることなんでしょうね。
⑥「冷たい方程式」トム・ゴドウィン
EDSは緊急時にパイロットと必要な積荷(医薬品等)と必要最小限の燃料だけを積んで目的地に向かう小型の宇宙船。もしそこに密航者が乗り込んできたら、有無を言わさず船外に放り出さなければならない。たとえそれが、兄に会いたい一心で何も知らずに乗り込んできた18歳の少女だったとしても……。
パイロットのバートンはこの事態を「どうしようもないこと」だといいます。確かに少女が降りなければバートンと6人の探検隊が命を落とすことになるでしょう。これは宇宙という厳しい世界が作り出した、変えることのできないルールなんです。
この冷たい方程式というのは天災のようなものを想定しているのでしょうか。大地震や大津波といった天災は、被害にあった人が「死ぬようなことはしていなくても」かまわずにその命を奪うものですよね。バートンはその天災の外にいて、サバイバーズギルトを感じているのかな。
少女の気持ちの変化と、毅然としてエアロックに向かう様は本当に胸を打たれて涙なしには読めないんです。が!このEDSのシステムの杜撰さに腹が立ったよわしゃ!!何で飛び立つ前に点検しない??というかなんで飛び立つ前に一般人がやすやすと入り込めちゃうの??そもそも人が入り込めちゃうスペース無駄じゃね???危険な場所に行くときは行き返りで燃料の1/3になるようにするのが常識だろ!!!
悲しさゆえに八つ当たりする管理人。
⑦「信念」アイザック・アシモフ
物理法則を完全に無視した空中浮遊の能力を得てたのが、物理学者だったとしたら……?という設定がとても面白い。大変でしょうね。既存の理論をぶち壊してこその研究者だと思うのですが、万有引力の法則を否定するのは天動説を否定するくらいきっと今では困難でしょう。ほかの物理学者の知り合いから気が違っただの奇術だのと非難される教授が可愛そう。そこで彼が取った手段とは……?
どうでも良いけどこの話に出てくる精神科医のサールが粋でかっこいい。

