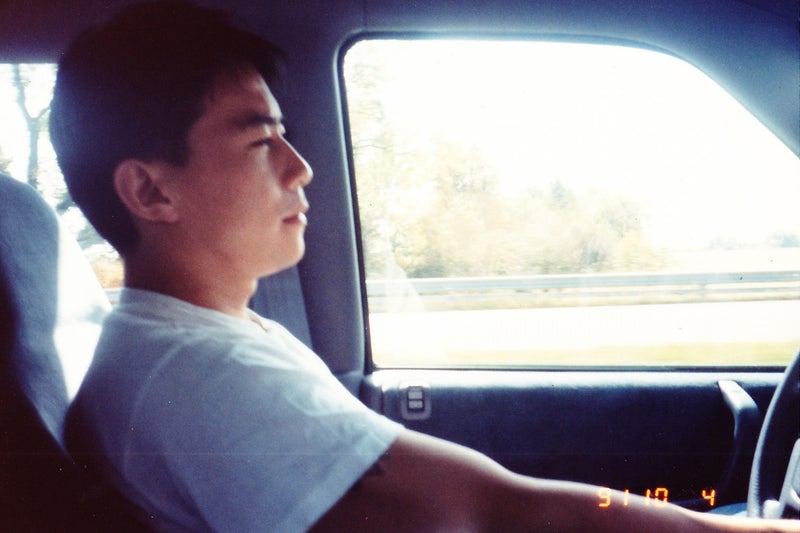その時腕時計のケースを作ったのは、単なる思い付きではなかった。
『何代にも渡って使える腕時計』 は、そもそもジャンクヤードの頃からの念願だったのだ。
ただ 「そのうちに」 とか 「いつか時間が出来たら」 と先延ばしになったまま何年もが過ぎていて、、、腰の重い私は、ようやっとそのモデル作りを始めたという訳だった。
ちなみに、懐中時計を改造した腕時計は、以前から販売していた。
これはシカゴのケース屋ボブさんがうちのために作ってくれていたのだが、アンティークの懐中時計にそのままラグをロウ付けして、バンドを取り付けたもの。
アンティークだけに中身のムーブメントは丈夫だし、見た目にもクラッシックで良かったが、、ケースに防水性がない。
だから手洗いする時は水が掛からないように腕から外し、汗をかく夏場などは使わないようにする等、使用にあたっては相当に気を遣う必要があったし、実際、水や埃の混入による故障が、珍しくなかったのだ。
私とタマちゃんの合作の腕時計ケースは、形状も仕様も好ましい感じに出来ていたが、、これも、防水仕様ではない。
防水仕様にするには、べゼルや裏ブタを捩じ込みにしてパッキンを装着する必要があるが、これを当時のパスタイムにあった機材でやるのは無理だった。
だからプロトタイプを持ってケースメーカーを訪ね、ほぼ同じ形状でありながら、防水仕様にしたケースを製作してもらう算段。
ところが何社かをあたった時点で、技術的、数量的な問題で予想以上にハードルが高く、、計画はすぐに頓挫。
結局、このプロトタイプはそれから1年以上、私の引き出しに入りっぱなしになった。
それはともかく、このプロトタイプの製作を通じ、研修生のタマちゃんには、なかなかの腕があることが判った。
勿論時計の方の話ではなく、彫金、金工の方の話だが、、、折角だから、何かその腕を活かす手はないか?
聞いてみると、本人も、彫金では食べてゆけないから 「時計の仕事を」 となっただけで、、、彫金が仕事になるのなら、それに越したことはないという感じ。
それじゃあ試しに、と、ケースのなくなった懐中時計のムーブメントを渡し、、、「タマチャン、この時計のケース作ってみて。」
「分かりました。」
タマチャンは、純銀の棒に火を掛けてなましては金床の上でトンチンカンチン叩いて丸め、端っこ同士をロウ付けして、大きなドーナッツを3つ作った。
次にドーナッツ状の一つを旋盤にセットして削り、ムーブメントがピッタリ入る大きさになるまで、穴の内側を削る。
そんな具合にベゼルや裏蓋も削り出し、、その後、ヤスリで作った蝶番やペンダントをケース本体にロウ付け。
旋盤の使い方や大まかな段取りこそ手ほどきしたが、、、タマチャンは、ほぼ自力で銀の懐中時計ケースを完成させた。
「よしタマチャン、今度は文字盤ね。」
次に私は、文字盤が派手に割れてしまっているエルジンの懐中時計をタマチャンに渡し、銀で手彫りの文字盤を作るよう言った。
こいつはそう簡単にはいくまい。
内心、そう思っていた。
文字盤は、ただ彫れればいいという訳にいかない。
秒針の穴や固定用の裏側の足の位置は、正確に機械部分と合致しなければいけないし、、、それに、彫り入れる分刻みのインデックスやMasa’s Pastimeのロゴは、肉眼では読めないほど細く、小さくないと格好が悪い。
だからもう何10年も前から、、、メーカーものの時計の文字盤は、プレス加工や印刷技術で大量生産されている訳だ。
しかし結果から言うと、タマチャンの作った銀の文字盤は1枚目こそ野暮ったい感じだったが、、、ここをもっと正確に、もっと細かく!
うるさい注文をつけているうち、、数か月後には、いよいよ商品化出来るレベルになった。
まさに、東北人の粘り強さを見る思い。
「出来んじゃん、タマチャン! これならいけるよ!」
こうして、時計師を目指してパスタイムにやって来たタマチャンは、、幸か不幸か、彫金で飯が食えそうな見込みが立った。
結果的には、パスタイムにとっても仕事の広がりが出来るし、、、本人も満更では無さそう。
それはそれで良かったのだが、、、一方で、解決しなければいけない問題はそのまま。
時計職人は相変わらず私と岩田の2人だけで、、、時計の直し手は足りないのだった。
(続く)