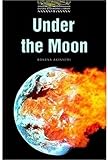こだわりのつっこみ -9ページ目
一応、今回で最終回の、おかしな喩えシリーズですが、今回はオーケストラの曲を聴くにあたって、私が特に重視というか興味を持っている部分です。それぞれの音というのはもちろんありますが、互いの音をブレンドさせることで、また違う響きを生む のです。オーケストレーション と言います。ボレロ 」を聴いてみてください。 リズムというのは、最初の小太鼓で聴こえるとおり、 この曲、10分以上かかるので、2つに分けてあります。前半
。 0:20~ 小太鼓0:30~ フルート 1:16~ クラリネット 2:02~ ファゴット 2:50~ クラリネット(小) 3:38~ オーボエ・ダモーレ 4:26~ フルート+トランペット(弱音器つき) ※フルートとトランペットのブレンド 5:13~ テノールサックス 6:02~ ソプラノサックス (以降ハープ略)6:50~ ピッコロ+ホルン+チェレスタ ※意外な音が感じられます 後半
。次第に盛り上がっていきますよ~。 0:25~ 弦楽器+ファゴット+ホルン+トランペット(弱音器つき)0:30~ オーボエ+オーボエ・ダモーレ+イングリッシュホルン+クラリネット 1:18~ トロンボーン 2:06~ 木管楽器たち 2:54~ 木管楽器+ヴァイオリン 3:42~ 木管楽器+ヴァイオリン 4:30~ 木管楽器+弦楽器+トランペット 5:17~ 木管楽器+金管楽器+弦楽器 6:06~ 高音木管楽器+トランペット+ヴァイオリン 6:54~ 高音木管楽器+トランペット+トロンボーン+ヴァイオリン 標準的な曲では30種類を越えませんが、音の組み合わせではそれこそ何百という変化を見せる のです。楽器にもそれぞれ出しやすい音、響きやすい音 があります。 さて、今回のポイントは 楽器は食材である。 真面目に(?)音楽の歴史を探ってみたい と思いますレベル: 若干長めですが、中学2~3年生レベルなので数時間で読めると思います。
ジャンル: ファンタジー あらすじ(背表紙から):
面白さ: ★
※以下、結末まで話します。嫌な方は見ないでください。
Alice in Wonderland, Level 2, Penguin Readers (.../Lewis Carroll
¥598
Amazon.co.jp
内容:
ある暑い夏の日、姉と共に木の下に座っていたアリス は、とても退屈でした。 感想: 全然、分かりません。話が脈絡がなさ過ぎるし、理不尽すぎるし、私自身の圧倒的な英語の知識の不足があるから 」です。この作品は、駄洒落、パロディ、風刺、なぞなぞ、内輪笑いなどが満載 とのこと。 ----------------------------------------------------------------- 日本を代表する大作家先生であり、色んな解説本も出ている中で恐縮ですが、今回は村上春樹さんのデビュー作である長編小説風の歌を聴け を紹介です。あらすじ はと言いますと(しかし、よく頭に入っていないので間違いもあるかと思います)、僕 」が夏休みに故郷へ戻り、「鼠」という金持ちらしい同世代の男と知り合い、「ジェイズ・バー」でビールを飲んだり、小説について語り合ったりという退屈な毎日を送ります。 では以下はネタバレ含むので、いやな方は見ないで下さい。 風の歌を聴け (講談社文庫)/村上 春樹
¥370
Amazon.co.jp
~1回目 2010.6.14~ あらすじの続きといきたいところですが、実のところあらすじを書くようなまとまったストーリーがない、というのがこの作品の特徴でもあると思い、かなり変なあらすじになってしまうと思うので、ここはバッサリ核心部分のみを紹介しておきます。感想 文体が独特 (翻訳調といいましょうか)。なにかを喪失し、それを追いかける(または追いかけようとする) 。なんかしっくりこないんだよなぁ 心がない役者に演じさせている いやでも小難しい用語を並べた左翼的な雰囲気が漂う20代って、こんなこと実際言いそうだったのか なぁ(笑)「何故牛はこんなまずそうで惨めなものを何度も何度も大事そうに反芻して食べるんだろう」(p130) 総合評価:★☆ ★☆ キャラ:★ 読み返したい度:★★★ レベル: 若干長めですが、中学2~3年生レベルなので数時間で読めると思います。
ジャンル: SF あらすじ(背表紙から):
面白さ: ★★★
※以下、結末まで話します。嫌な方は見ないでください。
Under the Moon: Stage 1: 400 Headwords (Oxford .../Rowena Akinyemi
¥627
Amazon.co.jp
内容:
オゾン層がなくなり、太陽からの熱が直接影響を受けるようになってしまった地球。Kiah と妻のRilla 。Gog や妻のBel は私腹を肥やすのに必死で、人工オゾン層の修復への金を拠出を拒んだばかりか、KiahとRillaを牢屋に入れます。オーストラリア方面司令官 はGogとBelの暗殺を謀ります。Adai だったのです。 感想: これ、最終的な結末は触れられていないのです宇宙戦争 レベル: 若干長めですが、中学2~3年生レベルなので数時間で読めると思います。
ジャンル: 恋愛 あらすじ(背表紙から):
面白さ: ★★☆
※以下、結末まで話します。嫌な方は見ないでください。
Remember Miranda: Level 1 (Bookworms Series)/Rowena Akinyemi
¥626
Amazon.co.jp
内容:
早くに両親を亡くし、兄弟姉妹もいなかったキャシー は、ある縁でハーヴェイ家の家政婦?養育師?としてお世話になることになります。ダンカン 、2人の子供たち、そしてダンカンの母親(お婆さん )がおり、母親のミランダは2年前に亡くなったとのこと。ジュリエット もハーヴェイ家を訪れます。ニック と仲良くなり、夕食を共にする仲にまで進展しますが、なぜか反対され、ミランダの死の真相も誰も語らないなど、だんだんとその謎の多さに不信感を抱くキャシー。 動揺します。
感想: どろどろしとりますなぁ~ ニック&ジュリエット カップルは好きになれませんねCopyright © CyberAgent, Inc. All Rights Reserved.