わたしはまだ、何かを心から悲しんだり憎んだりすることがない。だから、悲しみや憎しみがどんな思い出になるのかも、よくわかっていない。漠然とだが、どういうことに立ち向かっていくのはもっと先のことだろうと思っていた。
できればこのまま若く、世間の荒波にもまれず、静かに生活していきたいが、そういう訳にもいかないだろう。それなりの苦労は覚悟しているつもりだ。わたしは、いっぱしの人間として、いっぱしの人生を生きてみたい。できるだけ皮膚を厚くして、何があっても耐えていける人間になりたい。
将来の夢、というのや、人生をかける恋、など、何も思い描けなくても、そういう望みのようなものだけはうっすらとあるのだった。
(p49より)
---------------------------------
あとから芥川賞受賞作品だったことを知りました。
青山七恵さんのひとり日和です。
まずはあらすじ。
主人公の三田知寿は、離婚した母と埼玉で2人暮らし。
高校を卒業していた知寿はアルバイトを転々としながら暮らしていましたが、国語教師である母が先生同士の交換留学というもので中国に行くことになりました。
当然知寿も中国へ行かないかと誘われますが、東京に行きたいということで、断ります。
大学への進学は考えず、かといって物価も家賃も高い東京での生活も送れるのかは定かではありません。
そういう知寿に母は、東京にいる親戚のおばさんがいるのでその人の家に厄介になりなさいと言い、知寿もしぶしぶながら従うことに。
さて、母と別れて東京の親戚のおばさんの家へとやってきた知寿。
親戚のおばさんといっても、もう70歳くらいのおばあさん。
その親戚のおばあさん荻野吟子との生活を通じて、知寿は少しずつ成長していくという物語です。
では以下はネタバレを含む個人的な感想なので、いやな方は見ないで下さい。
- ひとり日和/青山 七恵

- ¥1,260
- Amazon.co.jp
~1回目 2011.5.10~
さて、あらすじの続きです。
惰性で付き合っていた陽平との関係も終わり、春から知寿はコンパニオンのバイトと駅のキオスクでのバイトを始めます。
かたやおばあさんである吟子は、社交ダンスを習い、ホースケさんという仲良しのおじいさんとも良い関係。
知寿はかなり性格がひねくれていて、それでいてその自分のことを客観的に分かっている女の子。
ホースケさんと仲良しで、おしゃれもする吟子に毒づいたり、軽い対抗感を示したりします。
さて、そんな知寿も新たな恋をします。
駅でバイトとして働いている藤田君。
徐々に親密になり恋人に。さらにはホースケさんも交え吟子の家で4人で食事したりすることもしばしば。
恋にバイトに順調だった知寿ですが、秋になると藤田君の様子がおかしくなります。
前の彼氏である陽平と同じように、「惰性」という言葉がちらつきますが、知寿は藤田君のことが好きで、関係を終わらせたくないと思っています。
しかし、終わりの決定打になる出来事が。
それは、藤田君のバイトに、糸井というかわいらしい女の子が来るのです。
イトちゃんと呼ばれている彼女は、知寿と藤田君の関係を知っていながらも気さくに3人で遊びに行ったり、ご飯を誘ったりします。
自分に対する接し方、そしてイトちゃんに対する接し方を目の当たりにし、次第に知寿は恋の終わりを感じることになり、事実藤田君は知寿に別れを告げることになるのです。
藤田君が実際にイトちゃんと新たな関係になるかどうかは分からないにしろ、未練が残る知寿はすぐにキオスクのバイトを辞め、池袋にある会社の事務員としてアルバイトすることにしました。
そして年末になり、母親が日本に帰ってきます。
すると母親は求婚されていることを告白し、さらに年が明けると知寿自身も正社員にならないかと言われ、段々と知寿を取り巻く環境が変わってきます。
正社員になるということは、吟子の家から出るということ。
吟子との生活、ホースケさんも含めた3人での食事も慣れてきてある種の安心感をもっていた知寿ですが、「ひとりになってみたい」というわずかにある気持ち、そしてここで居座ることで何も知らないままに一生を終えてしまうということを思い、吟子の家を出ることにするのでした。
感想です。
まず面白かった点は、すごく描写や表現が上手いなぁと思ったところです。
具体的な名場面や名台詞が満載だったということではなく、全体を取り巻く描写が非常に新鮮でした。
もちろん、名台詞もいくつか吟子の口から出てきます。
「吟子さん、外の世界って、厳しいんだろうね。あたしなんか、すぐ落ちこぼれちゃうんだろうね」
「世界に外も中もないのよ。この世は一つしかないでしょ」
(p162)
みたいな。
あとは藤田君との最初の会話の場面、売り物のガムを押し付けて藤田君にあげちゃう感じが幼女のようでほほえましかったです。
ただ、主人公や周りの人々の感情がたくさん描写されているにもかかわらず、どうしても好きになれません。
知寿がひねくれていて、先述の藤田君との最初の会話の場面以外は全然かわいくないし、藤田君も結局すぐに知寿に飽きちゃう感じだし。
吟子さんも、名台詞を吐く場面で無言ってことが多いし、ホースケさんもいまいち素性が分からないし。
これが私小説なのか、まったくの創作かは分かりませんが、いずれにしても人物描写があまりにも薄っぺらいといいましょうか。。。
例えば、冒頭で母親と駅で別れる場面があります。
「迷惑じゃないところに移動しようとして母の腕に触れたら、彼女ははっと身を固くした」(p6)
なんていう意味深な文言が出てきます。
これで知寿と母親の関係が微妙なんだということが分かり、さらに母親の方が知寿に対して遠慮というか距離を持ちたいのかな
 ということを感じます。
ということを感じます。が、読み進めるうちに、知寿の方がなんだか母親に距離をつくろうとしている感じが随所に見られ、むしろ母親は母親らしい心配をしてくれていることを感じました。
となると、この冒頭の文章は何なんでしょう


こういう場面が随所に出てきて、最後まで感情移入というか、理解がしづらかったです。
そして、結局この作品は前向きになっていくようでいて、実はすごく後ろ向きなんじゃないかなという風に感じてしまいました。
確かに、知寿は吟子の家を出るときに、今までためておいた思い出箱を壊します。
思い出箱というのは、知寿の癖で何かちょいとしたものを盗んで、自分のものにしてしまい、それをためておく箱の事です(まあその行為自体もちょっといただけないんだけど)。
これによって、過去との決別を示唆していると思うんですがしかし、春から正社員として働き始めた最後の章では、不倫をしていることになっています。
それ自体に文句はないんですが、この文章
「見込みがなくても、終わりが見えていても、なんだって始めるのは自由だ。もうすぐ春なのだから、少しくらい無責任になっても、許してあげよう」(p166)
には解せない。
春だから自分を許すという、軽い遊び心。全然1年前と変わっていないじゃん

この主人公は吟子と暮らしたことで何が変わったわけでもなく、相変わらず自分本位で無責任な人なのですね、ということになりゃしませんか。
吟子さんの家が駅のプラットホームが見える位置に立っており、それが小説の中では効果的に使われるのですが、最後の文章では、
「電車は少しもスピードをゆるめずに、誰かが待つ駅へとわたしを運んでいく。」(p169)
とあります。
これを一見すると、なんか初々しい新たな出会いなり人間的な成長を感じさせますが、しかし電車って決められたレールを、周期的に定時に回っているだけとも言えます。
結局、この知寿は大きく羽ばたくことがない、決められたコースをたどっていく、という比喩なのでしょうか?というくらいにまで妄想してしまいました

総合評価:★☆
読みやすさ:★★★★
キャラ:★★
読み返したい度:★

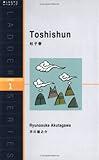




 」という感じで脳が揺れました。
」という感じで脳が揺れました。
