「もっと落ち着いて食べたら?」雅子があきれて言った。
「今にも目が覚めて、すべてが夢だったと言われるんじゃないかと落ち着かないんだ」
「本当に夢だったらどうします?」
「またゆうべのところからやり直すよ」
雅子はパンにバターを塗りながらたしなめるような顔で言った。「簡単にやり直せるみたいな言い方ね」
「簡単だろうが複雑だろうが、やり直せることだったらやり直すさ。つまずいても転んでもまたやり直せばいい。いまのぼくたちならそれができる」
「ぼくたち? Weなの?」
(p195より)
---------------------------------
今回は志水辰夫さんの行きずりの街を読みました。
彼はシミタツという名前で、熱狂的なファンがいらっしゃるみたいですが、私にとっては初体験です。
さっそくあらすじです。
かつて東京の敬愛女学園で高校教師として勤務し、現在は地方で塾講師をしている波多野和郎は、12年ぶりに東京へやってきます。
その目的は、東京で行方不明になっている教え子広瀬ゆかりを探すこと。
しかし、彼女が住んでいるというアパートは、およそ専門学生が住めるものではない代物で、部屋に入ると角田良幸という人物宛の手紙がありました。
さらに部屋が荒らされた形跡があったことから、どうやらゆかりはなんらかの事件に巻き込まれ、その事件には角田が関わっているだろうと踏んだ和郎は角田の行方を追うとともに、ゆかりがバイトをしていたとされるサパークラブで手がかりを探すことにしました。
しかし、そのサパークラブで出会ったのは、憎き大森幸生と池辺忠賢。
彼らこそ、波多野を学園から追いやった者たちなのです。
大森は、和郎にある女性の存在を告げた後、彼のもとを去って行きます。
和郎は学園で、ある一人の女性と恋に落ちました。
その女性は学園の生徒であり、彼女が大学に入ると結婚をしました。
しかし、それが性的スキャンダルとして突如俎上にのぼり、理事長の引責自殺と和郎の失職、結婚破綻を引き起こしてしまったのでした。
大森が和郎に告げた、その女性の名は別れた妻の雅子。
彼女との再会を果たし、学園に行くなどして、避けていた自身の過去に触れながら、ゆかりと角田探しを進めていく和郎。
そうするうちに、どうやら過去と両者の意外な接点が浮かび上がってくるのでした。
では以下はネタバレ含むので、いやな方は見ないで下さい。
- 行きずりの街 (新潮文庫)/志水 辰夫
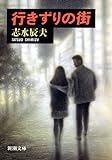
- ¥580
- Amazon.co.jp
~1回目 2011.6.9~
では、あらすじの続きを。
和郎の憎き相手である池辺は、現在は敬愛学園の理事として、さらに裏では東亜開発興産の経営者として学園の拡大を図っていたものの、保守派の理事長を排除するために和郎の結婚をスキャンダルとして責任を押し付け、学園経営を思いのままに動かそうと画策していたことが分かりました。
つまり、和郎のスキャンダル自体が問題ではなかったのです。
事実理事長は自殺して池辺が台頭するかに思えました。
しかし、そう上手くはいかず、理事長の後任として妻の夏江が学園経営に乗り出すことにしました。
その夏江の腹心として辣腕を振るった経理担当が、ゆかりとともに失踪したと思われる角田。
夏江によって池辺の計画は一時頓挫するものの、夏江は事故により急死してしまいます。
夏江という後ろ盾が無くなった角田は学園から孤立したため、裏金や帳簿操作などの学園の弱みにつけこみ、おどしにかかります。
しかし同時に学園の理事となっていた池辺らに対してもある材料を手にしておどしたため、池辺一派に彼女だった年のだいぶ離れたゆかりとともに捕まったという事実が明らかになりました。
角田がにぎった池辺をおどす、その「ある材料」とは、夏江を殺したことが分かる写真。
つまり、夏江は池辺一派によって事故に見せかけ殺されたのです。
いよいよ事件が池辺や部下の大森が中心にいることが分かった和郎ですが、ゆかりの行方は依然として分からず、困った和郎は最初に訪れたゆかりのマンションに戻ってみました。
すると、玄関からでてきた男に不審を感じ、つけてみるとその先にゆかりがいることを見つけたのです。
ゆかりは、自分を唯一認めてくれた角田との結婚を真剣に考えていました。
しかし、角田があるマンションの鍵と車を託して失踪したとのことでした。
和郎が角田の車を調べてみると、裏金などの存在を示した書類と、写真を発見。
ゆかりのいたアパートに戻り、ゆかりを連れ出して地元に帰ろうとした和郎ですが、アパートに戻るとゆかりの姿はそこにはなく、一人の男が彼を待っていました。
男の名前は中込。
中込に言われるまま、和郎はゆかりと角田が捕まっていると思われる場所へと行くのでした。
さて、中込が連れて行った場所は、学園の旧短大校舎の建物内。
すべてをしってしまったせいで、書類や写真を奪われた挙句、和郎は殺されそうになりますが機転を利かせて脱出に成功。
角田がゆかりに用意していたマンションには、車に入っていたような書類と写真が用意されていました。
恐らく角田は池辺一派に殺された、そう考えた和郎は準備を整えて再び旧短大校舎に向かいます。
ゆかりを連れ戻すために。
自分の過去を清算するために。
旧短大校舎で和郎を待っていた中込と交渉し、和郎はまず大森のもとへ向かい、池辺一派にいて犯罪に手を染めることに拒否感をもつ中込とともに大森を返り討ち、さらに和郎は単身で悪の権化、池辺の住む家に乗り込みます。
またしても和郎は殺されそうになりますが、実は和郎を追いかけてきていた中込に助けられ、一命を取り留めます。
しかし、中込は池辺の銃弾に倒れ、池辺は自殺したことでこの事件は収束に向かいます。
そして、和郎は雅子のところに帰り、ゆかりとともに田舎に帰ることにするのでした。
さて、感想です。
若干ストーリーを時系列を無視した形であらすじを書いてしまいましたが、このあらすじを書くのには苦労しました。
ミステリーにはあまり慣れていないからかもしれません。。。
まず、面白かったところは、文章。
普通なら1~2行で書けるようなところを半ページくらいの分量で書かれていることもザラで、それが個人的には興味深く読むことができました。
それに加え、その文体もなかなかなもので、例えば久しぶりに雅子と会った和郎が、雅子の家に招かれた場面。
わたしたちは食卓を挟んで向かい合わせに座った。顔を突き出せば唇が触れ合うほどの距離。しかしいまそれは背中合わせになり、地球を挟んで向かい合っているのと同じことだった。
(p185)
とか、和郎が中込とともに大森のもとへと向かう車での描写。
大小の車がすこしでも相手の前へ出ようと突っ走って行くありさまは、いかにも暗示的だった。このような活力が上昇志向となり、国なり人なりを押し上げていることは認めなければなるまい。好むと好まざるとにかかわらず、だれもが参加させられているレース。マイペースを保持するほうがむしろ多大なエネルギーを必要とする。
(p310)
などが印象に残っています。
しかし、この作品に関しては、それ以外は全然心には入ってきませんでした

状況などを説明する文章に関して言えば、前述したように面白かったのですが、それが会話になると、かなり説明染みていて、まどろっこしくて現実感が沸かない。
特に和郎と雅子の会話は、空虚感すら漂うような印象を受けました。
さらに決定的な馴染めなさには、都合が良過ぎるということがあります。
もちろん、和郎のスキャンダルと、ゆかりの失踪を絡めること自体は別にお話としてはいいと思うのですが、様々な場面でそれらを繋がせるということはどうなんでしょう。
別に前理事長の愛人が、実は雅子の母親だったかどうかなんて、ストーリー本編にはかかわりがさほどないように思います。
それに加え、和郎と雅子の再開後の関係にも都合の良さが感じられます。
あんなに辛い別れをし、その後一切連絡を取っていなかったはずなのに、再会した後、1日2日で体の関係を結び、さらに翌朝冒頭で引用したような会話が生まれるでしょうか?
都合が良すぎるばかりにストーリーが逆に薄っぺらく感じてしまいました。
ということで星は低めで。
総合評価:★
読みやすさ:★☆
キャラクター:★
読み返したい度:★
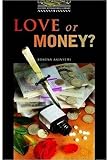






 しかし、子どもを救うのも、そして未来の人材をを育てていくのも大人なんですよね
しかし、子どもを救うのも、そして未来の人材をを育てていくのも大人なんですよね