もしも警察官などならなければ、もしかしたら一生降り立つこともなかったかも知れない町。単に住んでいるだけなら、どうということもないかも知れないが、こんな仕事をしているお陰で、嫌な面ばかりを見ることになった町。日中のこの町には、老人と女ばかりが溢れている。考えてみれば当然のことだ。男たちは皆、働きに出ている。ネクタイを締めて、満員電車に揺られて、都心の、ビルの中に吸い込まれていく。
男たちに取り残された町を、自分たちはこうして歩き回っている。駐車禁止の場所に車を停め、客に頭を下げながら、それでも生き生きと動き回っているに違いないサラリーマンに比べて、何だかひどくつまらない仕事だからといって、どうして自分がしなければならないのだという気持ちばかりが膨らんだ。
(p379より)
---------------------------------
今回は乃南アサさんの長編小説、ボクの町を読みました。
表紙に警察官が敬礼をしていたので、警察小説であることは分かったんですが、犯人を推理して捕まえる・・・というタイプのものではなく(刑事ではなく警察官ですからね)、踊る大捜査線のような日常の悲喜こもごもを描くというものでした。
さて、まずはあらすじです。
警視庁城西署の霞台駅前交番に卒業配置として初めて交番勤務の実習を行うことになった高木聖大。勤務先が違うものの、華奢な親切男、三浦と同期の桜としてお互いに警察官の職をまっとうすることにします。
しかし、夢に見た警察とは少し異なり・・・
初日からおばあさんの話し相手や、道案内などの雑務に追われます。
直接の指導係宮永に教えてもらう職務質問もろくに対応できず、警察官の現実を目の当たりにします。
そんなこんなでもどかしい日々が続いている最中、三浦が職務質問で窃盗の常習犯を検挙するという手柄を挙げるに至り、高木はなんともやるせない気持ちになります。
なんとか手柄を挙げたい高木ですが、その後も雑務に終われ、なかなか成功することができません。
業を煮やした高木は、宮永不在のもと単独で職務質問にでかけます。
そこで怪しい男に職務質問をかけると、なんと逆にボコボコにされる始末。
交番に戻っても、先輩たちからは無線(SW)で応援を求めなかったことなどを叱られ、誰も心配してくれないことへの寂しさといらだちがつのります。
その後も初めての変死体処理をしたり(させられたり)、少しの手柄(無線受令機とラジオと入れ替えたために、轢き逃げされた男を音楽で救うなど)を挙げたりするものの、警察官としての仕事が順調に行っているわけではありませんでした。
そこに来て、学生時代の旧友勝俣からの誘いを受け、かつての彼女、南條真奈と再会。
彼女にもう一度振り向いてもらうために警察官になったようなものの、彼女は新しい彼氏(しかも旧友)ができてしまい、もはや警察官を続ける動機さえ失ってしまうのでした。
自分は警察官には向いていないのではないか?
そう思い始めた高木ですが、大きな転機を迎えます。
それは、町で連続放火事件が発生したことに端を発します。
では以下はネタバレ含むので、いやな方は見ないで下さい。
- ボクの町 (新潮文庫)/乃南 アサ
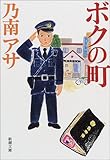
- ¥740
- Amazon.co.jp
~1回目 2012.1.30~
では、あらすじの続きを。
高木の働く町で連続放火事件が発生し、にわかに慌しくなる霞台駅前交番。
市民からの圧力も日増しに高まるのですが、犯人を捕まえられない高木らはなんとか放火犯を捕まえようと町を駆け回ります。
そんな中、不審火犯らしき者を三浦が発見、追い詰めます。
しかし、捕まえる寸前に車が急にやってきて、三浦を轢き、不審火犯も逃亡。
「不審火犯は30代くらいの女性だ」という言葉を残し、三浦は高木の見ている前で搬送されます。
同期が死ぬかもしれない状況の中、高木は不審火犯をなんとか捕まえようと気持ちを高めます。
交通課のミニパト勤務、小桜まひるとともに犯人を追い詰めることに。
途中、職質をかけて下着ドロを逮捕し、職質による検挙という初手柄がありつつも、じわじわと犯人を追い詰めていきます。
機転を利かせ、墓で待ち伏せた高木と小桜。
なんとその賭けが成功し、とうとう放火犯を逮捕することができたのでした。
本当の大きな手柄を得ることで警察官としての誇りを感じ、また小桜への淡い想いを抱きながら、高木は警察官を続けることにしたのでした。
さて、感想です。
いや~、あらすじだと薄っぺらいですね

内容は面白かったです。
特に主人公である高木のなよなよした感じが妙にリアルで、警察官というものを題材にとっただけで、これって若者が社会に出て職業人になっていく一般的な様が描かれているのではないかと思えます。
職業を選ぶ動機なんて警察官だろうが先生だろうがサラリーマンであろうが、多分こうだろうなぁと思わせるところに、非常に高木君に親近感が沸くと共に、自分の社会人ほやほやの頃はこうだったんだろうなぁと懐かしくなりました

しかし、この作品はあくまでも警察小説なので、その部分で面白いなぁと感じたこともいくつもありました。
まずは、高木が警察官としての職を覚えてきたことをうかがわせるところ。
放火犯を小桜まひると共に追う場面。
〔城西署管内。不審火の訴え。場所、霞台三丁目〕
全身の神経がいっぺんい目覚めた。
「まただ、また燃えてる!」
イヤホーンに神経を集中しながら言うと、小桜巡査の「どこっ」という声が返ってきた。聖大は、それを手で制し、通信指令本部からの声を聞いた。
「三丁目だって――丘の上だ。二十二の三だから――ええと、何とかという歯医者の傍ですかね」
「了解っ!」 (p456より)
これって簡単に歯医者の傍と言っていますが、辛いと思いながらも町を歩いてきた高木が足を使って覚えた知識ですよね。ここらへん、文章ではすらーっと流れていますが、こうした発言から、
「成長したなあ、高木君」と思えるのです。
また、放火犯を警察全体が徐々に追い詰めていく場面を無線によって表現しているところ、とても興奮しました。
聖大は、息を詰めて、それらのやりとりを聞いていた。さっきも感じたことではある。だが今、この闇の中にいて、城西署に隣接する他の警察署までもが、たった一人の放火犯人を捕まえるために、一斉に動き始めたことが、実感となって迫ってきた。
〔戸越一から警視庁〕
〔戸越一、どうぞ〕
〔第二京浜、戸越三丁目交差点から配備につく〕
〔警視庁了解〕
〔雪谷大塚三から警視庁!〕
〔雪谷大塚三、どうぞ〕
〔環八通り、奥沢三叉路から検索中〕
〔警視庁了解〕
〔自由が丘一から警視庁〕
〔自由が丘一、どうぞ〕
〔目黒通り八雲三丁目から検索中〕
〔警視二〇六は、中原街道平塚交差点から!〕
〔警視二〇四は、環七通り大森東交差点から!〕
〔馬込四は、山手通り大崎郵便局前から!〕
〔警視庁、了解!〕
四キロ圏配備内の各警察署のパトカーが、犯人の退路をふさごうとしているのだ。・・・(中略)・・・今度こそ、今度こそ、と誰もが同じ思いでいる。
聖大は、胸が熱くなるのを覚えた。仲間がいる。自分で思っているよりも、もっとずっと多くの仲間が、今この時、ひとつの目的に向かって動いているのだ。 (p458-459より)
そうでなくとも、警察24時的な番組が好きな私にとってみれば、この部分は高木と同じように胸を熱くしました。
ただ、このように、高木、宮永、おいしいところをもっていく大関主任などの警察内部の(それも霞台交番の)人物描写はかなり細かく、とても感情移入できるのですが、それ以外の人物があまりにも薄いなぁという印象もぬぐえません。
例えば、迷子の捜索願のくだりとして登場した母子、高木が対応した女性の城野友香里など、出てくる割にはなんとなくなバッサリフェードアウトをかましていて、
「おいおい、どうなったんだ」という。。。
特に迷子の件では、高木が「また交番に来いよ」と小説的になにか伏線を張っている様子なのに、その後一切触れられず

城野も単なる嫉妬女として終わっています。
もっと広げて欲しかったなぁ~。
でも逆に広げなくてもいいところもあって、それは男色川辺主任。
なんでここで男色を出すのかが全く分からないです

全員が全員ではないことは分かっているし、作品によっても違うのかもしれないけれど、こういう女性作家による男を描く作品って、なんだか高確率でホモセクシャルをにおわせる人物や記述がありますよね。
すごく僻々とします。
それが作品の核となるもの(例えば高村薫の『李欧』なんかは友情を越えたものが核となっていますよね)ならばいいのですが、そうではないあってもなくてもよいサイドストーリーに持ってこられると一気に引いてしまいます。個人的には。
ただ、サイドストーリーの物足りなさを除けば、等身大の警察官を描いたものとして、とても面白いと思いました。
総合評価:★★★☆
読みやすさ:★★★★
キャラクター:★★★
読み返したい度:★★★
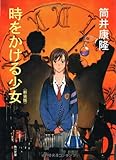
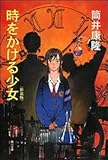
 ということが伝わるのだと思います。
ということが伝わるのだと思います。