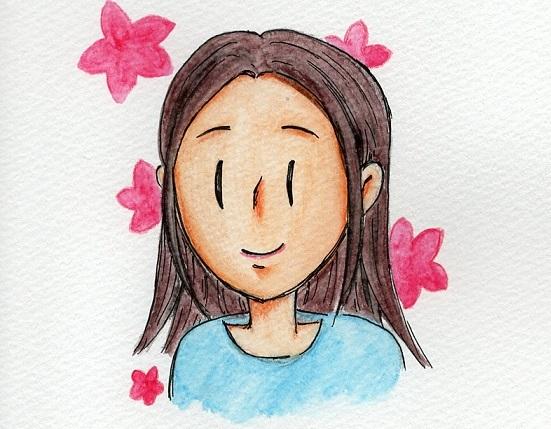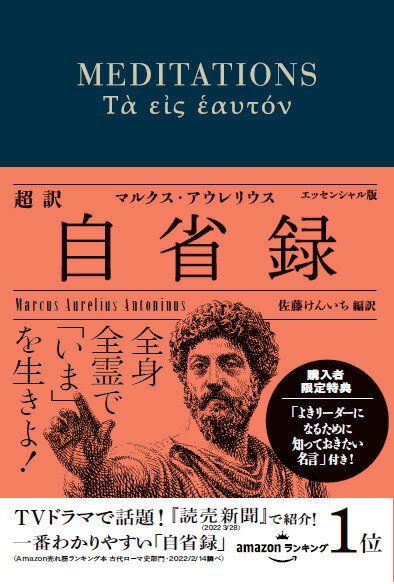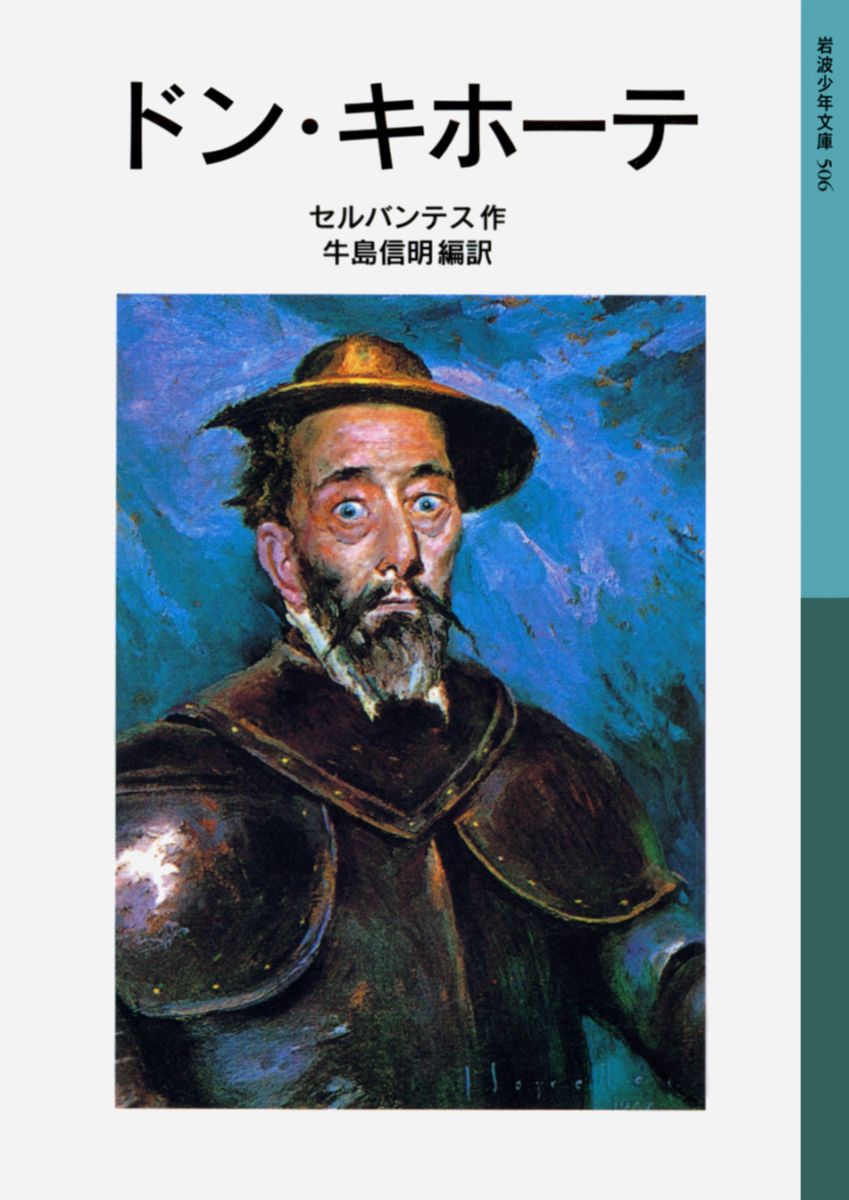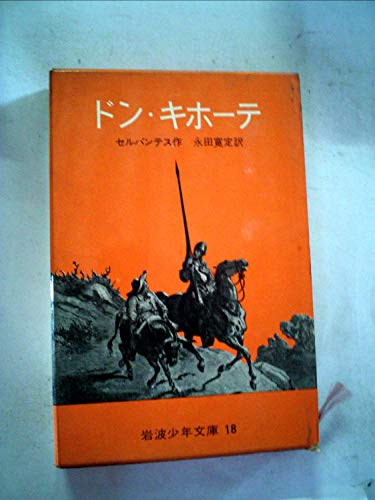二月の閑話休題です。
2026年2月のテーマ
「まとめ版・名作古典」
でおすすめしてまいりました。
以前にも書いたことがありますが、私は海外の名作古典作品はできるだけ完訳版で読みたい派です。
名作古典…特に物語などでは、まず触れてもらう入り口としてストーリーが簡略化された形の本がたくさんあって、特に子供向けのものは挿し絵もかわいらしかったりもしてそれはそれで楽しいものです。その昔子供だった頃の私もこれらの本を読みふけったものですが、すでに基礎知識を得てしまってからでは、簡略化されていると物足りないとかもっと詳しく知りたいという欲が出てきたため最近では完訳版を探すことが多いです。
しかしながら、なじみのない分野の本とか、興味が深まるかわからないけどまずはちょっと内容に触れてみたいな…なんて時には、先に挙げたように入り口として概要を抽出してまとめてある本はやっぱりありがたいです。
今は、子供向けの児童書だけではなく、本を読む時間がなかなかとれない受験生のために文豪の書いた作品を漫画でサクッと読めちゃうシリーズなんかも出ているようです。
こういった漫画版名作古典に関しては、私はあまり好きではありません。
受験勉強として内容を押さえておく目的には叶うのでしょうが、楽しみとして本を読む私にとっては、雑にエッセンスを抽出しているように感じられる上に初読の楽しみがなくなってしまうのではデメリットしかありません。
ただ、漫画化に携わっている漫画家さん達を悪く言いたいわけではありません。描き手の方々は作品を読み込まなければならないでしょうし、(私は古典文学はストーリーだけが大事なわけではないと思うのですが)まずストーリーを限られたページ数の中に漫画という形でまとめるのだけでも大変だし無理があると思っているので、"雑にエッセンスを抽出"するしかないんじゃないかと思ってしまうのです。
しかし、漫画版名作古典を読むと想定されるユーザー層から私は外れていると思われるので、外からいちゃもんつけるのは良くないですね。読みたくなけりゃ読まなきゃいいだけの話。…反省。
ええと、話を元に戻しますと、「完訳版で読みたい派を自認する私ですが、まとめ版や簡略版のお世話になることも割とあります」ということと、「色んな形、目的のまとめ版や簡略版があるので、その都度自分に合う形のものを選べばいいと気づいた」と言いたかったのです。
では、そろそろタイトルの「本との出会いは突然に」の話にまいりましょう。
小田和正さんの名曲『ラブストーリーは突然に』みたいなタイトルつけちゃいましたが、この記事を書いているまさに今日、図書館で思いもかけない本に出合ったのでそのお話をしたいと思います。
私はブログの中で、"紹介する本を自分が手に取ったきっかけ"の出来事を時々書いています。
大抵は、他の本を読んでいた時に別の本の引用があったとか、作品名が出ていたとか、そんなところから興味を持って頭の片隅に作品名がインプットされて、後日何らかの機会に手に取ってみるというパターンです。
映画を見ていて気になった本とかも多いです。
で、今日図書館で出会った本は「ティンブクトゥ」というアメリカの小説なんですが、私は「ティンブクトゥ」という言葉が本のタイトルだということすら知らなかったので、見つけた時ちょっと衝撃を受けました。
「ティンブクトゥ」という言葉を知ったのは、私の大好きなコージーミステリー、ローラ・チャイルズさんの「お茶と探偵」シリーズでのことでした。
シリーズのどの作品に出ていたかはもう忘れてしまいましたが、"ティンブクトゥに行く"というような記述があったのです。
聞いたことない言葉だったので、「地名みたいだけどどこだろう?実在の場所というよりは物語に出てくる架空の場所(アヴァロン[アーサー王物語]とかファンタージエン国[はてしない物語]みたいな感じ?)のような気がするけど…」と思って頭の隅っこにその名をしまっていました。
何らかの物語の中に出てくる架空の場所の名前なら、その物語を偶然引き当てないと私の疑問は解消されませんが、本で引用されているくらいだから有名な作品に出てくる言葉なんだろう、それならそのうちどこかで出会えるかもしれないな…とそんな感覚でした。そんなことがあったのがもう10年以上も前のこと。
そしたら図書館の書棚にその言葉がまんまタイトルになっている本を見つけたのです。
突然の出会いに忘れていた言葉が脳内によみがえりました。(『ラブストーリーは突然に』が脳内で再生されているとご想像ください。)
10数年前の私はその言葉を調べてみることを思いつきませんでした。
まあ、その言葉についてどうしても知りたいという気持ちでもなかったので、調べなかったのでしょう。
しかし、運命的な出会いをしてしまったからにはこの本を読まねばならないという謎の使命感に駆られて、借りてきてしまいました。そのうちブログに書くかもしれません。
海のものとも山のものとも知れない、前知識ゼロの状態で「ティンブクトゥ」という本を読んでみることにした…こんなこともあるんだね。我ながらびっくりしたというお話でした。
さて、来月のテーマとまいりましょう。
2026年3月のテーマ
「人物伝」
でおすすめしたいと思います。
自伝、伝記、回顧録…実在する人物について書かれた本について書きたいと思います。
なんか、私の中でうまくジャンル分けできない本ってのが結構ありまして…。
特定の人物について書いてある本もその一つです。著者と書かれている人物との関係性も様々だし、アプローチの仕方も色々。(その人の生涯を描いたり、その人を知る大勢の人に聞き取りをして人物像を構築したり、ある出来事に関して中心人物だった人にフォーカスを当ててあったり。"伝記まんが"とか"偉人伝"みたいに書いてある児童書はわかりやすいんですけどね。)
どういうテーマにすればこれらの本を記事にできるのか悩んで出てきたのが"人物伝"。…工夫も何もあったもんじゃないテーマになってしまいましたが、よろしければ覗いていただけると幸いです。(*^▽^*)