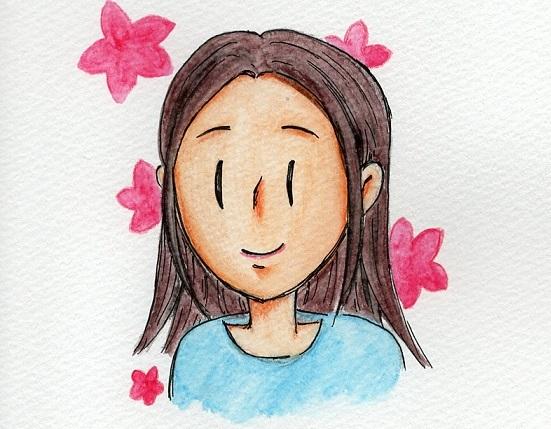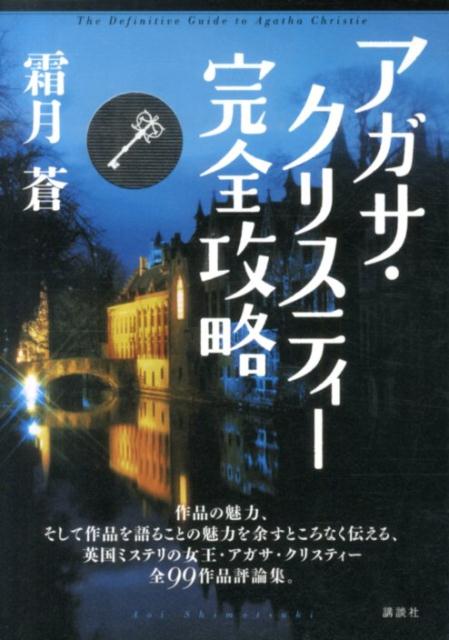2025年11月のテーマ
「私が何度も読んでいる漫画」
第一回は、
「メダリスト」
つるまいかだ 作、
講談社 アフタヌーンKC、 2020年~発表
です。
この記事を書いている時点で13巻まで出ていて、まだ完結していません。
今年の1月からの1クールでアニメ放送していまして、それを観て知りました。
来年1月からアニメ第2期の放送があり、今から楽しみにしています。
あらすじは、アイスダンスで全日本選手権出場を果たした明浦路司(あけうらじつかさ)はアルバイトをしながらアイスショーへの出演を目指して就職活動中に、アイスダンスの元パートナー・高峰瞳(たかみねひとみ)が主催するスケートクラブのコーチにならないかと誘われます。自分自身がスケーターとして仕事をすることを諦めていない彼は渋るのですが、小学5年生の結束いのりと出会い、彼女をコーチする決心をします。
話は前後しますが、司は中学生でフィギュアスケートに出会い、高校生から一人で練習をしてちゃんとしたコーチについたのは20歳からという異色の経歴の持ち主で、もっと早くからきちんとしたコーチに教えてもらえていれば…という思いを根底に抱えています。
一方のいのりはずっとフィギュアスケートをやりたかったのですが、フィギュアをやっていた姉が怪我で辞めたことや、いのりが物事を覚えるのに時間のかかるタイプであることを心配する母親が禁止するため、隠れてリンクに通っていました。
スケートをやりたければきちんと親にお願いしてやらせてもらわないといけないと司に諭されたいのりは、勇気を出して母親に自分の気持ちを伝え、それでも諦めさせようとする親に司がコーチすることを申し出て認めてもらいます。
大好きなフィギュアスケートを始めることになったいのりちゃんと、彼女がなりたいと望むスケーターに近づくサポートをする司先生との師弟コンビの成長を描く物語です。
そもそもの話、私はフィギュアスケートが好き(観るの専門です)で、子供が生まれる前はテレビで試合を放送していればよく観ていました。(最近はちょっと遠ざかってました。)
トリノオリンピックの少し前辺りから観るようになって、浅田真央選手がシニア初出場のシーズンにグランプリファイナルで優勝した試合もリアルタイムのテレビで観てました。
この作品がフィギュアスケートの物語だと知って、アニメで演技をどのように描いているのかと気になって観始めたのが最初のとっかかりでした。さくっとアニメにはまって、続きを知りたいと原作の漫画を読んでみたら、これが本当によかった。今でも読むたびに涙が出てしまうくらいです。
しかも、よかったと感じた点に、フィギュアスケートのお話だからというのはあまり関係がなかったというのも付け加えておきたいです。
では何がいいかというと、アニメでしか観ていなかった時にも感じていたことではありますが、この作品の登場人物の言葉はぐっさぐっさ胸に刺さるのです。
コーチである司がいのりに向けた言葉や、いのりが司に向けて言った言葉だけではなくて、時には他の登場人物たちの言葉も、形にしづらい感情や気づきにくい事柄なんかを上手に言語化して伝えてくれるのです。
いのりちゃんは物語の初めでは小学生だけど、成長して中学生になっていきます。
素直にコーチの教えを何でも聞いていた頃には苦労していなかった意思の疎通のズレみたいなものも生まれてきたりするのですが、なんで伝わらないのか、どうすれば伝わるのか、大人として司先生は考えますし、他所のクラブのコーチたちとも悩みを分かち合ったりします。
私が過去に読んだことのあるスポ根漫画では、指導者側の葛藤とか悩みってあんまり描かれていなくて、選手が悩み苦しんで殻を打ち破り、新しい技術を習得したりする展開がお約束なイメージがあったのですが、「メダリスト」は違ったんです。
(以下、文章中で作品よりセリフを引用させていただきます。)
例えば、跳べないジャンプの特訓をしているときに、いのりちゃんが「跳びたい、跳ばなくちゃ」と強い思いで、必死の形相で取り組んでいるとき、司先生は「成功を願いすぎちゃだめだ。」と言います。
「これは思いの強さで跳べる魔法じゃないんだ。必要なのはガムシャラになることじゃない。」
そして、
「成功するためじゃなくて、跳んでいるときにどんな感覚なのか先生に教えるためにたくさんの言葉を探して。どれだけ細かく世界を感じられるかがコントロールの鍵だよ。」(長いので若干セリフを編集してます)
と教えます。
これって、スケートに限ったことではなくて、スポーツに限ったことでもなくて、人生で"どうしても今これをできるようになりたい、ならないと"って場面に出会ったなら、だれにでも当てはまる(言ってほしい)言葉のような気がするのです。
ガムシャラになれば願いが必ず叶うわけではないということを、多くの人が知っています。
だけど、どうしても願いをかなえたいときにどうすればいいのかわからない。必死になりすぎていると視野が狭くなりがちです。どうしても超えたい壁にぶち当たったときに、ちょっと冷静に攻略法を探すことも大事だなって思いました。
漫画だから、主人公が根性で壁をクリアしちゃう展開だってできちゃうのに、ちょっとブレーキをかけていのりちゃんにできるヒントをあげるところが、"都合の良いストーリー展開"にならない絶妙なバランスを感じます。
(遅くからスタートした主人公が才能を開花させてものすごいスピードで成長…って展開が、漫画ではよくありますし、それ自体が"都合の良いストーリー展開"ではありますけれども…。)
他にも、いのりちゃんが、うまくいっていないと感じてもやもやしてしまっている気持ちを吐き出した場面で、
「私もできない私の悪口を心の中でいっぱい言う…」
「自分で自分の悪口を言っている時って別の人間になれた気がするから…」
「でも最近はできない私ばかりだから、自分の悪口を言いすぎちゃって、ちょっと苦しい…」
「悪口を言っても私は私なのに…」
っていうんですが…これって中学生のセリフですか!?
ワタクシもう中年を通り越してますけど、こんなにちゃんと自分を客観視できていないよ…。
いのりちゃんから学ぶこと多いです。
書いたのはほんの一例で、私の心に刺さったセリフってのはもっとすごくたくさんあるんですが、もちろんセリフだけじゃなくてスケートの試合も日々の練習風景とかでも胸が熱くなる展開が満載で、読んでて何度も泣いてしまっています。
来年1月スタートのアニメの2期も楽しみにしています。
なんたって、アニメではスケートのプログラムが丸っと観れますもの。漫画では決してできない、音楽に乗せて滑る演技が観られるのはアニメならではですからね。
というわけで、おばちゃんの心を熱くしてくれている漫画「メダリスト」、おすすめいたします。(*^▽^*)