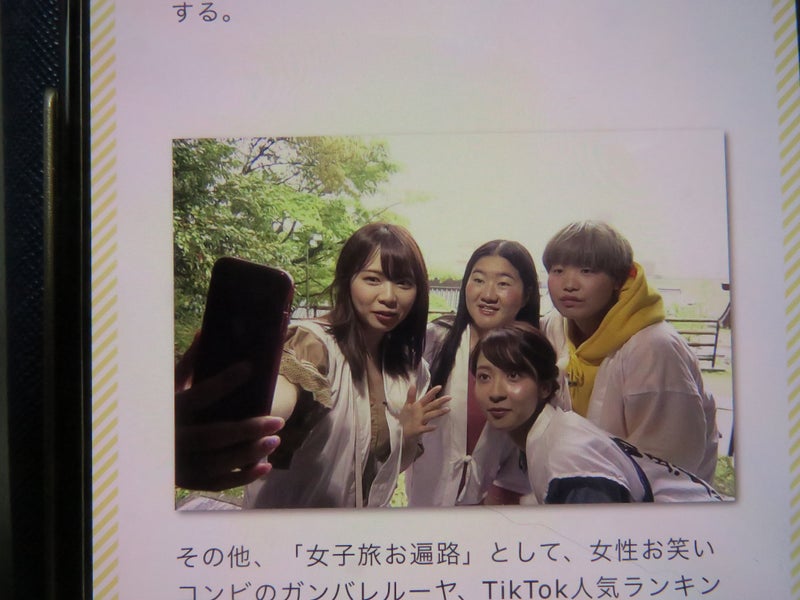- 前ページ
- 次ページ
今回のブログで最後ですが、ランキングバナー、ポチしといてネ!
指に余力がありましたら・・・
もう二つも宜しく
※お知らせ。
最近仕事の関係上お遍路で歩いていないので、今回のブログで勝手ながらお遍路ブログはお休みさせて頂きます。
次の再開は何年後になるか分かりませんが、2巡目の室戸市以後のお遍路の再開のめどが立てばまた掲載して行きたいと考えていますが??
本当に最後までの長いお付き合い有難う御座いました。
広い新道脇の川沿いを歩いて行きますが、ご覧の通り陽は真上から射しているので、殆ど影がありません。
 立体写真で観ると良く分かるかと思いますが、ソフトクリームのようなこんな花の紫陽花があるのですね。
立体写真で観ると良く分かるかと思いますが、ソフトクリームのようなこんな花の紫陽花があるのですね。
また新道をひたすら歩きます。
遍路道上にあると、野宿のお遍路さんが利用しやすいですね。
 あづり越え(あずり越え)自体知らなかったので、一巡目はそのまま直進してしまいましたが、今回はあづり越えを歩いてみましょう。
あづり越え(あずり越え)自体知らなかったので、一巡目はそのまま直進してしまいましたが、今回はあづり越えを歩いてみましょう。
※それではここまで歩いて来た様子を動画でご覧下さい。
※この先のお遍路の続きは遡って2017年12月6日のブログに続きます。
つまり二巡目お遍路のブログは今回で終わりますが、この続きは2017年12月6日のブログから続いています。
良かったら過去のブログに遡ってこの続きもご覧下さい。
室戸市までは歩けます。
リブログはその2017年12月6日のブログです。
ランキングバナー、ポチしてネ!
指に余力がありましたら・・・
もう二つも宜しく
※お知らせ。
地蔵越え遍路道を歩いてあづり越えの分かれ道迄掲載すると、2017年12月6日の『あづり越 その1』のブログに繋がります。
最近仕事の関係上、お遍路で歩いていないので今回の地蔵越え遍路道のブログであづり越えの分かれ道迄繋がったトコロで勝手ながらお遍路ブログはお休みさせて頂きます。
次の再開は何年後になるか分かりませんが、2巡目の室戸市以後のお遍路の再開のめどが立てばまた掲載して行きたいと思います。
掲載出来るブログがあと2回となりましたが、最後までのお付き合い宜しくお願い致します。
下界に下りてここからは平らな道を歩きます。
こんな辺ぴな所なのに沢山のお客さんですね。
狭い旧道は民家の前をゆっくりカーブ・・・
ランキングバナー、ポチしてネ!
指に余力がありましたら・・・
もう二つも宜しく
※お知らせ。
地蔵越え遍路道を歩いてあづり越えの分かれ道迄掲載すると、2017年12月6日の『あづり越 その1』のブログに繋がります。
最近仕事の関係上、お遍路で歩いていないので今回の地蔵越え遍路道のブログであづり越えの分かれ道迄繋がったトコロで勝手ながらお遍路ブログはお休みさせて頂きます。
次の再開は何年後になるか分かりませんが、2巡目の室戸市以後のお遍路の再開のめどが立てばまた掲載して行きたいと思います。
掲載出来るブログがあと3回となりましたが、最後までのお付き合い宜しくお願い致します。
自動車道に出ましたが、ガードレールの裏に・・・
 ロープが張られていない時には、沢山のお遍路さんがころんでいたのかも知れませんね。
ロープが張られていない時には、沢山のお遍路さんがころんでいたのかも知れませんね。
 上り坂はしんどいだけですが、下り坂は危険を伴いますから・・・
上り坂はしんどいだけですが、下り坂は危険を伴いますから・・・
ランキングバナー、ポチしてネ!
指に余力がありましたら・・・
もう二つも宜しく
※お知らせ。
地蔵越え遍路道を歩いてあづり越えの分かれ道迄掲載すると、2017年12月6日の『あづり越 その1』のブログに繋がります。
最近仕事の関係上、お遍路で歩いていないので今回の地蔵越え遍路道のブログであづり越えの分かれ道迄繋がったトコロで勝手ながらお遍路ブログはお休みさせて頂きます。
次の再開は何年後になるか分かりませんが、2巡目の室戸市以後のお遍路の再開のめどが立てばまた掲載して行きたいと思います。
掲載出来るブログがあと4回となりましたが、最後までのお付き合い宜しくお願い致します。
ここから暫くは舗装されている自動車道を歩くのでしょうか?
 でも何の変化もない自動車道を歩くよりは厳しい道の方が楽しいです。
でも何の変化もない自動車道を歩くよりは厳しい道の方が楽しいです。
人生も同じでしょうか?
ふとそんな事が頭の中に浮かびました。
自分の脚で苦労を乗り越え強くなって行くのですね。
そろそろ頂上なのかな?
 木の根がむき出しになっている所からの前方が見えませんが・・・
木の根がむき出しになっている所からの前方が見えませんが・・・
少し先が・・・
自動車道が出来る以前からのものですね。
・・・という事は、下界から人の手で運ばれて来て、設置されたもののようです。
※何度も再生していて気が付きましたが、再生時間の1:26時点に超高速で飛んでいる蝶(昼行性の蛾の一種でキンモンガと思われます)が2カットのみ映っています。
勿論そんな早く飛ぶ蝶や蛾は存在しませんが…
音速で飛んでいるのか?2カットのみ映っています。
…何だコレ!
ランキングバナー、ポチしてネ!
指に余力がありましたら・・・
もう二つも宜しく
※お知らせ。
地蔵越え遍路道を歩いてあづり越えの分かれ道迄掲載すると、2017年12月6日の『あづり越 その1』のブログに繋がります。
最近仕事の関係上、お遍路で歩いていないので今回の地蔵越え遍路道のブログであづり越えの分かれ道迄繋がったトコロで勝手ながらお遍路ブログはお休みさせて頂きます。
次の再開は何年後になるか分かりませんが、2巡目の室戸市以後のお遍路の再開のめどが立てばまた掲載して行きたいと思います。
掲載出来る残りのブログが後少しとなりましたが、最後までのお付き合い宜しくお願い致します。
※2枚並んでいる画像は肉眼で観れる3D画像です。
パソコンは画面と目の間を40~50cm、スマホなら25cm位で頭を傾けずに水平にした状態で写真と目の中間位の位置に人差し指を立てて指先をじっと見つめて下さい。
視線が寄り眼の状態になって右目で左の写真を左目で右の写真を向見ている状態です。

人差し指の向こう側にぼんやりと3枚の写真が見えて来るので、寄り眼の視線を保ちながら、真ん中の写真に焦点を合わせると真ん中の写真が立体に見えて来ると思います。
道しるべのお地蔵様なのでしょうね。
地元の方でしょうか?傘をさしてありますね。
 上から立体写真で観ると、手摺の役目をしている事が分かりますね。
上から立体写真で観ると、手摺の役目をしている事が分かりますね。
 木を倒した休憩ベンチや、竹製の休憩ベンチも設置されています。
木を倒した休憩ベンチや、竹製の休憩ベンチも設置されています。
 地蔵超え遍路道をなめてはイケません、意外と厳しい遍路道です。
地蔵超え遍路道をなめてはイケません、意外と厳しい遍路道です。
沢沿いの道は、ここまでで・・・
その先はロープ伝いの急斜面です。
 一巡目の時にもあった、クレヨンしんちゃんの矢印はまだ残っていました。
一巡目の時にもあった、クレヨンしんちゃんの矢印はまだ残っていました。
遍路道が自動車道が通って、途中で切られているのですね。
ランキングバナー、ポチしてネ!
指に余力がありましたら・・・
もう二つも宜しく
※お知らせ。
地蔵越え遍路道を歩いてあづり越えの分かれ道迄掲載すると、2017年12月6日の『あづり越 その1』のブログに繋がります。
最近仕事の関係上、お遍路で歩いていないので今回の地蔵越え遍路道のブログであづり越えの分かれ道迄繋がったトコロで勝手ながらお遍路ブログはお休みさせて頂きます。
次の再開は何年後になるか分かりませんが、2巡目の室戸市以後のお遍路の再開のめどが立てばまた掲載して行きたいと思います。
掲載出来る残りのブログが後少しとなりましたが、最後までのお付き合い宜しくお願い致します。
さぁーこれから、地蔵越え遍路道を越えて行きます。
従是恩山寺12.5km。
 一巡目の時にも驚いたのですが、徳島市内の街中のすぐ近くに・・・
一巡目の時にも驚いたのですが、徳島市内の街中のすぐ近くに・・・
冷たい湧き水が流れています。
※それではここまで歩いて来た様子を動画で観て下さいね。
ランキングバナー、ポチしてネ!
指に余力がありましたら・・・
もう二つも宜しく
※2枚並んでいる画像は肉眼で観れる3D画像です。
パソコンは画面と目の間を40~50cm、スマホなら25cm位で頭を傾けずに水平にした状態で写真と目の中間位の位置に人差し指を立てて指先をじっと見つめて下さい。
視線が寄り眼の状態になって右目で左の写真を左目で右の写真を向見ている状態です。

人差し指の向こう側にぼんやりと3枚の写真が見えて来るので、寄り眼の視線を保ちながら、真ん中の写真に焦点を合わせると真ん中の写真が立体に見えて来ると思います。
ランキングバナー、ポチしてネ!
指に余力がありましたら・・・
もう二つも宜しく
※2枚並んでいる画像は肉眼で観れる3D画像です。
パソコンは画面と目の間を40~50cm、スマホなら25cm位で頭を傾けずに水平にした状態で写真と目の中間位の位置に人差し指を立てて指先をじっと見つめて下さい。
視線が寄り眼の状態になって右目で左の写真を左目で右の写真を向見ている状態です。

人差し指の向こう側にぼんやりと3枚の写真が見えて来るので、寄り眼の視線を保ちながら、真ん中の写真に焦点を合わせると真ん中の写真が立体に見えて来ると思います。
境内の庭には石のテーブルと椅子が設置されてあります。
ランキングバナー、ポチしてネ!
指に余力がありましたら・・・
もう二つも宜しく
地蔵院まで歩いて来ました。
山門前で一礼。
※2枚並んでいる画像は肉眼で観れる3D画像です。
パソコンは画面と目の間を40~50cm、スマホなら25cm位で頭を傾けずに水平にした状態で写真と目の中間位の位置に人差し指を立てて指先をじっと見つめて下さい。
視線が寄り眼の状態になって右目で左の写真を左目で右の写真を向見ている状態です。

人差し指の向こう側にぼんやりと3枚の写真が見えて来るので、寄り眼の視線を保ちながら、真ん中の写真に焦点を合わせると真ん中の写真が立体に見えて来ると思います。
山門脇の仁王像はかなりの年月が経過しているようで、製作当時は色彩豊かに彩られていたと思われますが、その色は痕跡だけ残っているようです。