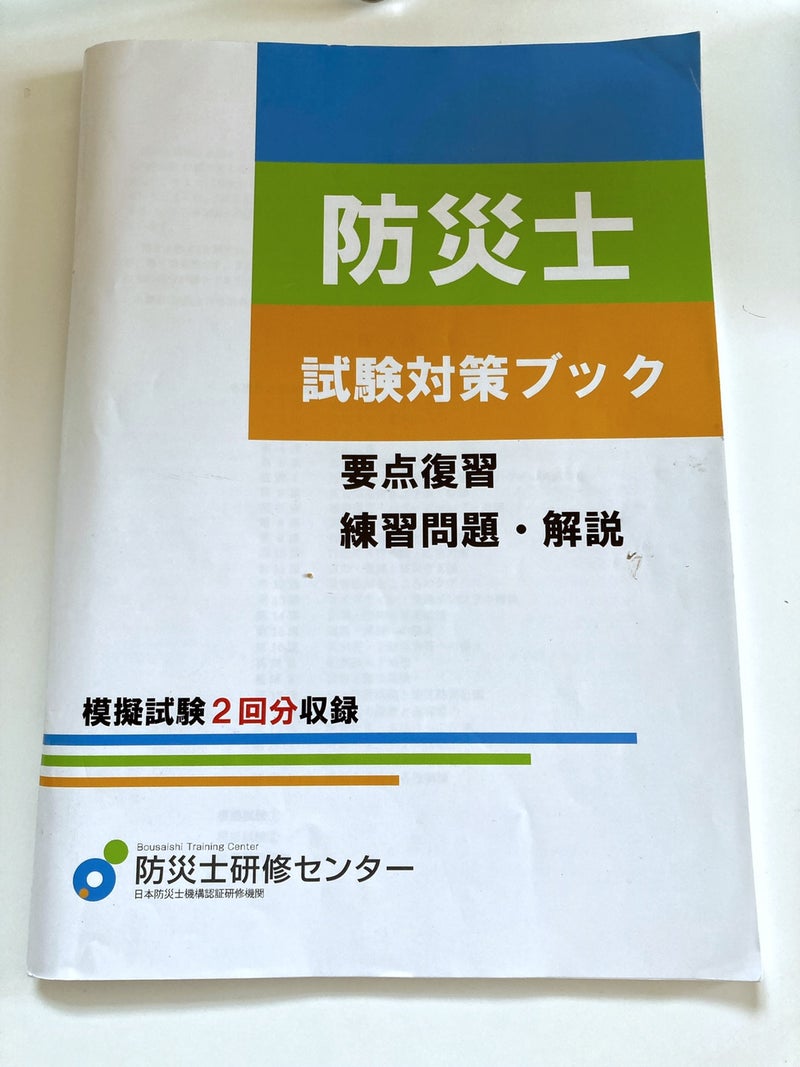家を片付けるにあたって、絶対外せないこと。
その一つが、災害対策だと思います。
要らないものを取り除いて、きれいに収納して、いくら使い勝手がよくなっても、万が一の非常時に、自分を守ってくれる家でなければ意味がない。
そういったことも、整理収納サービスを提供する中で伝えていきたいと思っています。
そのためには、まずは自分が災害、防災について正しく知る。それが大事だと思い、この度、防災士の資格を取ることにしました![]()
前回は概要をお伝えしましたが、今回は、教本とレポートをメインにお伝えしていきます。
送付物一覧
8月上旬に申し込み、支払いを完了しましたが、教本等が送られてきたのは、9月2日でした。研修までちょうど1か月前。だいたい3~4週間前に届くようです![]()
封筒の中に入っていたものは以下の一式。
・受講票
・受講カード
・感染症対策 お知らせとお願い
・災害対策基本法に伴う避難情報の見直しについて
・受講の手引き
・会場研修の案内
・履修確認レポートと回答シート
・試験対策ブック
・防災士教本
詳しくは次回(研修時の様子)お伝えしますが、さすが(?)防災士団体だけあって、感染症対策がしっかり行われていて、安心でした![]()
教本とレポート(試験対策)
教本
噂には聞いていましたが、かなり分厚いです![]()
索引を含め370ページあります!![]()
全21講+補講4つで、合計25章。
「災害」と聞くと、まず思い浮かべるのは、地震や津波、台風、最近は集中豪雨も多いので、そのイメージもあるかもしれませんね。しかし、実際はもっと範囲が広いです。
地震、雷、火事、親父![]() の他にも、
の他にも、
・津波
・台風
・高潮
・大雨洪水(集中豪雨)
・大規模火災
・竜巻
・土砂災害(土石流、がけ崩れ、地滑り等)
・火山噴火
(本当に、日本は災害が多いですね。研修では、その理由についての話もありました。)
それらの発生のメカニズムや災害対策、近年の主な自然災害(新型コロナウィルスを含む)や予報と警報などについて学びます。
さらに、国や行政、企業などの対策や危機管理、災害救助や応急対策、災害医療や被災者の心のケア、ボランティア活動や保険や耐震についてなどなど、内容は多岐にわたっています。
履修確認レポート
レポートは、研修初日の朝に提出します。もし内容に問題があれば、再提出の可能性もあるようです。
レポートの内容は、教本のポイントの抜き出しなので、難しくありません。
教本の文章の、一部が穴あきになっていて、そこを埋める、というスタイルです。つまり、テキストを見れば誰でも答えは分かります![]()
それでも、上記のような内容(厚さ)ですので、抜き出して記入するだけでも、一日はかかるんじゃないでしょうか![]()
抜き出して、ただ写すだけでも、レポートは完成します。しかし、研修講座では、テキストに沿った講義は行われないので、事前に自主学習しておかないと、試験には合格できません。
せっかく資格取得するのであれば、名前だけではなく、教本の内容程度の知識はしっかり身に付けたいところです![]()
そのためには、かなり教本を読み込む必要があります。
私の場合は、試験対策も兼ねて、
・教本を見て、口頭で確認(1回目)
・教本を見ずに、口頭で確認(2回目)
・教本を見ながら、回答記入(3回目)
というふうに、三回取り組みました![]()
ただし、まったくの教本からの抜き出し問題なので、教本を見ないと書けないような、文章丸っと穴あきなんて問題もありました![]()
試験対策ブック
教本のほかに、同封されてくる試験対策ブックを使って復習。
各講のポイントと、練習問題、模擬試験2回分がついています。
模擬試験は2回ずつ解答。
正しいものを選ぶだけでなく、どこが間違っているのかを考えると、試験で違った形で出題されても対応できるかなと思います![]()
練習問題や模擬試験は、法律的なことや実際の災害の被害数などの問題が目立ちましたが、実際の試験では、ほとんど出題されませんでした![]()
代わりに、練習問題にはなかった問題が多く出ていたように思います。
今でも、教本のどこに書かれていたのか分からない問題が、いくつかあります![]()
(あくまで個人的な感想です)
最初は、講ごとにノートにまとめようと思ったのですが、内容が濃すぎるうえに、時間が足りないので、すぐに断念![]()
繰り返し読む&解く方法にチェンジです。
研修を受けた後に気づいたことがあります。
様々な事例が教本には載っていますが、ぜひYouTubeなどで映像を確認しながら、勉強することをお勧めします![]()
津波や台風などは、イメージがつくと思いますが、がけ崩れや火山噴火などは、(ニュースなどでも)映像を見る機会があまりないと思います。
研修で、映像を見せていただいたのですが、先に見ておくと、教本の内容がもっと、すっと理解できたかも!と思いました。
研修日の持ち物
「会場での物品の貸し出しは行っておりません」と書かれていたので、念入りに確認して、忘れ物がないように会場に向かいました。
持ち物は以下の一式。
① 受講票
② 受講カード
③ 防災士教本
④ 履修確認レポートの回答シート
⑤ 筆記具(ボールペン、鉛筆、消しゴム)
⑥ 顔写真2枚
上から説明していきますね。
①受講票
A4サイズの紙です。毎朝受付で提示します。
②受講カード
名刺サイズの紙です。受験番号と受講コースの名前が書いてあります。研修の間、ネームホルダーに入れて、首からかけなければいけません。忘れずに持っていきましょう。ネームホルダーは会場に用意されています。
③教本
絶対必須ですね。教本に沿って授業が行われるわけではありませんが、確認のために見たり、試験の復習をしたりと活用する場面は多いです。
④レポートの回答シート
初日の朝に提出します。問題冊子は持っていかなくてよいです。
⑤筆記具
書類書いたり、封筒に宛名書いたりするので、ボールペンは必須。鉛筆(またはシャーペン)と消しゴムは、試験の時だけ使いました。
ただし、試験も「鉛筆じゃないとダメ」というアナウンスはなかったので、ボールペンでも良かったのかもしれません。私は普段、鉛筆を使わないので、初日の朝、コンビニで調達してから行きました。
⑥写真
自撮りなどではなく、証明写真をおススメします。縦3㎝×横2.5㎝、カラー、無背景のモノを用意。私はこれも初日の朝に、駅の証明写真の機械で撮りました。会場で「防災士認証登録申請書」を作成しますが、そのとき写真2枚が必須です。
いかがでしょう?
防災士の資格は、簡単だと言われていますが(合格率89%!)、勉強する内容はとても広く、深いです。
試験に合格するだけなら、難しくないのかもしれませんが、本当に理解するのは、大変ですね![]() (何事もそうですが)
(何事もそうですが)
次回は、いよいよ研修講座初日についてお伝えします![]()
その他防災士の記事はこちらから。