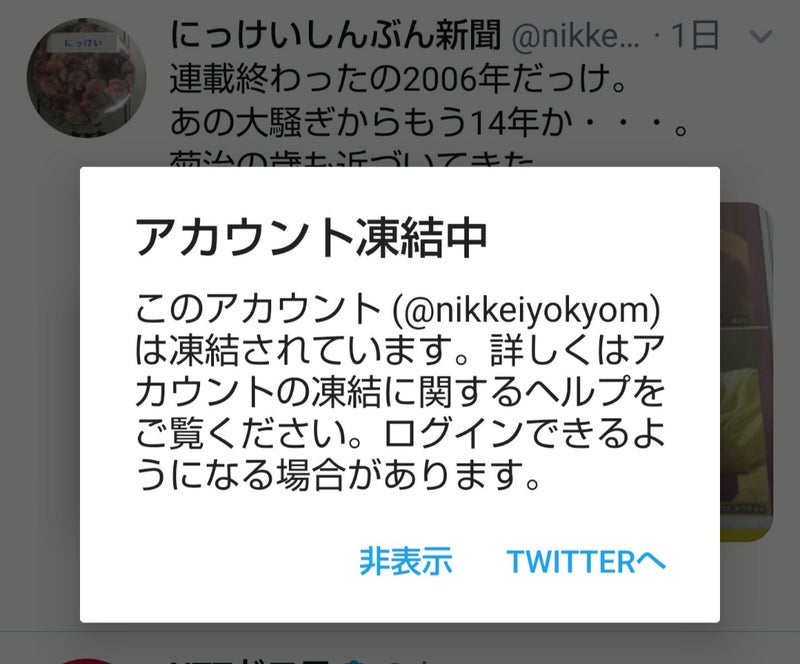たまにログインしてみると機能がいろいろになりすぎてて迷子になって挫折。。。
おまけにあれこれやって散々調べた挙句、プラグインでつぶやいてるのが表示されないのがIEブラウザのせいだとわかりさらに脱力。。。
てか僕、最後にアゲた記事が2年前のこれだったのか。。。(16/09/17記)
私の履歴書 黒田東彦 「国益を追って」
え!
履歴書、今日から黒田前総裁!?
せっかくなので会見で毎回絡んできた勘違い自己満足フリーランス記者に反撃してやってください。
昨日も植田総裁を国賊呼ばわりして超失礼だったよ。
こどもに10万円支給 -子育て支援?-
こどもに10万円支給、バラマキ批判を受けて年収制限をつけようとしてる件。
こども同士では「何買ってもらった?」とか普通に話すると思うよ。
悪気なく「うちもらってない」とか言うこどもいると思うよ。
「お前んち年収1000万!?」とかなるって。
こどもの間で「もらった」「もらってない」が出ると、親の年収でこどもに分断が生まれる可能性があることは問題じゃないか?
親の間にも年収ばれちゃって「○○さんは高所得者」とか、逆に金持ちエリアじゃ「あそこのおたくは受給したんですって」とか、ママ友パパ友の間でも変なことにならないか?
ワンダーランド急行#249[2021/11/05]
ロータリーのはずれのあのよろず屋だけが・・・さて今回はどうしよう。
そこそこ、そこのよろず屋だかばあさんだかがカギ握ってんのよ!
前回の会話思い出せって!!
違和感なかったか!?
ワンダーランド急行#161[2021/07/19]
次の異世界へご案内~・・・の予感。
ていうかずっと思ってるんだけど、これって異世界じゃなくて「並行世界」とか「違う世界線」とかじゃないの??
荻原浩「ワンダーランド急行」(161):日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO73984800W1A710C2BE0P00/
2021/05/26
もしかしてこれで記事書けるのか!?
日経平均続伸、午前終値50円高の2万8604円:日本経済新聞https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB00004_W1A520C2000000/
縮む日本 失う不安映す -久しぶりにめっちゃ気になった-
タモロス あまロス ペットロス -日経MJ1面-
え?
久しぶりに渡辺先生以外の記事あげるのに何でMJ?
と自分でも思いますが、久しぶりなんで軽めのほうがいいです。
突っ込みどころが多かったし。
リハビリ気分で記事を見ていきましょう。
「笑っていいとも」が終了し、ネットで話題になった「タモロス」。「あまちゃん」終了時に「あまロス」という言葉も生まれた。母親の死を受け入れられない「母ロス」、ペットの死で深く落ち込む「ペットロス」。近年の「ロス」現象は何を意味しているのだろう。
・・・いや、もう、この時点でついていけませんね。「あまロス」「タモロス」と「ペットロス」ましてや「母ロス」を同じ土俵で語る感覚がわかりません。
「悲しみがいえない心情をネットを通じて共有できるようになり、ロス現象として広がっているからだろう」とつなげているのですが、んー、「ペットロス」や「母ロス」が現象としてネットで広がっているのでしょうか・・・。
まあこれくらいは記事のストーリー作りとしてよくあること。
我慢して読むと、記事はなんかそれっぽく社会学的な考察を加えていきます。
ある研究者さんの「家族、企業、社会の絆が一段と弱まり、ペットや番組への感情移入が強まっているからではないか」という指摘を挙げ、社会の変化を背景とした人々の深層心理にも理由がありそうだというのです。
いやー、なんか強引っすねー。
そしてありきたりっすねー。
だいたい、「絆」って言葉でまとめた分析結果はあてにならない気がしますよねー。
そして執筆者さんの論はさらに強引に続きます。
成長の時代が終わり、人口減が進む日本では「得る」ことより「失う」ことが増えていく。年金問題などもあり、孤独感は増すばかり。かつてない存在不安が人々を襲い、ロス現象を助長しているというわけだ。
ひー!!
年金問題が「あまロス」「タモロス」を助長してるんですか!!
まさかの因果関係ですよ!
おい、厚生省!!
責任とってあまちゃんを超える朝ドラつくってくれ!!
あと、バイキングの視聴率なんとかしてやってくれ!!
・・・そう訴えたくなるような理屈ですよ。
訴えませんけど。
で、続いて「失う悲しみは得るときの喜びの2倍大きい」なんてノーベル賞学者の言を持ち出してきて、どう展開するのかと思ったら、いきなり
企業は定番ブランドを磨くのに必死。この結果、70-80年代の音楽やドラマ、漫画など「レトロ」コンテンツ志向も強まっている。喪失感を吸収するだけの新しいエネルギーが生まれていないとも言える。
へ?
流れがよく分からないんですけど?
てか、意味もよく分からないんですけど?
んー、後番組がいまいち面白くないってことですか?
なんかかなりちんぷんかんぷんなまま結びの段落に向かうのですが、
日本は「閉塞感」「停滞感」といわれて久しい。ネットの普及はプラスの面も大きいが、よりお得感を求める志向も強めた。
『お得感』て!!??
もう、「ロス現象」関係ないじゃん!!
なんでいまさらこんな消費関連の記事書くときのテンプレみたいな文持ち出してくるの!?
これでここから最後はどう締めるのよ!?
縮む日本で損失を取り戻すのは大変な時代。ロスを恐れる心理はさらに強まるかもしれない。
えええー!
なにこれ!!
「タモロス」も「あまロス」も「ペットロス」も「母ロス」も全部すっとばしちゃってんじゃん!!!
「○○ロス」って、ロスを恐れて何かしてる訳じゃないし!!
てか、ロスはロスでも、「失うこと(喪失)」と「損失」はぜんぜん意味違うし!!
・・・で、けっきょく何が言いたいのよ、この記事??
よく見るかける論調の「最近の消費者はお得感を求め、損をすることを嫌う」ってことを言いたかったの?
そのためにぜんぜん関係ない「タモロス」「あまロス」「ペットロス」「母ロス」まで持ち出してきて、「ロス」って言葉の枕にしたの??
それとも「タモロス」「あまロス」で1本記事を書こうとネタ集めて書き始めて、いつもの調子で経済とか消費者心理に話をつなげてまとめようとして、レトリックに走ってるうちに自分で何のこと書いてんのかよくわかんなくなっちゃった?
あるいは時間がなくなって無理やり強引にまとめちゃった?
それにしても、今さら旬でもない「タモロス」をネタにするって・・・。
この記事、わざわざ1面の目立つ箇所に執筆者(編集委員)の名前入りで載っちゃってますけど・・・この方にとってはロスのほうが大きいかもしれません・・・。
え?
久しぶりに渡辺先生以外の記事あげるのに何でMJ?
と自分でも思いますが、久しぶりなんで軽めのほうがいいです。
突っ込みどころが多かったし。
リハビリ気分で記事を見ていきましょう。
「笑っていいとも」が終了し、ネットで話題になった「タモロス」。「あまちゃん」終了時に「あまロス」という言葉も生まれた。母親の死を受け入れられない「母ロス」、ペットの死で深く落ち込む「ペットロス」。近年の「ロス」現象は何を意味しているのだろう。
・・・いや、もう、この時点でついていけませんね。「あまロス」「タモロス」と「ペットロス」ましてや「母ロス」を同じ土俵で語る感覚がわかりません。
「悲しみがいえない心情をネットを通じて共有できるようになり、ロス現象として広がっているからだろう」とつなげているのですが、んー、「ペットロス」や「母ロス」が現象としてネットで広がっているのでしょうか・・・。
まあこれくらいは記事のストーリー作りとしてよくあること。
我慢して読むと、記事はなんかそれっぽく社会学的な考察を加えていきます。
ある研究者さんの「家族、企業、社会の絆が一段と弱まり、ペットや番組への感情移入が強まっているからではないか」という指摘を挙げ、社会の変化を背景とした人々の深層心理にも理由がありそうだというのです。
いやー、なんか強引っすねー。
そしてありきたりっすねー。
だいたい、「絆」って言葉でまとめた分析結果はあてにならない気がしますよねー。
そして執筆者さんの論はさらに強引に続きます。
成長の時代が終わり、人口減が進む日本では「得る」ことより「失う」ことが増えていく。年金問題などもあり、孤独感は増すばかり。かつてない存在不安が人々を襲い、ロス現象を助長しているというわけだ。
ひー!!
年金問題が「あまロス」「タモロス」を助長してるんですか!!
まさかの因果関係ですよ!
おい、厚生省!!
責任とってあまちゃんを超える朝ドラつくってくれ!!
あと、バイキングの視聴率なんとかしてやってくれ!!
・・・そう訴えたくなるような理屈ですよ。
訴えませんけど。
で、続いて「失う悲しみは得るときの喜びの2倍大きい」なんてノーベル賞学者の言を持ち出してきて、どう展開するのかと思ったら、いきなり
企業は定番ブランドを磨くのに必死。この結果、70-80年代の音楽やドラマ、漫画など「レトロ」コンテンツ志向も強まっている。喪失感を吸収するだけの新しいエネルギーが生まれていないとも言える。
へ?
流れがよく分からないんですけど?
てか、意味もよく分からないんですけど?
んー、後番組がいまいち面白くないってことですか?
なんかかなりちんぷんかんぷんなまま結びの段落に向かうのですが、
日本は「閉塞感」「停滞感」といわれて久しい。ネットの普及はプラスの面も大きいが、よりお得感を求める志向も強めた。
『お得感』て!!??
もう、「ロス現象」関係ないじゃん!!
なんでいまさらこんな消費関連の記事書くときのテンプレみたいな文持ち出してくるの!?
これでここから最後はどう締めるのよ!?
縮む日本で損失を取り戻すのは大変な時代。ロスを恐れる心理はさらに強まるかもしれない。
えええー!
なにこれ!!
「タモロス」も「あまロス」も「ペットロス」も「母ロス」も全部すっとばしちゃってんじゃん!!!
「○○ロス」って、ロスを恐れて何かしてる訳じゃないし!!
てか、ロスはロスでも、「失うこと(喪失)」と「損失」はぜんぜん意味違うし!!
・・・で、けっきょく何が言いたいのよ、この記事??
よく見るかける論調の「最近の消費者はお得感を求め、損をすることを嫌う」ってことを言いたかったの?
そのためにぜんぜん関係ない「タモロス」「あまロス」「ペットロス」「母ロス」まで持ち出してきて、「ロス」って言葉の枕にしたの??
それとも「タモロス」「あまロス」で1本記事を書こうとネタ集めて書き始めて、いつもの調子で経済とか消費者心理に話をつなげてまとめようとして、レトリックに走ってるうちに自分で何のこと書いてんのかよくわかんなくなっちゃった?
あるいは時間がなくなって無理やり強引にまとめちゃった?
それにしても、今さら旬でもない「タモロス」をネタにするって・・・。
この記事、わざわざ1面の目立つ箇所に執筆者(編集委員)の名前入りで載っちゃってますけど・・・この方にとってはロスのほうが大きいかもしれません・・・。